

�m�n�D�W�O

�Q�O�O�Q�N�P�P���P�T���@
�A�N�Z�X������Z���^�[
�ڎ�
|
�w�Z��� |
������ | ������ | ���J�͎���� | ���̑� |
| �}�g���� �i���� | �K�n�x�ʋ������C
�@ |
�@ |
��s���͎��P�P��
�@ �@ �@ |
�w�Z���
�}�g�����@�w�Z������i�O�Q�N�P�O���P�Q���j
�P�@���Z���@��ؐ搶
�w�Z�̊T�v
���������ŗB��̒j�q�Z�B������сB
�Z���͂P���B���Z���Q���B�S�T���̋����X�^�b�t�B�i���u�t�P�W���j
���w�͊e�w�N�R�N���X�A���Z�͊e�w�N�S�N���X�̏��K�͂Ȋw�Z�B�n���T�U�N�B
�Ɨ��s���@�l���Ɋւ���
������w�̖@�l�����X�X�̍�����w���������B
�}�g������������ψ���Ō������Ă���B
�Q�O�O�S�N���獑����w�@�l�ɁB
�������Z�����ψ���ł͌���ʂ�}�g��ƈ�̂ƂȂ��Đi��ł������ƂŌ���B
�t�����Z�Ƃ��Ă̋�̑����������Ă���B
�����̕����Ƃ��Ă̖����͌p�����Ă����B
�@��w�̌����Ɏ�����i��w�Ƌ����Ō����ɓ�����j�B
�@��w���̋�����K�Z�B
�}�g����͒�����тŎЉ�̃g�b�v���[�_�[����Ă邱�Ƃő�w�ƈӌ�����v�B
�g�b�v���[�_�[����Ă�Ƃ������Ƃ��}��݂̒��S�I�ȕ����Ƃ��Ĉʒu�Â�����B
�^�̃G���[�g�Ƃ́B
������тʼn���ڎw���̂��B�E�E�Љ�̃g�b�v���[�_�[����Ă�B
�U�N�Ԃ̋���ł�����w�ɓ���邱�Ƃ�ڎw���̂ł͂Ȃ��B��w�͂U�N�Ԋw�Z�����̌��ʁB
��w�̐�i��w�@�A�Љ�j���������āA���̂��߂̊�b�E��{�����炵�����B
�Љ�v���̂ł���G���[�g����Ă�B
�X�[�p�[�E�T�C�G���X�E�X�N�[���̎w��Ɋւ���
�w�͂̒ቺ�A�����ȗ��ꌾ���钆�ŁA��w���Ƃƒ�g���āA���Z���̂��i���ȁA���w�̃J���L���������v�������w�Z�ōs�Ȃ��ė~�����ƕ����Ȃ���W�B
�����̕����Ƃ��đS���̒����֏��M����̂��}��̖����ł��낤�Ɖ��傷��B
�S���łQ�U�Z���w�肳���i�����Q�P�A�����Q�A�����R�j�B
���̑����̊w�Z�͕��n�̎��Ǝ��Ԃ����炵�ė����n�̎��Ԃ𑝂₵�đΉ����悤�Ƃ��Ă���B�}��͂���܂ł����n�A���n���ł��邾���x���܂ŕ������ɂ����B���Z�Q�N���܂ł͓����J���L�������Ŋw�K����B
�Љ�ɏo���Ƃ��Ɏ����̐�傪�ǂ������ʒu���߂�̂��A�O���猩���Ƃ��ɂǂ������Ӗ������̂��Ƃ��������I�Ȏ��_�������Ă��炢�����B
�����I�Ȏ��_���������l�Ԃ���Ă邽�߂ɒ}��̒��ł̃J���L�������A���ނ�����Ɍ������đ��̊w�Z�ɔ��M���Ă����B
�V���ɗ\�Z�����܂�B��w���̊��������̌ォ���̓I�Ȏ��Ƃ������o���B
����܂łɁA���̉@���⏕��ɂ�鐔�w�̘b�Ⓦ���}�g��w�̋����ɂ�鉻�w�A�����A��b�H�w�̓��ʎ��Ƃ��P�O���ԂقǍs���B
���Z�Ő������U���Ă��鐶�k���ċx�݂Ɉ��m���̌������Ő������̌ږ�ƍ��h���Ď������s���B
����܂ł̒}��̋���̐ςݏd�˂̒��ʼn��n���ł��Ă����B
���w�I�����s�b�N�E�E���{���疈�N�U���o�ꂷ�邪���N�͒}���Q���B��܂Ɠ��܂ɁB
�L���t�i���w���̑S�����w���j�E�E���N�P�ʂƂS�ʂɁB
���Z���w�O�����v���E�E�P�ʂƂR�ʂɁB
�X�p�R���v���O���~���O���i��w�����Q���j�E�E�R�N�����ĂP�ʂ��Q�ʂɁB
���n�}�E�E���Ƃ̒��Ŏ����̒n��̊��n�}�����B�D�G��i����ɉ���B�E�E���y�n���@�܂ɁB
�S�����Z���N�C�Y�I�茠�E�E�Q�ʂɁB�R�N�O�͂P�ʂɁB
�X�[�p�[�T�C�G���X�X�N�[���Ɏw�肳�ꂽ���Ƃɂ�钆�w���̃����b�g������B������уJ���L�������̒��Ŋe���Ȃ������̋��ނ̈�ѐ����l���Ă���A���Z�ŃX�[�p�[�T�C�G���X���s����ł̐��ʂ����̂܂ܒ��w���̎��Ƃ̒��ɔ��f�����B�\�Z���t���̂ō����ȋ@�킪�w���ł��A����𒆊w�������ƂŎg�����Ƃ��ł���B
���Ɛ��̐i�H���͎������Q�Ƃ��Ă��������B
���w�P�N���ɑ���w�Z�̍l����
���w�����͌����ē�������o���Ă���킯�ł͂Ȃ����A�������x���̐��k������B
���ʂƂ��ďm�A�\���Z�ɍs���Ȃ���Γ��w�ł��Ȃ������F�����Ă͂��邪�A�����R�N�قǒ��w�P�N�������Ă��āA�q�������̕�����ԓx�A���̍l�����Ƀ}�C�i�X�̉e�����^�����Ă���B
�Ƃ����O������̓��@�t���ŕ����Ă���B
�}��ŕ����Ă�����Ŏ����̓�������̓��@�A�D��S���d�v�Ȃ̂ɐg�ɂ��Ă��Ȃ��B
�ŏ��̎��ƂŁA�����ł��̂��l���邱�Ƃ̏d�v���A�����ł��̂��l����ƌ������Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂���b���B
���w�ɓ�������ƒ�ł����I�ȍD��S�A���@���ɂ��ė~�����B
�}��ł͓��I�ȓ��@�t�������������B
�Q�@�r�f�I�ɂ��w�Z�Љ�E�E�r�f�I�͋����̎���
���w���@���̑̈�ق͋��̐��E��Y�Ƃ�����B�����I�����s�b�N�̎����m�̖��������K�����B
�c�A���@���P�ƍ��P�����c��Ƃ�S���B
���y�Ձ@�����w�N�̒��P�̎��ƍ��R�̎��̈Ⴂ���B
�̈�Ձ@�N���X�R�B�V�F�i���Z�S�F�A���w�R�F�j�B�Q���ԁB
�Z�O�w���@�T���̉��{�ɒ��P���獂�Q�����ꂼ��Z�O�ɏo������B
�E���@�č��͑����w�K�̈�тɂȂ��Ă���B
�݂��@�c�����Ă͐Ԕтɂ��đ��Ǝ�����w���̎��ɔz��B
�٘_���@���w�������B�e�N���X�Ńe�[�}�����߂ĕَm�𗧂Ă�B
���[�h���[�X�@������̉͐�~�𒆊w���S�q�A���Z���W�q�B
�����Ձ@�R���ԁB�ł��傫�ȍs���B���Q�܂ł̓N���X���\�B���R�̓N���X����̂��ĔǂŊ����B�����ǁA�H�i�ǁA�X�e�[�W�ǁA�i���Ǔ�������B
�R�@���������@�{���搶�E�E�w�K�ɂ���
�����W�c�S�T���̓����E�E�ŋ߁A��Őe���▼�����t�����Ȃ��Ȃ����ƌ����邪�A�}��ɂ̓E���E������B
�ςȐ��k�����邪���܂�ڗ����Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�ςȋ��t�����邩��B
�n����i���k����͒���肷���č���ƌ����Ă���j�ƌĂ�A�����s�����w�Z�T�b�J�[�I���`�[���̋����R�[�`�Ɠ����ɗ��w���m�ł����鋳�t�B
���k�Ɋւ��̂���l���d���a�ɂ��������ƕ����āA���L�V�R�܂Ŗ��̐���T���ɍs�������t�B
�X�v�[���Ȃ��̂ł��鉻�w�̋��t�B
�P�N�ԉH�D�тŒʂ��Ă��鋳�t�B
�싅���̌ږ�����Ă��镨���̋��t�͓���싅�����̉E�������ł��������̋��t�B
�}��̋����̓��F�Ƃ��đ�w�̔��u�t�����C���Ă���搶�⒆���̋��ȏ��̕ҏW�ɊW���Ă���搶�������B�ł��r�f�I�Ō��Ă����������悤�ɁA�}��̐��k�ɑ��Ď�����ƂȂ��S�͂Ŏ��g��ł���B
�w�Z�ē��Ɗw�Z��������̃J���L�������\�̐����ɈႢ�����邪�A�w�Z�ē��̕��̐����͕����Ȋw�Ȃ̒�߂��W�����Ԃ��f�ڂ��Ă���B�W�����Ԃ̒��ɂ���I���̎��Ԃ��e���ȂɐU�蕪���Ă���B��������̒��̐��������ۂ̎��Ǝ����B
�@�@�@�@���P�@�@�@�@���Q�@�@�@�@���R
����@�@�S�i�S�j�@�@�S�i�R�j�@�@�S�D�T�i�R�j
���w�@�@�S�i�R�j�@�@�S�i�R�j�@�@�S�i�R�j
�p��@�@�S�i�R�j�@�@�S�i�R�j�@�@�S�i�R�j
�i�@�j�͊w�Z�ē��̎��Ǝ����B
�����̎��Ƃ̓��e�Ɋւ��Ă͐�������̂V�y�[�W�ȍ~���Q�Ƃ��Ă��������B
�J���L�������ɑ����{�I�ȍl�����́A��{�w�K�����p�͂�{���w�K���X�l�����W�I�Ɋw�Ԋw�K�̗��ꂪ�x�[�X�ɂȂ��Ă���B
���Z�ł̓X�[�p�[�T�C�G���X�n�C�X�N�[���Ƃ��č��x�Ȋw�K���p�ӂ���Ă��邪�A����������Ȃ蒆�w���ɍs�����Ƃ͂ł��Ȃ��B
��b��{����������g�ɂ�����łȂ��Ɛ��k�ɂƂ��ď����ł��Ȃ��B
��b�E���p�E���W�Ƃ������ꂪ�U�N�Ԃ̗���̒������łȂ��A��̒P���̒��A��w���̎��Ƃ̒��A��N�Ԃ̎��Ƃ̒��ł��J��Ԃ��s����B�e���Ȃ̗l�X�ȃJ���L�����������̐��ʂ̂��Ƃɑg�܂�Ă���B
���Șg�ӊO�̊w�K�Ƃ��đ����w�K���s���B
���w�Z�ł͂T�̃��j���[��p�ӂ��Ă���B
�����w�K�`�E���c�w�K
�P�ɓc�ނɂ����ēc�A��������܂ł��o�����邾���łȂ��A����ƕ��s���ċ����Ő����̋��t�����ʂ��Đ����̎��Ƃ��s������A�Љ�ȂŊ��������グ����A����ȂŕĂƕ����Ƃ��������������A�Z�p�Ȃŕč��ƎY�Ƃ������Ƃ����悤�ɋ��Ȋ����ƑS�ă����N���Ă���B
�����w�K�a�b�E�n�挤���i�����E���k�j
���k���������̔ǂɕ����ꂻ�ꂼ��̃e�[�}��ݒ肵����I�Ɍ�������B�Љ�Ȃ̒n���Ȃ����S�ƂȂ邪�e���Ȃ��w������B
�ǂ��Ɏ�ނɍs���̂��A�N�ɘb���̂��k�����N�����������Čv��B�A�|�C���g���Ƃ�Ƃ��납��X�^�[�g����B���N�����Q�̓����n�挤���̕W�͂S�O�O�y�[�W����B
�����w�K�c�E�e�[�}�w�K
�w�N���オ��ɂꐶ�k�̋����S���L�����Ă䂭�̂ɑΉ��������l�����̑I�����ƂƂ��ăe�[�}�w�K���s���B�ʏ�̋��Ȋ����Ƃ͈�������_�ł̍u����p�ӂ���B
�Q�O�O�Q�N�̗�
������肩������́i���j
�����i���{�Ё{�p�j
�l�͂Ȃ����܂����̂��i���j
�l���悤�s���̎i�@�Q���i�Ёj
���w�̊ዾ��ʂ��Č��鐢�E�i���j
�����w�K�d�E���ʉۑ�
�S�������ʂ̉ۑ�Ńt�B�[���h���[�N���s���B
�}��ł͂������������w�K��ʂ��ĖL�x�ȃ��j���[��p�ӂ��Ă���B
�S�T�l�̋����ł͂���Ȃ�̌��E�����邪�A�����₤�l�ނ̃X�g�b�N�A�l�b�g���[�N���}��ɂ͂���B
�Ⴆ�e�[�}�w�K�́u�����v�ł͔��N�ԂŊ؍��A�y���[�A�G�W�v�g�A�g���R�̕����w�Z�ɏ����Đ��k�Ƙb���@���p�ӂ���B���̒��N���������w�Z��K�₵�čݓ��Ɋւ��ċc�_������B�m�I��Q������Ɋւ���Ă���n�a�̘b���B
�U�N�Ԃ̊Ԃɂ͐��\�l�̗l�X�Ȑl�Ɖ�@��������Ƃ��ł���B
�Ȃ������܂ł��̂��B���}��̖ڎw���Ă��鋳��͂U�N��ł͂Ȃ��B
��N�̎Q���҂̊��z�ɁA�}��̐�����ł͑�w���i���тɂ��Ĉꌾ���G��Ȃ������Ƃ����̂��C���^�[�l�b�g�̌f���ɍڂ��Ă����B
���N��������͂Ȃ��B
���ꂼ��̐��k�̑�w�i�w���т��ւ肽���C���������邪�A��������ɂ�����������Ƒ�ȋ��̓`���i��w�i�w�ɕς������Ɖ��l�̂�����̂��w�Z�����ɂ���ɈႢ�Ȃ��Ɛ��k�A���t���v�������Ă���Ƃ���ɂ���}��炵���j������ƍl���Ă���B
���̂R���ɂT�O���������Ƃ��ĂV�U�O�O���߂����Ɛ�������B���̂����P�O�O�O�����鑲�Ɛ��������E�⍂�x�Ȑ��E�ɏA���Ă���B����͂U�N��ł͂Ȃ�����ɂ��̐�̎Љ�v���Ƃ��������Ƃ܂ł��ڎw��������̐��ʂł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B
�}��Ƃ����Ɖ����ƂĂ��v���������Ĕ\�͂̂Ȃ����k�͂���Ă����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����s����������邩������Ȃ�������Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B
�`�������W�w�K�E��K�I������
���k�ɂ���Ă͕s���ӂȉȖځA���ȉȖڂ��ł��Ă��܂��B���R�̍Ō�̔��N�ԂɎ�������ԕ₢�������Ȃ�I�����ďW���I�Ƀg���[�j���O������B
���N�A����͂Q�O���ɑ��ĂQ�l�̋����őΉ����Ă���B
�������ڂꂽ�炻�̂܂ܒu���čs�����̂ł͂Ȃ����Ƃ����S�z�͂���Ȃ��B
���̑��ɕ�K�������{���Ă���B
�ی�҂̕����炷��Ζ{���̕����łU�N�オ�C�ɂȂ�Ƃ��낾�Ǝv���B
�ŋ߂͊w�Z�ɂ��s�ꌴ�������荞��ł��Ă���B����������Ɍ��ʂ����߂錴���Ƃ��āB�R������A���N��ɖڂɌ�����`�Ō��ʂ��o��悤�ȃT�[�r�X���w�Z�Ɋ��҂���Ă�����������Ă���B
�ʂ����ċ���Ƃ������̂͂����������̂Ȃ̂��B�^�̃��[�_�[�Ƃ͉��Ȃ̂����l����ꍇ�����̖��͔����Ēʂ�Ȃ��B
�F����͐e�Ƃ��Ďq���Ɍ�����������������B���̂��߂ɁA���A�m�ɒʂ킹���Ă���Ǝv���B���w�Z�S�N����T�N������X���A�P�O���Ƃ������ԂɊO�ɂ���B���̂��Ǝ��̂����S�ȏ�Ԃł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ͕S�����m�̏�ŁA�����Ă���������Ȃ��F����̃W�����}�Ƃ������̂��w�Z���Ƃ��Ă��[���������Ă���B
����̂ɁA�����}��̋���𗝉�����A�}��ɓ��w���ꂽ�ۂɂ́A�l����Ă�Ƃ������Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂�����X�ƈꏏ�ɍl���ė~�����B
���i���\�̓��ɁA���i�������u�ԂɁA�����Ċ��̏�����߂�ƌ����Ă����Ȃ�m�̐�����ɑ����Ă�������������B�q���̗���ɗ����čl���Ă݂��Ƃ��ɁA����܂łQ�N�R�N�x���܂Ŏ������Ă��āA�x�ފԂ��Ȃ��܂��U�N�ԕ����Ƃ����X�g���X�ɑς�����̂ł��傤���B
��������L�т������S���̂悤�ɂȂ��Ă��邨�q���������B�������Ƃɂ͖߂�Ȃ��Ȃ��Ă���B�}��ł͂��������q�����Ȃ�ׂ��o�������Ȃ��B���������������ƍ\���āA�l����Ă�Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂����ꏏ�ɍl���Ă���������F����ɂ����ł������������B
�����������͊w�K�ʂ݂̂Ȃ炸����̐������Ɋւ���Ă���B����ɂ��Ă͐��k��������B
�S�@���k�����@����搶�E�E�w�Z�s���A�ۊO�����ɂ���
�r�f�I�Œ}��̊w�Z�s���ɂ��Ă͗������ꂽ���ƂƎv���B
�}��͍s���������A���̑���������肭�����Ă���Ƃ������ɂȂ�����������܂��A�����ł͂Ȃ��B
�w�Z�s���A�N���u��������ɑ�ȋ���@��ƍl���Ă���B
�w�ƁA�s���A�N���u�����̂R�Ő��k����ĂȂ��ƁA���k�̑S�ʓI�Ȕ��B�͑����Ȃ��B
�����Ղ����Z�̂����ɍs���ƒP�ɋ����̒��ɕ���u���Ă���t���[�}�[�P�b�g�ɉ߂��Ȃ��ꍇ�������B�ǂ��������Ȃ̂��B�P�P���Q�E�R�E�S�ɍs����}��̕����Ղɐ��ė~�����B�S���ʼn��������グ�镶���ՂɂȂ��Ă���B
�Ȃ��s����N���u�����Ɉꐶ�����ɂȂ�̂��B
�����̂U�N�Ԃ͏��w�Z�̂U�N�ԂƂ͑S�R�Ⴄ�B���w�Z�̂U�N�Ԃ͒����I�ɑ̂��S���������Ă������A�v�t���̐����ߒ��̓W�O�U�O�ł��낢��ȃp�^�[��������B
�}��ɓ��w���Ă��鐶�k�͎����ł��鐶�k�B�����ł���ƌ������Ƃ͑f�����Ƃ������ƁB���R����悤�Ȏq�͎����~�߂Ă���B
���ꂪ���w�ɓ���Ƃ��Ȃ��̎������}���A�k�ɕ�������悤�ɂȂ�B�O����ł͐S�̒��łǂ���������������̂��킩��Ȃ������ɂȂ�B���̏Փ����o�Ă���B
�S���̂��傫���h��Ă����B
����ɑ��Đe�͎������v�t�����߂����Ă��Ȃ���A���̎��̂��Ƃ��قƂ�ǖY��Ă���B
�����v���o�A�y�������ƁA�撣�������Ƃ͓��̒��Ɏc���Ă���̂����A�������v���Y��ł������Ƃ͂����ۂ�Y��Ă��܂��B
�v�t���̒j�̎q�͕��������Ă��{�邭�炢�����Ȏ����B�e�ɂƂ��Ă͎v�t���̎q�����킩��Ȃ��B�q�����g���������Ȃ��Y��ł��邩������ł��Ȃ��B
���̎v�t���̒��̍����𗝉����Ȃ��ŕ��A���ƒǂ����ĂĂ����܂��s���Ȃ��B
�e�͌����I�Ȃ��Ɓi������w�ɍs�����߂ɁA�������������邽�߂ɕ����Ȃ����j�⏫���̂��Ƃ��������Ȃ��B�������A���w���ɂƂ��Ă͍����S�āB
�v�t���̍����̒��Ŏq���̐����⎩����҂����Ȃ��B
�e�q�W�E�E�Â��E�ˑ��Ǝ����̍č\�z�B
�F�l�W�E�E�F�B�I�сE�E�����ɂ��������Ԃ�I�т͂��߂Ă����B
���������e�q�W��F�l�W��ʂ��Ď����Ƃ͉������l���͂��߂Ă��������B���������A�������̎����B
���̎��������⎩�����𑣂��̂��w�Z�s���A�N���u�A�w�Z�����B
�U�N�Ԃ̐S�̐����i�z�z�����Q�Ɓj
���P�E�E�l�q���̎���
�@�@�@�@���݂����ώ@���Ă���B
���P�㔼�`���Q�E�E������
�@�@�@�@����̉萶���E�E�e�̌������Ƃ��Ă����q����������悤�ɂȂ�B
���R�E�E��������͍���
�@�@�@�@���S�ł����⒇�Ԃ�T���B�E�E���̎��Ɋw�Z�s����N���u�������傫�ȃE�F�[�g���߂�B
���P�E�E�O���[�v������
���P�㔼�`���Q�E�E�O���[�v�ւ��A���ꏊ�ւ����N���鐶�k���o�Ă���B
�@�@�@�@������x���������ߒ����Ă���B
���R�E�E��l��
�@�@�@�@�C�̍������ԂƂ̌�
�@�@�@�@���҂ɑ��銰�e�����o�Ă���B
�@�@�@�@���t�ɑ��Ă��u�搶����ς��ˁv�Ƃ������������o�Ă���B
�e�̊ւ���
���w�Z���E�E��l�O�r
�@�@�@�@�q��Ă̊O�����E�E�K�����A�m�B���܂̃A�E�g�h�A���G���ɏo�Ă���悤�Ȍ`�ŁB
�@�@�@�@�e�q���ւ��@����Ȃ��B
�v�t���E�E�q��Ă̊O�������ł��Ȃ��B
�@�@�@�@�q���̔Y�݂���ʂ̖��͊O���ł��Ȃ��B���e�q�����������A�Ԃ���@��K���B
�@�@�@�@�ŏ��͂ǂ����Ă������킩��Ȃ��B�����R������ł����Ӗ��ł�����߁B
�@�@�@�@���X�Ɍ����p���ɁB
�@�@�@�@�Ō�͑A�]�ɁB
��������w�Z�s����ʂ��āA���̒��������̑����q�����Ȃ��Ɗm���Ȑl�Ԑ��ɂȂ�Ȃ��B�w�͂͐l�Ԑ��̒��ł������������B
�����������蒣���ĂȂ���Ίw�͂̎}�����L�����Ƃ��Ă������B
�N���u�����͏T�R��`�S��B
�T�b�J�[�A�o���[�{�[���A�o�X�P�b�g�͂͂����̂Ƃ��닭���B�s�łQ�O�ʈȓ��ɓ���B
�w�Z�s���������܂ł̉ߒ��ŁA�N���X���ł����Ԃ������A�c�_�����Ă���B���ꂪ�厖�B�����Ղ����R���P�N�Ԃ����ď������Ă���B
�����Ղ������̐l�i�`���ɉe���������k�ɃA���P�[�g�ɑ��āA���R�͂W�R���̐��k���Ӗ�������Ƃ��Ă���B
���w���ꂽ��A�N���u������w�Z�s����ʂ��Đl�Ԃ̊������č����ė~�����B
�T�@���������@���V�搶�E�E���w�ґI�l�ɂ���
���N�̐�����̐\���҂͂Q�U�W�W���ō�N�̂S�������B
�}��ɂ͋��ȏ��������Ă���搶�����l������B�ǂ����Ȃ璘�҂ɏK���������悢�B
�����}��̋��t�͋��ȏ��������Ă͂��邪���ȏ����قƂ�ǎg��Ȃ��B
���̋��ȏ��ɏo�Ă����i�I�Ȏ��Ƃ�����Ă���B
��{�I�ɂP�������A�Q������������B
�P�������E�E���I�i�����Q�N�Ԃ͍s���Ȃ������j
�Q�������E�E�w�͌����ƕ��𑍍��I�ɕ]���B
�菑�͂P�P���Q�T�����玖���������ɂĖ����Ŕz�z�B
�菑�̎�t�͂P���X���A�P�O���B�X�F�O�O�`�P�T�F�O�O�B�����͍��G����̂łQ���ڂ𗘗p���Ă��������B
�P�������i���I�j�͂P���P�V���B��W����P�Q�O���̖�V�{��ڈ��ɍ��i�҂��o���B
�����Q�N�Ԃ͉���҂��V�{���Ȃ������̂Œ��I�����{�����B
�Q�U�N�O�ɕ����Ȃ���S���̕����w�Z�ɑ��Ē��I�����{����悤�����w��������B���݂������Ȋw�Ȃ̊NJ��ɂ���w�Z�Ƃ��Ē��I��]�V�Ȃ�����Ă���B
���I���ɂ͂P�l��������Ȃ��B
���I�ʉߎ҂͂P���Q�Q���A�Q�R���ɏZ���[�Ə��w�Z����̕����o�B
���͂P�S�N���猒�N�Ɋւ��鎖���̗����Ȃ��Ȃ�B���N�Ɋւ��Ĕz�����ė~�������Ƃ�����ΊY�����ɋL������B���N�ɂ���č��ۂŕs���v���邱�Ƃ͑S���Ȃ��B
�O�Q�N�͂قƂ�NjL���͂Ȃ������B
�Q�������͂Q���R���B�X�F�O�O�`�P�Q�F�S�O�B
�e���ȂS�O�����B�e�P�O�O�_���_�B
�����̓��e�́A���w�Z�̊w�K�w���v�̂Ɋ�Â��Ă��邪�A�P�Ȃ�f�ГI�Ȓm�������łȂ��Ȋw�I�A�_���I�Ȏv�l�͂�₤���̂���A�Ƒn����K�v�Ƃ���悤�Ȃ��̂̏o��ɂƂ߂Ă���B
���Ȃ̂S�O�O�_�{�����P�O�O�_�Ɋ��Z�����T�O�O�_���_�ő����I�ɍ��ۂ�����B
������Ε]���ɕς�������A���w�Z�ŏ��w���炵���w�Z�����𑗂��Ă������ő����B
�O�Q�N��������
�P������Ґ��@�V�X�S
�Q���o��Ґ��@�V�U�U
�Q���Ґ��@�U�P�R
�Q�����i�Ґ��@�P�R�Q
��N�P�O�����̓��w���ގ҂��o��B
�J��グ���Җ�P�O���B���\�������B�ŗX���B
���ގ҂��o�Ē�����P�Q�O�����������炻�̓s�x�J��グ���s���B
�O�Q�N�͂P�P���ɌJ��グ���҂̘A���𑗂�B
�O�Q�N�͂P�R�Q�����P�V�������ށB���҂̒�����U�������w�B�J��グ���i�����ގ҂͂T���B�O�Q�N�͂��܂��܂P�P���S���ɌJ��グ�̘A�����������B
�J��グ���i�҂ƒʏ�̍��i�҂Ƃ̐��т̍��͂����͂��B���w��̐��тɂ����͂Ȃ��B
�J��グ���i�ł����M�������ē��w���ė~�����B
�Q���X���i���j�ɍ��i�Ҏ葱������B����Ɍ��Ȃ���Ǝ����I�ɓ��w�����ނ������̂Ɣ��f����B
�o�莑�i�ɒ��ӂ��B
���w��A���w�ݐЎ��ɒʊw���O�ɓ]�o�����ꍇ�͍ݐЂ����������B
�A��������ʎ��Ɠ��������ŕʘg�͂Ȃ��B
���������̒��s�ǂ̏ꍇ�͕ی����ł̎��\�Ȃ̂ʼn����Ȃ��\���o�Ă��������B
���������͂���������ɂ͂���ƕی�҂Ƃ͉�Ȃ��Ȃ�B��������ΌW�̋����ɐ\���o�Ă��������B
���w�҂̊w��
�@���w�͏��o��ŔN�z�@��P�W�O�C�O�O�O�~
���k�̊w�Z�������x������㉇��
�@������@�R�O�C�O�O�O�~
�@���@�@�N�P�C�O�O�O�~
�@��t���@�Q�T�C�O�O�O�~�ȏ�
http://home.catv.ne.jp/dd/tukukoma/hp/index.htm
�˕����@���R�����W����
�P�P���P�X���i�j�`�Q�Q���i���j�@�P�R�F�R�O�`�P�U�F�R�O
���w���̎��R������i����A���܍���͂��ߗ͍�A���j�[�N�ȍ�i�����̊��ԓW������Ă���B
http://www.toho.ed.jp/curriculum/curriculum.html#���R����
�����H��t���@�O�R�N�����v��
�P��@�Q���Q���@�j�q�P�O�O���@�Q�ȂS��
�Q��@�Q���S���@�j�q�@�S�O���@�Q�ȂS��
�R��@�Q���U���@�j�q�@�S�O���@�S��
���w�葱�͊e��Ƃ��Q���P�T���P�O�F�O�O�܂ŁB
�w�Z������
�P�P���P�V���i���j�@�P�O�F�O�O�`�@�e���Ȃ̐���������ݒu
�@�P���P�P���i�y�j�@�P�S�F�O�O�`�@�������O�E�X���Ƒ�����
http://www.musako.ed.jp/
�_�ސ�w���@�I�[�v���L�����p�X�i��S��j
�P�P���R�O���i�y�j�@�P�O�F�O�O�`�P�Q�F�O�O�A�P�R�F�R�O�`�P�T�F�R�O
�ی�Ҍ����w�Z��������J��
���O�̐\���͕s�v
���Ƒ̌�
�@�p��ŗV�ڂ��i�p��ȁj
�@�p�Y���Œ��w���w�Ƀ`�������W�i���w�ȁj
�@����������u���i���ȁj
�@�������ɒ���
�@��
�N���u�̌�
�@�\�t�g�e�j�X��
�@�o�X�P�b�g��
�@�o�g����
�@������
�@�A�j���[�V����������
�@��
http://www.kanagawa-kgs.ac.jp/
�����w���@������������
�����̎��Ɠ������Ŗ͋[���������āA���̉��������B
�����@�P�Q���Q�P���i�y�j�@�X�F�O�O�`
�ꏊ�@�����w��
�������@�M�L�p��
�Ώہ@�����w���̈�ʎ��l���Ă���U�N��
�\�����@�@����̐\�����ɋL���̏�A�X���܂��͂e�`�w
http://www.int-acc.or.jp/senzoku/
�������@�O�R�N�����v��
�P��@�Q���P���@�ߑO�@���q�R�O���@�Q��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ߌ�@���q�Q�O���@�Q��
�Q��@�Q���Q���@�ߑO�@���q�P�O���@�Q��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ߌ�@���q�P�O���@�Q��
�R��@�Q���S���@�ߑO�@���q�P�O���@�Q��
�P��ߌ�͓��Ґ������B
�@�`���ҁ@���w���ƂR�N�Ԃ̎��Ɨ��Ə�
�@�a���ҁ@���w���ƂP�N�Ԃ̎��Ɨ��Ə��i�N���Ƃ̌������ɂ��X�V����j
�@���Ґ������ƈ�ʓ����̖����e�i��Փx�j�͈قȂ�B
�@���w��̃N���X�Ґ������Ґ��N���X�ƈ�ʃN���X�ɕ������B
���w�葱�͊e��Ƃ��Q���V���P�V�F�O�O�܂ŁB
�w�Z������
�P�P���Q�P���i�j�@�P�O�F�O�O�`�P�Q�F�O�O�@���ƌ��w����
�P�Q���P�S���i�y�j�@�P�O�F�O�O�`�P�Q�F�O�O�@�C���O���b�V���f�C�̌��w����
�@�P���P�P���i�y�j�@�P�O�F�O�O�`�P�Q�F�O�O�@�������O�A�h�o�C�X
http://www.nakamura.ed.jp/
�i�����@�O�R�N�����v��
�P��`�@�Q���P���@�@�@�@�j���X�O���@�Q�ȂS��
�P��a�@�Q���P���ߌ�@�@�@�@�@�@�@�@ �Q��
�Q��@�@�Q���Q���ߌ�@�j���S�O���@�Q��
�R��@�@�Q���R���@�@�@�@�j���P�O���@�Q�ȂS��
���ʁ@�@�Q���T���@�@�@�j���P�O���@�@����܂��͎Z���@�ʐ�
�P��͂`�E�a���킹�Ēj���X�O���̒���B
�P��a�͊w�Z�̑��ɒr�܂̃z�e�����g���|���^����������B
�P��a�̏�ʐ��ɓ��Ґ����i�s�B
���ʓ����ł͖ʐڂ���B
�w�Z������
�P�Q���P���i���j�@�P�S�F�O�O�`
�@�P���T���i���j�@�P�S�F�O�O�`
http://www.shukutoku.ed.jp/main.html
�ˈ��w���@�w�Z��������i�O�Q�N�P�O���P�X���j
�X�F�O�O�`�P�O�F�Q�O�܂ł��Q���ԑ����̎��ƌ��w�A���̌�A�������A���z�[���ɂĐ�����B�ߑO���̒j�q���̂ݎQ���B
�T�@��������e
�@�z�z�����Ɠ����e�̂��߁A�z�t������蔲�����f�ځB
�i�ڎ��j
�P ���w�Z�E��������w�Z�̊F����w�@�@�Z���@�L�쏸
�@�i�P�j���Z�Ƃ̈Ⴂ�@�@�@������e�Ǝ{�݁E�ݔ��B
�@�i�Q�j����ڕW�@�@�@�����|�O������{�Ƃ��Ắu������́v�̗{���B
�@�i�R�j�i�w���ʁ@�@�@���ʂƂ��Ƀg�b�v�̐��ʁB
�@�i�S�j������e�@�@�@�ق�Ƃ��́u�m�v�̕����B
�Q �ˈ�������F����w
�@�i�`�j�ˈ��w���ɂ��������Ē�������������e
�@�i�a�j���E�{�݁E�ݔ�
�@�i�b�j��������w�Z
�@�i�c�j�ˈ��w���̑�w��������
�@�i�d�j���N�x�����ɂ���
�i�{�ҁj
�P ���w�Z�E��������w�Z�̊F����w�@�@�Z���@�L�쏸
�@���{�̋���͑傫�ȓ]�����ɗ��Ă��܂��B���w���獂�Z�Ƃ����厖�Ȏ��Ɉ��S���ĔC������w�Z���ǂ����A���w�ł͐e���q�ǂ��̈ꐶ�����E����w�Z���A���ꂼ��̖ڂŊm���߂邱�Ƃ��K�v�ł��B����ɂ́A�ӂ���̊w�Z�ł̐����k���������Ă���Ă��邩�ǂ����Ƃ������ƂƁA�U�N��̐i�w���т��ǂ������m�F���邱�Ƃł��B
�@�ˈ��̑�w�i�w���т́A�S���Ńg�b�v�N���X�ł��B���т̗ǂ��q�����łȂ��A�����鐬�т̎q��L����������A���̐��ʂ��\�������߂Ă��܂��B��N���j�q���͂S�N���X�́w��������w�Z�x���J�݁A�܂����q���͍��N���w��������R�[�X�x�����N���X�ݒu���܂����B
�@���܂ł̒j�����w���ɂ��Ă��A��������w�Z�Ƃقړ����J���L�������Ŗ����Ȃ��w�͂̂��w�����A�����y���݂Ȃ�����w���u�m�̍\�z�v�����Ă���܂��B
�i�P�j���Z�Ƃ̈Ⴂ�@�@�@������e�Ǝ{�݁E�ݔ��B
�@������e�Ǝ{�݂����Z�Ƃ͈Ⴄ�̂ŁA���k�̊w�͂Ƒ̗͂��L�сA�i�w���т́A�S���g�b�v�B�N���u����������S�����x���̊���B�L���ȏ��Љ����B
�@ �ׂ������炪�ł���̂́A��^�Z�ŁA���ʋ����ȊO�̍L����Ԃ̒��ɍŐV�̂k�k�����E�o�b�����Ȃǂ��낢��̐ݔ��������Ă��邩��ł��B���̎{�݂̒��ŁA�p��i���w���N�������j�E���w�E�Õ������i���w�R�N����j�ɂ��Ă͔\�͕ʎ��ƁB���̑��̋��Ȃ̓z�[�����[�����ƂŁA�w�͂⋳�Ȃ̐��i�ɑ����đg�D�I�ȃJ���L�������Ŏw�����܂��B���Z�̏㋉�w�N�ɂȂ�ƁA�����E�����̕��n�E���n�ƁA�R�[�X�ʂɋ��Ȃ��Ƃ̔\�͕ʂɕ�����A����ɋ��Ȃɂ���ẮA�\���l�̎��ƂƂ����ו������ł��܂��B��������̋��������邪��ł��邱�ƂŁA���������ׂ�������́A���Z�ł͂ł��܂���B
�A
���E�����ꂼ��ʂ̓��ʋ����E�}���فE�^����E�̈�فi�����̒�����эZ�́A���Z�Ƌ��p�j�̂ق��A�����z�[���ȏ�̃������A���z�[���ňꗬ�̌|�p�̊ӏ܂��ł��܂��B�w�����p�̑�̈�قɁA��N�͒m�̓a���������A���A�J�f�~�E�����������܂����B�܂��A�ˈ����l��w�̋����ɂ�鐔�w�◝�Ȃ̃Z�~�i�[�ɒ��w�����Q�����Ă��܂��B
�B �j�����w�@�@���w���獂�Q�܂ł͒j���ʊw�ŁA���R�ɂȂ�Ɛi�w���Œj�����ꏏ�ɂȂ�A��L�̂S�R�[�X�ɕ�����܂��B�������A�z�[�����[���͍��P���獂�R�܂ŕς��܂���B���R�ɂȂ��Ă��A���q�͏��q�����̃z�[�����[���ł��B�N���u�������ʂł��B�j�q�̗ǂ��A���q�̗ǂ���L���A�����w�����������肷�邽�߂̂����A�j�����w�ł��B
�i�Q�j����ڕW�@�@�@�����|�O������{�Ƃ��Ắu������́v�̗{���B
�@�����|�O���@�@���������Ƃ������A�D���Ȃ��Ƃ��y���߂�N���v�����ȂǁA�w�Z�������̒��S�ɂȂ�܂��B�m�ɍs���Ă������̂ł����A�s���҂͂قƂ�ǂ��܂���B
�@�S�N���̈ꗬ��w���i�ɕK�v�Ȋw�͂����邽�߂ɁA�͂̑���Ȃ����k�̊w�͂�āA����ɐL���A�͂�������b���鋳������܂��B
�@����A�L�������g���āA�X�|�[�c�ɁA�N���u�����ɁA�D���Ȃ��Ƃ��y����ł�鋳������܂��B�ˈ����l��w�̋����̃Z�~�i�[�ȂǂōL�����{���g�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B
�@�������A���z�[���ł̌����Ɛ��k�̔��\�A���y�E���p�̓��ʋ����ł͐��k���y���݂ɂ��Ă�����Ƃ��s���Ă��܂��B�����̎��Ƃ��Z�����ƎQ�����ɁA�ݍZ���̕���ƈꏏ�Ɍ��ĉ������B���O�̐\���݂͂���܂���B������t�ɐ\���o�ĉ������B
�i�R�j�i�w���ʁ@�@�@���ʂƂ��Ƀg�b�v�̐��ʁB
�@�𒆊j�Ƃ���S�l����E�E�{�Z�قǑg�D�I�ɑ�w�����ɑ�����𐮂��Ă���w�Z�͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�@�i�w���сE�E�j���S�����S�N���̈ꗬ��w�ɓ��w�u�]���A�܂�������ʂ����Ă��Ă�����т������Ă��܂��B
�@��w�����ɐ�������ƂƂ��ɁA�Q�P���I�����[�h���鍂簂ȑn���I�l�ނ���ĂĂ���V�G���[�g�����ڎw���Ă��܂��B
�i�S�j������e�@�@�@�ق�Ƃ��́u�m�v�̕����B
�@���{�l�̔\�͂͂ǂ�ǂނ��Ă���E�E�u��Ƃ�̋���v�Ƃ������̂��ƂŁA�啝�Ɋw�K���Ԃ�����Ă��܂��B�����̎��Ԃ�������_�ŁA���{�͍��ۋ����ɔj�ꂽ�����R�A���{�̍œ�֑�w�ł��A�����̑�w�ɕ����Ă���̂�����ł��B
�@�ˈ��̋���́A�ق�Ƃ��́u�m�v���q�ǂ��ɋ��炷�邱�Ƃ����w���Ă���܂��B�ËL�łȂ��ق�Ƃ��́u�m�v��g�ɂ������邽�߂ɁA�ˈ����l��w�̋����𒆐S�Ƃ������t�̃v���W�F�N�g�`�[����Ґ����A�J���L�������쐬�Ɏ�肩�����Ă��܂��B
�@��������w�Z�̏ꍇ�A�J���L�������̑g�ݕ�����r�I���R�ɂł��܂��B�e���Ȃ̊w�K������E�p�������A�n���I�A������ۂ��Ƃ�S�|���A�q�ǂ������̋������������ĂāA�ǂ�ǂ�z���ł��鋳����e�ł��B�܂��A��������͈̔͂��L���A�N�w�̎��Ƃ�g�ݍ��ނ��Ƃɂ���āA���ȁA�Љ�A�����A�o�ςƘA�������Ă̐l�ԋ�����s���܂��B
�@�]���̕��^������ы���ɂ����_�͂�������A���̈ێ��E���W�ɂƂ߂邱�Ƃ͂������ł��B�ˈ��͑�^�Z�ł��B�q�ǂ������̂��낢��Ȕ\�͂��u��āv�u�L���v�����āu�b����v�Ƃ���́w��x���ˈ��͂��������Ă���̂ł��B
�Q�@ �ˈ�������F����w
�i�`�j�ˈ��w���ɂ��������Ē�������������e
�P�D�ڕW�Ƃ���Ƃ���@�@�ꗬ��w���i�Ɛl�ޗ{���̂��߂̖L���ȋ���
�i�P�j���ꂼ��̊w�N������L���Ɋy��������Ȃ���A��]�����w�ɐi�w���A�e�l����]����Љ���������́i�m�́E�̗́E����́E���_�́j��{�����Ƃ��ł���悤��������Ă��܂��B
�i�Q�j�C���[�W�Ƃ��ẮA�G���[�g����B
�u�m�v���鋳��B�����ɗ����ꂸ�A�j���Ƃ����ꂼ�ꂪ�V���������n��͂����Ă�悤�ɂ��鋳��B�p�v���b�N�E�X�N�[���i�C�M���X�j�A�v���b�v�E�X�N�[���i�A�����J�j�Ɠ����u�m�v���邱�Ƃ�ڎw���Ă��܂��B
�i�R�j�̂т̂тƂ������͋C�̒��ŁA���ꂼ��̐��k�̔\�͂����A��āA�L���A�b���鋳������Ă�����т́A���Ɍ����Ȃ��Ƃ̎����������Ă��܂��B
�Q�D����@�@�L���ȋ���̓��e�@�@���k�̐����Ƌ��t�̎w���̂����
�i�P�j�����̂�����E�E�����A�w�Z�ɗ��邱�Ƃ��y���݂Ƃ������Ƃk�͎����Ƃ��Ē͂�ł��܂��B
�E�����y����ł��Ă��܂��B�i�ꂵ�����Ƃ�������z����y���݁A�Q�[���̂悤�ɕ�����y���݁A�m�I�Ȋy���݁j
�E�X�|�[�c���y����ł��邽�߂ɁA�N���u�����������A���w�����^�����邽�߂̐�p��Ԃ��m�ہB
�E�����̍D���Ȃ��ƁA�S�̐[�����Ƃ��y����ł��鐶���́A���n������������Ȃ��Ƃɕ\���Ă��܂��B
�i�Q�j���Z�͓����i�w�҂ƊO�����w�҂قړ����̐��k�Ńz�[���E���[�������A�p��͓��O�����̃��b�X���Ґ��A���w�͍��Q�܂œ��O�ʂ̃��b�X���Ґ��Ŋw�K���Ă��܂��B
�i�R�j���t�̎w��
�E���̎w���͂��ׂĊw�Z�A���t�����܂��B�m�A�\���Z�͕K�v�Ƃ��Ȃ����т������Ă��܂��B�����̐i�w�Z�ł́A�قƂ�ǂ��ׂĂ̐��k���\���Z�Ŋw�K����A�_�u���E�X�N�[�����i�w�Z�̎��Ԃł��B
�E�w���̐ӔC���m���@�@���k���ӂ����Ƃ������t�͋�B�ӂ����������t�̐ӔC�Ƃ����w�����j���m�����Ă��܂��B
�i�S�j�j�����w
�ʊw�A���w�̒������Ƃ�A���Q�܂ł͕ʊw�B�L�����p�X�A�Z�ɂ��ʁB���R�ɂȂ�ƃz�[���E���[���͒j���ʂł��邪�A�w�K�͎u�]�R�[�X�ƃ��b�X���ɂ�苤�w�B
�R�D�m��̋�̓I���@
�i�P�j�\�͕ʎw��
���{�ł͍ł������A�܂��A�ł��V�������@�ł̔\�͕ʎw���i�p�E���𒆐S�j�����Ă��܂����B�킩����ƁA�L�����ƁA�b������Ƃ��s���A�w�͂��Œ肵�����̂ƌ��܂���B���Ίw�͕͂K���L�т�̂ł��B���l�͕��̈ꗢ�ˁA�ǂ�ǂ�ς��܂��B���l�����z���邱�Ƃł��B
�i�Q�j���B�x����
���t�́A���������Ƃ̍Œ�V�O���k�Ɋw�͂Ƃ��Ē蒅����悤�w�����܂��B���ӂȋ��Ȃ�L���A���ׂĂ̋��Ȃ𐅏��ȏ�ɂ��邽�߂ł��B�����B�̉Ȗڂɂ��ẮA���ȒS�����t�̐ӔC�Ŏw�����܂��B
�i�R�j���e�X�g
�����ԁA�S�Ȗڂɂ��A�O��K��������蒅�����邽�߂̏��e�X�g���s���܂��B�]���̂��߂̃e�X�g�ł͂���܂���B�͂����邽�߂̕��@�ł��B
�i�S�j�����I�ȕ������邽�߂̊w�K���Ԓ���
���̂ł��鐶�k�́A���Ԃ������ĕ����Ă��܂��B�ʂ��K�v�ł��B�₪�ėʂ����ɕς��܂��B�������A�����ς���Ă��A����Ȃ�̗ʂ�K�v�Ƃ��邱�Ƃk�͒m��悤�ɂȂ�̂ł��B�w�K���Ԓ����\�B���b�X���ʁA�N���X�ʂɕ����Ԃ��킩��A�����I�ȕ��������邽�߂ł��B�f�����w�͂����̂������Ƃ������Ƃ���̓I�ɕ�����܂��B
�i�T�j�V���o�X�i���ƌv��j
���Ƃ����邽�߂̃��j���[�A�d�l���A�_�ł���V���o�X�����J�B���k�ƂƂ��Ɏ��Ɠ��e�̊m�F�ƌ����}��܂��B���k�̔ᔻ�E��]���Ƃ߂Ă̎w�������܂��B���̕��@�́A���{�̐S�����w������Ǝ��{���n�߂����@�ł��B
�i�U�j��w�����ɂ����ʍu�K
���H�喼�_�����Ŗ{��w�����ɂ�鐔�w�E�����E�������邢�͖@�w�̓��ʍu�K�ŁA��w�̂��߂̕��Ƃ͈�����A�L���A�[���w�K������@���݂��Ă���܂��B
�S�D�Љ���w���E��������@�@�m�[�u���X�E�I�u���[�W��
�i�P�j�d�ԁE�o�X�ł̒ʊw���̃}�i�[�A�����ł̎��Ƃ��鎞�̃}�i�[�i��w�ł�������̑������Ƃ��Q����Ă���j�ȂǁA�Љ���������ł̖o���w�Z������ʂ��Đg�ɂ���悤�w�����Ă��܂��B
�i�Q�j�T�}�[�E�L�����v�i�o�R�j�V���k�R���S���l�A�E�C���^�[�E�L�����v�i�X�L�[�j�P���k�S���T���l�̏W�c�����ł��B��͐��k�̊��ɂ�铢�_��A���̑������{���Ă��܂��B
�i�R�j�Љ��d�����@�@�ċG�S���k�ɂ�鑽����͐�~���|�i�j�q�j�A�V�l�z�[���K�ԁi���q�j�A��������A���̑������I�ȃ|�����e�B�A���������サ�Ă��܂��B�C���^�[�A�N�g�E�N���v�A�ԏ\���ψ���Ȃǂɂ����āA�L�u�̐��k�����ʂȊ��������Ă��܂��B
�T�D���k����@�@���k��̉�A�����̂Ȃ�葽��
�w�Z���y�������邽�߂̃N���u�����A�����ՁA�z�[���s��
�@�N���u�����i�j�q�j
�̈�n�F�����A�_���A�T�b�J�[�A���O�r�[�A�o�X�P�b�g�E�{�[���A�n���h�E�{�[���A�o���[�E�{�[���A��싅�A�싅�A�d���닅�A��닅�A���㋣�Z�A���ю����@�A�o�h�~���g���A���j�A�̑��A
�����n�F�u���X�o���h�A�ʐ^�A�V���E�C�ہA�͌�E�����A�����A�A�}�`���A�����A���p�A���|�A�S�������A���w�A�p��b�A���y�����A�d�Z�@�A�C���^�[�A�N�g�A�V�~�����[�V�����A���y�A�����A�y���y�A�R���s���[�^�[�A�����y�A�A�E�g�h�A�A�A�j���A�O���[�N���u�A
�A�N���v�����i���q�j
�̈�n�F�����A�_���A�o�X�P�b�g�E�{�[���A�n���h�E�{�[���A�o���[�E�{�[���A�싅�A�d���닅�A��닅�A���㋣�Z�A���ю����@�A�o�h�~���g���A���j�A�|���A�_���X�A�̑��A���N���X�A�\�t�g�{�[���A
�����n�F�NJy�A���y�A�����A���邽�A�ʐ^�A���p�A�����A���|�A�S�������A�����A���w�A�����A�����A��|�A���y�����A���挤���A���|�A�����A�ؓ��A�T�C�G���X�N���u�A���j�A�ÓT�����A���������AⵋȁA�y���y�A�C���^�[�A�N�g�A
�E���ޕ��͌l�̈ӎu�A��]�Ŏ��R�ɂł��܂��B
�E�L�u�ɂ��Љ��d�����@�@�C���^�[�A�N�g�E�N���u��ԏ\���ψ���Ȃǂ�����܂��B
�B������
�ˈ��t�F�X�e�B�o���i�S�w�������Ձj�̈�Ƃ��Ă̒j�q�͖Q�čՁA���q���a�P�Ղ��A���k�̊��Ŏ��H���܂��B���k���s�ψ����ƈψ��͑吨�̗����҂�����̂ŁA�I���Ō��߂܂��B�e�[�}���������ȂǁA���k�̑n���������̏�ł��B
�U�D�w�Z�s��
�i�P�j�������A���z�[���̒�������B
�ꗬ�̉��y�A�����A�f����ӏ܂��Ă��܂��B�m���A�̕���A���c���|�A�����I�y���A�\�E�����A����A�W�����W���E�h���A���X�N���E�}�[���C����A�O�����~���[�E�I�[�P�X�g���A�X�y�C�������o���G�@��
�i�Q�j�ꗬ�l�ɂ��w�p�u���A����E���Ɛ��ɂ��u���B
�i�R�j�w���̈�Ձi�P�O�����{�j
�x�m�X�s�[�h�E�F�C�ł̑S�w�}���\�����́A���N���V���l�̍��ۑ������Z��𒆐S�Ƃ����w���̈�Ղɔ��W���܂����B���N�͂P�O���R�O���i���j�Ɏ��{�\��B
�i�S�j�ˈ��w���u���̉�v�i�P�P���R���j�w���ҁF�r�J�r����
����Ɛ��k�̎Q���ɂ��A�������A���z�[���ł̉��t��i�T�O�O�l�j�ł��B�ˋ���i��e�R�[���X�j�c�c�����w���ҁF�ҏG�K��
�V�D���ی�
���Z�ʼnp���Q���ȏ�̊�]�҂̒�����I���i��R�O�l�j���āA�Z�����w�i�R�O���j�ƒ������w�i�P�N�j�����{���Ă��܂��B�č��̃v���b�v�E�X�N�[���i�A���h�[�o�[�A�`���[�g�A�G�N�Z�^�[�A�N�b�V���O���j�ƌ������w�B���ɂ́A�č��A�C�r�[���[�O�̑�w�ɓ��w����҂����܂��B
�i�a�j���E�{�݁E�ݔ�
�P�D�j�q���Ə��q���̋��p�́A�����v�[���̂݁A����ȊO�͒j�����ׂĕʂł��B�}�����A�̊y���A���p���A�����E���w�E�����������A�k�k�����A�r�f�I�����A�R���s���[�^�[���[���A�̈�فA�H���܂ł��ׂĒj�����ꂼ���p�ł��B
�Q�D��^�Z�̐���
�z�[�����[�����Ƃƃ��b�X���i�p�E���j���Ɓk�������n�Ƃ̕��p�B���ɍ��Z�̃��b�X�����Ƃ͂T�O�`�Q�O�l�̕��ŁA���l�Ȏ��Ƃ��ł��܂��B����@��̏[���Ōl�w�K�A�O���[�v�w�K���ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�����Z�ł͂ł��Ȃ��@�\�I�ȋ�������Ă��܂��B
�i�b�j��������w�Z
�����Ȋw�Ȃ͂T�����ƐV����ے������N������{���܂����B�������A���E�̒��Ŋw�̓��x���_�E�������Ă����Ԃɂ��Ă̔ᔻ���L�����Ă��邱�ƂɑΉ����āA�����Ȃ͐V����ے��͍Œ���������̂ƍl����ς��܂����B���܂ł̒��w����ł͉p�E���͌������w�͊e�w�N�S����A�����͂U���Ԃ���Ă����̂ł����A����͂����Ȃ��ƕ����Ȋw�Ȃ͎w�E���Ă��܂����B�Ƃ��낪�A�V����ے��ł́A����ȏ�ɂ��Ă������Ǝ����A��������w�Z�Ƃ�����ы���ł͑O���i���w�j�E����i���Z�j�ƂȂ�܂����A������e�ɂ��đ啝�ȍٗʂ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B��������w�Z���Ȋw�Ȃł͋߂��S���ɂT�O�O���\��ł����A���w�̐i�w�Z�����邨���ꂪ����Ƃ����w�E����A�����̏ꍇ�w�͂ɂ����������Ă����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B�ˈ��͓��i���ɂƂ��Ă͏]����������тȂ̂ł����A�]���̈�ы���ł́A�{���̈Ӗ��Łh�n���I�ɍl���邱�Ɓh�Ƃ����̂���ϓ���A�Ⴆ�A�O�p�@�̕������Ă��Ă��A���炭����Ƃ���𒆒f���đ㐔���w�сA���炭����ƁA�܂����f���č��x�͊�����Ƃ�������ɁA���������w���̂��n���I�ɓ��ɓ���Ȃ��Ƃ������Ƃ������Ă��܂����B����́A�w�N���ƂɃJ���L���������g�܂�Ă������Ƃ��v���������̂ł����A���̒�������w�Z�ɂ�����J���L�������ł́A�U�N�Ԃ̈�т������Ƃ̒��ŁA�e�w�K���ڂ�����E�p�������A�n���I�ȘA������ۂ��Ȃ���w�����邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂��B
�@�ˈ��w����������w�Z�̍ő�̓����Ƃ��āA�{�w�����݂��Ă���ˈ����l��w�̋�����ɂ����Ƃ��������܂��B�ˈ����l��w�̋����A���̕������́A�O����A���H��A�}�g��Ȃǂ̋����������l�������̂ł����A���̌o�������w�ŕK�v�ȁu�m�v��Ǝ��̃J���L�������A���ȏ��A���W��ҏW���āA�����ɂ����狳���Ȃ���A�������A��w�����ɔ����鋳������܂��B
�@���̑��̒��w���w�҂̋���ɂ����w�ȂǁA�����J���L�������E���ނ�p����Ȃǂ��ĐV����������̂�����ƂƂ��ɁA���܂ł̊w�͂�����ɐL�����߂ɋ�����e��傫���ς��܂����B�V����ے������{���邽�߂̂T�����ł�����A����ȏ�̋�������邽�߂ɂ́A�T�����ł͐��k�̕��S���d���Ȃ�܂��̂ŁA�ˈ��ł͂T���������̂܂܍̂����邱�Ƃ͂ł��܂���B�܂��A������w�̓������߁X�T���ȂV�ȖڂƋ�������邱�Ƃɔ����邽�߂ɂ��A�T�����͂��̂܂܍̂����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƍl���Ă��܂��B
�@�Ȃ��A���q���ł͍��N�̒��w�P�N���A�j�q�̒�������w�Z�ɏ����钆������R�[�X���P�N���X�ݒu���܂����B
�i�c�j�ˈ��w���̑�w��������
��w�������т͑S���Ńg�b�v�N���X�B�ˈ��ł͐��т̗ǂ��q�����łȂ��A�����鐬�т̎q��L����������A���̐��ʂ��\�������߂Ă��܂��B����ւ��S�X���B���H��͂Q�X���E�ꋴ��͂P�V���B�g�b�v�N���X�̐��k�����ʁA���ʎ҂��A�ǂ��̒����ɐi�w����������ʂ������Ă���Ƃ������тƎ����������Ă��܂��B�Ȃ��A���q�����ׂĂ̑�w�ŁA�g�b�v�N���X�̐��т������Ă��܂��B���̂��Ƃ́A�]��m���Ă��܂���B
�i�d�j���N�x�����ɂ���
�i�P�j�ȖڂƔz�_
�P ��������w�Z�i�j�q�j�@��������R�[�X�i���q�j
�i�P�`�R���Ƃ��j
�E�S�Ȗ�
�@�@����@�T�O���@�P�T�O�_
�@�A�Z���@���̂P�E�S�O���@�x�e�P�O���@���̂Q�E�S�O���@���v�Q�O�O�_
�@�B���ȁ@�S�O���@�P�O�O�_
�@�C�Љ�@�S�O���@�P�O�O�_
�Q �]���^���w�Z
�i�P�E�Q���j
�E�Q�Ȗڌ^
�@�@����@�T�O���@�P�T�O�_
�@�A�Z���@���̂P�E�S�O���@�x�e�P�O���@���̂Q�E�S�O���@���v�Q�O�O�_
�E�S�Ȗڌ^
�@�@����@�T�O���@�P�T�O�_
�@�A�Z���@���̂P�E�S�O���@�x�e�P�O���@���̂Q�E�S�O���@���v�Q�O�O�_
�@�B���ȁ@�S�O���@�P�O�O�_
�@�C�Љ�@�S�O���@�P�O�O�_
�@����E�Z���̍��v�R�T�O�_�ŁA�S�Ȗڌ^�E�Q�Ȗڌ^�����̍����_���������̖�T����I���B�c��̖�T�����A�c��̂S�Ȗڌ^������I���B
�E�p����ʎ^�i�P���̂݁j
�@�@�p��i���w�ے��I�����x�̓��e�j�@�U�O���@�P�O�O�_
�@�A�ʐځi���{��ōs���j
�i�R���j
�E�S�Ȗڌ^
�@�@����@�T�O���@�P�T�O�_
�@�A�Z���@���̂P�E�S�O���@�x�e�P�O���@���̂Q�E�S�O���@���v�Q�O�O�_
�@�B���ȁ@�S�O���@�P�O�O�_
�@�C�Љ�@�S�O���@�P�O�O�_
�i�Q�j��������
�ꎟ�@�Q���P���i�y�j
�@�j�q�@��������w�Z�@�@��T�O���@�@�]���^���w�Z�@�@��P�R�O��
�@���q�@��������R�[�X�@��P�O���@�@�]���^���w�Z�@�@��X�O��
�@�Q���R���i���j
�@�j�q�@��������w�Z�@�@��T�O���@�@�]���^���w�Z�@�@��X�O��
�@���q�@��������R�[�X�@��P�O���@�@�]���^���w�Z�@�@��V�O��
�O���@�Q���T���i���j
�@�j�q�@��������w�Z�@�@��T�O���@�@�]���^���w�Z�@�@��S�O��
�@���q�@��������R�[�X�@��P�O���@�@�]���^���w�Z�@�@��Q�O��
�i�e�j�O�Q�N�������ʏڍ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��W�l���@�@����Ґ��@�@�Ґ��@�@���i�Ґ�
�ꎟ�@�j�q�����@�@�@��@�T�O�@�@�@�R�O�S�@�@�@�@�@�Q�W�T�@�@�@�@�@�@�T�O
�@�@�@�@�j�q�]���Z�@ ��P�R�O�@�@�@�S�S�P�@�@�@�@�@�S�P�S�@�@�@�@�@�P�T�O
�@�@�@�@���q���@�@�@�@ ��P�O�O�@�@�@�P�U�X�@�@�@�@�@�P�T�W�@�@�@�@�@�P�O�O
�@�j�q�����@�@�@��@�T�O�@�@�@�U�U�U�@�@�@�@�@�S�T�V�@�@�@�@�@�@�W�P
�@�@�@�@�j�q�]���Z�@ ��@�X�O�@�@�@�W�O�W�@�@�@�@�@�T�P�R�@�@�@�@�@�P�U�X
�@�@�@�@���q���@�@�@�@ ��@�W�O�@�@�@�R�P�T�@�@�@�@�@�P�T�T�@�@�@�@�@�P�O�P
�O���@�j�q�����@�@�@��@�T�O�@�@�@�U�S�T�@�@�@�@�@�R�V�W�@�@�@�@�@�@�X�O
�@�@�@�@�j�q�]���Z�@ ��@�S�O�@�@�@�U�V�U�@�@�@�@�@�R�S�V�@�@�@�@�@�@�W�R
�@�@�@�@���q���@�@�@�@ ��@�R�O�@�@�@�Q�P�U�@�@�@�@�@�@�T�U�@�@�@�@�@�@�R�U
�k�Q�l �ҎG��
�@�܂��A�O��Ƃ��čēx�q�ׂĂ����˂Ȃ�Ȃ��̂́A�҂͓y�j�̌ߌォ����Ƃ����������߁A�X������10��20���܂ł̒j�q���̎��ƌ��w�݂̂����s���Ă��Ȃ��B����āA�����ŏq�ׂĂ��鎄���͂����܂Œj�q�̐i�w��z�肵����ł̎G���ł���B
�P �J���L��������`�̌���
�@���ƂQ�������̓��e��������蒆�w�R�N�܂ł̒i�K��ǂ��Č��w�ł����̂͂Ȃ��Ȃ��悩�����B�����Ŋ��������Ƃ͓����B��́A���Ǝ��Ԑ��ɂ��ے������悤�ɁA�ˈ��́u���v�́A�܂��Ɂu�ׂߋ�����v���̂ł������Ƃ������Ƃ��B�Ƃ��ɏ]���^���w�̊w�K�͂�����ƃJ���L���������g�܂�A����e�X�g�ŔN�S��N���X��30��������ւ��Ƃ����ē��������Ői�s���Ă�����e�ɃY�����Ȃ��B���������œ����e�̎��Ƃ��i�s���Ă���B�������A���Ƃ��Ήp��Ȃ�A�������@��\�������グ�Ă��Ă��A�P�ꃌ�x���≞�p�͈͂ɉϐ�������A�N���X�̎���ɉ������Ή����Ȃ���Ă���B�q�ǂ����g�����m���o�����Ă���ƁA���̂�����̃N���X�Ή��͎�����邩������Ȃ��B����ނ��Ƃ����m�ł����Łu�ׂߋ�����v�ƕ\�������̂́A�����̎��ƂɎI�Ȋ��o����������������ł���B�J���L�����������R�Ɛi�s����Ƃ������Ƃ́A���̕��A���t�̎��������������ɂ����B�������w�Ԃ̂̓J���L�������ł͂Ȃ��āA���t����ł���Ƃ����ϓ_�ɗ��ƁA���̎��Ƒ̐��ɂ͋^���������l������ɂ������Ȃ��B�܂��A�p�A���A���̃R�}���͑������A���A�ЂȂǂ͕W���v���X�A���t�@�ł���B��������R�}�ł̈�ۂł����Ȃ����A�ÓT��Љ�i�҂����w�����͓̂��{�j�E�n���j�̓J���L������������D�悵�Ă���悤�Ɏv���A���W�I�Ȃ������낳�͊������Ȃ������B�i���t�̓w�͂ɂ�������炸�A�Θb�^�Ɏ��Ƃ����W���Ă��Ȃ��̂�����Ǝv����B�j��b���甭�W�������p�́A�܂�A���_����t�B�[���h���[�N�ɗނ�����͍̂��Z���̑I���u���ł̗{���ւƂȂ���̂��낤���A��͂�u�`���S�A�\���Z�I�Ƃ������͂ʂ�������Ȃ��B���p�͉��K���S�A�m�[�g�ł͂Ȃ��v�����g����Ɋw�K���Ă�p���������Ƃ�����A���̊��������Ȃ�
�@�������A����A���ӔC�ȁu�l����������Ɓv���͎����I���Ƃ����l�������o����B�������Ƃ��\�������Ƃ����ʏ����C���^�[�l�b�g�ŏE���ē\��t���������̃��|�[�g���u�����I�Ȋw�K�v�Ȃǂƈʒu�Â��Ă��܂����Ղ���낤���͊������Ȃ��B�Z���̂��ƂΒʂ�u��b�w�͂̏[���v�Ƃ����Ӗ��ł́A�Z���^�[�����E���ʈꎟ�ȑO�́A�悢�Ӗ��ł̔����Ƌl�ߍ��݊w�K���s���Ă���킯�����A���Ȃ��Ƃ��q�ǂ��������������Ȃ��Ă͂����Ȃ����������Ȃ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B�������A�ꕔ�̎q�ǂ���������₨����ׂ�Ȃǖ��C�͉����Ă���悤�Ɍ������̂��m�������B�i���ƌ��w���s����ꍇ�A���t�����牉�o���s���A�ӂ���Ƃ������Đ��k����������Ă���̂��قƂ�ǂ̊w�Z�̎���B������A���̌�����A�����Ӗ��łƂ炦��A����ȊǗ����s���Ă��Ȃ��Ƒ����邱�Ƃ��ł���B�j
�Q ��������w�Z
�@��߂Ɋ��������Ƃ́A��������w�Z�̃J���L�������̃_�C�i�~�b�N���ł���B����̂��̍\���������Ƃ��͂����茩�����̂͒��w�P�N�̐��w�B
�@���t�A��g���X����u������ѐ��w�R�[�X�E���w�Q�v����������Ă���B�i�u�P�v�͍�N�����B�j���ǖ{�I�ȁu�`�����̂��ށv���Ȃ��Ȃ������[���B�U�N�Ԃ̓��e���T�N���Ŋw�ׂ���e�ɂȂ��Ă���B�w���v�̏����́A���ʂ������A�o���̈�����U�̂悤���D��������Ă��܂������w���A�S���Ǝ��̎��_�ōč\�z���Ă���B���M�҂͐��w�҂̎u��_��E�����H�Ƒ�w���_�����B���R���̋��ȏ��́A�����Ȋw�Ȃ̌�����Ă��Ȃ����A��������w�Z�̎��Ƃł͎g�p����Ă���悤���B���e�I�ɂ́A�����U�N���̓��e���u���Ǝ��ɂ��ẴR�[�X�v�Ɓu�}�`�ɂ��ẴR�[�X�v�ɓ��A���ۓI�Ȍv�Z�Ƌ�̓I�Ȑ}�`���W�Â��Ȃ���A���s���ċ����Ă���B���ɋ����[���e�L�X�g���B
�@�ċx�ݑO�ɍs���Ă����P�N���̐}�`�̎��Ƃł́A�u�p�ƒ����v�Ɂu�s�^�S���X�̒藝�v�������A���܂��܂Ȑ����Ŋe�ӂ̊W���v�Z�����A����ɁA�ӂ̒����P�̐����`�̑Ίp���̒������v�Z�����ꂸ�A���̒藝�Łu���[�g�Q�v�ɂȂ邱�Ƃ���A�������̊T�O���Ƃ炦�邱�Ƃ֔��W���ċ����Ă���B�i�w���v�̂ł̓s�^�S���X�̒藝�ƕ������͒��w�R�N�ŁA�ʁX�̕���Ƃ��Đ蕪���Ă������Ă���B�j����̎��Ƃł́A�����̎��Ƃŕ��������o�ꂵ�Ă����B���k�����̗L�������芵�ꂽ���̂ł���B�����鑤�̋Z�ʂ��������e�����A���̓W�J�̐����Ȃǂ��N���X�̎���ɂ��킹���Ă���A���ɒ��J�Ȉ�ۂ����B
�R ����̐�����E���ƌ��w�Ō��������́A�����Ȃ���������
�@�K�n�x�ʂ̊w�K���s���Ă���̂͐��w�E�p��ȊO�ɒ��R����̌ÓT�ł���B�܂�A����ȊO�̓z�[�����[���N���X�ɏ����Ă���킯�ŁA���ꂪ�q�ǂ������̊w�Z�����̊�ՂɂȂ��Ă���͂��ł���B������ł̓N���u�����̑��l���Ƃ����_����������Ă������A�N���u�����͔ނ�̐����̈ꕔ�ł����Ē��S�ł͂Ȃ��q�ǂ�������͂����B������ł́A�l�Ԃ̏W�܂�̏�Ƃ��Ă̋����̎��������ЂƂN���ł͂Ȃ������B
�@����ȃV�X�e���Ƃ��Ă̋ˈ��̊w�Z�����́A�����ǂ��\���I�ɂƂ炦�邩�ɃJ�M������悤�Ɏv����B�u�q�ǂ������̎�̐��v�Ƃ������Ƃ͊��Ɏ�C���t�������Ƃ����A�ǂ��Ɋ�������āu�^�Ɏ�̓I���v�ȂǂƂ����c�_��������Ƃ��Ă��A������l���u���̎q�͎�̓I���v�Ɗ�����q�ǂ��͂�͂�ꈬ��ł���B���w���Ƃ����̂͊T�ˌ�������鑤�̔N��w�ł��邵�A�����Ɏ�̐������߂邱�Ƃ͗��z�I�Ŏ����͂悭�Ă��A����Ӗ��ł͖��ӔC�Ȕ��z�Ƃ��v����B�J���L��������`�I�ȋˈ��́u��ꐫ�v�͔N��ɉ��������������ʂ����͂��ł���B�܂��A��������h������C���[�W���ꖇ�����A���܂��܂Ȋw�Z�̏�ʂ̂���u���ʂ̊w�Z�v�ł���͂����B�ʊw���鐶�k����������ɂ������v���B���܂��܂ȍl����u���̂���q�ǂ��������A���҂���F�߂��邱�ƂŃA�C�f���e�B�e�B�[���m�������Ƃ��Ċw�Z���@�\����Ȃ�A����ȁu��v�ł���Ԃ�A���́u���ҁi�������F�l�A���t�j�v�邱�Ƃ͏����Ȋw�Z���A�\���͍����B
�i�@�`�D�n���j
http://web.infoweb.ne.jp/TOIN-GAKUEN/
������
�K�n�x�ʋ������C�@������\�͕ʂɂR�i�K�Ł@�s����ψ���
�i�����V���@�P�P���R���j
�@�����s����ψ���́A���N�x��������������Z�̋�����\�͕ʂɂR�i�K�ɕ����A�e�i�K���Ƃɕʃ��j���[�̌��C���ۂ����Ƃ����߂��B�e�n�̊w�Z�œ������i�ޏK�n�x�ʊw�K�́u�搶�Łv�ŁA�����̗͗ʂɉ��������ߍׂ��Ȍ��C�����{����̂͑S�����B�Z����Ǘ��E���e�����̔\�͂肵�ĐU�蕪���邱�Ƃ���A�����g���Ȃǂ̔������\�z����邪�A�����̎�������̂��ߌ��C���[�������鎩���̂͑����A����̐��x�͑��̎����̂ɂ��e����^���������B
�@�]���̓s�̋������C�́A�Ζ��N���̓����������S���Q�����A��Ăɓ����v���O��������u������A�������g�Ɋ�]����v���O������I���Ă����B�������A��Ă̌��C�ł͊e������������ʂ̉ۑ�ɑΉ��ł��Ȃ����ƂȂǂ���A���ʂ��^�⎋���鐺���������B
�@���̂��߁A�V���x�ł͓����N��A�E���̋����ɁA�\�͂ɍ��킹�ĈقȂ���e�̌��C�����{����B�Ǘ��E���l���l�ۂ̒��ŋ�����]�����A�u��v�u���v�u���v�̎O�̃����N�ɕ�����B����ɋ��E�o���Q�`�P�O�N�̎��A�P�P�`�Q�O�N�̒����A�Q�P�N�ȏ�̃x�e�����ɕ����A���C���Ȃǂŗp�ӂ��ꂽ�����̌��C���j���[����A�Ǘ��E���l�ɂӂ��킵�����C�v���O���������A��u������B
�@�x�e�����ł��A�������k�̊w�K�w���ɖ�肪����ꍇ�͊�b�I�ȃv���O�������ۂ��A�t�ɗD�G�ƕ]�����ꂽ�����͑�w�@�̍u������u������A�����̊w�Z�̃��[�_�[�ɂȂ邽�߂̌��C��������B���C��́A����Ō��C�̐��ʂ���������Ă��邩�ǂ������Ǘ��E���]�����A���̌��ʂ��l���l�ۂɔ��f������Ƃ����B
�@�s���ς́u�����̎��������サ�A�q����ی�҂̊��҂ɉ�������͂����v�Ƙb���Ă���B
�@����ɑ��A�s���g�ɉ������Ă���j�����w���@�́u��������܂��Ȑl���l�ۂ����ƂɁA�����������N�������ĉ������錤�C�͕s�������A�F�߂��Ȃ��v�Ƙb���Ă���B
��w�Ŏ��ƎQ���@�w���u���̔N�ɂȂ��Ă܂Łc�v
�i�����V���@�P�P���Q���j
�@��w�ł��u���ƎQ�ρv�B�����o�ϑ�i�����s�������s�j�͂P�R�A�P�S�����A�o�c�w���̍u�`��ɔ�I����B�u���Ɨ����e�̓X�|���T�[�A��ɂ��Ȃ���v�ƁA�o���Ɍ��������e���Ƃo�q����_���Ƃ����B�����u���̔N��ɂȂ��ĎQ�ςƂ́v�Ɗw�������B�o�Ȃ��m�镃����A�܂����Ȃ��Ƃ����B
�@��Ă����͎̂ēc���E�o�c�w���������i�S�X�j�B���ă\�j�[�ŏ��i�J���ɂ���������B�u���Ƃ͂���Α�w�̏��i�B����͏o���Ɍ��������ʂ������炸�ɍ������Ɨ����Ă���B���i�����Ĕ[�����Ă����˂v�B�e�̖ڂ��C�ɂ��āA�w�����W�����Ă����Ƃ̊��҂��������B
�@������Ŕ��Έӌ��͂Ȃ��A��b�o�c�w�≞�p��L�ȂǂW�u�`�Ŏ��{����B
�@�ꐣ�v�v�o�c�w�����́u�c�t�ȑ�w�Ǝv���邩������Ȃ����A��w�͂����ƎЉ�ɊJ���ׂ����B���Ƃɂ͎��M������B���Ќ��Ăق����v�Ƙb���B
�@�����A�w�������̎͂悭�Ȃ��B����P�N���i�P�X�j�́u�����̐e�ɂ͐�ɗ��ė~�����Ȃ��B��w���ɂ��Ȃ��Ď��Ƒԓx���Ƃ₩��������̂͂��₾�v�B
�@��w���͗X���ŕ���Ɉē����o���A�Q�����t���Ă���B�P���܂łɉ��傪�������̂͂Q�l�����B�����Ȃ̂ŗ����Ȃ��l�������炵���B
�S���w�͒����@�S�O�N�Ԃ�ɍ��Z���P�O���l�Ώ�
�i�����V���P�P���V���j
�@�����Ȋw�Ȃ͂U���A�S���̍��Z�łP�Q���Ɉ�ĂɊw�͒��������{���邱�Ƃ����\�����B�S�����i���������j�̖�P�S�O�O�Z�̂R�N����P�O���T�O�O�O�l���ΏہB�u�w�͒ቺ�v�_�����܂�Ȃ��ŁA���k���ǂ̂��炢�w�K�w���v�̂̓��e��g�ɒ����Ă��邩������̂��_�����B���Z����Ώۂɂ����S���I�Ȓ����͂S�O�N�Ԃ�ƂȂ�B
�@���N�P�`�Q���A�U�N�Ԃ�ɍs��ꂽ�����w����S�X���l�ɑ��钲���ɑ������̂ŁA�������琭��������ے������Z���^�[�����{��̂ƂȂ�B
�@�Z���^�[�ɂ��ƁA�����Ώۂ͊e�n�̍��Z���疳��ׂŕ��ʉȁA���ƉȁA�H�ƉȂȂǂ̃o�����X���l�����Ē��o�B�����Ƃ��ĂP�Z�̂P�w�Ȃ���Q�w����I�B�Ȗڂ͍���P�A���w�P�A�p��P�A�����P�a�A���w�P�a�A�����P�a�A�n�w�P�a�̎��B�e�ȖڂƂ��Q��ނ̖���p�ӂ����B
�@���Ԃ͂P�ȖڂT�O���B�w�Z���ƂɎ��{�Ȗڂ��w�肵�A����A���w�A�p��̌v�U��ނ́A���ꂼ���P���U�O�O�O�l����悤�ɂ����B���Ȃ̊e�Ȗڂɂ͗��C�������k�����������ɗՂނ��߁A���k����̂͂P�`�R�ȖڂƂȂ�B���N�x�ɂ͒n�����j�A���������{����B
�@���ʂ͗��N�H���߂ǂɌ��\����\�肾�B���ꂼ��̖��ɂ��Ăǂ̂��炢�̊����̐��k�������������Ȃǂ�S���P�ʂŕ��͂���B�s���{���ʂ�w�Z�ʂ̌��ʂ��o�����Ƃ͂��Ȃ��Ƃ����B���k�̊w�K�ɑ���ӎ��⋳���̎w���Ɋւ���A���P�[�g�������Ď��{����B
�@���Z�ł̌p���I�Ȋw�͒����́A�T�U�N�x����U�Q�N�x�܂ōs��ꂽ���Ƃ�����B���Ȃ́A���s�̊w�K�w���v�̉��ł̎��{�͍������Ƃ��A���N�S���ɓ��w����P�N������ΏۂƂȂ�V�w���v�̂��蒅������Ɏ��̎��{���������߂�\�肾�B
�֘A�L��
�w�͒����@���Z�ł��S�O�N�Ԃ�Ɏ��{�@�R�N����P�O���l�𒊏o
�i�����V���@�P�P���U���j
�@���N�x���獂�Z�ł��V�w�K�w���v�̂����������̂�O�ɕ����Ȋw�Ȃ̍������琭�����͂U���A�S���̍����������Z�̂R�N����P�O���T�O�O�O�l�𒊏o���A�P�Q���Ɉ�Ă̊w�͒��������{����Ɣ��\�����B�q�������́u�w�͒ቺ�v�����O���鐺�����钆�A���s�w���v�̂Ŋw���Z���̊w�͂̋q�ϓI�ȃf�[�^���W�߂�̂��_���B���Z�ł̒����͂P�X�U�Q�N�x�ȗ��S�O�N�Ԃ�ɂȂ�B���ʂ͗��H���߂ǂɌ��\����B
�@�Ώۂ́A���������̑S�������Z�̕��ʉȂ⏤�ƉȁA�H�ƉȂȂǂ̂R�N���B���Z�͉Ȗڐ����������߁A���N�x�Ɨ��N�x�̂Q�N�ɕ����č���␔�w�ȂǂP�U�ȖڂŒ��ׂ�B���N�x�́A��P�S�O�O�Z�̖�P�O���T�O�O�O�l��ג��o���A����P�A���w�P�A�p��P�A�����P�a�A���w�P�a�A�����P�a�A�n�w�P�a�̂V�Ȗڂׂ�B�P�Ȗڂ̎������Ԃ��T�O���ƒZ���A�e�Ȗڂ̑S������J�o�[�ł��Ȃ����߁A�`�A�a�Q��ނ̖���p�ӂ��A�w�Z���Ƃɂ`�A�a�����ꂩ���w�肵�Ď��{����B���k�͗��C�ς݂̉Ȗڂ���悭�A�ő��łR�Ȗڂ̃e�X�g����B�y�[�p�[�e�X�g�̂ق��w�K�ӗ~��T�鎿�������B�e�w�Z�ō̓_���A���������Ńf�[�^���W�v���A�S���I�ȕ��͂��s���B�e�Z�ɐ��т͒m�点�Ȃ��B
�@���Ȃ́A�����w���̊w�͒����i���o�j�����N�P�A�Q���Ɏ��{���Ă���A����͂��̍��Z�ŁB�����w���́A�w�K�w���v�̂̉���ɍ��킹�Ċw�͒��������{����Ă������A���Z�ł͂T�U�`�U�Q�N�x�܂łP���̍��R���𒊏o�������������Ă������̂́A���̌�͎��{����Ă��Ȃ������B
�����{�@�������@�ʏ퍑���
�i�����V���P�P���U���j
�@�����}�̖������Y������͂U���̍u���ŁA�����Ȋw���̎���@�ցA��������R�c��������Ă��鋳���{�@�̉����ɂ��āu�����R�̒�Ă��ė��N�̒ʏ퍑��ɉ��炩�̌`�ł�肽���B������Ƃ܂Ƃ߂��������v�ƌ��A�ʏ퍑��ʼn������𐳖ʂ�����グ��l�����������B
�@�������́A���݂̊�{�@�ɂ��āu�ǂ̍��ɂ����Ă͂܂�悤�Ȋ�{�@�ŁA���{�Ƃ������̂����S�Ɍ������Ă���v�Ǝw�E�B�����R�����ԕ̑f�ĂŎg���Ă����u�����S�v�Ƃ������t���u����������S�v�ɏC���������Ƃ��ɋ����A�u���t�̗V�т݂����Ȃ��̂͂��낻�낢�������ɂ��A������Ƃ��Ȃ��Ƌ�������̂ł͂Ȃ����v�Əq�ׂ��B
�@����A�����}�̐_���\�͂U���̋L�҉�Łu�����}�͋����{�@�͌��@�ɏ�������̂ƈʒu�Â��Ă���B�������ɂ��Ăّ͐�������āA���Ԃ������ĐT�d�ɋc�_�����ׂ����Ƃ������ꂾ�v�Əq�ׁA��{�@�����ɐT�d�ȗ�������������B�����}�͂Q���̓}���ō̑������d�_����ŁA��{�@�������ɂ��āu���Ǝ�`�I�A�S�̎�`�I�A��O�ւ̕��Î�`�I�ȍl�������������ނ��Ƃ͒f�Ŕ�����v�Ƃ��Ă���B
�Z���^�[�����@�U�O���Q�X�T�O�l���o��@��������Q�l������
�i�����V���@�P�P���V���j
�@��w�����Z���^�[�͂V���A���N�P���Ɏ��{������w�����Z���^�[�����̏o����܂Ƃ߂��B
�@�u��Ґ��́A�U�O���Q�X�T�O�l�őO�N�x���W�U�O�l�i�O�D�P���j�����A�ߋ��ő��ƂȂ����B���͂S�R���W�O�Q�S�l�i�O�N�x��P�D�X�����j�A�Q�l���͂P�T���V�W�T�U�l�i���T�D�X�����j�A��w���w���i���荇�i�҂U�S�O�R�l�i���T�D�T�����j�ȂǁB�܂��A���ъJ������]������͂R�W���Q�U�X�T�l�łU�S�����߂��B���Z���^�[�́A�P�W�ΐl���̌����Ō����u��҂�����A�Z���^�[�����ɎQ�����鎄����̑����ȂǂŁA�Q�l���������Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ݂Ă���B
���Ē����w�������@���{�̒��w���A���Ɨ���x�Ⴍ���M���Ȃ�
�i�ǔ��V���@�P�P���W���j
�@�u���{�̒��w���́A���Ƃɂ��Ă������A�w��ւ̏�M���A���M���ӔC�����R�����v�\�\�B����Ȏ��Ԃ��V���A���Ē��R�����r���������@�ւ̒����ł킩�����B�ϋɓI�Ŏ��M���X�̕č��̒��w���A���w���u���ŋ�������ڎw�������̒��w���B���݂̂R���̐������A���̂܂ܓ��e����Ă���悤���B
�@�����́A��c�����|����U����A���{���N�������̗����c�@�l���A��N�P�O�����獡�N�R���̊ԁA�R���ł��ꂼ��P�O�O�O�\�P�R�O�O�l�̒��w����ΏۂɃA���P�[�g���s�����B
�@���w�̎��Ƃ̗���x�ł́A���{�́u�قƂ�Ǘ����ł��Ȃ��v�u�����͗����ł���v���v�R�T�E�S���ŕĒ��̂R�{�߂������B�i�w�̊�]�́A���{�͂R�W�E�X�����u��w�̊w���܂Łv�ōő��B��w�@�܂Ŋ�]����̂͂R�E�S���������B����A�����͔��m�ے��܂ł��S�V�E�T���A�C�m�ے����Q�R�E�V���B�w�����͂P�X�E�X���B�u�w�����͍����Ɠ����ƌ����Ă���v�i���N�������j�Ƃ���钆���̌��\�ꂽ�B
�@�u�����A��M�𒍂��������Ɓv�i�����j�ł́A���{�́u�X�|�[�c�v�i�R�Q�E�S���j�A�u���y�v�i�Q�T�E�P���j�Ȃǂ���ʂŁu�w��v�͂P�P�E�W���B�����́u�h�s�v���S�S�E�X���Ɠˏo�A�u�w��v���R�R�E�R���Ƒ������B�č��́u�X�|�[�c�v�i�S�U�E�U���j�A�u�w��v�i�S�T�E�V���j���قړ����������B
�@�N���X�̐l�C�҂́A�����łR���Ƃ��u���[���A�̂���l�v���U�����Ńg�b�v�B�����A�Q�ʂ͓��{���u���I�Ȑl�v�i�S�P�E�R���j�A�Ắu�X�|�[�c�̂ł���l�v�i�U�Q�E�T���j�A�����́u���̂ł���l�v�i�T�U�E�R���j�ƕ����ꂽ�B
�@�����ɂ��Ă̕]���́A�u�����ɖ������Ă���v�̂��A�č��T�R�E�T���A�����Q�S�E�R���A���{�͂X�E�S���B�u�����ɋN���������Ƃ͎����̐ӔC�v�ƍl����̂��č��T�X�E�V���A�����S�U�E�X���A���{�͂Q�T�E�Q���������B
�@�����̍��ɖ]�ގp�ł́A�������u�o�ϓI�ɖL���ȍ��v�i�R�O�E�U���j�A�u�R���ȂǍ��͂������A�����ɕ����Ȃ����v�i�Q�S�E�T���j�̏��B�č����u�O�����M�����A������A�h�o�C�X�����߂鍑�v�i�Q�T�E�W���j�B���{�́A�u�Љ�I�Ɉ��肵�A�s���̂Ȃ����v�i�R�V�E�P���j�A�u�o�ϓI�ɖL���ȍ��v�i�R�S�E�W���j�������B
�b�n�d�]�������@�e��w�ɒʒm�ցA�����Ȋw��
�i�ǔ��V���@�P�P���W���j
�@��w�@�̗D�ꂽ�����v��ɕ⏕�����o�������Ȋw�Ȃ́u�Q�P���I�b�n�d�i�Z���^�[�E�I�u�E�G�N�Z�����X�j�v���O�����v�ŁA�R���ߒ��̓����������ɂȂ������Ƃ���A���Ȃ͂V���A���������߂ǂɊe��w�ɍ̑��ƕs�̑��̗��R��ʒm������j�𖾂炩�ɂ����B�s�̑𗝗R�͑�w�ւ̒ʒm�ɂƂǂ߂邪�A�̑𗝗R�͌��\����B
�@��w�Ԃ̋����𑣂����ƁA���N�x�n�܂����b�n�d�ɂ́A�S���̍��������P�U�R��w����S�U�S���̐\��������A�T�O��w�̂P�P�R�����̑����ꂽ�B�������A�]�����e�͑S���������ꂸ�A�g���I�h������w�𒆐S�ɁA�u���������R��m�肽���v�Ƃ̕s�������ȂȂǂɊ��Ă����B
�@�]���́A���Ȃ̈ϑ��������{�w�p�U����I�l�ψ���i�ψ������]��扗�ށE�ʼnY�H�Ƒ�w���j��g�D���čs�����B
�������Z�w��ؔ[�@�R�J���ȏ�̊w��ؔ[�҂͂P�Z�P�R�D�T�l
�i�����V���@�P�P���X���j
�@�������s����w�i�Ɏ������Z�̊w����R�J���ȏ�ؔ[���Ă��鐶�k���A�P�Z�����蕽�ςP�R�D�T�l���邱�Ƃ��W���A�S�������w�Z���E���g���A���i�J����C�ψ����j�̒��ׂŕ��������B�e�̃��X�g����|�Y�A���S�Ȃǂ����R�Ƃ��ċ������A�q�������̋���ɐ[���ȉe����^���Ă��邱�Ƃ���������ɂȂ����B
�@�����́A���A���̑g���������鎄�����w�A���Z��ΏۂɎ��{���A�Q�T�s���{���Q�R�T�w���i���Z�Q�R�T�Z�Q�Q���U�W�T�O�l�A���w�X�R�Z�R���W�V�Q�Q�l�j������B
�@�X�������݂ŁA�R�J���ȏ�ؔ[���Ă��鐶�k�͍��Z�łR�P�V�T�l�A���w�ł͂Q�Q�P�l�B���w���Z�ƘA�����Ċw����x�������ɂS�Q�J���ؔ[���Ă���P�[�X���������B�P�N�ȏ�̑ؔ[���k�����鍂�Z�͂R�O�Z�A���w���W�Z����A�o�ϓI���R�łS���ȍ~�ɒ��ނ������k�́A���Z�łP�Q�T�l�A���w�͂P�l�������B
�@�ؔ[��ފw�̗��R�Ƃ��Ắu���e�̎��Ձv�i�����j��u�铦���v�i�ΐ�j�Ȃǂ�����A�ی�Ҏ��S�̗���V���������B
��w�̎��ƕ]���@�����V�U���A�S�N�O�Ɣ�ה{��
�i�����V���@�P�P���X���j
�@�w���������̎��Ƃ�]��������g�݂�������w���A�S�̂̂V�U���ɂ�����T�P�R�Z�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A�W���܂Ƃ߂������Ȋw�Ȃ̒����ŕ��������B�S�N�O�̂قڔ{�B�������m���݂��̎��ƎQ�ς������w�������A��w�̐搶�������]���ɂ��炳��闬�ꂪ�������Ă���B
�@�����͑S���U�V�P��w��ΏۂɁA������e�ɂ��č�N�x���_�ł̉��v���܂Ƃ߂��B
�@�w���ɂ����ƕ]�������{���Ă����w�́A�X�V�N�x�͂Q�V�Q�Z�������B���Ƃ̂킩��₷����b�����A����r�f�I�̎g�����Ȃǂ�]�����ڂƂ��Ă���Ƃ��낪�����B
�@�k�C�������ł́A�w���̕]���ɑ��Ă��ꂼ��̋��������ȓ_���������|�[�g���܂Ƃ߁A�z�[���y�[�W�ŏЉ�Ă���B�w���Ɋ��ӂ����茵�����]���ɔ��_������A�Y�܂������̂����𖾂�������Ƒ��l���B
�@�������m�őg�D�I�Ɏ��ƌ���Ɏ��g�ށu�t�@�J���e�B�E�f�B�x���b�v�����g�v�����{���Ă���̂͂U�P���̂S�O�X�Z�ŁA�O�N�x���U�W�Z�������B�V�C�����̌��C����J���Ă���̂͂P�R�W�Z�A�݂��Ɏ��ƎQ�ς����Ă���̂͂P�O�P�Z�������B
�@�����_�H��H�w���ł́A�X�X�N�x����D�ꂽ�u�`�����Ă��鋳���Ɂu�ŗD�G�u�`�܁v���Ă���B�w���A���P�[�g�Ȃǂ���I�ꂽ���҂���A�����Ԃ̓��[�őI�ԁB��҂͎��̂P�N�ԁA�V�C�����̃A�h�o�C�U�[�ƂȂ�B
�@�����ɂ��ƁA�P�R�U�Z�������̋���ʂł̋Ɛт�]���̑Ώۂɂ��Ă���Ƃ����B
���J�͎����
��s���͎��P�P���@���ꍇ���i�P�P���@�R���j
�O�N��Q�D�T���̑����B�j�q�̂قڍ�N���݂ɑ��āA���q�͂S�D�V���̑����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�Q�N�@�@�@�@�O�P�N�@�@�@�@�@�O�O�N
�j�q�@�S�ȁ@�@�@�S�X�U�O�@�@�@�@�S�X�P�S�@�@�@�@�S�S�V�W
�@�@�@�@�Q�ȁ@�@�@�P�R�O�S�@�@�@�@�P�R�S�V�@�@�@�@�P�S�W�X
���q�@�S�ȁ@�@�@�R�X�P�W�@�@�@�@�R�R�Q�P�@�@�@�@�Q�W�X�X
�@�@�@�@�Q�ȁ@�@�@�R�Q�T�O�@�@�@�@�R�T�Q�V�@�@�@�@�R�X�W�U
���v�@�@�@�@�@�@�P�R�S�R�Q�@�@�@�P�R�P�O�X�@�@�@�P�Q�W�T�Q
���\���͎��P�P���@���i����e�X�g�i�P�P���P�O���j
�O�N��P�D�X���̑����B�j�q�̂Q�D�X���̑����ɑ��āA���q�͂O�D�W���̑����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�Q�N�@�@�@�@�O�P�N�@�@�@�@�@�O�O�N
�j�q�@�S�ȁ@�@�@�V�W�O�S�@�@�@�@�V�Q�V�V�@�@�@�@�V�Q�Q�V
�@�@�@�@�Q�ȁ@�@�@�@�U�T�V�@�@�@�@�@�X�S�X�@�@�@�@�@�X�V�P
���q�@�S�ȁ@�@�@�T�W�T�P�@�@�@�@�T�Q�O�O�@�@�@�@�T�Q�T�Q
�@�@�@�@�Q�ȁ@�@�@�P�X�V�S�@�@�@�@�Q�T�U�S�@�@�@�@�Q�W�O�R
���v�@�@�@�@�@�@�P�U�Q�W�U�@�@�@�P�T�X�X�O�@�@�@�P�U�Q�T�R
���̑�
���ƌ������̗p�@��A�Z���Ɛ�A�P�펎������Ɏ�����̕s�����o
�i�����V���@�P�P���U���j
�@���N�x�̍��ƌ������P�펎���i�s���A�@���A�o�ρj�̍��i�҂��O�N�x���R���������̂ɁA�̗p����҂��O�N�x���݂ɂƂǂ܂�A�o�g�҂̑�w�����O�N�x�Ɠ����Q�T�Z���������ƂɁA������w�Ȃǂ̕s�������܂��Ă���B���l�ȑ�w�ɃL�����A�����̓����J�����v���������A���i���Ȃ���̗p����Ȃ������҂��S�O�O�l���A����Ґ��̏�ʂ�����Ȃǁu��A�v��w���Ɛ肷��\�}�͑��ς�炸�B���藦�̒Ⴂ��w�́u���傹��͂n�a�̗L���ō̗p�����E����Ă���v�ƕs�����ȑI�l�ߒ���ᔻ���鐺���傫���B
�@�l���@���s���P�펎���͕M�L�ɂ��P���A�ʐځA�_���ɂ��Q�������ō��i�҂����܂�B�P���ʉߎ҂͂Q�������O�Ɋ�]����Ȓ���K��B�قƂ�ǂ̏Ȓ��͂��̒i�K�ō̗p�������҂�I�сA�u���X��v���o���B�Q���������i��Ɂu����v�ƂȂ�B
�@���{�̍s�����v���i�{���͍�N�U���A�u��˂��L���J�����A���l�Ȑl�ނ��W�߂�v�ړI�ō��i�҂𑝂₷���Ƃ�����B���N�x�́A�O�N�x���P�V�U�l�����U�X�V�l�����i���A�o�g�Z���O�N�x�̂S�P�Z����T�W�Z�Ɋg�債���B
�@�������A�̗p���͂Q�X�O�l�ƑO�N���Q�T�l�����������������߁A�S�O�V�l���s�̗p�ƂȂ����B�̗p����҂ő����͓̂�����i�P�S�T�l�j�ȉ��A�c���A����c�A���s�̏��ŁA��ʂP�O�Z�̂����c���ȊO�͑O�N��葝�����B
�@����ŕ����̍��i�҂��o���������A���R�A�L���A��ʁA�R�w�@�ȂǂR�R�Z������҃[���B���Ɋ֓��ȊO�̎�����ł͓��藦���P�P�D�S���ƕ��ρi�S�P�D�U���j��傫�������A�n��Ԋi���������ɂȂ��Ă���B�l���@�����́u���x���������A�n�a�̑����ꕔ�̑�w�ɓ���҂��W�����邱�Ƃ𑣂����v�ƔF�߂�B
�@���N�x�A���i�҂P�Q�l���P�l�������肵�Ȃ�������q��̐E�Ǝw�����́u�Ȃ��s�̗p�҂�����Ȃɑ����̂��^��B�̗p���x�̓I�[�v���Ńt�F�A�ɂ��ׂ����v�Ƒi����B
�@���{�͗��N�x�A����ɍ̗p�g�̂S�{�܂ō��i�҂𑝂₷���j�ŁA�̗p�҂����N���݂ɗ}����A��W�V�O�l�̕s�̗p�҂����܂��v�Z�B������A�E�ۂ́u�Ȓ��ʐڂł͑�w�ɂ�����炸�����ɋ@���^����ׂ����B��ւ̎����Ɏ��Ă��̗p����Ȃ��w����������ƁA������߃��[�h���L����A���h������v�ƌ��O����B�s�v���i�����ǂ́u���茈�肪�s�������Ƃ��������������Ƃ͏��m���Ă���B����A�Ȓ��K��̌������ȂǁA������ڎw���l���@�ƒ������Ă����v�Ƙb���Ă���B�@�y�{�V�M�z
�y�P�����Ґ��E���n�O�Q�N�x�z
�@�@�@�@�@�@�J�b�R���͑O�N�x
�@�P�@������@�P�S�T�i�P�R�R�j
�@�Q�@�c����@�@�Q�X�@�i�R�R�j
�@�R�@����c��@�Q�V�@�i�Q�R�j
�@�R�@���s��@�@�Q�V�@�i�Q�U�j
�@�T�@�ꋴ��@�@�P�W�@�i�P�R�j
�@�U�@���k��@�@�@�V�@�@�i�P�j
�@�V�@����@�@�@�T�@�@�i�R�j
�@�W�@������@�@�@�S�@�@�i�Q�j
�@�W�@�����ّ�@�@�S�@�@�i�Q�j
�P�O�@�_�ˑ�@�@�@�R�@�@�i�Q�j
�A�E���藦
���Z���͉ߋ��ň��@��w�����O�N�����
�i�����V���@�P�P���P�S���j
�@���t���Ɨ\��ŏA�E����]���鍂�Z���̂����X�������݂ŏA�E�����܂��Ă��銄���i���藦�j�͂R�R�D�S���ŁA�ߋ��ň��������O�N�������R�D�U�|�C���g����������Ƃ��P�S���A�����J���A�����Ȋw���Ȃ̒����ł킩�����B��w���̓��藦���O�D�X�|�C���g�������ĂU�S�D�P���i�P�O���P�����݁j�ƂȂ�A�R�N�Ԃ�Ɍ����ɓ]�����B
�@���Z���̓��藦�͒j�q���S�D�R�|�C���g���̂R�U�D�S���A���q���Q�D�X�|�C���g���̂R�O�D�P���ŁA��������ߋ��ň��B���J�Ȃ́A���l�̏��Ȃ��n���u���̐��k�������A���ƂȂǂւ̉��傪�W�����Č��ʓI�ɕs�̗p�҂������Ȃ����ƕ��͂��Ă���B
�@���藦�͂��ׂĂ̒n��őO�N�����������A�k���i�x�R�A�ΐ�A����j���U�|�C���g���ƍł��������݂��傫���A�ߋE�i����A�ޗǁA�a�̎R�j���S�D�X�|�C���g���A�֓��i���A�ȖA�Q�n�A��ʁA��t�j���S�D�W�|�C���g���B
�@�������\���ꂽ���Z���̋��l�{���i�X�������݁j�͂O�D�V�Q�{�ƁA�O�N�������O�D�P�P�|�C���g�������ĉߋ��Œ�B���E�Ґ��͂U�D�U�������ĂQ�O���W�O�O�O�l�ƂȂ������A���l�����P�W�D�X���̑啝���łP�T���l�ƂȂ����B���ɁA�����ƁA���ƁA���E������E���H�X�Ȃǂ̋��l���傫���������Ă���B
�@���J�Ȃ́A���Z���̏A�E�悾��������Ƃ̍H�ꂪ�C�O�ړ]�������Ƃɉ����A�i�C�̐�s���s�������������Ċ�Ƃ̗̍p���f����N���x��Ă��邽�߁A�Ƃ��Ă���B
�@��w���̓��藦�́A�j�q���U�V�D�O���i�O�N������O�D�U�|�C���g���j�A���q���U�O�D�P���i���O�D�T�|�C���g���j�B���n�̓��藦�͂O�D�P�|�C���g���̂U�R�D�V���A���n�͂U�T�D�W���ƂS�D�V�|�C���g���������B����܂ŗ��n�̓��藦�����n��傫�������Ă������A�����Ƃ̋Ɛѕs�U�Ȃǂŗ��n�̏A�E�悪�������Ă��邱�Ƃ��e�����Ă���Ƃ݂���B
�@�Z��̓��藦�i���q�̂݁j�͂R�U�D�P���łO�D�T�|�C���g���������B�������w�Z�i�j�q�̂݁j�͂P�D�W�|�C���g���̂X�R�D�X���ƂȂ��Ă���B
�����Ȋw���@�L�ߊm��̍��Ό������̑ސE���Ԋҋ��߂�
�i�����V���@�P�P���W���j
�@�����Ȋw�Ȃ́A���N���[�g�����ŗL�߂��m�肵�����ΖM�j�E�������Ȏ��������ɑ��A�ސE���̈ꕔ��Ԋ҂���悤�����邱�Ƃ����߂��B���Ό������͂W�W�N�U���ɑސE�B���̍ہA�ސE�蓖�Ƃ��Ė�U�V�O�O���~������Ă����B
�@���ȏȂ̏��쌳�V�����������V���̋L�҉�Ō��y�����B�ݐE���̍s�ׂɊւ���Y�������ŗL�߂ɂȂ����ꍇ�̕Ԋ҂��߂����ƌ������ސE�蓖�@�Ɋ�Â��[�u�B
�@���Ό������͓������Ŏ��d�̍߂ɖ��ꂽ�B�ō��ّ�@�삪�挎�A�����Q�N�U�J�����s�P�\�S�N�A�ǒ����Q�Q�V�O���~�Ƃ����������ٔ�����s���Ƃ��錳�����̏㍐�����p���錈��������B
����聄
�@���̐}�̂悤�ɓ����傫���̐����`�̎����Q�����ׂ��}�`������܂��B�Ίp���`�a�̒������P�O�����̂Ƃ��A���̐����`�̎��P���̖ʐς́y�@�@�z���������ł��B�i�O�Q�N��叼�ˁj

�������ɒ����T�X���
����聄
���̍�i�̍�Җ��ƁA���̐l���ʐ^����̌�Q�̒�����I�сA�L���œ�����
�����B
�P �V�������@�@�@�Q �g���b�R�@�@�@�R �R����v�@�@�@�S ���ꃁ���X�@�@ �T �ɓ��̗x�q
�@��Җ�
�� ��[�N���@�@�@�� �X���O�@�@�@�� ���蓡���@�@�@�� �{���@�@�@�� �u�꒼�Ɓ@�@�@�� ���Ɏ��@�@�@���Ėڟ��@�@�@���H�열�V��
�@�l���ʐ^
�@�@�@�@�@�A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�G
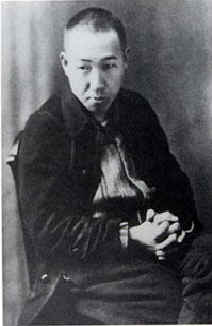 �@�@
�@�@ �@�@
�@�@ �@�@
�@�@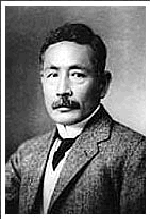
�@�@�@�@�@�@�@�I�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�J�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�N
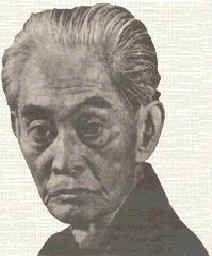 �@�@
�@�@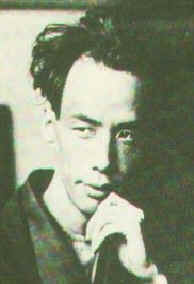 �@�@
�@�@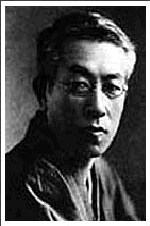 �@�@
�@�@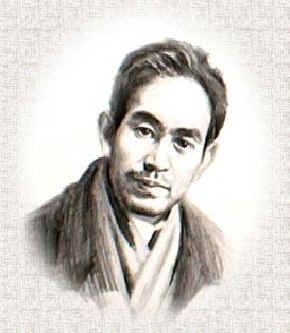
�i�O�Q�N�U�ʎЁj
����
�����܂ł��́I�H�ǂ̍�Ƃ��ǂ̂悤�ȍ�i�����������́A�w���w�j�x�Ƃ�������Ŏw���̑ΏۂƂȂ�܂����A�ʏ�A��ʐ^�܂ł������邱�Ƃ͂Ȃ���Ă��܂���B���̐l�ƂȂ��m���̎藧�ĂƂ��āA�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���B�ł���ŏ����킯�ł��Ȃ��ł��傤�Ɂc�c�B���Ȃ݂ɁA�A�͋{���A�L�͓��蓡���A�N�͎u�꒼�Ƃł��B
�@�@�����@�@�P���E�G�@�@�Q���E�J�@�@�R���E�E�@�@�S���E�C�@�@�T���E�I