

NO.76

2002年 10月 5日
アクセス教育情報センター
目次
|
学校情報 |
教育情報 | 模試情報 | 入試情報 | その他 |
| 鎌倉学園 | 都立高校独自入試 | 四谷大塚9月 | 03年主な入試要項変更 | 後悔しない学校選び |
学校情報
鎌倉学園 塾対象説明会(02年9月25日)
(校長 福井安正先生)
本校は地味で、対外的な活動はほとんどしていなかった。
創立80周年を迎えた昨年より、塾対象の説明会を開いた。(今回が2回目)
仏教系ではあるが宗教くさくなく、生徒たちはのびのびとしている。
「強制されてやる」のはよい生徒ではない。
自主自律の精神を守ってもらいたいというのが本校の精神。
(入試対策部長 竹内博之先生)
宗教的な行事はあまりない。
年間3回の坐禅教室(中1~高1)→親御さんからはもっとやって欲しいなどの希望がある。
古都保存法などがあり、校舎の建て直しはできないので、全教室をリニューアル。
中学生のクラブ加入率は、93%(70%は運動部)→活動日数の規制はない→文武両道。
名目上の5日制→中学3年間で公立中学校と比べ約1200時間差がある(主要5教科)。
土曜日は「鎌学セミナー」→英数国の特別講習(土曜日全体の90%実施)→全員参加、出席も取る。
総合的な学習の時間
中1・2「鎌倉を知る」
中3「国際理解」(ブリティッシュヒルズでの英語研修)
高1「自分を知る」
高2「国際理解」(オーストラリアでの語学研修)
先取り授業を行っている→英数は中2までに中学課程修了(中2より古典導入)→高2までに高校課程修 了→高3は受験対策
補習に関して
日常の補習(生徒のニーズに応じて、少人数で)
定期テスト終了後、年間3回の講習会(全員参加、当然無料)
0時間目、7時間目の特別補習(主に高2から)→遠くから通っている生徒もいるので、0時間目に行っ た補習を7時間目にもやる。
進学実績
今年は医学部の合格者が多かった→20名
6年連続、早慶上智の合格者が100名を超えた
<昨年度の入試を振り返って>
国語 漢字はきちんと「書く」練習をしてほしい。
受験生全般にいえることだが、論説文が弱い。
→ブルーバックス系・岩波ジュニア新書などの自然科学系の本を読むと良い。
雑に書くと×になる。
算数 1問4点。50分。100点満点。
基本的な問題の[1]~[4]までできちんと取れていないと確実に不合格。
応用問題の[5]~[8]は、誘導形式の問題なので、小問(1)、(2)
をヒントに考えて欲しい。
特殊算が2つからんだ問題は正答率が低かった。
社会 配点は地理分野22点、歴史分野22点、公民分野16点。
合格者の平均は、1次75%、2次73%。
重要語句の記述(漢字で書く)で差がついている。
理科 日常的な中での科学的認識を持って欲しい。
鎌倉をテーマにした問題であるが、鎌倉に住んでいなくても不利になることは
ない問題になっている。
合格者平均 1次75%、2次64%。
<2003年度入試について>
①2/2(日) 定員120→100名
②2/4(火) 定員50名
③2/5(水) 定員20名(今年度より新設)
1次試験の定員が減ったが、合格発表は今年と変わらないくらい出したい。
今年は238名発表した。
入学手続も余裕を持たせた。1次は2/4の12時までなので、浅野の9時の発表
を見てからでも間に合う。
今年より1次試験の出願も前日までOK。
合格発表は、インターネット・携帯を通じても発表する。
受験料は複数回受験の場合は割引あり(同時出願でなくても割引する)。
合否判定は総合点で。足きりはない。→昨年度は、320点満点中、①241点、②214点。
入試問題については10月以降の説明会で。
12月14日(土)10:00~12:00の説明会では、昨年度の入試問題の解説や入試のリハーサルも行うので、鎌倉学園に入学希望の生徒は是非参加して欲しい。
(感想)
「いつでも来ていただければ、校舎内を案内し説明します」というように先生方も生徒募集に力を入れている。数年前までは説明会など参加してもぱっとしなかったが、親御さんが聞きたい内容、そして鎌倉学園のことをしっかりと伝えられてるようになってきたと思います。場所柄、逗子開成との比較になりがちだが、進学実績などのことも含め、今年も鎌倉学園は人気になりそうです。
(報告 H.H)
http://www.kamagaku.ac.jp/
女子学院 03年出題範囲(募集要項より)
国語……新課程の指導要領の範囲で出題する。
算数……新課程とその応用の範囲で出題する。
新課程の範囲外のものは、誘導するなどして、習っていなくても解ける形で出題する。小数・分数の計算、計算の桁数については、旧課程の範囲で出題する。
社会……新旧両課程の教料書をふまえ、今日の社会問題を含めて出題する。
理科……5年生までの教科書、6年生は教科書と新課程で6年の教科書から削除または中学校へ移行統合された内容(下記参照)も含めた範囲で出題する。習っていなくても応用できるように、グラブ・表・図などを用いて文章で説明をつける。
日常生活の中で、経験していることや当然知っていると思われる自然現象についても出題する。
参照:削除または中学校へ移行統合された内容(第6学年)
人や他の動物の体のつくり、植物体の乾留、植物体の水や養分の通り道、でんぷんが成長に使われたり貯蔵されたりすること、中和、金属の燃焼、電流による発熱、北天・南天の星の動き、全天の空の動き、推積岩と火成岩。
http://www.joshigakuin.ed.jp/
三輪田学園 教育懇談会(02年9月7日 浅井教頭先生)
1887年創立。最初から女子の知育を掲げる。
中高一貫校。中1で180名募集だが、転勤等で抜ける生徒もおり高校では170名台の人数に。
6年間で4回クラス替えがある。高2、高3の間はクラス替えはない。
1学年180名というのは生徒一人一人がわかる適正規模。
高2の夏休みに自分史を書く。
三輪田は陰のカリキュラムとして道徳教育に力を入れている。
道徳教育では自分の進路、生き方を考える。そのまとめとして自分史を書く。
読書の時間を中1と中3の授業の中に取り入れている。
中1は国語の時間を使って週1時間図書館に。中3は社会の時間の中に週1時間取り入れている。そこで感想文やレポートを書く。
中1は本に興味を持ってもらう、中3は外の世界に目を向けてもらう狙いで行っている。
高1、高2での読書の課題につながっていく。
面接週間が年2回6月と12月にある。その間は授業時間を短縮して、放課後先生と生徒が1:1で話し合う機会を持つ。時間は一人15分程度。
勉強に関する話ではなく、生徒が今どんなことを考えているのか、悩んでいるのかを知るきっかけとして話し合う。
三輪田学園の三つの柱
1 教科指導
基礎・基本の徹底を図る。
高1までは塾、予備校に通わず学校の勉強を中心にと言っている。
小テストが毎時間のように行われている。理解できていない生徒は呼び出して再試験を。
英語は中1から中3まで分割授業。1クラス45名を2分割して。
中1は単純に2分割。
中2からは習熟度別の2分割。分割クラスはテスト毎に入れ替え。
国語は漢字を重視している。高2まで毎週のように漢字の小テストがある。
入試でも漢字の配点が20点と高い。
土曜講座を今年度から実施。授業を隔週5日制として、授業のない土曜日に土曜講座を実施。
普段の授業ではできない発展的な学習を中心とした講座になっている。
例えば希望者対象に、中1の2学期から英語の文法演習講座、中1・中2対象の社会科研究講座などがある。中3以上の生徒は何らかの講座を取っている。土曜日のクラブ活動は午後から。
高1までは全員同じカリキュラムを必修で行う。
高2から選択が入ってくる。選択により文系重視か理系重視に。
高3になると必修科目は少ない。カリキュラム表にある選択増加単位は入試問題演習。
高3もクラスは4つだがコース別授業に。文系コース3つ、理系コース2つ。
夏休みの初めと終わりに補習授業をほとんどの教科が組んでいる。
高2、高3で河合塾の模試を受けている。
高3になると7~8割の生徒が教科を選んで予備校に通っている。学校の勉強だけでも大丈夫と思うのだが。
2 進路指導
道徳の時間を使って自分にとって何が大切かをじっくり話し合う。
1クラス45名はいろいろなところから集まってきている。中には自分を押さえたり、背伸びしすぎたりする子もいる。担任がそれを把握する。
30年前から常駐のカウンセラーがおり、生徒の悩みを受け止められるようにしている。
生徒にとって自分の居場所を作ってあげることが大事。
中1の夏休みにクラス毎に4日間の追分け合宿を行う。
中3・・保護者の協力を得て仕事について考える、生きることについて考える講演会を行う。
高1・・10年後の私をイメージする。社会に出て仕事についている卒業生の話を聞く。
高2・高3・・大学に入学した卒業生に学習方法等について話してもらう。
高3になっても、自分が何をやりたいのかわからない人もいる。
3 行事指導
たくさんの行事、クラブ活動がある。
行事やクラブ活動に参加することで、役割分担、人間関係作り、自分の責任を果たすこと等を通じて、人間的な成長を図る。
学校の様子に関して
規模の小さな学校なので生徒も学年全体の顔と名前を覚えられる。
生徒は素直で真面目な子が多い。
何かあったときは何度も生徒と話し合う。
週2回、昼休みに校長室が開放されている。
入試に関して
3回入試。
1回 2月1日 女子100名 2科4科 面接
2回 2月3日 女子 50名 2科4科 面接
3回 2月5日 女子 20名 2科4科 面接
帰国生入試を1月10日に。
これまでに、1回、2回で不合格になりながら3回で合格した受験生もいる。
2科受験生は入学して最初のうちは社会、理科で苦労する生徒もいるがすぐに追いつく。
合計点で65~70%が合格基準ライン。
補欠発表はなし。02年入試では繰り上げ合格を出す。
繰り上げ合格を出す際は複数回受験生の方が有利。
入試問題は同じような傾向の問題が多いので過去問題をやっておかれるとよい。
新学習指導要領になったが入試問題を大きく変えるつもりはない。
NHKの週刊子供ニュースはお薦め。http://www.nhk.or.jp/kdns/
(報告 A.A)
02年入試問題について(配布資料より)
【国語】
例年通り、基本的な読み取りができているかを見ました。小説では、登場人物の心情を問う問題を中心に出題しましたので、心情を文脈に沿って客観的に読み取ることがポイントとなりました。記号選択や抜き出し問題、比喩など表現に関する問題はまずまずの出来でしたが、記述問題では設問の意図を的確に読み取り、必要な要素を入れてまとめることができたかどうかで差がつきました。
また字数制限のある記述問題では、設問の意図が読み取れても、限られた字数にまとめる力がないと高得点は望めません。字数に合わせて不要な言葉を削る、表現を変えることなどができたかどうかが合否のポイントとなったようです。この点については、各回ともほぽ同様の傾向です。
漢字の読み書きに関しては、第1回の出来はあまりよくありませんでしたが、第2回、第3回はまずまずの出来でした。
【社会】
例年通り、地理・歴史・公民の3分野から1題ずつ出題しました。県名など基本的知識を問うものでは、きちんと学習してきたか、そうでないかの差が大きく開きました。また、与えられた資料を用いて答える問題を出題しましたが、問題の意図がつかめず、覚えた知識だけで答えている答案が多く見られました。問題文をよく読むことを、先ず心がけていただきたいと思います。
【理料】
1~3回ともに例年通り、物理・化学・生物・地学の各分野から一題以上出題しました。また、身近な環境問題などの総合問題も出題しました。第1回では気体の発生、第2回では光合成によるデンプンの生成と方位磁針の性質、第3回では燃焼による気体の発生と振り子についての問題の出来があまりよくありませんでした。
内容の十分な理解とともに、日頃の計算練習も必要だと思います。
03年度入試出題傾向
【国語】
15年度の国語の問題も例年通りで、特に傾向は変わりません。
分量………・6000字程度で、長文1題もしくは、中位の長さの文章を2題出題します。
出題内容…・漢字の読み書きを、例年通り15~20題程度出題します。
・内容の読み取りについては、部分的な読み取りのほかに、全体の内容を問う問題もあります。
・接続詞(「しかし」「そして」など)や副詞(「まったく」「かなり」)などの空所補充問題は頻出です。
・慣用句の類は、本文に即した形で出題します。単独で出題することはありません。
対策………・漢字学習を大切にし、7割以上の正解を目指して下さい。(全体の出来と、ある程度の相関関係があります。)
・限られた時間の中でしっかりと文脈(全体の内容)をとらえる読解力を養うために、日頃からまとまった文章をたくさん読んで下さい。
【算数】
平成15年度の入試も出題傾向は変わりません。
1枚目は、いろいろな分野から基本的な内容の小問を10題前後出題します。
これらは、算数の基本的な知識を問うものです。いわゆる難問と呼ぱれるような問題や、長文の問題はありませんが、公式から単純に求められるものは少なく、「考える力」が必要とされます。いろいろな分野の問題を幅広く練習しておくことが大切です。
2枚目は、計算問題を3題と応用問題を2~3題出題します。
計算問題は、四則の計算の法則を理解しているか、分数や小数の計算が正確に出来るかということを見るものです。計算力は中学の数学でも大切です。
次に応用間題ですが、例年、グラフや表を使った問題、立体、平面図形の問題等が出題されます。問題の意味を正確に読み取る力を持っているかどうかが試されます。問題文を読みながら、要点を整理していく習慣を身につけておくとよいでしよう。
【社会】
新教育課程になっても出題傾向は変えず、従来通り地理・歴史・公民の3分野から出題します。基本的知識を問う問題では、漢字で書くべき県名や人物名などをしっかり覚えましよう。図表・グラフの読み取りや作成もできるようにして下さい。また、文の内容を読み取って答をまとめるような問題も1題は出しますので、日頃から文を読むことに慣れておくことが大切です。社会の動きをニユースなどで知っておくこともおすすめします。
【理料】
15年度も物理・化学・生物・地学の各分野からそれぞれ1題以上出題します。昨年と同様、4つの分野にわたる基本的な事項、身のまわりの自然現象や観察および実験を中心に出題する予定です。教科書はもちろんのこと、科学的な事象に関する新間やニュースなどからの出題もあります。また、計算問題は毎回出題する予定ですので、式を示して解を導くよう、日頃から練習して下さい。
三輪田学園の社会入試問題 これだけは勉強しておこう!
平成14年度の学習指導要領改訂に伴い、小学校で学習する社会科の知識が大幅に削減されました。私たち三輸田学園社会科では、新しい教科書による知織だけでは、入学後の社会科学習に充分に対応していくことは難しいと考えています。そこで、これだけは知っていてほしい!という知識や情報を、地理・歴史・公民の分野別にまとめてみました。これは、過去の三輪田学囲の社会入試問題を分析し、今後の出題傾向も含めたものですので、受験生の皆さんはぜひ、充分に準備をして試験に臨んでいただきたいと思います。なお、問題数、難易度、出題形式などは、昨年度入試といっさい変化はありません。
地理的分野
1.日本の都道府県と都道府県庁所在地の地図上の位置と名称
2.日本の国土と気候 …山地・山脈・平野・盆地・河川など、都市別雨温図
3.日本の産業
①農業…都遣府県別の農業生産、稲作・畑作物・畜産物の生産高、農業生産を高める工夫
②林業…日本の森林資源のようす、林業のかかえる問題
③水産業…漁業の種類と漁法、漁獲高の変化、漁業の中心となる港
④工業…工業の特色と種類、工業地帯、
⑤運輸・通信…空港・港・鉄道・高速道路の位置と名称とそれぞれの役割、通信網の拡大
4.日本の産業と世界のかかわり…産素別輪入と輪出の変化
5.作業 作図と資料の読み取り
①地図記号と地図の読みとり、等高線から断面図の作成
②表からグラフを作成する、グラフを読みとる
コメント 地理的分野の問題は、環境問題などの時事問題とからめて出題されることも多いので、関連させて学習しておくことが大切です。作図などの作業にも慣れておきましょう。
歴史的分野
1.時代区分とそれぞれの時代の特色
2.別紙の歴史年表に示されている程度の史実や事象・文化の理解
3.歴史用語の簡単な解説、または問題文からの抜き出しなどの、1行程度の論述
コメント 例年、3分野の中ではこの分野の配点が最も高くなっています。時代別では、近現代・近世の出題率が高いようです。また、世界文化遺産に指定された文化材に関連する出題が多いのも特色です。問題文が会話であったり、長文であることが多いのて、慣れておいてください。なお、世界史の出題はありません。
公民的分野
1.日本国憲法の成り立ちとその三大原則
2.国民の権利と義務
3.国会・内閣・裁判所の役割と三権分立
4.地方自治
5.選挙のしくみ
6.国際連合とその関連機関
7.世界の平和と日本の役割
8.時事問題(最近1~2年の出来事を中心に)
コメント 日本国憲法の三大原則では、基本的人権に関する問題が毎年出題されています。また、平和主義に関すろ問題や、憲法前文からの出題も多いので、要チェックです。
時事問題としては、近年では,沖縄サミット、地雷除去とNGOの活動、環境問題、介護保険、パリアフリー法、知る権利などが出題されています。
※なお、3つの分野が混ざっで、融合問題として出題されることもあります。
以上のような点に注意して、試験本番に臨んてください。これで三輪田学園の社会入試問題はバッチリです!受験生のみなさん、がんぱってくださいね!
http://www.miwada.ac.jp/
東京の私学14 毎日新聞で連載
雙葉中高 体育、徳育も重視の校風
四ツ谷駅から徒歩3分の緑あふれる高台に校舎を構える。00年完成の新校舎は落ち着いた雰囲気を醸し出し、4月には校舎前の土手いっぱいの桜が新入生を出迎える。
1909年、フランスの修道女メール・セント・テレーズが私財を投じて創立した「雙葉(ふたば)高等女学校」がルーツ。カトリックの精神に基づき、良き母親、良き社会人、良き国際人の育成を目指す。語学教育に力を入れ、英語のほか、中3から仏語も履修可能。家庭を守りつつ世界で活躍する多くの卒業生を輩出してきた。
国立、私立大学とも抜群の進学実績を誇るが、和田紀代子教頭は「学力だけで人間を判断することなく、知育、体育、徳育どれも同じように大切にするのが校風です」と強調する。
その言葉通り、7月の球技大会、10月の運動会の前になると、昼休みのグラウンドで、熱心に練習に打ち込む生徒の姿が見られる。
ボランティア活動も行っており、6学年24クラスに、各2人ずつのボランティア委員が置かれ、学年ごとに乳児院や養護施設、特別養護老人ホームと交流している。また、今年は全校生がアフガニスタンの子供たちに文房具を送る予定だ。
和田教頭は「勉強だけでなく、すべての面でコツコツと自分を磨くことのできる生徒を歓迎します」と話している。
ここが自慢--雙葉祭 毎年10月に行う学校最大のイベント。運動部は招待試合、文化部は展示、公演などで日頃の練習の成果を披露する。準備のための各学年の実行委は前年度に選挙で選ばれ、立候補、応援演説などの“選挙戦”もまた盛り上がる。
ホームページアドレス
http://www.futabagakuen-jh.ed.jp/
普連士学園中高 国際人育成へ選択科目
港区三田の静かな町並みに、レンガと白壁のおしゃれな校舎が映える。1887年、キリスト教フレンド派(クエーカー)婦人伝道会の有志が創立。「普連土」は「普(あまね)く世界に連なる」を表し、グローバルな学園を目指す思いが込められる。
学校の1日は、朝20分の「礼拝の時間」で始まる。教員や生徒が交代でスピーチを行い、体験を分かち合うことで一人一人の良さを認め合う。毎週水曜日には20分間沈黙し、内面を見つめる「沈黙の礼拝」もある。
5月の体育祭、10月の学園祭は学校全体が盛り上がり、「女子校ですが、体育祭前には朝早く来て騎馬戦の練習をする生徒もいます」と大井治広報部長。校内アンケートで生徒の大半が、結束が強く元気でアットホームな校風を魅力に挙げる。
カリキュラムでは、受験教育に力を入れる一方、長期的な国際人育成を目指しており、高3には「異文化理解」の選択科目がある。英米の週刊誌、新聞を素材に日本人教諭がまず読解の授業を行い、翌週、米国人教諭が指導し、討論する。楽しみながら国際的センスが身に着く。
クラブ活動は、文化系では演劇、音楽、コーラス、運動系では剣道、体操、テニスなどがある。
浜野能男教頭は「生徒一人一人が自分の良さを発見し、自分らしく成長するのを手助けする学校です」と話している。
ここが自慢--英語教育 週2回、希望者は米国人の留学生や英語圏からのゲストと昼食をともにし、生きた英語を学ぶ。8月には山中湖の寮で「3日間英語漬け」のイングリッシュキャンプがある。卒業のころには英語が身近なものになっている。
ホームページアドレス
http://www.friends.ac.jp/
文華女子中高 少人数で習熟度別指導
1916年、小石川に創設された東京家事裁縫研究所が前身で、70年に現在の場所に移転してきた。「質実・貞純・勤勉」が建学の精神で、心優しく、豊かな人間の育成を目指している。
中高一貫コースでは、少人数制の授業で個人の力を伸ばす。特に英数は習熟度別でさらにクラスを分け、きめ細かい指導を行っている。高校から入学した生徒は2年次から文系、理系のカリキュラムを選択できる。英語教育に力を入れており、英語が母国語の外国人講師も教えている。希望者は中3で英国研修、高2で豪州ホームステイができる。
週5日制で休みになった土曜も有効活用し、隔週で特別教育を行う。星座の研究や身体障害者への理解を深める調査、医師や警察官ら外部講師を招いての生活指導など、普段の授業ではできない貴重な体験ができる。
クラブ活動も盛ん。サッカー、ハンドボールなど運動部のほか、被服部のウエディングドレス製作など、女子校ならではの華やかな内容も目を引く。
「孔子の教えに『文質彬彬(ひんぴん)』という言葉があります。学問だけでなく、豊かな心も備わった望ましい姿のことですが、そんな女性を育てたい」と安部僖久枝教頭。
その教えは、来客にも気持ちよくあいさつできる生徒たちの礼儀正しい態度によく表れている。
ここが自慢 家庭教育寮 学校の敷地内にあり、中3、高3の生徒が2泊3日の宿泊研修を受ける。清掃、あいさつなど規律正しい生活習慣が身につくだけでなく、クラスの仲間が買い出しから食事作りまで一緒に行うことで、友情も深まる。
ホームページアドレス
http://www.bunkajoshi-j.ed.jp/
文化女子大付杉並中高 女子スポーツの名門校
暑い夏、生徒たちは大汗をかきながらスポーツに熱中していた。体育館やテニスコート、JR中央線の高架下を利用した弓道場や武道場で、「こんにちは」とはつらつとしたあいさつが響く。
文化女子大付属杉並中高(中学157人、高校774人)は知る人ぞ知る女子スポーツの名門。インターハイに6種目で出場、そのうち半分は武道だ。とはいえ、運動部員を特別扱いするような「セミプロ」式の体制ではない。特待制度もなく、赤点を取ると担任だけでなく顧問もしかる。
餅つきやひなまつり、七夕など四季折々の伝統行事を大切にしている。家庭で行うことが少なくなったせいか、生徒の楽しみの一つにもなっている。
野原明校長はマスコミ出身で教育問題のスペシャリスト。「わかる」教育を徹底。教師の名前を出して授業を生徒に選択させ、1年後には生徒が授業評価をする。「一方的な授業をして教師が自己満足しても意味がない」と野原校長。早朝授業や放課後の予備校教師の出張講習など、補習も充実させている。
服装学部のある文化女子大の付属でもあり、文化祭のファッションショーが恒例で、独創的なデザインの服がそろう。モデルも生徒で、最後を飾るのがウェディングドレス。驚くほど美しく変身する生徒もおり、涙する父親の姿が見られるという。
ここが自慢--フランス修学旅行 高2の2月に実施の修学旅行はフランス4泊6日。歴史のある街で本物にふれるほかユネスコ本部で海外で活躍する日本人の話を聞く。街並みの美しさやベルサイユ宮殿、ルーブル美術館などに感銘を受けている。
ホームページアドレス
http://www.bunsugi.ed.jp/index.htm
文京学院女子中高 750講座から選択できる
2学期制を採用して4年目。1日の授業時間も今年度から、60分が4コマ、40分が2コマの計320分とし、「1時間の授業は50分という固定観念」を破った。60分の授業ではじっくりと、40分の授業では集中的に学習に取り組む「メリハリ効果」があるという。
1924年に設立され、建学精神は「女性の自立」。生徒数は高校1316人、中学441人を誇る。野口由雄校長(高校)は「人生の一時期を同性とのびのび暮らすことができる。男性と一緒だと本当の自分を出せないデメリットがある」と強調する。
土曜日の「文京の時間」は、受験に備える講座のほか「科学を楽しもう」「趣味を極めよう」「福祉を体験しよう」など計750講座を用意し、生徒は興味のある分野を選ぶことができる。併設の生涯学習センターや文京学院大が全面協力するほか、卒業生や保護者も講師になるなど総力挙げて応援している。
生徒には年2回アンケートを実施し、「この授業はあなたにとっていい授業ですか」と自由意見を募る。教師は「黒板の字が小さい」などの指摘に応える。ボランティア活動も盛んで、最寄りのJR巣鴨駅周辺では中学生が月3回、掃除をする。
校舎の建て替えが進み、来年4月に全面完成の予定。バレーボール、アーチェリー、マーチングユース部は全国クラス。
ここが自慢--「元気」 知的障害者のスポーツの祭典「スペシャルオリンピックス日本」には100人以上がボランティア登録した。カナダで2週間のホームステイをする英語研修の参加者も80人を超すなど「好奇心が旺盛」。
ホームページアドレス
http://www.jhs.u-bunkyo.ac.jp/
文教大付中高 図書室と国語科が連携
「高齢化、情報化、国際化する社会に対応できるように教育を行っています」。早川明夫教頭は、学校の特色の一つとして図書室と国語科がタイアップした授業を挙げる。コンピューターを使って資料を調べたりリポートを書いたりする情報センターとして図書室を位置づけ、利用のマナーから教える。生涯学習の重要性にいち早く着眼した取り組みだ。 幼稚園から大学院まで、文教大学学園では約1万人が学ぶ。1927年の創立以来、女子校時代が長く続いた中学・高校も、98年から男女共学に。建学の精神である「人間愛」を基盤に、一人ひとりの生徒を大切にする教育を実践している。
「思いやる心を育てる」「一人ひとりの個性を生かす」「視野を広め、探究心を養う」が3本柱。ボランティア活動が活発で、クラブ・サークル活動や、中学校の弁論大会、高校の合唱コンクールなど学校行事も盛ん。オーストラリア・メルボルンの高校2校と姉妹校提携し、ホームステイをしながらの交換留学で国際感覚を養う。
文教大の付属校ではあるが、他校への進学が増加しているため、中高を「進学校的付属校」と性格づける。進路希望別に特別進学クラスや総合進学クラスなどに編成し、文系・理系のコースに分け、習熟度別授業でカリキュラムにも細かく配慮している。
ここが自慢--水泳部 ほとんど泳げない生徒から全国レベルの選手まで、めいめいに個別目標が設定され、練習メニューが組まれる。部員全員が水を得た魚のように生き生きしている。有力選手をスカウトする手法とは対極のクラブ活動の姿がある。
ホームページアドレス
http://www.bunkyo.ac.jp/faculty/ghsn/
法政大第一中高 特定教科に偏らず授業
1936年、旧制法政中学として市ケ谷に開校し、戦後に吉祥寺に移転してきた。生徒は一定の成績を修めれば、原則として法政大に全員進学できるため、知識の詰め込みに偏らない意欲的な学習ができる。
なかでも、中学で土曜に2時間設けられた「ワークショップ」はユニークだ。携帯ラジオを製作したり、小説やマンガを書いたり、世界の兵器について調査したりと、興味のある分野の研究に自由に打ち込める。特定教科に偏らない授業方針が学校の特徴で、森田勉校長は「文系、理系と早くから決めるより、さまざまな基礎知識を身に付け、可能性を広げてほしい」と話す。
来年4月からはコンピューター教室をリニューアルして、高1に「情報科」の時間も新設する。だが週5日制は当面採用しない方針。「普段の学習中心の生活を確立したい。それがなければ、5日も6日もない」(森田校長)という信念があるからだ。
高1の磐梯山での野外活動、高2のスキー修学旅行など行事も多い。甲子園経験のある野球部や、サッカー、ラグビー、ゴルフ、軽音楽部などクラブ活動が盛んで、レベルも高い。春には六大学野球の法政大を応援するため、中高合同で神宮球場に行けるのも付属校ならではの楽しみだ。卒業生にはプロ野球・阪神のチーフ打撃コーチの田淵幸一さんらがいる。
ここが自慢--自由な校風 「先輩は後輩の面倒見がよく、とにかく仲がいい。自由で明るい雰囲気に満ちあふれています」と森田校長は胸を張る。文化祭などの行事も生徒が手作りで進め、「自主・自律」の精神が行き届いている。
ホームページアドレス
http://www.hosei.ac.jp/general/ichi/index.html
宝仙学園中高 品格ある人間づくりを
1928年創立の「中野高等女学校」が前身の中高一貫女子校。「仏教の精神を基調に、知識と情操を兼ね備えた品格ある人をつくる」を建学の精神として、「心の教育」を重視している。
今年4月に就任した砂田芳宏校長は、埼玉県与野市の淑徳与野高校の副校長として学校改革を断行し、同校を全国トップレベルの進学校に押し上げた実績で知られる。とはいえ、宝仙学園中高の校長としては進学実績にこだわらず、「建学の精神に基づいて独自の教育を行うのが私学の使命。生徒のニーズに応えたい」と話す。
他校との提携により、生徒は中学校から保育体験や社会福祉体験、スチュワーデス体験、西洋料理のテーブルマナーなどを学び、「品格」を体得する。
国際化、情報化に対応できるように、中学校のカリキュラムでは英語の授業時間数を公立中学校の2倍近く確保。外国人講師による英会話や、パソコンを活用したリスニング、英検対策など、変化に富んだ授業を行う。高校でも4年制大学進学希望者を対象にした「特別進学コース」では、応用と演習に重点がおかれる。
数学は中1から、英語は中2から習熟度別に授業が展開される。
学内選考試験を受けることにより、保育学科と造形芸術学科をもつ宝仙学園短大への優先入学制度もある。
ここが自慢--生徒による授業評価 「分かる授業」を目指して指導技術を磨くため、7月と12月の年2回、生徒に全教員の授業を評価してもらう。話し方、熱意、統制ぶり、速さ、公平さなど、すべての項目が数値化され、授業改善に生かされる。
ホームページアドレス
http://www.hosen.ed.jp/
本郷中高 武道必修で健全な精神
JR巣鴨駅から歩いて3分。7000坪の広大な敷地の中に、中学、高校の校舎やグラウンドが並ぶ。野球やサッカー、ラグビー部の生徒たちが掛け会う声が、校庭に響いていた。部活動は盛んで、中学生の約8割、高校生の約5割が運動部に入部している。
1923年に、旧高松藩の第12代当主でのちに貴族院議長となった松平〓壽伯爵が、旧本郷区(今の文京区の白山通の東側)で、将来を担う子供の教育に取り組もうと、私立の男子校を創設。文武両道を実践する学校を作り出すために、自宅の土地の一部を提供した。
高橋雄校長は「本郷に学校があったことはないが、建学の由来が学校名に生かされている」と話す。現在は中学生660人、高校生1017人が学ぶ。
健全な精神を育てるため、高校3年間を通じて、剣道か柔道の武道科目が必修。段位取得を目指して、鍛錬に励んでいる。また、毎年1月の大寒の時期に合わせ行われる1週間の「寒げいこ」は同校の名物行事。剣道、柔道部員はもちろん、自主的に参加する生徒や、近隣の学校からも積極的に加わる生徒もいる。
高橋校長は「生徒一人一人が自分の目標を見つけるきっかけを作り出すことができるように、日々の授業や学校行事に工夫を凝らしている」と話す。
ここが自慢--土曜日の活動 中学生は午前中にクラブ活動と、語学や芸術などを楽しめる教養講座が開かれる。また、高校から入学した1年生を除く高校生は、学年の枠を超えた単元別講座の進学講習が行われ、予備校の教師などから指導を受けられる。
ホームページアドレス
http://www.hongo.ed.jp/
明星学園中高 選択肢広いカリキュラム
大正13(1924)年、緑に囲まれた井の頭の地に創設。リベラリズムに満ちあふれた当時の雰囲気そのままに、今も生徒は自由で明るい学園生活を満喫している。制服はなく、生徒手帳もない。
特徴的なのがカリキュラム編成だ。選択の幅が広く、特に高3では体育と政治経済以外のすべての授業を自由に選べる。受験教科だけでなく、文学批評、哲学、宇宙、ボイス・トレーニング、幼児教育、サッカー、ドイツ語など、実に多彩だ。
学習旅行も選択制。台湾、マレーシア、屋久島、奈良・京都など、毎年各地に用意される旅行コースに、生徒はどの学年でも、いくつでも参加できる。事前学習を徹底し、現地の高校生との交流を深めるなど、ただの旅行に終わらせない内容だ。
「この雰囲気に、高校から入った生徒や教師の中にはカルチャーショックを受ける人もいます。でも、単なる自由ではなく、一人一人の自立が必要。自由は厳しさも伴います」と瀬野卓志・教務部長は話す。
インターハイ常連の女子バスケット部、陸上部のほか、クラブ活動は音楽部や演劇部も盛ん。留学制度も充実し、豪州、ドイツへの交換留学がある。
卒業生には写真家の並河万里さん、女優の岩下志麻さん、料理研究家のケンタロウさんらがいる。
ここが自慢--生徒の表情 「大人になる過程で、とても多様な価値観がこの学校では形成されます。生き生きとした生徒の表情、これが何より自慢です」と、自らも卒業生で美術教師の山領直人・入学広報部長は話す。芸術を愛する生徒、教師が多いのも学園の特徴だ。
ホームページアドレス
http://www.myojogakuen.ed.jp/index.html
三輪田学園中高 自分史で人生振り返る
学校の東側には靖国神社があり、校舎の窓からは大きく成長した木々が四季折々の姿をのぞかせる。学校はJR市ケ谷駅から歩いて約8分のところにあり、「青雲台」と呼ばれるあずまやには、高さ約6メートルのしだれ桜があり、春には満開の花が新入生を迎える。緑豊かで静かな環境で、西惇校長は「夏でも木陰を作り出すので、部活動の練習をしている生徒が木の下で涼んでいたりします」と笑う。
1887年、徳育と知育を掲げる女子教育を実践するために創立された。中学540人、高校499人が学ぶ中高一貫校だ。
高校2年の夏には、全員が17年間の人生を振り返る「自分史」をまとめ、将来の進路選択に活用している。
読書教育に力を入れ、30年近く続く歴史を持つ。中1の国語、中3の社会の授業では週1回、クラス単位で図書館で文学や社会情勢に関する本を読む。少なくとも年8回、読んだ本の要約と感想や意見などをノートにまとめ提出する。担当教師はコメントを添えて生徒に返却する。
高1の世界史の授業で関連図書の読書リポートや、高2の選択科目の社会科でも、同じような課題がある。西校長は「中高の6年間はあっという間だが、読書をしている時には自分と向かい合い心と語り合う時間となってくる」と話す。
ここが自慢--生徒面接週間 生徒面接週間は6月と11月に約10日間行われる。生徒がリラックスして話せるよう、好きな場所で面接を受けられる。「青雲台」や「大観堂」と名付けられたあずまやや校庭など場所もさまざまで、教師と生徒が歓談する。
ホームページアドレス
http://www.miwada.ac.jp/
※高校の募集はなし
武蔵中高 本物にふれる授業徹底
武蔵中高(中学526人、高校507人)の校門をくぐると、植栽と一緒に岩石標本が並んでいた。案内板には「簡単な解説をつけたが、詳しく知りたい者は地質学教室に」とある。知的好奇心を誘う仕掛けだ。多くが国公立の理工系、医歯系に進むのもうなずける。
「御三家」の一角をなす有名校だが、東大入学者数は近年、減少傾向にある。福田泰二校長は「どこの大学にも合格できる学力をつけるのが理想なので憂慮している。しかし、有名大学合格を高校の目的にしてはいけない」と話す。
塾関係者から、中学生相手に大学院の授業をしていると評されたことがある。大人や本から得た知識の切り売りで満足しないよう、本物にふれる授業を中学で徹底しているからだ。中1で変体仮名を読ませたり、植物の問題を解くのに図鑑や本を見るのを禁止して観察させたり。福田校長は「塾でついた大人のアカを落としたい」と説明する。自主的な校外活動を支えようと教師、OBの基金で旅費を助成し、これまで日本海重油事故にボランティアに行った生徒らが利用した。
財界の大物、根津嘉一郎が1922年、社会貢献のために創設した7年制中学校が前身。「制服・校則なし」の外形的な自由だけでなく、言いたいことを言い合える雰囲気が、「自由な校風」につながっているようだ。
ここが自慢国外研修制度 中3から第2外国語で独、仏、中国、韓国の4カ国語を学ぶ。上級コースまでやり遂げた生徒たちから選考し十数人を2カ月間、4カ国語圏や英国の提携校に派遣。ホームステイや寮生活を体験し、日本の文化も紹介する。
ホームページアドレス
http://www.musashi.ed.jp/
※高校の募集なし
武蔵工業大付中高 進学校の姿勢、明確に
「進学校としての姿勢を明確にする」。大学の付属校としての位置付けにとどまらず、3年前に立てた方針に従い高1から本格的な進路指導を行う。数学は中1の2学期で中2の内容を終え、高2で高3の内容をすべて終える。「文部科学省の教科書では対応できない」と数学では学校オリジナルの教科書を使う。
中学は週3日、高校は週4日の補習を実施。夏休みなど長期休暇の補習も充実させ、「全員が希望の大学へ」と意気込む。理系の生徒が多いが文系も3割に上る。このため、高2からコース制を採用し、堤清教頭は「文系に変わって進路を見失うことがないようにしている」と話す。
一方、単なる詰め込み教育には否定的で、体験学習も盛んだ。中学の修学旅行は東北地方で農家などに泊まり込み、酪農や漁業を体験する。中学では毎週2時間、理科の実験授業があるが1時間は全員参加でデータを取り、残りの1時間で考察した内容をリポートにまとめさせる。
高3を除く中高全学年の国語の授業で「10分間読書」の時間を設け、考える力をつけさせる。今年から高2を対象にした大学の「出前講義」も行われ、ロボット、建築などの講義を聴くことができる。
体育祭や文化祭などの学校行事は生徒が企画・運営し、自主性を育てている。
ここが自慢--英会話 中学の英会話では、教師がタンバリンを鳴らしながら「Howareyou?」と授業を進める。会話のリズム感を身につけてもらうのが狙いで、生徒からは「にぎやかで楽しい。アッという間の50分」と好評という。
ホームページアドレス
http://www.musako.ed.jp/
武蔵野女子学院中高 元気で聡明な女性に
10万平方メートルの広大な敷地には武蔵野の面影が今も残り、春はソメイヨシノ、秋はイチョウ並木がキャンパスを彩る。植えられた樹木は1万本以上。「この自然環境も、大きな魅力です」と植田正司教頭は話す。
1924年に世界的な仏教学者・高楠順次郎博士が創設。大正時代に既に「聡明(そうめい)で実行力のある女性」を建学の理念にするなど、当時からチャレンジ精神のある元気な女子教育を目指していた。剣道部、筝(そう)曲部、マンドリン部など約40のクラブも活発で、高校バトン部は全国大会の常連だ。
2学期制、週6日制を採用し、授業時間を確保している。中2~高1までは英語、数学を習熟度別でしっかり身に着けさせ、高2からは進路別のコースを選択できる。今春の卒業生は約3割が武蔵野女子大・短大に進んだが、その他の多くは他大、特に難関国公私大へ数多く進学した。
欧米などへの留学制度も充実しており、高校1、2年で留学した生徒も、帰国後に単位が認定され、そのまま進級できる。01年度は15人、02年度は7人が旅立った。
生徒は気軽に職員室に出入りし、教師に授業での疑問点やさまざまな相談をする。「優しく明るい生徒が多い。のびのびした学校ですよ」と植田教頭。各地で個展を開く絵手紙作家の山路智恵さんは卒業生で、現在は武蔵野女子大に在学中だ。
ここが自慢--心の教育 週1時間、仏教精神を学ぶ時間を設けている。他の宗教を取り上げたり、臓器移植、少年犯罪など社会問題をテーマにすることも。「人に優しく接し、愛することを教えたい。その背景には宗教が必要」と植田教頭は話す。
ホームページアドレス
http://www.mj-net.ed.jp/
明治学院中・東村山高 英語教育にも力を注ぐ
教職員の約4割がクリスチャンという中高一貫校。創立者は、ヘボン式ローマ字などで知られる宣教師のヘボン博士で、「私たちの教育理念はキリスト教に支えられています」と森信幸副校長は話す。
学校の一日は毎朝約20分間の礼拝から始まり、週1時間、聖書の授業がある。「隣人を愛する」というキリスト教精神に基づき、高校では東南アジアの恵まれない子供たちへの献金活動や、近隣の福祉施設でのボランティア活動に取り組んでいる。中学では「身体障害者や高齢者の立場を理解できるように」と授業の一環として、アイマスクを付けたり、腕などに重しを付けて歩く「インスタントシニア」体験などを行っている。
英語教育にも力を入れている。高校で72年から毎年続けている米国でのホームステイは、日本では草分け的存在。ホストファミリーはすべてクリスチャンの家庭で、40日間過ごす。中学では週6時限の英語の授業のうち2時限は、外国人教師による英会話。1クラスを二つに分ける少人数制を取っている。
高校の生徒のうち約3割が系列の明治学院大へ進学する。04年度入試から移行試験制度が大幅に変わり、学科試験が廃止されることになった。高校3年間の評定平均値順に希望学科を受験することができる。受験内容は書類審査、小論文、面接など。
ここが自慢--校舎 98年に完成した新校舎は鉄筋コンクリート3階建て。広い中庭を備え、大学のキャンパスを思わせる。車椅子の生徒でも自由に通行できるように、エレベーターを完備するなどバリアフリー化が進んでいる。
ホームページアドレス
http://www.meijigakuin-higashi.ed.jp/
教育情報
都立高校独自入試 八王子東高と国分寺高が来春から独自入試導入
(読売新聞9月27日)
来年度の都立高入試で、八王子東高と国分寺高が自校作成の問題を取り入れた「独自入試」を行うことを決めたことで、独自入試導入の動きが多摩地区にも広がり始めた。両校では記述式問題を増やすなどし、受験生の思考力や表現力などを見極めたい考え。これを機に特色ある学校づくりを目ざしたい思いもあるようだ。
独自入試は二〇〇一年度入試で日比谷高(千代田区)が公立校として全国で初めて導入。国語、数学、英語、理科、社会の入試科目のうち、英国数の三教科の問題を自校で作り始めた。同様の独自入試は今年度入試で西高(杉並区)が、来年度は多摩地区の二校のほか、戸山高(新宿区)と新宿高(渋谷区)も取り入れることが決まっている。
背景には、従来の短答式が中心の入試問題では、進学校になるほど受験生の平均得点が高いレベルに集中し、差が出にくいという実情がある。八王子東高の宗像敏夫教頭(50)は「上のレベルの争いになると、どんな能力が高いのか見えてこない」と指摘する。
このため多摩地区の二校では、来年度入試から英数国の三教科で、答えを導き出すプロセスなどを重視する記述式問題の割合を増やして、思考力や表現力などをより正確に把握したい考え。その結果を入学後の指導にも役立てたい意向だ。
一方、各校には独自入試を機に進学校としての特色づくりを進めたい狙いもうかがえる。先行する日比谷高は今年度から、五分の休憩をはさみ二時限連続の「九十分集中授業」を導入。完全学校五日制施行後の授業時間確保のため一日七時限(一時限四十五分)の時間割も取り入れ、二年生の数学では少人数の「習熟度別授業」も行っている。
同高の応募倍率は、独自入試前の二〇〇〇年度から今年度にかけて、男子が一・五三から二・五六に大幅に上昇。女子も一・四七から二・〇三に増え、人気アップにもつながっている。
柴田哲教頭(48)は「独自入試は改革の第一歩。生徒や保護者のニーズにこたえられるよう学校の中身を充実させていく」と語る。
国分寺高は今年度から多様な選択科目を持つ「進学重視型単位制」高校に、八王子東は昨年九月に進学指導を重視してカリキュラム編成や教員配置をする「進学指導重点校」に都教委から指定された。両校とも日比谷高と同様、特色ある学校づくりを進めている。
国分寺高の佐藤徹校長(54)は「独自入試を通じて、欲しい生徒像を示し、『顔の見える』学校になれれば。チャレンジ精神が盛んな生徒を多く受け入れたい」と期待している。
民間から校長登用 神奈川県立総合学科高校
(毎日新聞)
神奈川県教委は、2004年度開校予定の県立総合学科高校(仮称)の校長予定者として、民間から石川裕二氏(54)を採用する。県内の公立学校で初の民間人校長となる。採用は10月1日。
石川氏は1971年4月、横浜銀行入行。横浜駅前支店長などを歴任。整理回収機構取締役を経て、今年6月から浜銀ファイナンス監査役を務めている。
同高校は、県立高改革の一環で設置される新しいタイプの高校。普通科と職業科、専門科を総合し、県内に5校が開校する。そのうちのいずれかの校長に赴任する。県教委は「リーダーシップと折衝能力に優れた人材。産業界でのネットワークを活用し、特色ある学校づくりに手腕を期待している」と選考の理由を話した。
県教委は、05年度に開校予定の「総合産業高校」(仮称)の校長に、さらに民間人1人を採用する予定。石川氏は開校までの間、県教育庁管理部総務室に勤務し、開校準備に当たる。
文科省COE選定 重点支援大学は国立大が4分の3
(毎日新聞10月3日)
大学を世界最高水準の研究教育拠点にするため、特定の大学に予算を重点配分する文部科学省の「21世紀COE(卓越した拠点)プログラム」の選定結果が公表された。同省から委託された日本学術振興会が、各分野の専門家による選考委員会を設け、生命科学など5分野で163大学464件の応募から50大学113件を選んだ。東京大など旧帝国大を中心に国立大が4分の3を占め、私立大は2割ほどにとど
まった。大学に競争原理を導入する初の試みだが、選考理由などは公開されず、不透明さも残った。
COEプログラムは、大学院博士課程の専攻科を対象に募集。今年度分、182億円を使途を限定せずに配分する。選考は、学術振興会が専門家による「21世紀COEプログラム委員会」(委員長、江崎玲於奈・芝浦工業大学長)を作り、その下に「生命科学」「化学・材料科学」「情報・電気・電子」「人文科学」「学際・複合・新領域」の5分野ごとに審査・評価部会を作って選んだ。
選ばれた研究のうち、国立大が31大学84件と大半を占めたのに対し、私立大は15大学25件にとどまり、“国高私低”が浮き彫りになった。公立大は4大学4件だけだった。特に東京大や京都大など予算や研究の陣容が整った旧7帝大は49件と、全体の4割以上を占めた。こうした結果は、従来の研究用補助金(科学研究費補助金)の配分割合とほぼ同じで、これまでの資金配分の枠組みをなぞった形だ。
学際領域では、砂丘を利用した砂漠化防止の研究(鳥取大)など地域の特色を生かした研究をする地方国立大や、人文科学でも演劇学の確立を目指す研究(早稲田大)など、ユニークな提案をした私立大も選ばれた。同委員会は、選ばれた大学と落選した大学には「コメントを付けて結果を説明する」としているが、応募した全大学名や選考方法・基準などについては公表を避けた。
21世紀COEプログラム
昨年6月に文科省が打ち出した大学活性化構想(旧名称はトップ30)。自然科学や人文科学、複合領域を10分野に分けて、大学院博士課程の専攻科を対象に、1分野10~30件を選定。5年間にわたって毎年1億~5億円程度の予算を重点配分し、世界最高水準の大学作りをする。今年は生命科学など5分野、来年は医学や数学、物理など5分野で選考。2年目でそれまでの実績を評価し、入れ替えもある。
関連記事
「トップ30」 どこがいいのか分からない(毎日新聞 10月5日)
大学の先生たちは、自分のペースで研究を続けてきた。ところが、文部科学省が、「さあ世の中は変わった。もっと競争しなくては」と尻をたたき始める。先生たちは右往左往である。大学の状況は今、そのように見える。
文科省は「大学構造改革」の旗を振っているが、その文科省も旗を授けた小泉純一郎首相から、尻をたたかれている。
「21世紀COE(卓越した拠点)プログラム」も、改革策の一つ。いわゆる「トップ30」だ。世界最高水準の研究教育拠点作りを目指し、論文応募で採択された国公私立大学の研究機関には国の予算を、重点的に配分する。
審査を続けてきたプログラム委員会が、その結果をこのほど公表した。採択されたのは申請163大学464件中、50大学113件である。その判断が妥当であったかどうかを問う前に、審査方法そのものが多くの問題を抱えていることを指摘せざるを得ない。
申請は5分野に分かれている。部会で書類審査し、ヒアリングの対象を絞り込んだ。部会の判断を経て、委員会が了承した。
まず問題なのは審査の時間が、あまりにも短かったことだ。多くの部会長も認めている。原因は文科省側にある。動きは昨年6月、遠山敦子文科相が突然発表した「大学の構造改革」(遠山プラン)に始まる。
国立大の再編・統合や法人化も強調している。狙いは、大学にも競争原理を導入することにある。
募集開始は今年の6月で、審査の時間は8、9月しかない。拙速が避けられない日程である。これでは、ヒアリングも受けられずに落とされた研究機関は納得できないだろう。
さらに問題なのは、審査の過程がほとんど公表されていないことだ。採択の基準は次の3点だったという。(1)すでに、世界的レベルで拠点として認められている(2)5年間で拠点になりうる(3)研究内容がユニークである。
しかし、「研究の秘密」などを理由に、採択された研究が、この3点のどれに当てはまるのかすらも明らかにされなかった。不採択組については何も分からない。
競争を促すには、社会の目が欠かせない。しかし、これでは出発点である審査の是非すらも、社会的に評価するのは不可能だ。
遠山プランの発表当初から、「採択は旧帝国大や特定の私立大に偏るのではないか」と指摘されている。結果は、その通りになった。どこまでユニークさが評価されたのか、疑問がわいてくる。
こうした問題の背景には、「とにかく大学でも構造改革の格好だけはつけよう」という、文科省の安易な姿勢がうかがえる。
ぬるま湯状態の大学を改革することは必要だ。
しかし、「密室状態」では大学に新しい風を巻き起こすのではなく、逆に現状を固定させる。これを打ち破るには、社会的な評価にさらされるだけの情報を公開することが前提だ。
私学への財政支援 大阪府、授業料引き下げた学校に財政支援
(毎日新聞10月3日)
大阪府は3日、授業料を引き下げた府内の私立高校に、値下げ分の大部分を財政支援で補う方針を明らかにした。早ければ来年度から実施する。厳しい不況の下、公立学校に比べ重い保護者の経済的負担を軽減するのが狙い。こうした助成制度は全国で初めて。この日の府議会代表質問で、太田房江知事が述べた。
府によると、府内の私立高は93校。授業料は年間84万~約25万円(平均約51万円)。府立など公立高校の授業料約14万円とは、平均で約37万円の開きがある。府はこの格差に加え、私立高進学者(今春は約2万人)が例年、全高校進学者の約3割を占める点を重視した。
私立高の救済策でないことを強調し、「高校の減収分の補てんではない」としており、全額は補わない。しかし、「大部分は補助する」としている。財源は来年度当初予算案の編成作業の中で検討する。また、支援は制度開始から2~3年の間とし、その間に高校側にコスト減などの経営改革を求めたいとしている。
府内の私立高校中退者で保護者の失業など「経済的理由」を挙げたのは00年度で119人。全中退者の5.2%。府は今年度、私立高進学者に対する府育英会の奨学金を、前年度比2.6倍引き上げている。
納入金返還訴訟 大学の入学辞退者ら90人が提訴
(朝日新聞 9月25日)
私立大学の入学辞退者ら90人が合格時に払い込んだ納入金の返還を学校側に求めたのに、応じないのは不当だとして24日、短大を含む私立大学41校と専門学校3校を相手に総額1億2433万円の支払いを求める訴えを東京、横浜両地裁に起こした。6月に関西地方であった集団提訴に続く動きで、24日は3大都市圏でそれぞれ提訴があった。
東京地裁に訴えられた大学は、日本、北里、立正、法政、上智、独協、帝京、明治、東海、中央、早稲田、慶応など。請求の最高額は、東邦大医学部をこの春受験した学生が入学金などとして払い込んだ930万円。
原告のうち70人は今春の受験生。訴えでは、昨年4月施行の消費者契約法に基づき、「入学辞退で実際に学校側が受けた損害を超えて支払う義務はない」と主張。同法施行前の93~01年度の受験生は、民法上の中途解約権などを根拠に訴えた。
また、この日は関西でも141人が50校を相手に1億7254万円、中部では4人が3校を相手に約290万円の返還を求める訴えをそれぞれ起こした。
この問題をめぐっては、文部科学省も5月、入学辞退者からは授業料や施設設備費を徴収しないよう指導する方針を表明している。
弁護団は6月に「全国一斉110番」を実施。相談のうち、大学・短大20校、専門学校12校、高校1校とは和解が成立し、計約4650万円が支払われたという。
公開模試情報
四谷大塚9月 合不合判定テスト(02年9月22日実施)
前年比9.0%の増加。男子の9.3%の増加に対して、女子は8.6%の増加。
首都圏だけでは9.2%の増加。
02年 01年 00年
男子 4科 7108 6460 6623
2科 623 612 738
女子 4科 4978 4161 4138
2科 1405 1717 2038
合計
14114 12950 13537
9月三模試合計
三模試合計で前年比6.2%の増加。男子の6.7%増に対して、女子は5.8%増。
7月の三模試合計は四谷大塚と日能研の実施日が重なりながら前年比4.1%の増加だった。
来春の首都圏入試は5%以上受験生が増加する可能性がますます高くなった。
02年 01年 00年
99年
男子 4科 19138 17728 16950 16684
2科 2369 2437 2729 3111
女子 4科 14441 12391 11542 10935
2科 5807 6756 7701 8398
合計 41755 39312 39122 39128
入試情報
03年主な入試要項変更
首都圏の主な入試要項の変更を項目毎にまとめました。
アクセス教育情報センター内の会員のページに一覧を載せております。
そちらをご覧ください。
http://www.j-acc.co.jp/
その他
後悔しない学校選び 「日常」を見て判断しよう
(毎日新聞10月3日 記者の目より)
◇受験本ではわからない
東京都内版で3月から都内の私立中学、高校243校について連載してきた。私は25校を訪問、取材した。これだけ、多くの学校に足を運ぶ機会はめったにない。実際に教育現場を歩いて気付いたのは、自分の先入観や学校に対する社会の誤解だ。私の「学校探訪記」を報告したい。
まず、授業を含めて取材に対して抵抗感のない学校が多いことに驚いた。校舎が新しいとか、整然とした雰囲気だとか、「立派な学校」と誇れる学校ばかりではない。飲みかけのペットボトルが置きっぱなしの教室や、授業中に売店の周りでウロウロする生徒も見た。教師と一緒に廊下を歩いていた同僚記者は、自転車に乗った生徒に遭遇したという。本当は飾ったり、隠したりしたいのだろう。しかし「日常の風景」なのだから、隠しようがない。
「学校は閉鎖的」だと思っていた私は、この開放ぶりについて、ある学校で聞いた。教頭の答えは明快だった。「生徒募集ですよ。保護者は熱心ですから、まず、授業を見たがる。断って受験してもらえなければ、困りますから」。見学したら見学したで、「教え方が古い」と指摘されたこともあるという。「開かれた学校」とよく言うが、「開かざるをえない学校」というのが実情のようだ。
少子化で学校経営は困難な時代を迎えている。有名校ならともかく、多くの学校は「生徒募集」を意識せざるをえないのだ。「親の目・子の目」にさらされ、私立学校の変化は急だ。
「大学現役合格を目指す中高一貫教育」「実践的な英語教育と留学制度」「少人数教育」「修学旅行は海外か体験型宿泊研修」
驚くほど似ている売り文句からは、「トレンド」がはっきり見てとれる。「うちの子に提供してほしい教育サービス」という保護者の要望を反映しているからだ。それぞれの学校が「生徒募集」を意識した結果、私立学校が本来持つ個性が後ろに下がり、よく似たトレンドだけが目につくことになる。
一方、公立の「私学化現象」が進んでいる。東京都教委による都立高改革で、来春から全校に年間の経営計画と事後評価を義務付け、「学校経営」を意識させることにしている。現在は、私学に工夫をしている学校が多く目立つが、今後は、公立私立というイメージで区別できなくなるのではないかと感じる。
公立が国の教育改革に従順で、私学では不熱心だとは単純には言い切れない。聖心女子学院のように74年から週5日制を導入している例もある。一方、都立高の少なくとも3分の1で土曜日の教科講習を実施、自習室でOBらが教える自主登校にしている所もある。
土曜日の使い方もさまざまで、授業をしている学校ばかりではない。畑を借りて農作業をする学校があった。最初は土を触るのさえ嫌がっていた生徒が、農家の人に教えてもらいながらジャガイモの収穫まで体験すると反応が変わるという。週6日・授業5日制をとり、体験学習や勤労観を養う社会人講座など教科外学習に知恵をしぼっていた。
生徒募集のうたい文句は同じでも、実際には違いがある。生徒の気風や校風は自分で感じるしかない。学校生活を送るうえで重要なことは、具体的な言葉や数字には表れにくい。しかし、受験本では、偏差値と進学実績という「入り口」と「出口」の情報ばかりが強調されがちだ。その結果、同じくらいの偏差値のブランド校を受けまくる受験生がなくならない。
親も子も望んだ学校だったのに、早々に不登校になってやめてしまったという例も聞く。入り口と出口だけに捕らわれず、学校の日常を知ったうえで選んでほしいと思う。
また、ちまたの教育議論に、現場では違和感を感じていることも指摘したい。早稲田大高等学院で入試やカリキュラム改革に取り組んできた伴一憲・前学院長は「学力低下の議論は枝葉だ。21世紀には考える人間を育てなければいけないからこそ、必要な教育改革なのに。本質論をしてほしい」と話す。現場を知らない人の議論が先行し、文部科学省はブレているとも批判した。
「教育」は誰しもが通る道であるだけに、誰もが自分流の議論を展開できる。そのためか、50年前に受けた自分の教育を引き合いに出して論じる人すらいる。教育現場が急激に変化しつつある今、現場に即した議論をしなければ意味がない、というのが取材を終えた実感だ。
<問題>
次のように数をかけていきます。
まず1に2をかけて、その結果に3をかけて、さらにその結果に4をかけて、……、このように、1から順に次々と数をかけていきます。次の問いに答えなさい。
(1) ある数までかけると、0が一の位から連続して4個並びます。ある数として考えられるもののうち、最も小さい数を答えなさい。
(2) ある数までかけると、0が一の位から連続して7個並びます。ある数として考えられるもののうち、最も小さい数を答えなさい。また、1からその数までかけたとき、一の位から数えて8けた目の数字を答えなさい。
(02年筑波大駒場)
入試問題に挑戦第55回解答編
<問題>
もも組の児童40人のお母さんの名前に、恵、美、子の文字があるかないかを調べたところ、次の4つがわかりました。
① どの文字もない人と3文字ともある人の数の和は全体の1割
② 恵も子もない人の数は全体の1割
③ 子、美がある人の数は、恵のある人の数の各々4倍、2倍
④ 子だけ、恵だけがある人の数は、美だけある人の数の各々8倍、2倍
恵、美、子の文字のうち2つ以上ある人は何人ですか。(02年東洋英和)
<解説>
もも組40人の様子をベン図に表してみると、下の図1のようになります。
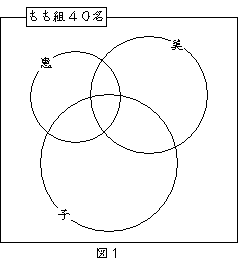
まず、①と②から、図2と図3の赤と青の部分の和がいずれも、40×0.1=4(人)ということがわかります。
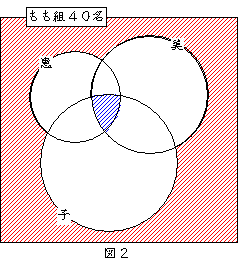
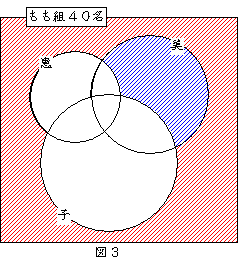
また、赤の部分は共通なので、『3文字ともある人』と『美だけある人』の人数は等しいことがわかります。
次に、④の条件から、『美だけある人』を①とおくと図4のように、『恵だけある人』が②、『子だけある人』が⑧となります。
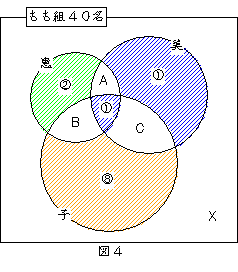
ここで、図4の空いている部分をそれぞれA,B,C,Xとするとき、①の条件から、①+X=4なので、①の範囲は0~4人になります。
①=0人のとき、X=4 → A+B+C = 40-4 = 36(人)
①=1人のとき、X=3 → A+B+C = 40-(①+①+②+⑧)×1-3 = 25(人)
①=2人のとき、X=2 → A+B+C = 40-(①+①+②+⑧)×2-2 = 14(人)
①=3人のとき、X=1 → A+B+C = 40-(①+①+②+⑧)×3-1 = 3(人)
①=4人のときは、全体が40人を越えるので不適。
さらに、③の条件から、『恵がある人』と『美がある人』と『子がある人』の比は、1:2:4になります。
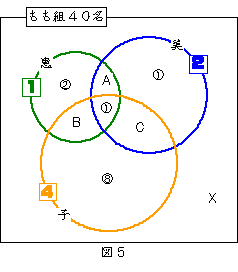
『恵がある人』 = ②+①+A+B = ③+A+B
『美がある人』 = ①+①+A+C = ②+A+C
『子がある人』 = ⑧+①+B+C = ⑨+B+C
なので、この3つの和は、⑭+(A+B+C)×2となります。
ここで、『恵がある人』と『美がある人』と『子がある人』の和は、1+2+4=7の倍数になることを利用すると、
⑭は7の倍数なので、(A+B+C)×2も7の倍数にならなければなりません。
よって、この条件に合うのは、①=2人のときのA+B+C=14(人)だけとなります。
最後に、2つ以上の文字がある人は、A+B+C+① = 14+2 = 16(人) になります。