
�m�n�D�V�P

�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�O�Q�N�@�W���P�T��
�ڎ�
|
�w�Z��� |
�w�Z��� | ������ | ������ | ���̑� |
| �}�g���� | �����̎��w�P�P | ������w�[�t�� | �������w�Z�̗�[�� | �w�Z������\������ |
�w�Z���
�}�g�����@�w�Z������
�P�D���{�����F�����P�S�N�P�O���P�Q���i�y�j�C�P�R���i���j
�@�P�O�F�O�O�`�P�P�F�R�O
�@�P�R�F�O�O�`�P�S�F�R�O
�@�P�T�F�R�O�`�P�V�F�O�O
�@�v�U��C�e�����S�V�O��
�Q�D���F�{�Z�V���قR�K
�R�D�\�����ݕ��@�F
�@�X���P������X���Q�T���i����L���j�܂łɁA�Q���l���i�P���܂��͂Q���C�ő�Q���j�y�ъ�]���������͂��@���ɋL�����A�{�Z���ɗX�����ĉ������B
�@�i������̉�ɂ��Q�������������́A�{�Z�Ō��߂����Ă��������܂��B�j
�@����F���P�T�S�|�O�O�O�P�@���c�J��r�K�S�|�V�|�P
�@�}�g��w������ꒆ�w�Z�@�w�Z������W
�@�����͂����L����
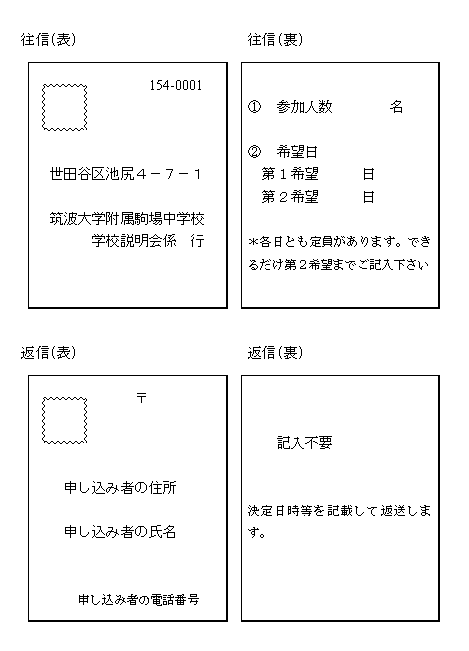
http://home.catv.ne.jp/dd/tukukoma/hp/index.htm
��ȗ��R�@�O�R�N��蒆�w��V��
�O�R�N�����v��
�P��@�P���P�Q���@���q�T�O���@�Q�ȂS��
�Q��@�P���P�X���@���q�Q�O���@�Q�ȂS��
�R��@�Q���@�T���@���q�P�O���@�Q�ȂS��
�P������͊w�Z�̑��ɑ�{���i��{�\�j�b�N�V�e�B�j���ݒ�B
�P��E�Q��̓��w�葱�͂Q���S���P�U�F�O�O�܂ʼn����ł���B
����̓��F
�i�P�j�g�Ȋw����S�h�̈琬
�@�@�Ȋw����S�Ƃ́A�N�����M���Ă���悤�ȕ��ՓI����ɑ��Ă����A�Ȃ����낤�Ƃ����^��������A����������������Ă����S�ł��B�����ɂ͒m�I�D��S�������A���m�̐��E��m���Ă����w�т̊y����������܂��B���Ȍn�̎��Ƃ����łȂ��A���ׂĂ̎��Ƃɂ����āg�Ȋw����S�h����Ă邱�Ƃ�ڕW�ɂ��܂��B
���H�@�A�@���Ȃ̎��Ǝ������w�R���N���v�P�S���ԁB�i�W���W�D�R���ԁj
�@�@�@�@�C�@�����E���K���d������B
�@�@�@�@�E�@�����I�w�K�y�ы��Ȃ�ʂ��āA���|�[�g�쐬���K�������A�R�N���ɂ͑��ƌ������s���A���\����B
�i�Q�j�g�\������́h�̈琬
�@�@�R�~���j�P�[�V�����\�͂́A���M����\�͂ƂƂ��ɁA����̔��M����e����\�͂��K�v�ɂȂ�܂��B�u���t�͍���b����v�\������͂��琬���邱�Ƃ́A�L���Ȑl�Ԑ����琬���邱�ƂɌq����܂��B
���H�@�A�@�T�T���̒��Ǐ��𒆐S�Ƃ����Ǐ��w���ŔN�ԂT�O����ǔj����B
�@�@�@�@�C�@����ɂ�����\���w�K�̏d���B
�@�@�@�@�E�@���_�A�f�B�x�[�g�A�v���[���e�[�V�����B
�i�R�j��O�w�K�̏d��
�@�@�{�Z�̌b�܂ꂽ���R�����������A�����ł̍��w�����łȂ��A���܂��܂ȃt�B�[���h�E���[�N���s�����ƂŁA�m���������̒������̂��̂łȂ��A����̑̌���ʂ������������̂ɂ��Ă����܂��B
���H�@�A�@�I�I�����T�L�̎���A�ώ@���̃v���O������ʂ��āA���R�Ƃ̂ӂꂠ����[�߂�B
�@�@�@�@�C�@�����ق���p�ٓ��̌��w��ʂ��āA���y��n���ւ̗�����[�߂�B
�i�S�j���̏[��
�@�@��Љ�ɑΉ��ł���͂�{�����邽�߂ɁA�R���s���[�^��Ƃ��Ďg�����Ȃ��邾���łȂ��A���̕��́A�����̕��@���w�т܂��B
���H�@�A�@���̏����A���͂ɂƂǂ܂炸�A���𐳂����F�������p�ł���悤�ɂ���B
�@�@�@�@�C�@�o�b�u�����J�u����B
�@�@�@�@�E�@���|�[�g�A���R�����̓R���s���[�^�ō쐬�ł���悤�ɂ���B
�@�@�@�@�G�@�e���ȂŃR���s���[�^�����p�������Ƃ��s���B
�i�T�j���ۗ����̋���v���O����
�@�@���ۉ������Љ�Ŏ������������Ƃ��čs���ł��邽�߂́A���ۓI�����g�ɂ��A�ٕ����ɑ��闝����[�߂邱�Ƃ��߂����A�܂��A���E���ʌ�Ƃ��Ẳp��b�̏K�n�ɓw�߂܂��B
���H�@�A�@���l���ɂ��p��b�N���X��݂���B
�@�@�@�@�C�@�X�y�����O�A���V�e�[�V�����A�X�s�[�`���̍Z���R���e�X�g���s���A�Z�O�ł̃R���e�X�g�ɐϋɓI�ɎQ���ł���悤�ɂ���B
�@�@�@�@�E�@���Q�܂ł̂s�n�d�e�k�T�T�O�_�ȏ���߂����B
�@�@�@�@�G�@���Q�̉p��b�w�K�i�����j�A�Z�����w�A�Z���X�^�[���w�A�P�N�Ԃ̒������w�ȂǁA�U�N�Ԃ̌�w�K���̃v���O�����B
�@�@�@�@�I�@���l�̍��̐l�����Ƃ̌𗬉�����{����B�@
�w�Z������
�@�X���Q�P���i�y�j�@�P�O�F�O�O�@�̌����Ƃ���
�P�O���P�R���i���j�@�P�O�F�O�O
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�R�F�R�O�@�̌����Ƃ���
�P�P���Q�Q���i���j�@�P�R�F�O�O
�P�Q���P�S���i�y�j�@�P�O�F�O�O
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�R�F�R�O
�̌����ƎQ����]�҂͎��O�ɓd�b�A�e�`�w�A�d�|mail���ŗ\�K�v�B
http://www.otsuma-ranzan.ed.jp/
�y�Y�����@�O�R�N��蒆�w��V��
�O�R�N�����v��
�P��@�@�P���@�V���@�j���X�O���@�Q�ȂS�ȁ@�ʐ�
�Q��@�@�P���P�X���@�j���U�O���@�Q�ȂS�ȁ@�ʐ�
�R��@�@�Q���@�Q���@�j���P�O���@�S�ȁ@�@�@�ʐ�
�A��
�P�Q���@�W���@�j������@����܂��͉p��A�Z���@�ʐ�
��ʓ����̖ʐڂ͕ی�Җʐ�
�A�������̖ʐڂ͎��ƕی�Җʐ�
�Q������̎������͊w�Z�̑��ɔ�����p��
�w�Z�̓��F
�P�@�\���Ɩ����d���鋳��
�m���Ȑl�Ԍ`����ڎw�����߁A�����w���̐��ɂ������܂����B
�T�U���̏[���������Ɠ��e�A�U�N�Ԉ�ы���A�`���[�^�[���x�̎�����̂ق��A�]���̂悤�Ȉ�Č`���̎��Ƃ����ł͂Ȃ��[�~�i�[���`���̎��Ƃ�������Ď��{���܂��B
�Q�@�u�Θb�v���d����������
���k��ی�҂Ƌ��E�����u�Θb�v�����邱�Ƃ͂������A���k���ǂ�Ȗ����Ɓu�Θb�v�����悤�Ƃ��Ă���̂��A�����āA���k���n�����n�A���E�̏�₻���ŕ�炷�l�X�⑽�l�Ȑ����Ƃ��u�Θb�v�ł���悤�ȖL���ȐS���鋳���ڎw���܂��B
�R�@���E�ɒʗp����p��͂̈琬
�Љ�C�O�ɑΉ�����u�^�̊w�́v�Â���B
�P�A�R�A�T�N���ɂ͑S���A�ꃖ���C�O��w���C�������Ȃ��܂��B
�R�N������͉p��̎��Ƃœ��{����g���܂���B
��w���i�͒ʉߓ_�ł���A�����ăS�[���ł͂Ȃ����Ƃ��ӎ����A�l�ߍ��݂�ËL�^�ł͂Ȃ��A�{���ɎЉ�ɖ𗧂\�͂̊J���ɗ͂��������܂��B
�S�@�����O�̑�w�ɂ��Ή������w��
�����̑�w�i�w��]�҂͂������A�C�O�̑�w�i�w��]�җp�ɂ͂����p�̃v���O������p�ӂ��Ă��܂��B���E�̂��܂��܂ȑ�w�ɐi�ފ�]�҂̂��߁ATOEFL��ASAT��̎��Ƃ��p��ōs���܂��B
�w�Z������
�P�O���@�U���i���j�@�ߑO�E�ߌ�@�y�Y���卂�Z
�P�O���P�Q���i�y�j�@�ߑO�E�ߌ�@�y�Y���卂�Z
�P�O���P�R���i���j�@�ߌ�@�@�@�@�@�����ۉ�c��
�P�O���P�X���i�y�j�@�ߌ�@�@�@�@�@�U�E�N���X�g�z�e����
�P�O���Q�O���i���j�@�ߌ�@�@�@�@�@�V��J ��t
�P�O���Q�V���i���j�@�ߑO�E�ߌ�@�y�Y���卂�Z
�P�P���@�Q���i�y�j�@�ߑO�E�ߌ�@�y�Y���卂�Z
�P�P���@�X���i�y�j�@�ߌ�@�@�@�@�@���ˎs�����
�P�P���P�O���i���j�@�ߑO�E�ߌ�@�y�Y���卂�Z
�P�P���P�U���i�y�j�@�ߑO�E�ߌ�@�y�Y���卂�Z
�P�P���P�V���i���j�@�ߌ�@�@�@�@�@�����ۉ�c��
�P�P���Q�R���i�y�j�@�ߌ�@�@�@�@�@�U�E�N���X�g�z�e����
�P�P���Q�S���i���j�@�ߑO�E�ߌ�@�y�Y���卂�Z
�P�Q���@�P���i���j�@�ߑO�E�ߌ�@�y�Y���卂�Z
�^�C���X�P�W���[��
�ߑO�@�@�X�F�R�O�`��t
�@�@�@�@�P�O�F�O�O�`�T�v����
�@�@�@�@�P�P�F�O�O�`�ʑ��k
�ߌ�@�P�R�F�O�O�`��t
�@�@�@�@�P�R�F�R�O�`�T�v����
�@�@�@�@�P�S�F�R�O�`�ʑ��k��
��10/13 , 10/19 , 10/20 , 11/9 , 11/17 , 11/23�͌ʑ��k�݂̂�13�F00�`15�F30�܂ōs���܂��B
http://www.tng.ac.jp/chugaku/index.html
�ˌ��w���@���獧�k��T�v�i�O�Q�N�V���Q�R���j
�n���Q�T�N�ڂ̊w�Z
�P�X�V�W�N�ɒj�q�̍����w�Z�Ƃ��ăX�^�[�g�B
�P�X�W�Q�N�ɒj�q�̒��w�Z���J�݁B
��K����u�K��
���Z�J�Z�����͂ǂ��ɂ��s���Ȃ����k�����w���Ă����B�����A�������ł����������Z�̊`�����̕���Z�������B
�������w�������k���^�ʖڂɂ���Ă��ꂽ�B
���ʂ̍����w�Z�̎��Ƃ�����Ă�����������Ȃ��B���ی�A�������k���c���Ē��P�̓��e�����蒼���������B�E�E���ꂪ�ˌ��w���̕�K���x�̃X�^�[�g�ɂȂ��Ă���B
���̈���������т��o���Ă���āA���w�҂̃��x�������X�ɏオ���Ă����B
���w���J�݂����Ƃ����A���w�Z�̓��e�݂̂Ȃ炸���w�Z�̓��e�̕��K���s���B
���k�̃��x�����オ��ɂ�A��K���̂̓��e���ς���Ă���B
���Z���͍��Z�̎��Ɠ��e���A���w���͒��w�Z�̎��Ɠ��e�����������˂������e�ɁB
��w�������x���̍u�K�����X�ɑ����Ă����B
���k�̃��x���A�j�[�Y�ɉ����ču�K���e���ω����Ă����B�����鐶�k�ɂƂ��ĉ����K�v�Ȃ̂������m�ɖ����B
�{�����Ƃ����S�ł��邱�Ƃ�O��Ƃ��āA�ˌ��w���ł͍u�K�ɓ��F������B
�u�K�̖ʔ����Ƃ��Đ��k�����R�ɑI�ׂ�Ƃ����_������B
�����u���ł��W�܂�搶�Ƃ����łȂ��搶���o�Ă���B�E�E���i�̎��Ƃ��L�`���Ƃ���Ă��Ȃ��Ɛ��k����I��Ȃ��B���̈Ӗ��ł͋����Ɏ���Ă͔��Ɍ������B
�܂��A���R�ɑI�ׂ�Ƃ������ƂŐ搶�Ɛ��k�̊ԂɓƓ��̐M���W�����܂��B�����͑I��ł������k�����Ƃ����������悤�Ƃ���B
�ˌ��w���̑S�̑�
�����Ŗ�R�O�O�O���̐��k���ʊw�B
���Z�F���w�@�Q�F�P
�j�q�F���q�@�Q�F�P
���P�͂X�N���X�i�j�q�U�N���X�A���q�R�N���X�j
�S�O���~�X�N���X�@�@�j�q�Q�S�O���A���q�P�Q�O������{�I�Ȑl���B
���N�͏��q�̓��w���ގ҂��������q�͂R�R���~�R�N���X�ɂȂ��Ă���B��N�͏��Ȃ������B
�⌇�J��グ�͂ł��邾���o�������Ȃ��̂ŁA���̐l���ŃX�^�[�g�B
�j�q�͂Q�T�V�������w�B�S�Q���N���X�ƂS�R���N���X������B
��l�S�C���Ŋe�N���X�ɐ�C����l�����B
�j�q�@�U�N���X�E�E�P�Q��
���q�@�R�N���X�E�E�@�U���i���q�̓N���X�S�C�̂����P���͏������������j
�w�N�S���̂P�W�����U�N�ԒS������B���̂��߃L���ׂ����w�����ł���B
�W���K�C����Ƃ��Ɉm���C�ꂠ���Ă��ꂢ�ɂȂ�B
������搶�Ɛ��k���C�ꂠ���Ė������Ƃ����̂��n���҂̍l�����B
����͐��k�Ɛ搶���ꏏ�Ɋ������邱�Ƃɂ���Đ��藧�B
�w�Z�s���ł������͐��k�Ɛ搶���ꏏ�ɐQ���܂肵�A�H�����ꏏ�������B
�w����̃L���ׂ������ǂ��V�X�e�������Ă������B
�P�@��l�S�C��
�Q�@���b�X����
�Ⴆ�Βj�q�̂U�N���X�͂g�q�͐��тɊW�Ȃ������ŕҐ��B
�����̓��_�Ŋe�N���X�̍ݐЎ҂������ɂȂ�悤�ɐU�蕪����B
�p��A���w�����ꂼ��K�n�x�ʂɁB
�R�N���X���ꏏ�ɂ��ĂR�i�K�ɍĕҐ�����B
��ԏ�ʃN���X�̐��ѕ����L����B��N����P�N���X�r�N���X��ݒu�B
�j�q�͂P�i�r�N���X�j�{�R�i�R�N���X���R�i�K�j�{�R�i�R�N���X���R�i�K�j�̃��b�X�����ɁB���q�͂R�N���X���R�i�K�ɍĕҐ�����B
���w�͂P�N�O������B�p��͂P�N�������B
���b�X���̓���ւ��͎����i�N�S��j�̓x�ɍs����B��ʃ��b�X���ɂS�E�T���A���ʃ��b�X���ɂS�E�T���ړ��B
���b�X���N���X�̏オ�������k�ɂ̓N���X�ړ��ɔ�����K���s���B
���b�X���N���X�̉����������k���ǂ��t�H���[���邩���|�C���g�ɂȂ�B
�R�@����Ƃ̏��̂����
�S�@�P�O���ԃe�X�g
���̃z�[�����[���i�W�F�Q�O�`�W�F�R�O�j�̎��Ԃ𗘗p���Ď��{�B�Q�T�ԂP�T�C�N���ŁA�R���Ԃ������A�R���Ԃ��t�H���[�B
�W�O�����Ȃ����k�͕��ی�c���ĕ�K�B���������̐��k�͖��_�����B
�N�S��̒�������̌��ʂɊ�Â��w���ł̓^�C�~���O�悭�w���ł��Ȃ��B
���e�X�g�Ŋ�{�I�ȓ��e�̗����̃`�F�b�N�ƂƂ��ɁA�{�l�̗l�q���`�F�b�N����B
���i���̂Ȃ����k�Ȃ̂ɓ_�������Ă��Ȃ������肷��Ɖ����������̂ł͂Ȃ����ƋC�ɂ�����B�Z�����Ԃ̒��Ő��k�̗l�q���m�F���Ă����B
�s���E��
���b�X���A�b�v��u
���w�T�}�[�L�����v�E�E�e�w�N���ɐ��k�����B�L�����v���[�_�[���w������B
�@���[�_�[�V�b�v�̊�{�͂g�q�B�g�q�Ŋw�Z���������܂��Ă��܂��B
�@�g�q�̂S�O�l�̐l�ԊW���ǂ�����Ă����̂����w�Z�S�̂��x����p�ɂȂ��Ă���B
�Ċ��u�K
�@���w���̎Q�����X�T���B���Z���̎Q�����V�T���B
�@�ߌ�̓N���u�������s���Ă���B
�Ċ����ʍu�K
�@���я�ʎґΏۂ̍u�K
�z�[���X�e�C�E�E��]�ґΏ�
�@�j�q�R�O���A���q�R�O���̘g�����邪�ŋ߂͊�]�҂����Ȃ��Ȃ��Ă���B
�J�E���Z���[�ʐM�E�E����I�ɔ��s
�@�Q�l�����ŏ풓���Ă���B
�@���ΐ��E�E�����J�E���Z���[
�@���؋��E�E�j���J�E���Z���[
�@�ŋ߂͐��k������I�ɗ��p���Ă���B
�@�e�����ڑ��k���邱�Ƃ��\�B
�}���فE�E���ی�P�W�F�R�O�܂ŊJ���Ă���B
�@���q�͂P�W�F�O�O�����Z���ԁB
�@�j�q�͂P�X�F�O�O�����Z���ԁB
�@�y�j�����X�F�O�O�`�P�U�F�O�O�܂ŊJ���Ă���B
�ċx�ݒ����w�Z�S�ق����R�Ɏg����B
�@�����̋����Ŏ��K���Ă��鐶�k�������B
�@�������o�Ă��Ă���̂Ŏ�����o����B
�@���K��������B
�@�i�w�Ō��ʂ��o�����k�͊w�Z�ɂ��Ă���B
�w�Z����
���ƁA�g�q�A�w�Z�s���A�N���u�������w�Z�����̑傫�Ȓ��B
�N���u������ϋɓI�ɐi�߂Ă���B
���w�łW�T���̎Q���B���Z�łV�O���̎Q���B
��w�����Ɍ����ō��i���鐶�k�̓N���u�����ɑł�����ł���B
���P�̂U�����̓N���u����������Ă���ƕ��ł��Ȃ��Ƃ������k���������A�Ă����z����ƒ��w���̑̂ɂȂ��Ă���̂ő��v�ɂȂ�B�Ă܂ő҂��ĂƘb���B
���Z���͊������𐧌����邱�Ƃ͂Ȃ��B
���w���͌����Ƃ��ďT�R���B
�싅���E�T�b�J�[���̊��ڗ����A���|���E�����������Ă���B
�w�Z�̃��x�����オ��ƌ������Ƃ͕������̃��x�����オ�邱�ƁB
�������̃��x���͎w�����鋳���̃��x���ɍ��E�����B
�y�j�u�K
�Q�O�O�P�N����y�j�����u�K�ɂ��Ă�B
�Q�O�O�Q�N�A�Q�O�O�R�N�̎w���v�̂̉����͊w�Z�̓Ǝ�����ł��o���`�����X�ƂƂ炦��B
�܂��T���������āA���̌゠��Ăēy�j���̎g�������l�����̂ł͂Ȃ��B
�y�j�����u�K���x�Ŏg���������߂Ɏ��ƂT�����Ɉڍs�B
�T�R�S���Ԏ��Ƃ��R�O���Ԏ��ƂɁB
�p�������P���Ԃ��J�b�g�i�U���Ԃ��T���ԂɁj�B�E�E����܂łU���Ԃł���Ă������e���T���Ԃł���Ɣ��f��������B
���̏�œy�j���ɕʂ̃J���L�������ōu�K��g�ށB
�u�K�Ŏ��ƈȏ�̌��ʂ������邱�Ƃ�����܂ł̌o���Ŏ������Ă����B
�V�������Ƃ͑g�܂Ȃ��i�T�O���~�U�����j�B�E�E���ی�̃N���u�����A��K���s�������B
���w�̓y�j�u�K
�P�E�Q�����ڂɉp���������[�e���V�����łR�T�ԂɂQ�s���B
�R�E�S�����ڂ̓��j�[�N�u�K�B�����A���K�A�|�p�A�̈�̊֘A�̍u�K���s���B
���Z�̓y�j�u�K
�P�E�Q�E�R�����ڂ��g���ĉp�����̍u�K���B
�S�����ڂɃ��j�[�N�u�K���B
�y�j�u�K�ł́A�����̐�含�������A��肽�����g�݂��ł���B�u�K�Ɏ��g�ދ����̈ӋC���݂����k�̊w�K�̓��@�t���ɂȂ�B
���Z�����Ȃ̔p�~
�Q�O�O�R�N���獂�Z�̗����Ȃ̖��̂�p�~����B
����܂ŗ����Ȃ͍������Ή��̃J���L�������A���ʉȂ͎��咆�S�̃J���L�������ɂȂ��Ă���A���Z�i�w���Ɋ�]�Ɛ��тŗ����ȁE���ʉȕ����Ă����B�R���̂P�������ȁA�R���̂Q�����ʉȂɂȂ��Ă����B
���k�̃��x���A�b�v�ɂƂ��Ȃ��A�S�̂��������Ή��̃J���L�������ɂ��A�͂��o��̖��͕̂��ʉȂɁB
�N���X�Ґ������P�ł͂r�`�N���X�i���i�N���X�j�Ƃ`�N���X�i���ʃN���X�j�ɁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i���@�@�@������
�@�j�q�@�r�`�N���X�@�@�Q�N���X�@�@�Q�N���X
�@�@�@�@�@�`�N���X�@�@�@�S�N���X�@�@�Q�N���X
�@���q�@�r�`�N���X�@�@�P�N���X�@�@�P�N���X
�@�@�@�@�@�`�N���X�@�@�@�Q�N���X�@�@�P�N���X
���Q���當�T�i�������n�j�A���U�i�������n�j�A���T�i�������n�j�A���U�i�������n�j�̂S�R�[�X�ɁB���T�͒j�q�R�N���X�A���q�Q�N���X�A���P�͒j�q�R�N���X�A���q�Q�N���X��\��B
���w�����Ɋւ���
���w�����͂S����{�B
���������D������Ƃ������Ƃ͓��ɂȂ��B
�e��Ƃ��������x���ɂȂ�悤����ݒ肵�Ă���B
�S��������k�łS�Ȃ̍��v�_���P��P�R�T�_�A�Q��P�S�O�_�A�R��P�T�W�_�A�S��P�X�T�_�Ƃ������k�������B�S��ڂō��i�B
���Ɋ��ꂽ��A�������̕��͋C�Ɋ����Ƃ������Ƃ͂���B
���̑�
��C���͂X�P���B�����P�U�V�����P�T�Q������C�B
��C����������y�j�u�K���ł����l�ȍu�����ݒ�ł���B
���ʍu�K�̏�ʎ҂͉p�������ꂼ��j���łR�O���w���B
�N�R����͎���������A���͎����̓��b�X�����ɊW�Ȃ��w�N���ʁB
���Z�ł̓X�|�[�c���E�łP�N���X������Ă��邪�A���w��̓��ʈ����͈�Ȃ��B
http://www.toko.ed.jp/
��������@������тւO�S�N�x�ɒ��w�Z���J��
�i�M�Z�����V���@�W���P�S���j
�@������卂�Z�i����s�j���^�c����w�Z�@�l�A������{��w�w���͏\�O���A�O�S�N�x�ɒ��w�Z���J�݂���v��𖾂炩�ɂ����B�����Z�ƕ��݂��A��w�i�w���d������������ы�����s���B�����Ŏ������w�̊J�݂́A�w�Z�@�l���v�w�����^�c���鍲�v�������i���v�s�j�ɑ�����Z�ځB
�@������{��w�w���͌��֒��w�Z�ݒu��\�����Ă���A�������w�Z�R�c����o�ė��N�\���ɐ����ɔF����錩���݁B
�@�v�悾�ƁA������卂�Z�~�n���ɍZ�ɂ����݂��A�O�S�N�S���P���ɊJ�Z�B�̈�قȂǍ��Z�̎{�݂����L����B��w�N�͈�w���l�\�l�Ōv��w���Ƃ��A���N�x�͈�w���l�\�l���W����v�悾�B��N�����獑������w�ւ̐i�w���ӎ���������ے���g�ށB�J�Z���͏T�Z�����Ƃ���B
�@��������E������卂�Z���́u�������ݒn�ł���Ȃ��璷��s�ɂ͎������w�Z���Ȃ��B������ы���ō�������w�ɍ��i���鐶�k�̈琬��ڎw�������v�Ƙb���Ă���B
�����̎��w�P�P
�����Ɛ��w�@�����@���P�O���Ԃ̓Ǐ��̎���
�@�u��������悤�v�B�Z��������Ă���ƁA���k�����������������킷�����������Ă���B
�P�X�R�X�N�Ɍ��Ă�ꂽ�����Ɛ��w�@�������w�Z���N���B�n���ҁA��]�X�~����̌��w�̗��z�ł���u�j�����������������i�m�j�v�u�u�����������i���j�v�u�`�����i�Z�j�v������ڕW�Ƃ��Ă���B
���Ă͉ƒ됶���̒��̋Z�p�Ƃ��Ă̈Ӗ������߂�ꂽ�u�Z�v�B���������́A����̐��k�ɍ��킹�āu�����Œm����������邽�߂̍H�v��Љ��g�ɒ����邽�߂̋Z�ɓǂݑւ��悤�Ǝv���Ă���v�ƁA�������Z���͐�������B
�n���ȗ����琶�k����͊����B���k�̎��含����Ă邽�߂ɁA�����Ղ�^����Ȃǎ�Ȋw�Z�s���͐��k���������^�c��S������B
�i�H�w�����u���k�̊�]���ɂ���v�B�ŋ߂͐i�H��]�����l���B�����Ɛ��w�@��w�A���Z����w�Ȃǂ̕��ݍZ�ɂ́A�������ł̐��E���w���\�����A���݂͐��k�̂X�������̑�w�A�Z��i�ށB�܂��A���n�u�]�҂̑����ɂ��A���N���痝�n�R�[�X��V�݂���B
�����R�N�قǁA���̃z�[�����[���̑O�ɂP�O���Ԃ̓Ǐ��̎��Ԃ�݂��Ă���B��҂̊�������̐H���~�߂ƁA���������Ď��Ƃɓ��邽�߂̑Ԑ����̈Ӗ�������B����ȊO�ł���A�D���Ȗ{���ǂ߂�B���܂́u�n���[�E�|�b�^�[�v���l�C�B
�����������|�|�ۊO����
��]�҂͒����Ɖؓ����w�Ԃ��Ƃ��ł���B�����͗���ƁB���R�ȏオ�ΏۂŁA�R�N�ŏ��t�̖͂Ə���擾�ł���B�Z���ɂ͖{�i�I�Ȓ������B����A�ؓ��͑�a�ԓ��ŁA������͑S�w�N���w�ׂ�B�U�N�ŏ��t�̖͂Ə��炦��B
�z�[���y�[�W�A�h���X
http://www.kasei-gakuin.ac.jp/chuko/
�����Ɛ���t���q�����@�u�j�Љ�Ő�����v�`��
�@�i�q�鋞���A�\���w���~��āA���q�吶�������������ֈꏏ�ɕ����ƁA�ɕ�܂ꂽ�Z�ɂɂ��ǂ蒅�����B�V���S�O�O�O�������[�g�����̍L��ȃL�����p�X�ɂ́A�����̍Z�ɂ̂ق��c�t�����w�A��w�@�A���U�w�K�Z���^�[������B�q�����獂��҂܂ŁA���܂��܂ȔN��̐l�X���s�������B
�P�W�W�P�N�ɑn�����ꂽ�a�m�ٖD�`�K�����N���Ƃ��A�P�Q�O�N����`��������B�n�ӐM�q�Z���́A�u�j���s�����̎���ɁA�j�ɗ{����̂ł͂Ȃ��A�Z�p�������Ď������悤�Ƃ������Ƃ���n�܂����v�Ɛ�������B�����u�j�Љ�̒��Ő��������͂̓`���͎c���Ă���v�����ŁA���w���ł������̖������Ƃ��͋�̓I�ȐE�Ƃ��o�Ă���B
�ŋ߂͎��w�u�������܂�i�H�����l���B���k�̔����͕��݂̓����Ɛ���֓������E�Ői�w�B����ł͉h�{�m�A�ۈ�m�A���w�Z���@�Ȃǂ̎��i���擾�\�B����A����w���u�]���鐶�k�͗��n���l�C�B���t�͖�ȑ��Ō�w�Z�̍��i�҂��ڗ����A�n�k�̌������������Ƌ�B��i�w�������k���B�u���q�������NJÂ����Ȃ��B�w���U�����Ő������鏗���x����Ă邱�Ƃ����痝�O�v
���w�Ɖp��ɂ��Ă͒��P�ł͂P�N���X���ɕ��������l�������ƁA���Q���獂�P�ł͏��l���̏K�n�x�ʎ��Ƃ����{�B���̂P�O���ԓǏ���̕��ꋳ���Ȃǂ�ʂ��Ċ����������B
�����������|�|�Ɛ��r�I�g�[�v
�����̍Z�ɂ̈�p�ɂЂ�����Ə����Ȓr������B��N�̏t�ɒa���B���k�⋳�@�A�E���T�P�l�ł���u�Ɛ��r�I�g�[�v�̉�v�����������Ă���B���S��N�����_�J�������B�g�߂Ɏ��R�������邱�Ƃ��ł���B?
�z�[���y�[�W�A�h���X?
http://www.tokyo-kasei.ed.jp/
�������S���q�����@���a�w�K�Ɖp��ɗ�
�@�u�}���A���܁@����Ȃ��Ƃ͎�����낱��Łv�@�Z�ɓ�������ƁA�n���ҁE�V�X�^�[�]�p���X�̌��t�ł���w���W�ꂪ�A�����炱����Ɍf�����Ă���B���~�q�Z���́u�����̐������̗��z�Ƃ��āA����}���A���f���Ă��܂��v�Ɛ�������B
�P�X�U�S�N�ݗ��̒�����я��q����̃~�b�V�����X�N�[���B��N����͊w���̃��[�c�ł��钷������Z�Q�N�����R���S���ŖK��w����̂́u���S�����v���ݒu���������z�[���Ȃǂ�K�₵���a�w�K���s���Ă���B
�J���L�������͏T�U�����B���w�P�A�Q�N���u�������v�����w�R�N�A���Z�P�N���u�W�J���v�����Z�Q�A�R�N���u�������v�\�\�ƂR�X�e�[�W�ɕ����A���ߍׂ����w�����s���Ă���B���k�͒������킹�ĂW�O�X�l�B���l�������ƂŁA���E�|�p�n�͌l�w���ɂȂ邱�Ƃ�����B
���ɗ͂����Ă���̂��p�ꋳ�炾�B���w�P�N����N���X���ɕ����Ẳp��b���Ƃ�����ق��A���w�Q�N�͂R���S���̉p��L�����v�A���Z�P�N�͂Q�S���Ԃ̊C�O�z�[���X�e�C������B���Z���́u�w�p��������̕���ł������o���邩��厖�ɂ��Ă���v�Ƙb���B
���N�P�Q���i���N�͂Q�R���j�ɂ͊w���O�̎��̐S����₻���ƁA���k�Ƒ��Ɛ������S�ƂȂ����u�N���X�}�X�E�y�[�W�F���g�v���J�Â��Ă���B�u�S�̋���ƒm�I����̗����v���w���̊�{���O���B?
�����������|�|�J��̎���
�L�����p�X�͑�R���R�����̒����B�L���Ȏ��R�̒��ʼnԁX��_�앨���͔|���Ď��n����u�J��v�̎��Ƃ�����B�u���R����w�Ԃ��Ƃ͖����v�Ƃ̍l���ŁA�n���ȗ��̓`�����B���Z�R�N���̓T�c�}�C�����͔|���A�Ă����ɂ��ĐH�ׂ���A�V�l�z�[���ɂ������������Ă���B
�z�[���y�[�W�A�h���X
http://www.t-junshin.ac.jp/
�������w�ْ����@���k�Q�O�l�ɒ��J�Ȏw��
�@�ɓ������炪����Ă������q���珧���u���E�̏����ƑΓ��Ɍ��ۂł���l�ނ��琬�������v�ƂP�W�W�W�N�ɑn���B�������j���̕⏕�҂Ƃ��ĂłȂ��A���Ȏ�����B���ł���悤�ɂƁA�P���I�ȏ�ɂ킽���ď��q����Ɏ��g��ł����B
���{�l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�[���m�����A�p��͂�ɐ��E�̕���Ń��[�_�[�V�b�v�����Ċ��鏗���̈琬��ڎw���B
�p��Ɛ��w�𒆐S�ɁA�N���X���ɕ������������Ƃ����{����A�����P�l�����k�Q�O�l���x��Ώۂɒ��J�Ȏw�����s���B������������ی�܂ŁA�������ɂ͐��k�����X�Ǝ���ɖK���B���������̗����A���ۓI����̈琬�ƕ���ŁA���a����A������A���A�{�����e�B�A�w�K�̐��i���d�_�ۑ�Ƃ��Đݒ肵�Ă���B
����i�E���Z���́u�������j�̒��ŁA��Ȃ��̂Ƃ��Ďp����Ă����̂́w�i���x�ł��v�Ƙb���B����l�w�Z�ƌ���ꂪ�������A�Z���̕��͋C�͖��邭�A�ɂ��₩�B�u���t�Ɛ��k�̋������߂��̂������v�i�����F�������j���Ƃ����B
�u�C�M���X�ł͍��M�Ȑl�͔��𒅂�v�Ƃ̗��R�ŁA�P�X�R�O�N���琧���͔����Z�[���[���B���V���N�̃��{���A���̃X�J�[�g�B�V���A���i���o�[�����܂ꂽ����̍Z�́A�X�p�b�f�U�C���̃R�[�g�ƍ��킹�A�����̐l�C�͌Q���Ă���B
�����������|�|�������C
�u�ٕ������ݗ����v��ړI�ɁA�ċx�݂ɕč��Ⓦ��A�W�A�Ō��C����v���O�����B�A�����J�������C�ł́A��w���ɑ؍݂��A�����č��l�����ɂ��Ă܂��A����̐������ɑ̌�����u�V���h�[�C���O�v���s���B
�z�[���y�[�W�A�h���X
http://www.h.tjk.ac.jp/
�������q�w�@�����@���A������A���y����Ƃ�
�@�����V�h�����c�n�ꂩ��P�W���A���}�łR�w�ڂ́u�����ցv�́A�����̂Q�R����Ō�̒�ԉw�B�L�����p�X�͉w����k���R���̌�ʎ��ւȏꏊ�Ɉʒu����B�������u�̏�Ɍ��Z�ɂ̑�����́A���ꂽ���A�͂邩�����ɕx�m�R��������B
�L���Ȏ��R�Ɉ͂܂ꂽ�Z���́A���ǁA�L���A���A�֎q�ɂ�����܂ŁA���ׂĖؑ��d�グ�B�n���҂́u���͐l������v�Ƃ̗��O����A�̉�������ɂ��Ă���Ƃ����B�{�i�I���{���z�̗�@����A���p�ق�����B�R�������쑺�ɂ��L�����p�X������A���p���C����h�����������B
��Q�O����Ƃ��ăt�����X��܂��͒����ꂪ�K�C�B���Ă̓t�����X���I�����鐶�k�������������A���݂ł͒�����Ɣ��X���Ƃ����B
�|�p�������߁A��������|�����߁A���w�Z�ł͏T�Q���ԁA�u���y��v�̎��Ƃ��s���B�o�C�I�����A�r�I���A�`�F���A�R���g���o�X�̂S��ނ̒�����I�ԁB�����̓��݉Ȗڂ́A�w�Ԃ��Ƃ̊y������̌������邱�ƂƁA��l�ЂƂ�̌������A�˔\��L�����Ƃ��ړI���B
���{�����̐��_�ƒ��a�̂Ƃꂽ���������w�ԏ����Ƃ��āA�u��@�v�u�ؓ��v���K�C�ƂȂ��Ă���B����Z���́u�L���Ȑl�Ԑ��͑f���ȐS�A����S�A�v�����̐S�A�E�ϐS�����������邱�Ƃɂ��琬�����v�Ƙb���Ă���B
�����������|�|����������
�u�܂��߂ɐ����邱�Ƃ̉��l��m��A�[�������l���𑗂�v�l�Â����ڎw���A���w�̐��_�́u�����̐������̂��̂�����v�B�Q�O���ɂ́u�I�[�v���L�����p�X�v�Ŋw�Z�̓��F��������A�����ʑ��k�����{����B
�z�[���y�[�W�A�h���X
http://www.tjg.ac.jp/
�������q�w�������@�u�i�w�t�F�A�v������
�@�u�l�̒��Ȃ�l�ƂȂ�v�����痝�O�B�������q�w�������i���g���v�Z���A���w�Q�R�S�l�E���Z�S�Q�U�l�j�͗��N�A�n���P�O�O���N���}����B�u���ꂼ��̏�řz�i���j�Ƃ��ċP���Ăق����Ƃ����肢�̂��ƁA���k����l���̊w�Z�A���k�̖�����w�Z�Â����i�߂Ă���v�ƒC�����q�����͘b���B
���w�̕�u�A���Z�̒ʔN�u�K�E�Z���W���u�K�ȂǂŐi�w�w�����[�������邪�A������m��A���R��Љ��m��u�i�H�w�K�v�Ȃǂ�ʂ����l�i�̓���i�Ƃ���j���d�����Ă���B�u�����ōl���A���������߁A�l�̈ӌ����A�����̈ӌ��\�ł��鐶�k�ɂȂ��Ăق����B���ꂪ�w��l���x�ɂ��Ȃ���܂��v�ƒC�������B
���w�̉p��͊�����{�����e�B�A�����Ȃǐ��E�̏o�������p��ŕ����A���\����B���Ȃ͊ώ@������𑽂�������A�Љ�ō]�ˎ�����w�Ԃɂ͗���������B�̈�̑n��_���X�͑傫�ȁu���ȕ\���v�̏ꂾ�B
���Z�ɂ͑����̑I���Ȗڂ��p�ӂ���A��]�҂��������A���Ƃ����l�ł��J�u����B�P�P���ɂ͑�w�̓����S���҂������A���k�����R�ɑ��k�ł���u�i�w�t�F�A�v�k�̎���ŊJ�ÁB��N�͂W�P��w���Q�������B
���g�Z���́u�Ȃ��w�Ȃ���Ȃ�Ȃ����k���g�ɋC�t������͓̂���B����𗝉����A�[���������@�̊J�����ۑ�ł��傤���v�Ƙb���Ă���B
�����������|�|���E���W
�u�搶�A�����āv�B�E�����O�̃��E���W�ɂ͊��ƈ֎q������A�x�ݎ��Ԃ���ی�͂����ɐ��k�����ł����ς��ɂȂ�B���k�Ɛ搶�̃R�~���j�P�[�V���������ɖ��ŁA�搶�̖ʓ|���̂悳�́u�a���Ĉ��S�Ȋw�Z�v�̏ؖ��ł�����B
�z�[���y�[�W�A�h���X
http://www.tokyo-joshi.ac.jp/
���������咆���@���ɓI�Ȏq�ɂ��ڌ���
�@���������咆���i�ؓ��G���Z���j�͌Z��E�o�����������ɒʂ��Ă���P�[�X�������B���l�ɐU��ꂪ���Ȋw�Z�I�т����A�v���X�A���t�@�̍Z���������{���̎��w�̓������`�Â����Ă���B���ꂾ���Ɂu�搶�Ɛ��k�̒��������v�u���ɓI�Ȏq�ɂ��ڂ������Ă����v�Ƃ����ی�҂̐������Ă��邱�Ƃ��ւ肾�Ƃ����B
�V��������e�[�}�Ƃ��āu�n�����Ǝ����v���f����B�u���w�Ŋ�{�I�Ȑ����E�w�K�K����g�ɒ������Z�Ŕ��W������B�����ōl���A�����𗥂��邱�Ƃ̂ł���l�ނ���Ă邱�Ƃ��ڕW�ł��v�ƕ���G���͌����B
���w�i���k���S�O�O�l�j�ƍ��Z�i���P�P�P�U�l�j�͈�уR�[�X�𒆐S�Ƃ��A���w�E���Z�R�N�Ԃ��Ƃ�����������������A�S�N�{�Q�N�Ƃ����l���������B�i�w�R�[�X�̍Ō�̂Q�N�ԁi���Z�Q�A�R�N�j�͕��n�A���n�ɕ������ق��A�p��A���A�c������A�����Ƃ��������k�̊w�т����Ƃ����ӗ~�Ə����̊�]�ɉ��������ߍׂ��ȃJ���L��������p�ӂ��Ă���B
���k���m�A�ݍZ���Ƒ��Ɛ��̂Ȃ���������o�[�V�b�v�ƌĂ�ő��d���A�N���u������̈�ՁA�����ՂȂǂ̃C�x���g�͐��k�́u���含�v�ɔC���Ă���B�{�فE�ʊقƂ��V�����������Ƃ��Ă���A�e�K�Ƀ��E���W������B���݁A���q�������邪�A�O�R�N�x�̐V��������S�ʋ��w�������B
�����������|�|�T�^�f�[�v���O����
�u�͈͂⎞�Ԃ��ċ�����Nj����鎞�ԁv�Ƃ��āA�T�T�������t���p���A���w����Ώۂɓy�j���Ɏ��{�B�����A�����A���t�y�A�X�|�[�c�A���|�Ƒ��ʂŁu���Ԃ�Y��Ėv���ł��鎩�R�I���̃v���O�����v�Ƃ����B
�z�[���y�[�W�A�h���X
http://www.tokyoseitoku.ac.jp/
�����d�@�咆���@������ώ@���d�v��
�@�P�X�O�V�N�n���́u�d�C�w�Z�v����̂ŁA�X�Q�N�Ɍ��݂̏ꏊ�Ɉړ]���Ă����B�X�U�N�ɒ��w�Z�݂��A�X�X�N�x����w�Ȃ̕Ґ��Ƌ���ے������߂Ēj�����w�ɂ����B�u�l�Ԃ炵��������v���Z�P�B��w���܂߂����H�n�����w���Ƃ��āA���Ȃǂɗ͂����Ă���B
���k�̐i�H�͑��l�����Ă���B����ɑΉ����邽�ߍ��Z�Q�N���痝�n�E���n�̃R�[�X�ɕ����A���k�̓K���ɑΉ������i�H�w�����s���Ă���B���k�̂R���͍��Z���ƌ�A���n��i�H�ɑI��ł���B
�����A���v�L�B�Z���́u�^����������ƔF�����邽�߂ɂ́A�����Ɗώ@�ɐG���@��K�v�v�Ƙb���B�i�H�ɊW�Ȃ��A���n�̒m����g�ɒ����邱�ƂZ�ł͏d�v�����Ă���̂��B
���w�ł́A�Q�N�����Η͔��d���A�R�N�����]����́u�K�X�̉Ȋw�فv�����w����ȂǁA���n�ւ̊S�����߂鋳����s������A�ό���N���b�V�b�N���y�ӏ܂ȂǕ������{������[�����Ă���B
�p�ꋳ��ɂ��͂����Ă���B���w�ł́A�O���l���t�ɂ��ߑO�W������́u���[�j���O���b�X���v�A���Z�ł͊w�����ɕ��������l������ȂǂŁA�p��b�\�͂̌����ڎw���Ă���B
�����������B���Z�̎��]�ԋ��Z���͖��N�S�����ɏo�ꂵ�Ă���ق��A�Ȋw���ł͔M�C����^��ǃA���v�삷��ȂǁA��w���畉���̊��������Ă���B
�����������|�|���
�p�\�R�����S�T��ݒu���ꂽ�������R������A���w����v���[���e�[�V�����E�\�t�g�̎g�������w�ԂȂǎ��H�I�ȋ�����s���Ă���B���w�A���Z�̐��k�S�������[���A�h���X�������A���|�[�g�̒�o���C���^�[�l�b�g�ōs���Ă���B
�z�[���y�[�W�A�h���X
http://www.kgn.dendai.ac.jp/
����������
�L���X�g���w�Z�t�F�A�i��R��j
�s���̃v���e�X�^���g�n�̃L���X�g���w�Z�P�V�Z���W�܂�A�W���Q���A�R���̂Q���ԁA����̓���������Z���^�[�ōs��ꂽ�B
���k�ɂ��w�Z�����̏Љ�≹�y�̒��ׂ�ʂ��Đ��k�̗l�q��m���Ă��炨���Ƃ���\���ɂȂ��Ă����B
 �@�Q���Z�̐��k�ɂ�鉉�t
�@�Q���Z�̐��k�ɂ�鉉�t
������
������w�[�t���@���Ɨ��[�t���@�R�O����ʼn��P�@�[�t����������
�i�����V���@�V���Q�W���j
�@�����傪�O�[���������Ɨ��Ȃǂ���w���ގ҂ɕԊ҂��Ȃ����ŁA��Ȏ���⎄�����̂قƂ�ǂ��A�O�R�N�x�̈�ʓ����ł͎��Ɨ��Ȃǂ̔[�t���������������������̍��i���\���ȍ~�ɐݒ肵�A�u�ڂ�������v�����P��������ɂ��邱�Ƃ��A�����V���Ђ̒����ŕ��������B�����Ȋw�Ȃ̒ʒm�ɉ������[�u�ŁA���E���w�ł���U�����������̔��\��ɑO�[���̕Ԋ҂ɉ�����Ƃ��Ă���B�������A���w���͂�����̑�w���Ԋ҂��Ȃ����j�ŁA���̕s���͎c�肻�����B
�@�����͊w�����T�O�O�O�l�ȏ�̑�w�ƈ�ȑ�̌v�P�P�U�Z�i���Ɨ��Ȃǂ�S�z�ݗ^���鎩����ȑ�A�Y�ƈ�ȑ�������j�ɗ��N�x�̑Ή������B
�@��ʓ����ł͂O�Q�N�x�A�R�R�Z�i�Q�W���j���A���Ɨ��Ȃǂ̔[�t��������w�����ނ����ꍇ�̔[�t���̕ԊҊ��������������������̍��i���\�i�R���Q�S���j�O�ɐݒ肵�Ă����B���̂��߈ꕔ�̎��͍�������̍��ۂ�������Ȃ������Ɏ��Ɨ��Ȃǂ�[�߁A�Ԋ҂����Ȃ������B
�@�������A���N�U���A���n��̌����T�W�l���Q�W�̑�w�A���w�Z�����Ď��Ɨ��Ȃnjv��T�X�O�O���~�̕Ԋ҂����߂�W�c�i�ׂ��N�����A����́u�ڂ�������v����艻�B�����Ȋw�Ȃ��A��������̌�������̔��\��܂őO�[���̔[�t��P�\���A�Ԋ҂ɂ�������悤�ʒm�����B
�@���̂��߁A�O�R�N�x�͂R�O�Z���]���̑Ή������߂�Ɖ��A�P�P�R�Z�i�X�V���j���[�t������ԊҊ����������������̔��\��ɐݒ肵���B�P�Z�������������̑O�ɐݒ肵�����{�̈����u�O�S�N�x�ȍ~�͍����̔��\��Ƃ��邱�Ƃ������v�A���w�@��Ɛ��R���w����́u�������v�Ɖ����B
�@�P�P�U�Z�̂������E���w�Ȃǂ����{���Ă���̂͂P�P�S�Z�ŁA�O�Q�N�x�ɑO�[���������Ɨ��Ȃǂ������������̔��\��ɕԊ҂��Ă����̂͂R�Z�����������B�O�R�N�x�͂V�O�Z�����ׂĂ̐��E���w�ō����������̍��i���\��҂��ē��w���ގ҂ɕԊ҂���ӌ����������B
�@����A������ȂǂX�Z�́u���E���w�ł͌����Ƃ��ĕԊ҂ɉ����Ȃ��v�ƉB��R��ȂǂP�T�Z�́A����w�Ƃ̕����F�߂鐄�E���w�ł͕Ԋ҂ɉ����邪�A��萄�E�̍��i�҂ɂ͌����Ƃ��ĕԊ҂��Ȃ��Ƃ��Ă���B
�@���̌��ʁA���E���w�̂Ȃ����Q�Z�ƁA���ׂĂ̐��E�ŕԊ҂ɉ�����V�O�Z�����킹���V�Q�Z�i�U�Q���j�ŁA�S���i�҂������������̌��ʂ�������ŁA�O�[����[�߂邩�ǂ������f������A�O�[����Ԋ҂��Ă��炦�邱�ƂɂȂ�B
���Ȍn�łU�O�`�W�O���~
�@����̕��Ȍn�ł́A���w���i�P�O���`�R�O���~���x�j�ƁA�������̎��Ɨ��Ǝ{�ݔ�����킹�ĂU�O���`�W�O���~���x����w�葱�����ɔ[�t������Ƃ��낪�����B���H�n�̔[�t�z�͂������⍂���S���\���~�B���ł͓��w�������łP�O�O���`�Q�O�O���~�ɂȂ�A�[�t���͂U�O�O���`�P�Q�O�O���~�O��ɂȂ�B�����Ȋw�Ȃ̂O�P�N�x�����ł́A�S����̏��N�x�[�t���͕��ςP�Q�W���~�A�������w�����Q�W���~�ƂȂ��Ă���B
�����{�@�������@�������c�_�T�v�̗v�|�A�����R
�i�����V���@�V���Q�X���j
���S�̂ɂ��ā�
�@���s�@�̕��ՓI�ȗ��O�͎c���Ȃ���A���@�̘g���ŐV������{�@�͂ǂ�����ׂ�����������B
������̖ړI��
�@�ȉ��̐V���Ȏ����荞�ޕ����Ō����B�i�P�j�l�̔\�͂̐L���A�n�����̟��{�i����悤�j�A�l�̎��Ȏ����i�Q�j�u���v�̈ӎ��A�����S�A�����S�A�K�͈ӎ��i�R�j���ې��A�`���╶���̑��d�A���y�⍑��������S�̈琬
������̋@��ϓ��Ȃǁ�
�@�K���ɉ��������l�ȃ��[�g�̑I���A�����Ɣ\�͂ɉ���������𐄐i���ׂ����Ƃ̈ӌ�������B
���w�Z�A�ƒ�A�n��̖�����
�@�����̎g������Ӗ��m�ɂ���B�ƒ�̖�����ӔC���K�肷��B�w�Z���m�E���E�̂��������ł��邱�Ƃ��K�肷�ׂ����Ƃ����ӌ�������B
���@�����灄
�@�u���ՓI�ȏ@���S��������K�v�v�u�w�Z�ł͏@������łȂ�����������s���ׂ����v�ȂǑ��l�Ȉӌ�������B
��d�����ƕ]���@�������Z�̃{�����e�B�A�����ɐ��ѕ]�����A�����R
�i�����V���@�V���Q�X���j
�@���N�̕�d�E�̌������̐��i����������Ă�����������R�c��i�����וF��j�͂Q�X���A�������Z�̎��Ƃ̈�Ƃ��ă{�����e�B�A���������{���邱�Ƃ�A�������e���L�^����u�p�X�|�[�g�v�������̂����A������A�E�����ȂǂɊ��p����悤���߂铚�\���܂Ƃ߂��B�w�Z�ł͋��犈���Ƃ��Ď��{����{�����e�B�A�����Ȃǂ����ѕ]���̑ΏۂƂ���Ƃ��Ă���A�����シ�ׂĂ̎q���̎Q�������߂Ă���B�����Ȋw�Ȃ͂�����A��d�E�̌��������w�K�w���v�̂ɐ��荞�ނ��Ƃ���������B
�@���\�́u���ׂĂ̐��N�ɕ�d�E�̌������̋@���^���邱�Ƃ��d�v���v�ƒ�N�B�w�Z�⋳��ψ���A���̂��ꂼ�ꂪ�x������u����K�v������Ƃ����B
�@��̓I�ɂ́A�s���{����s�������A���Z����̃{�����e�B�A�����̎��т��L�^����u�����O�E�{�����e�B�A�E�p�X�|�[�g�v���쐬���ē���I�Ȋ������L�^���A��������Ƃɍ��Z�ŒP�ʂ�F�肵����A��w������A�E�Ɋ��p���邱�Ƃ��Ă����B�܂��A�p�X�|�[�g�����҂ɂ͔����قȂǂ̕����{�݂�X�|�[�c�{�݂̗��p������������Ȃǂ̓��T��^����Ȃǂ��Ď��m���A��҂̊����ւ̎Q����U������悤���߂��B
�@�������Z�ł́A���Ȃ���w�K�̎��ԁA�w�Z�s���Ȃǂ̒��ŕ�d�E�̌����������{����Ƃ��Ă���A������̑S���Q�������߂���j���������B���Ȏw���ɐ��荞�܂��A�]���̑ΏۂɂȂ邪�u��d�E�̌������̕]���͓_���������A�q���̗ǂ��ʂ�ϋɓI�ɕ]������v�Ƃ��Ă���B�܂��A���Z�����ł��A�{�����e�B�A������ϋɓI�ɕ]�����邱�Ƃ����߂Ă���B
�@���̂ق��A��w�ł��{�����e�B�A�u�����J�݂�����A�{�����e�B�A������P�ʔF�肷��ƂƂ��ɁA�A�E�̍ۂɊ�Ƃ⍑���A�w���̗������ɕ�d�����̗L�����L�ڂ��闓��݂���悤�����B
�@�{�����e�B�A�����Ȃǂɏڂ����u����₩�������c�v�������ŕٌ�m�̖x�c�͂���̘b�@�w�Z����ɎЉ�v��������������邱�Ƃ́A�l�Ԑ��E�Љ�����コ����_�����炾�B������A���{���@���d�v���B�ǂ�Ȋ������ǂ̂悤�ɂ��邩�A���̐��ʂ��ǂ��L�^���邩�Ȃǂ͎q�������̎��含�ɔC���āA����𗧂�т𖡂�킹��ׂ����B���܂��������������o���A�q�������͎���i��Ŋ������A�l��Љ�ɖ𗧂�т��w�Ԃ��낤�B�搶�̎w���̎d���łǂ��ɂł��Ȃ�u���n�̌��v�Ƃ�������B�n��Љ�̋��͂����߂�̂��������낤�B
�֘A�L���@�����R����d�����̋`�������\�@���Ɍ����̔�����
�@��������R�c��i�����וF��j�͓�\����A��d�������������Z�̋���v��Ɉʒu�t���ĎQ����������`����������ŁA���Z�A��w�ŒP�ʂƂ��ĔF�肵����A������A�E�̍ۂɕ]�������肷��Ȃǂ̐��i����A���R�֎q�����Ȋw���ɓ��\�����B
��
�@��d�����̎�����̋`���������߂��\����̒����R���\�ɑ��A���Ɍ����ł͌˘f�����L�����Ă���B��_�E�W�H��k�Ђł̓{�����e�B�A���傫�Ȗ������ʂ����A���w��N����ΏۂƂ����u�g���C���E�E�B�[�N�v�́A�S���̎Љ�̌������̐�삯�ƂȂ����B���ꂾ���ɕ�d������]���̑ΏۂƂ��邱�ƂɁA��������ӌ������Ȃ��Ȃ��B
�@�쐼�s�̒��w���@�i�S�X�j�́u�k�Ў��A�q�ǂ������͎���I�Ƀ{�����e�B�A�ɎQ�����A�����炱���͂������B���ꂪ�]���̑ΏۂɂȂ�A�q�ǂ����˘f���̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����B
�@���ɂ̌������Z�����́A���\���Ɠ����̐��т��䗦�ŕ]������B���\���̊������������߁A����ł����k��ȂǕ]���ɂȂ��銈���ɊS���W�܂�Ƃ����A�u�`�����ɂ���āA�{�����e�B�A���_���������ɂȂ�Ȃ����v�ƐS�z����B
�@���Ɍ��͈��㎵�N�A���w��N�����n��̎��Ə��ȂǂŎЉ�̌�������u�g���C���E�E�B�[�N�v���X�^�[�g�B�S�����璍�ڂ���A����̒����R�̋c�_�̒��ł��u������v�Ƃ��ďЉ�ꂽ�B
�@�u�g���C���v�͈ӗ~�̗L���ȂǁA�]���̑ΏۂƂȂ��Ă���B�������A���Ԍ���̑S���Q���ŁA��d�Ɍ��肹�����L�������𐄐i���Ă���B
�@�������Z���@�i�T�R�j�́u��d������]�����邱�Ƃ͓���B���ǂ͉ŋ����悤�Ȍ`�ɂȂ�v�Ǝw�E�B���Ɍ����ς�����u��d�̈Ӗ��������邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��v�ƌ��O�̐����������B
�@�{�����e�B�A�c�̂̎~�߂͂ǂ����B�����c�������@�l�i�m�o�n�j�u�s�������Z���^�[�_�ˁv�̎��g�Ў����ǒ��́u��d�̋`�����̓i���Z���X�B�����I�ӗ~�̂Ȃ��l���������āA�ΐl�T�[�r�X�ɂ������̂͂Ƃ�ł��Ȃ����ƁB��Q�҂⍂��҂͋���̓���ł͂Ȃ��v�Ɣᔻ����B
�@�m�o�n�@�l�u�R�~���j�e�B�E�T�|�[�g�Z���^�[�_�ˁv�̒������q�������́u�m���ɑ����Ȏ����Ƀ{�����e�B�A�œ�����̂͑傫���B�w�Z�����[�g���J���Ă����̂͂��肪�������A�{�����e�B�A�����Ȃ����Ƃŕs���v�ɂȂ�̂͂��������B��������͎^���ł��Ȃ��v�Ƙb�����B
���ȏ����茩�����@�w�K�w���v�̂ɂȂ����e�̋L�q�F�߂�@���ȏȂ̐R�c��
�i�����V���@�V���R�P���j
�@���ȏ����x�̌��������������Ă��������Ȋw�Ȃ́u���ȗp�}�����蒲���R�c��v�͂R�P���A�������Z�̑S���ȏ��Ŋw�K�w���v�͈̂̔͂����u���W�I�Ȋw�K�v�荞��A����ɂ���Č������قȂ錩�������鎖���ɂ��Ĉ�w�u�o�����X�̂Ƃꂽ�L�q�v�����߂邱�ƂȂǂ������܂Ƃ߂��B������ē��Ȃ́A�������������A���N�x���狳�ȏ��S�̂̂����A�����w�Z�łP���A���Z�łQ�����x������ɔ��W�I�L�q��F�߂���j���B
�@�ł́A���W�I�Ȋw�K�Ƃ��āA�P�w�N��Ŋw�ԓ��e��w�K�w���v�̂ɂȂ����e�������A���ȏ��ւ̋L�q��F�߂��B���ׂĂ̎����E���k���ꗥ�Ɋw�K������̂ł͂Ȃ����Ƃ���A�{���ł̋L�q�͋������A���O��R�����Ȃǂň����A���W�I�Ȋw�K���e�ł��邱�ƂL���邱�Ƃ��K�v���Ƃ��Ă���B�����̊w�̓e�X�g�ɂ͏o�肵�Ȃ��悤���߂��B
�@�܂��A���ȏ��̓��e�𗝉����₷�����邽�߁A�]������w�L�q�Ɍ�������o�����X�����߂���Ƃ��A���j�̎��ۂȂǂŕ����̌���������ꍇ�A���܂��܂Ȍ��������邱�Ƃ������E���k���͂�����F���ł���悤�ȋL�q�����߂��B
�@���̂ق��A�����̂̋��ȏ��̑��ɂ��Ă��A���݂W���P�T���ɂȂ��Ă���������Q�T�Ԓ��x�������A���Ԃ������Ē����ł���悤�ɂ��ׂ����ƒB����ψ���Ȃǂɋ��ȏ���Ђ����錩�{�̕����𑝂₷���Ƃ�A�����̎����̂ō\�������̑�n�悲�Ƃɍ̑����鋳�ȏ������߂邽�߂̃��[�����߁A�ǂ̋��ȏ����̑����邩�Ō����������ꂽ�ꍇ�́A���[���ɉ����Ď葱����i�߂邱�Ƃ��K�v���Ƃ��Ă���B
�@�܂��A�Â��ȍ̑��̊����K�v�Ƃ��A����ψ���Ȃǂɑ���W�Q����������ꍇ�́A�x�@�Ȃǂ��܂ދ@�ւƘA�g���ċB�R�i������j�Ƃ����Ή������悤���߂��B
�����ȏ��@���Q�����ρA���t�V�݂̂R�������w�ō̑��ց@�������ł͑S����
�i�����V���@�W���W���j
�@���Q�����ς��A������ы���̓����ɔ����ė��t�V�݂��錧�����w�R�Z�ŁA�u�V�������j���ȏ��������v�̃����o�[�炪���M�����}�K�Ђ̒��w���j���ȏ����̑����錩�ʂ��ł��邱�Ƃ��V���A���������B�������ł̍̑��͑S���ŏ��߂ĂƂȂ�B�����ȏ��͍�N�A�̔ۂ��߂����Ďx���A�s�x���̌������_�����N���Ă���A�Ăєg����Ăт������B
�@�����ς͍�N�W���A�u���y�������A�����̏Z�ލ��Ɍւ�����Ă�q������Ă�Ƃ����_�ŁA�������D��Ă���v�i�g��������E�����璷�j�ȂǂƂ��Č����{��A�낤�w�Z�̈ꕔ�œ����ȏ����̑����Ă����B
�@�����ϊ����͖����V���̎�ނɑ��A�u��N�Ɠ������ȏ���R�c���āA�ʂ̌��_���o�����Ƃ͖�������v�Ƃ��Ă���B
�@�����ς͂V���A�̑��ɂ��ĐR�c���鋳��ψ��������A�̑��������̍����P�T���ɊJ�����Ƃ����肵���B
�֘A�L���@�V�݂̒�����эZ�ŕ}�K�Дŋ��ȏ����̑��@���Q�����ρi�����V���@�W���P�T���j
�@���Q������ψ���i�U�l�A�ψ�������֘a�F�E��F���H��c����j�͂P�T���A���t�J�Z���錧��������ы���Z�R�Z�Ŏg�����j���ȏ��Ɂu�V�������j���ȏ��������v�哱�̒��w�Z���j���ȏ��i�}�K�ДŁj���̑������B��N�Ɍ����̗{��A�낤�w�Z�̈ꕔ�ō̑������̂ɑ������肾���A�����Ȋw�ȋ��ȏ��ۂɂ��ƁA�������̕��ʒ��w�Z�ŕ}�K�Дł��̑������̂͑S�����B
�@�}�K�Дł��̑������̂́A���w�݂���`�łO�R�N�S���ɊJ�Z���錧���̒�����ы���Z�̍������i�����s�j�A���R���i���R�s�j�A�F�a����i�F�a���s�j�̂R�Z�B���t����v�S�W�O�l���g�����ƂɂȂ�B
�@���̓��A���ȏ��R�c�͔���J�Ŏ��{���ꂽ�B�����ǂ��e���Ȃ̍̑����X�g�������ē��e������B���j���ȏ��ł͕}�K�Дł������LjĂƂ��Ď����A���F�����B�ψ��ɂ͂U���Ɍ��荇�i�W�Ђ̋��ȏ����z�z����A�ʂɌ�����i�߂Ă����B
�@����͂V�����납��A�}�K�ДłɎ^���A���̗��h�������ς�ψ���ւ̒�E�v���𑱂��Ă����B���̂��߁A�����ς́u��������������v�Ƃ��āA�̑��̊����ƂȂ��Ă���P�T���Ɉψ�����J���ĐR�c�����B
�@��N�͓����s���{��w�Z�̈ꕔ�ƈ��Q�����{��A�낤�w�Z�̈ꕔ���̑������B���H�̓��Ȃ̒����ɂ��ƁA���t����g�p�����}�K�Дł͎����Z���܂߂ĂT�Q�P���ŁA�S���V�F�A�͂O�D�O�R�X���������B
�}�K�З��j���ȏ��@��t�E���V���Ŏg�p�i�Y�o�V���@�W���P�T���j
�@��t�����s�̎������V��(���J�f���Z��)�͂P�S���܂łɁA�V�������j���ȏ��������̃����o�[�����M�ɉ�������}�K�Ђ̗��j���ȏ��𗈏t����g�����Ƃ����߂��B�}�K�Ђ̍̑��͎�s����s�O���̎������ł͏��߂āB
���Z�́u�m�́E�����́E�̗͂̃o�����X�̂Ƃꂽ���k�̈琬�v��������j�Ɍf���č��t�J�Z�����B
�o���Z�̗��V���Q��(�����Q�s)�͂��łɍ��t����}�K�Ђ̗��j���ȏ����g�p���Ă���B
���V�����o�c����A�r�w���́u�葱����ŋ��ȏ����r�����������ʁA���肵���B���łɕی�҂ɐ������A�����Ă���v�Ƃ��Ă���B
�@�}�K�Ђ̗��j���ȏ��͎��������Z�Ɠ����s���{��w�Z��Z�ꕪ�����A���Q�����{��w�Z��Z�A���W(�낤)�w�Z��Z�ō��t����g�p����Ă���B
�@���Z�ɂ��ƁA���̋��ȏ��Ɣ�r�������ʁA�}�K�Ђ̗��j���ȏ��́u�����̗��j�E�����Ɍւ�������Ƃ��ł��A���k�����j�ɑ��ċ�����S�����Ă���e�ł���v�Ƃ��Č��߂��Ƃ����B
�����ꂩ��͊w�Z�I�т̍ۂɁA���勳�ނ������Ă��邩�̑��ɁA�ǂ�ȋ��ȏ����g���Ă��邩�����f��̈�ɂȂ�ł��낤�B��
���������w�Z�̗�[���@���ȏȕ��j
�i���o�V���@�V���R�P���j
�@�����������ł�����������Ăˁ\�\�B�����Ȋw�Ȃ͂R�P���A�Q�O�O�R�N�x������������w�Z�̕��ʋ����̗�[����i�߂Ă������j���ł߂��B���ʂ͐V���z���K�͉��C�Ɍ��邪�A�����I�ɂ͏����Ώۂ��g�債�Ă����l�����B
�@�ƒ��E��A���w�͗�[����������O�ɂȂ�Ȃ��A�����w�Z�̕��ʋ����͎��c���ꂽ�`�������B���ȏȂɂ��ƁA�����n��Ȃǂňꕔ��O�͂��������A��{�I�ɗ�[���̑Ώۂ͏]���A�E�����̂ق����y���A�R���s���[�^�[���ȂǓ��ꋳ���Ɍ����Ă����B
�@���ʋ����ɂ��Ắu�ł������G�߂͉ċx�݂Ő��k�����Ȃ��v�Ȃǂƍ����ȑ�����F�������Ă����B�������A�s�s���ł̓q�[�g�A�C�����h���ۂȂǁA���ĈȊO�ł��C���͍����B�܂��A���N����͊��S�w�Z�T�����̗]�g������A�u�ċx�݂̕�K�Ȃǂ��ڗ��v�i���ȏȁj���Ƃ���[�������̂��������ɂȂ����B
�@�{�ݐ�����p�͓��ꋳ�����l�A�R���̂P�����ɕ��S�ł܂��Ȃ����j�B��[���͂V���̍����s�̃^�E���~�B�[�e�B���O�ŁA���R�֎q���ȑ��������ӗ~�������Ă����B
����͌�����@���i�Z�Q�O�O�Z���w��A�ǂ݁E�����E���_���A�����Ȋw��
�i�����V���@�W���R���j
�@�ቺ���S�z�����q�������́u����́v�����コ���邽�߁A�����Ȋw�Ȃ͗��N�x����A�S���̌����������Z�̒�����u���ꋳ�琄�i�Z�v��Q�O�O�Z���w�肷��B���Ƃł́A�Ǐ���앶�Ȃǂ̂ق��ɁA���_�̎��ԂȂǂ���������B�܂��A�搶�̓��{��͂����߂邽�߁A�A�i�E���T�[�Ȃǘb�����̃v���ɂ�錤�C�u�������{����B���Ȃ��{�i�I�ɍ���͌�����ł��o���̂͏��߂āB
�@���N�P���ɕ����������{�����u����Ɋւ��鐢�_�����v�ɂ��ƁA���{�l�̍���͒ቺ�ɂ��Ă̎���ɁA�u�����͂��ቺ���Ă���v�Ɖ����l�͂X���ɏ��A�u�ǂޗ́v�͂V���A�u�b���́v�͂U�����u�ቺ���Ă���v�Ɠ������B�����������ʂ���A��������R�c��╶���R�c��́u���ꋳ��̏d���v�\���Ă����B
�@�u���ꋳ�琄�i�Z�v�ł́A�q�������̕��͗͂�v��́A�\���͂�{�����Ƃɏœ_�����āA�앶�w����Ǐ��̐��i�A���_�A���\��Ȃǂ����ƂɐϋɓI�Ɏ������B����ɏ������Z��P�O�Z�Ń��f���n������A�n��ɏZ�ޕ��w��o��Ȃǂ̐��Ƃ̗͂���A�q�������ɒ��ڎw�����Ă��炤�B���w��i��ÓT�̘N�ǁA�Ï������i������j���B
�@����A�w�Z�̐搶�ɑ��Ă͕������Ƌ����Łu����w���͌���u���v�����{�B���ƂŎq�������ɕ�����₷�����{����g���ċ�������悤�A���͂̏�������b�������g���[�j���O����B�u�t�ɂ̓A�i�E���T�[�⍑�ꌤ���҂̂ق��A����ƂȂǁu�v���̘b����v��z��B���ׂĂ̋��Ȃ̐搶��ΏۂɎ��H�I�Ȍ��C���s���u������₷�����ƍ��v�ɖ𗧂Ă�B
�@���Ȃ͍��N�x����A���Z�ŗ�����������{����u�X�[�p�[�E�T�C�G���X�E�n�C�X�N�[���v��p��͌����}��u�X�[�p�[�E�C���O���b�V���E�����Q�[�W�E�n�C�X�N�[���v��ݒu���Ă���A���ׂĂ̊�b�ƂȂ鍑��͂��[�������邱�ƂŁA�q�������̂��������̊w�͌����}��B
����̓s���`�@���Z���A�}���قŖ{�肽���ƂȂ��S�P���@�u�ςށv�Ə����Ȃ��S�U��
�@�u�}���قŖ{���肽���Ƃ��Ȃ��v�u�h�����Ƃł����{�͓ǂ܂Ȃ��v�Ƃ����q�ǂ������ꂼ��Q���O�ア�āA���w�E���Z���t�̂W���́u�q�ǂ��̍���̊w�͂��ቺ���Ă���v�Ɗ����Ă���\�\�B����Ȏ��Ԃ��A�����Ȋw�ȍ������琭�����̌����҂��s�����u�Ǐ�����Ɋւ��钲���v�Ŗ��炩�ɂȂ����B�Ǐ�����̌X���͊w�N���オ��ɘA��Đ[���ɂȂ��Ă���A���t�̑����́u��l�⋳�t���{��ǂ܂Ȃ��Ȃ����v���Ƃ������ɋ������B�����ɍs���������̏�����蒲���ł́A���w�S�N�ŏK���u�ςށv�������Ȃ����Z�����T���߂��ɏ�����B
�@�����́A�L���G���E�������������������̃O���[�v����N�x�A�S���̏��w�S�N�ȏ㍂�Z�Q�N�܂ł̂Q�P�Q�O�l�Ə������̋��t�Q�T�X�l��Ώۂɍs�����B
�@�������k�ւ̎���ł́A�u�y���ޓǏ��v�͂V�P�����D���Ɠ��������A�Q�Q���͂��̂��߂ɐ}���قŖ{���肽���Ƃ��S���Ȃ������B���w���͂��̐������R�O���A���Z���͂S�P���ɂ��B�����B�u�h�����Ƃł����{�͓ǂ܂Ȃ��v�͑S�̂łP�W�������A���Z���͂R�R���B�u���ȏ��������{��ǂ��Ƃ��Ȃ��v���S�̂ł͂P�U���������Z�ł͂Q�R�������B
�@�Ƃɂ���{�́u�Q�O������P�O�O���v���S�W���ň�ԑ����������A�u�P������P�O���v���Q�P�������i���Z���͂Q�W���j�B
�@�܂��A���w�Z���t�̂S�P���A���w�A���Z�͂Ƃ��ɂV�W�����u�����̂���ɔ����̊w�͂����������Ǝv���v�Ɠ����A�u���w�N�ł��P��ł����b���Ȃ��v�i���w�j�A�u���{�ꂪ�ʂ��Ȃ��v�i���w�j�A�u���܂�Ɏ��������Ȃ��v�i���Z�j�ȂǁA����͂́g����h��Q��������������ꂽ�B
�@���̌����ɂ��ẮA�u��l�⋳�t���{��ǂ܂Ȃ��Ȃ�������v���R�X���A�u���t���������w�������Ȃ��Ȃ����v�Q�Q���A�u�ƒ닳�炪�������Ȃ��Ȃ����v�P�X���̏��i�����j�B���R�L�q�ɁA�e���r�Q�[���̕��Q�������鐺���ڗ������B
�@�q�ǂ��ɂ͏������Ȃǂ̍���͒������\�Q�Ɓ����s�������A���w�S�N�ŏK���u�ςv���������̂͏��w���R�T���A���w�R�X���A���Z���T�S���B�P�N�ŏK���u�쉺�v���A���w���̂P�W�����ԈႦ���B
�q�ǂ��ɑ��銿���������e�X�g�̐������i���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�K���w�N�@�@�@�@�@���@�@�@���@�@�@��
�쉺�i���킵���j�@�@�@�@���P�@�@�@�@�W�Q�@�@�@�W�R�@�@�X�O
���i�́j��ā@�@�@�@�@�@���Q �@�@�@�@�V�S�@�@�@�W�R�@�@�X�O
�����i�����́j�@�@�@�@�@���R�@�@�@�@ �U�V�@�@�@�X�Q�@�@�X�S
�����i��ˁj�@�@�@�@�@�@���R�@�@�@�@ �T�X�@�@�@�X�R�@�@�X�R
�E�i�Ђ�j���ā@�@�@�@�@���R�@
�U�O�@�@�@�U�W�@�@�V�X
�ρi�j�@�@�@�@�@�@���S�@�@�@�@�@�R�T�@�@�@�R�X�@�@�T�S
��n�i�ڂ��j �恁�@�@�@���T
�@�@�@�@�@�@�@ �n���@�@�@���Q�@�@�@�@ �R�S�@�@�@�U�U�@�@�W�P
���[�i�݂����j �������Q
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�[����p�����@�@�@�Q�@�@�@�T�T�@�@�W�P
���i�����j�����@�@�@�@�@ ��p�����@�@�@�P�@�@�@�S�T�@�@�U�T
���i�ɂ��j�����@�@�@�@�@��p�����@�@�@�P�@�@�@�R�R�@�@�T�X
����p�����́A���Z�܂łɂ��������ǂݏ������ł���悤���߂��Ă���B�����Ώۂ́A���w�����S�N���ȏ�A���w���͑S�w�N�A���Z���͂P�A�Q�N��
�w�Z��{�����@�呲�Q���͏A�E�E�i�w�����@�s�o�Z���w���͂R�U�l�ɂP�l
�i�����V���@�W���P�O���j
�@���t�A��w�𑲋Ƃ����l�̂Q���A���Z�𑲋Ƃ����l�̂P�����A�E���i�w�����Ȃ��������Ƃ��A�����Ȋw�Ȃ��X�����\�����O�Q�N�x�̊w�Z��{��������ł킩�����B���w��Q�l�Ȃǂ��܂܂�邪�A���Ȃ͑����͐E�ɂ��A�����A�w�Z�ւ������Ă��Ȃ��Ƃ݂Ă���B����A�s�o�Z�̏����w���͉ߋ��ő��̂P�R���X�O�O�O�l�ɒB�����B�ŋ߂P�O�N�Ŕ{�����A���w�Z�ł͂R�U�l�ɂP�l���s�o�Z�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@����ɂ��ƁA���t�̑�w���Ǝ҂͉ߋ��ő��̂T�S���W�O�O�O�l�B�����U���l�i�S�̂̂P�O�D�X���j����w�@�Ȃǂi�w���A�R�P���Q�O�O�O�l�i�T�U�D�X���j���A�E�����B
�@�i�w���A�E�����Ȃ������̂͂P�P���X�O�O�O�l�i�Q�P�D�V���j�ŁA�O�O�N�x�̂P�Q���P�O�O�O�l�i�Q�Q�D�T���j�Ɏ��������ƂȂ����B����Ƃ͕ʂɁA�A���o�C�g��_��Ј��ȂǂP�N�����̈ꎞ�I�Ȏd���ɏA�����l���ߋ��ő��̂Q���R�O�O�O�l�i�S�D�Q���j�����B
�@�Z����A���Ǝ҂P�R���P�O�O�O�l�̂����A�i�w���A�E�����Ȃ������l�͂Q���T�O�O�O�l�i�P�X�D�T���j�A�ꎞ�I�Ȏd���ɏA�����l�͂P���P�O�O�O�l�i�W�D�T���j�𐔂����B
�@���Z�ł͑��Ǝ҂P�R�P���T�O�O�O�l�̂����A�E�����̂͂Q�Q���S�O�O�O�l�ŁA�A�E���͉ߋ��Œ�̂P�V�D�P���������B��w�E�Z�����w�Z�ȂǍ�������@�ււ̐i�w�͂U�Q�D�W���B�i�w���A�E�����Ȃ������l�͑O�N���W�O�O�O�l�����P�R���W�O�O�O�l�i�P�O�D�T���j�ŁA���݂̕��ޖ@�ɂȂ����V�U�N�ȍ~�ōő��������B
�@�o�u���������X�O�N��O���ȍ~�A�A�E���͋}���ɒቺ�A�t�ɏA�E���i�w�����Ȃ��l�������Ă���B���ȏȂ͌i�C����ɉ����A�u��E�ɏA���Ȃ��Ă��\��Ȃ��v�Ƃ����ӎ����L�������ƌ��Ă���B
�@����A�O�P�N�x�ɂR�O���ȏ�w�Z�����Ȃ����s�o�Z�́A���w�Z�łQ���V�O�O�O�l�i�O�N�x��O�D�T�����j�A���w�Z�łP�P���Q�O�O�O�l�i���S�����j�B�v�P�R���X�O�O�O�l�ŁA�O�N�x���S�O�O�O�l�i�R�D�R���j�����ĉߋ��ő����X�V�����B
�@����ψ���͊w�Z�ɕ��A����̂�҂u�K���w�������v�̊g�[�Ȃǂ̑���u���Ă��邪�A�����X���Ɏ��~�߂͂������Ă��Ȃ��B���ȏȂ͂X���A���Ԓc�̂����������͎҉�c�����߂ė����グ�A�����Ή���ƒ�x���Ȃǂ��l����Ƃ��Ă���B
�֘A�L���@�����w���̕s�o�Z�A�ő��P�R���X�O�O�O�l�@�i�����V���@�W���P�O���j
�@�O�P�N�x�ɕs�o�Z�𗝗R�ɂR�O���ȏ�w�Z���x�����w�����A�O�N�x���R�E�R������P�R���X�O�O�O�l�ɒB���A�ߋ��ő����X�V�������Ƃ��X���A�����Ȋw�Ȃ����\�����u�w�Z��{��������v�ŕ��������B
�@���̌`�Œ������n�߂��X�P�N�x����P�O�N�A���̑����ŁA���N�x�̂Q�{�ȏ�ɑ������B���Ȃ͊w�Z�ɃX�N�[���J�E���Z���[��z�u����Ȃǂ̑���u���Ă��邪�A�s�o�Z�̑����Ɏ��~�߂�������Ȃ����Ƃ���A�����ɂ����҂ɂ���c��݂��A����܂ł̑�����������Ƃ����߂��B
�@����ɂ��ƁA�s�o�Z�̏��w���͂Q���V�O�O�O�l�A���w���͂P�P���Q�O�O�O�l�ŁA���w���͑O�N�x���P�R�O�l�A���w���͂S�R�O�O�l�������B�X�P�N�x�ɔ�ׁA�����w�Z�Ƃ��ɔ{�����Ă���A���w�Z�ł͂R�U�l�ɂP�l�A���w�Z�͂Q�V�T�l�ɂP�l�̊����ŁA���w�ł͂P�N���X�ɂP�l�ȏ�̕s�o�Z���k������v�Z���B
���̑�
�w�Z������\������
�\�����@�ɂ��Ă͊e�w�Z�̃z�[���y�[�W���A�N�Z�X���|�[�g�̃o�b�N�i���o�[�ł��m�F���������B
�������\�����ԁ@�@�@�@�@�@�@�@�W���Q�P���`�R�P��
�@�@�A�N�Z�X���|�[�g�m�n�D�U�T�Q��
http://www.komabatoho-jh.ed.jp/
�J��������\�����ԁ@�@�@�@�@�@�@�@�X���@�Q���`�Q�O��
�@�@�A�N�Z�X���|�[�g�m�n�D�U�Q�Q��
http://www4.justnet.ne.jp/~kaisei/
�ԗt������\����t�J�n�@�@�@�@�@�X���P�O��
�@�@�A�N�Z�X���|�[�g�m�n�D�U�P�Q��
http://www.futabagakuen-jh.ed.jp/
���q�w�@������\����t�J�n�@�P�O���@�Q��
�@�@�A�N�Z�X���|�[�g�m�n�D�U�V�Q��
http://www.joshigakuin.ed.jp/
���ώ����@�j���Ƃ����E���
�i���o�V���@�V���R�P���j
�@���{�l�̕��ώ����͒j�����V�W�D�O�V�A�����͂W�S�D�X�R�ƂȂ�A�ߋ��ō����X�V�������Ƃ��R�P���A�����J���Ȃ��܂Ƃ߂��u�Q�O�O�P�N�ȈՐ����\�v�ŕ��������B�j���Ƃ����E��ƂȂ錩���݁B�Q�O�O�P�N�ɐ��܂ꂽ�Ԃ����̂����A�j���̔����ȏ�A�����̂S�l�ɂR�l���W�O�̒a�������}����v�Z�ɂȂ�A�����I�㔼�̒����Љ�����яオ�����B
�@�P�O�N�O�i�P�X�X�P�N�j�ɔ�ׁA���ώ����͒j���͖�P�D�X�U�A�����͂Q�D�W�Q�Ή��т��B���ɍ���w�Ŏ��������т�X��������A���J�Ȃ́u��N�͑傫�Ȋ����ǂ����s���Ȃ�������A�j���̂���̎��S�������������肵���e�����傫���v�ƕ��͂��Ă���B
�@���ώ����͑O�N���j���͂O�D�R�T�A�����͂O�D�R�R�Ή��сA�i�����L����X�����������j���̍��͏k�܂����B�j��������̎��S����������A�O�D�P�Q�Β��x���ώ����������グ���̂ɑ��A�����͌�ʎ��̂Ȃǂɂ�鎀�S�������������e���Ƃ݂���B
���w�I�����s�b�N�@���{�͂P�U��
�i�����V���@�W���Q���j
�@�W�S�J���E�n��̍��Z���ȉ��̐��k���Q�����ĉp���ŊJ���ꂽ��S�R�ې��w�I�����s�b�N�ŁA���{�͂P�U�ʂ������B���w�I�����s�b�N���c�i�����j���Q�����\�����B���N�̂P�R�ʂ�艺����A�X�R�N�Ȃǂ̂Q�O�ʂɎ����ᐬ�тɏI������B�l�ł́A�Q���S�W�P�l���A���т��ł��D�G�ȃO���[�v�ɍ��䒼�B����i�卂�R�N�j������A�����_�����l�������B
�@�D�������̂͒����ŁA�S�N�A���B�Q�ʂ����V�A�ŁA�R�ʂ͕č��B�A�W�A���ł̓x�g�i���A�؍��A��p�A�C���h���x�X�g�P�O���肵���B���{�͂P�S�ʂ̃g���R�A�x�����[�V�Ɏ����A�J�U�t�X�^���Ɠ����������B
�@���{�͂X�O�N�ɏ��Q�����W�ʂ��ō��B���Ă͓��{�ŏ��߂ĊJ�����B
�@���䂳��̂ق��A�哇�F������i�}�g��t����ꍂ�Q�N�j�A�����I�u����i���j�A�ߓ��G������i�J�����R�N�j�̂R�l����_���A���c�m�V����i���Q�N�j�������_�����l�������B
����聄
�}�̂悤�ȓ����A�`�n�_����a�n�_�܂Ō���ǂ肹���ɍs���܂��B
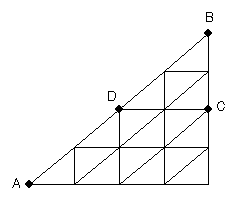
�i�P�j�@�`�n�_����K���b�n�_��ʂ��Ăa�n�_�֍s���ɂ͉��ʂ�̍s����������܂����B
�i�Q�j�@�`�n�_����c�n�_��ʂ炸�ɂa�n�_�֍s���ɂ͉��ʂ�̍s����������܂����B
�i�O�Q�N�X���w���j
�������ɒ����T�O���
����聄
����d��������̂ɁA�a�͂P���ɂ`�̂R���̂P�A�b�͂`�̂S���̂R�̗ʂ̎d�������܂��B�Q�l���g�ɂȂ��Ďd���������Ƃ���A�`�͂S���ԁA�a�͂R���ԁA�b�͂R���Ԃ̎d�������Ă��傤�ǎd�グ�邱�Ƃ��ł��܂����B���̖₢�ɓ����Ȃ����B
�i�P�j�`�Ƃa���P�g�ɂȂ��Ďd���������͉̂����Ԃł����B
�i�Q�j�`���������̎d���������Ƃ���Ɖ���������܂����B
�i�O�Q�N���c�J�w���j
����
�i�P�j�R�l�ŁA�ׂ̂P�O���ԁA�d�������Ă��邪�A�P��������Q�l���Ȃ̂ŁA
�@�@�@�i�S�{�R�{�R�j���Q���T�i���ԁj
�@�@���̂����A�S���͂`���d�����Ă���̂ŁA�c��̂P�����a�Ƃb�̂Q�l�ɂȂ�B
�@�@����āA�`���d�������S���Ԃ́A�a�Ƃb���Q�����d���������ƂɂȂ�B
�@�@�ȏォ��A�`�Ƃa���ꏏ�Ɏd���������̂́A�Q�����B
�i�Q�j�`�C�a�C�b�R�l�̂P��������̎d���ʂ̔�����߂�ƁA
�@�`�@�F�@�a�@�F�@�b
�@�R�@�F�@�P
�@�S�@�@�@�@ �F�@�R
12�@�F�@�S�@�F�@�X�@
�@�@�܂��A�d���ʑS�̂́A
�@�@�@�P�Q�~�S �{ �S�~�R �{ �X�~�R �� �W�V
�@�@�@�W�V���P�Q���V�@���܂�@�R
�@�@����āA�V���ł͏I���Ȃ��̂ŁA�W��������B