
�m�n�D�U�X

�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�O�Q�N�@�V���Q�T��
�ڎ�
|
�w�Z��� |
������ | ������ | ���J�͎���� | ���̑� |
| �C�钆 | �Z���^�[���� | ��Ε]���P | ��s���͎��V��
�@ |
�ċx�ݎ��R�����T�C�g |
�w�Z���
�C�钆�@�m�Ώې�����i�O�Q�N�V���T���j
�@������͂V���T���A�Z���̍u���ōs��ꂽ�B�����͊����l�����Ƃ����āA�w���͐Â܂肩�����Ă����B������͖��N�̂��ƂƂ������ƂŁA������ł̎����z�t�Ȃǂɂ͎芵�ꂽ���͋C���Y���B�P�O����������ɊJ�n�B�ȉ��A���ҏ��ɂ��̊T�v���L���B�i���Z�����̓��e�Ɋւ��Ă͈ꕔ�������j
�P �a�c�Z���u�V�����a�m���v
�@�{�N���V�C�B���_�Ƃ��āA�ύX�_��V�w���v�̂ɑ���l���Ȃǂ����b�ɂȂ�B
(1) �w�Z������ւ̎��g��
���w����������S��A���Z����������R��Ɖ͍�N�Ɠ��������A��Č^�ł͂Ȃ��A�ꕔ��Θb���₷���ʃu�[�X�ɂ�鑊�k��ւƌ`�Ԃɕς���B
�@���w����������
�@�@�X���P�P���i���j�i�P�S�F�O�O�`�@����S�T�O���j
�@�P�O���P�O��(�j�i�P�R�F�R�O�`�@����P�T�O���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�P�S�F�R�O�`�@����P�T�O���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�P�T�F�R�O�`�@����P�T�O���j
�@�P�P���@�X���i�y�j�i�P�R�F�R�O�`�P�T�F�O�O�@�u�[�X�`���E�ʑ��k��j
�@�P�P���R�O���i�y�j�i�P�S�F�O�O�`�@����P�Q�O�O��)
(2)�V�w�K�w���v�̂ւ̎��g��
�@�����I�Ȋw�K�Ɋւ��ẮA�P�O�N�O����A���R���̑��_�փS�[�����߂��A���ׂ�A�l����A�܂Ƃ߂�A���\����Ƃ�������@����������Ƃ����݂���B�V�ے��ł́A����ɍ��Z�̓��e����悹����Ή����s���B
�@�܂��A�{�N��蕶�n�ɂ����镶�`�E���a�Ƃ����R�[�X�n�R�[�X�Ƃ��ē����B���n�Ƃ̂Q�R�[�X�Ƃ���B�������A���̓�R�[�X�Ɋւ��ẮA�Z���^�[������95���ȏ�Ƃ������炢��������З��C�P�ʐ����Ƃ���B
(3) ���[���}�K�W���̔��s
�@�V���Q���Ƀz�[���y�[�W��ł͔��\�ς݂����A���C���m���Ă��炤���߂Ƀ��[���}�K�W���̔z�M���n�߂�B�z�[���y�[�W��������ڕW�ɃA�b�v�f�[�g�������B�z�[���y�[�W���͖{�Z�����̎���̂��́B
(4) �V�����a�m��
�@�C��w���́u���Ɓv�E�Љ�ɗL�ׂȐl�ނ��琬����v�Ƃ������w�̐��_�Ɋ�Â��A�t�F�A�Ȑ��_�E�v�����̐S�E�����`�����ԓx�E���m�Ɉӎu��`����\�͂����˔������u�V�����a�m�v��y�o����̂�ڕW�Ƃ��Ă���B�����āA�����́A���̂Ȃ��ŁA�u���m�Ɉӎu��`����v���R�~���j�P�[�V�����\�͂��d������A�Ƃ������Ƃk�ɘb���Ă���B���݂̍ݍZ���������Љ�̒������ɂȂ��Q�O�`�R�O�N��A���{�ɂ͂R�O�����z����O���l�i�J���ҁj������邱�ƂɂȂ�A�R�~���j�P�[�V�����\�͂Ɍ�������̂͑Ή��ł��Ȃ����ƂɂȂ�B�w�K�ے��͂����������͂��₤�̂ł��肽���B
�Q �֊w�K�w�������u����u���̂��߂̎����������̂ł́A�w�Z�ł͂Ȃ��v
(1) �i�w��
�@��N��ł́A������w�̍��i�ґ����i�O�Q�N�x���i�ґ����T�R���B���������R�O���j�����������B���k����ѕی�҂̓����Ƃ��āA���萫�����߂Ĉ�Ȏ��Ȍn�̑�w�ւ̎u�]�҂������Ă��邩�炾�Ǝv����B�����Ƃ��ẮA��N���ꂼ��ꌅ��������������ю����̈�w�n�̑�w�ւ̍��i�҂��{�N�͈ȉ��̒ʂ�ł���B
�@������w���@�R�W���i���������P�W�j
�@������w���@�S�X���i���������Q�R�j
�@���̐i�w�Z�ł́A���N�O���炱�̌X���������Ă���悤�ł���B
�@�܂��A��w�����̂̃{�[�_�[���C�����������Ă���悤���B��t��w��w���Ⓦ����Ȏ��ȑ�w�Ƃ�����������w���̃Z���^�[�����̃{�[�_�[���C���͂V�Q�O�^�W�O�O�������̂��A�����͂U�W�O�`�U�X�O�_������܂ʼn������Ă���B�S���I�Ɍ���ƍ���̓��_�����������Ă���P�W�O�^�Q�O�O�͂��납�P�U�O����Ȃ��B
�@����c�E�c��̍��i�҂͗�N�ƑS���ς���Ă��炸�A�����������Ӗ��ł͊w���̃��x�����������Ă���̂ł͂Ȃ��A���ɕی�҂̈���u�������������Ă���悤�Ɏv����B�i�H�w������K��鐶�k�̎������w���Ɋւ�����̂������Ȃ����B
�@�����̐��k������ƁA�l�i�w�Z��\���Z�^�m�j�ɗ���q�������A�����ł��������邱�Ƃ����ɂȂ��Ă��Ă���悤���B�����悭�_�����Ƃ��A������ӓ|�֑̐���ς��Ă��܂��悤�Ȃ��Ƃ́A�Љ�I�Ɋ댯�Ȃ̂ł́H�@�w�Z�̖����͂��̂悤�Ȃ��̂ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă���B
(2)�V�ے��Ɋւ���
�@�T���������邩�ǂ����͋c�_�����������A�U�����s����B�J���L���������]���Ɠ����ł���B���s�̐V���ȏ��͂ƂĂ�������㕨�ł͂Ȃ��B���w�Ɏ����Ă͊G�{�����l�ł���B���W���͂Q�N���ߋ��̂��̂����߁A���݂͂�����g�p���Ă��邪�A���ݓƎ��̃J���L�������Ő��i�ł���悤�ɋ��ނ��쐬���ł���B
�@���w�����̓�x�͗�N�ƕς��Ȃ��B���Z�����Ɋւ��Ă͌������B���Z��N�͓��i���ƍ����N���X�ɂȂ�̂͊C��̑�O��B���x�������������͂Ȃ��B���݂͐��w�T�U���Ԃ̂����R���Ԃ�ʃN���X�őΉ��B�v���X��K�����{�B�܂��A����ł͌ÓT�𒆊w�Ŏ�舵���Ă��邽�߁A�������K������B����ĕ�K�͏T���A���ꂼ��R���Q�T������W�O���B���Z����̐��k�͊T�˂܂��߂ŁA�ꐶ�������g�ނ̂ŏ������Ă���B�����@��c��`�m�ł͂Ȃ��A�C�鍂�Ȃ̂́A��͂��w���u�]�҂��������炩������Ȃ��B�܂��A���w���ł���w�@�i�w�����Ă�����̂������Ă���B�Ƃ͂����A����͂��ꂾ���̑Ή��ł͂��߂�������Ȃ��B�������Ă���������̂���͍����ł���B�S�z�Ȃ̂́A���s�̐V�ے����K�p����Ă���S�N��̐��k�B���i���͒��w���Ƃ��ď���{�̂��߂̌|�p�ӏ܂Ȃǂ̍s�����������s���Ă���B
�@���̎��ƂɊւ��ẮA�����̐�������Ȃ��̂��ǂ̍��Z�ł�����̂悤���B�{�Z�ł����̋����Ƌ��������Ă���͈̂�l�B�u�K��J����Ă��邪�A�����D��Ŏ������Ȃ��Ȃ�����Ă���Ȃ��B�C��ł́A�����Z�ł͏��͐ϋɓI�Ɏ��g�܂Ȃ��Ă������̂��Ƃ������Ă���i�j�B
�@���Z�ł̃R�[�X�����͍Z�����ӂꂽ�Ƃ���A����c�E�c��i�w�ґΏۂ̕�A�R�[�X���������n�i�w�ґΏۂ̕�B�Ɠ����A�I�𐧂̎��ƂőΉ�����B�O�q�̒ʂ�A�����Ή��^�ōi�荞����������̂ł͂Ȃ��A������Ɗ�b���{��t��������ׂ����ƍl���Ă���B����āA���Ȃ��A���n���k�ł����Ă������E���w�E�����̗��C��K�C�Ƃ��Ă���B
�R �\����������
�@���w�����Ɋւ��ẮA��{�I�ɕύX�_�͂Ȃ��B�����A�O�R�N�x����A���w���ގ҂ɂ́A�{�݁E�ݔ����ы���[����i�v�j�P�W���~�j�͕ԋ��i�������A�Q���Q�W���ߌ�R���܂ł̐\���o�ɑ��āj�����邱�ƂɂȂ����B
(1) �O�Q�N�x���ʁE���_��
��P��@�@�@�@�@�@���v�@�@�@�@����@�@�@�Z���@�@�@�Љ�@�@�@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�U�O�@�@�@�P�Q�O�@�@�@�P�Q�O�@�@�@�@�U�O�@�@�@�@�U�O
���i�ҕ��ρ@�@�@�Q�P�V�D�P�@�@�U�U�D�S�@�@�W�Q�D�O�@�@�R�U�D�S�@�@�R�Q�D�R
�S�̕��ρ@�@�@�@ �P�W�O�D�V�@�@�T�V�D�X�@�@�U�R�D�W�@�@�R�P�D�T�@�@�Q�V�D�T
�ō��_�@�@�@�@�@�@�Q�W�U�@�@�@�@�X�Q�@�@�@�P�Q�O�@�@�@�@�T�X�@�@�@�@�T�Q
���i�Œ�_�@�@�@�P�W�V�i�T�P�D�X���j
��Q��@�@�@�@�@�@���v�@�@�@�@����@�@�@�Z���@�@�@�Љ�@�@�@����
���i�ҕ��ρ@�@�@�Q�S�O�D�U�@�@�V�V�D�U�@�@�X�O�D�P�@�@�R�T�D�Q�@�@�R�V�D�V
�S�̕��ρ@�@�@�@ �Q�O�O�D�O�@�@�U�W�D�X�@�@�U�W�D�Q�@�@�R�O�D�T�@�@�R�Q�D�S
�ō��_�@�@�@�@�@�@�R�P�W�@�@�@�P�O�S�@�@�@�P�Q�O�@�@�@�@�U�O�@�@�@�@�T�S
���i�Œ�_�@�@�@�Q�P�O�i�T�W�D�R���j
�@�Ȃ��A�Ȗڃo�����X���������k�͕s���i�ɂȂ�\�����傫���B����_�Ɋւ��Ă͔N�x�ɂ���ĈقȂ�A���S�̂̕��ϓ_�⓾�_���z�A����ɋ��Ȃ̏o��҂̈ӌ��i���̃e�X�g�̒��Ɋ܂܂��{���Ɋ�{�I�Ȗ��̔z�_�̍��v�Ȃǁj���l�������肷��B��{�I�ɂ͍��v�_�����i���C���ɓ����Ă��鐶�k�ɂ͓K�p����ɂ������A�O�Ⴊ�Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B����_�����݂���̂́A��b������d�����邽�߁B
(2) ���i�Ґ�����ѕ⌇�̗L���ɂ���
�O�Q�N�x
�@�@�@�@�@�@��P��@�@�@�@��Q��
����@�@�@�P�Q�O���@�@�@�P�Q�O��
����ҁ@�@�S�O�Q���@�@�@�X�X�W��
���i�ҁ@�@�P�T�R���@�@�@�Q�T�U��
�J��グ���i�͑�Q��̂݁A�����̂T���܂łɘA���B
(3)�K�v���ނɊւ���
�@���w�Z�̒��������A���ׂĕs�v�B
�i���Z�����Ɋւ��ẮA�����ł͊������邪�A��Ε]����w�Z�Ԋi�����l�����A���\�_�̃E�G�C�g��������Ƃ̂��ƁB���̂Ԃ�A�M�L�����ŏd���ƂȂ�B�j
(4) ���̂ق�
���Ґ��x�͂Ȃ��B
�P�N���X��45���ɖ����Ȃ��������Ō������o���ꍇ�A�C�O�A���q���̂ݑΏۂƂ��ĕғ��������s���B�������A���Q�̉Ă܂ŁB
�i�G���j
�@���N�s���Ă���m�Ώې�����Ƃ����āA�w�Z�̏Љ�ł͂Ȃ��A�i�w������ɓ�������������ł������B���S���̐搶�����Z�����̕��������̂��A���ӎ������Z���̊w�͒ቺ�ɂ���̂��A���w�������̊w�͍\�z����Ȃǂ�荂�Z�����ɃE�G�C�g���u����Ă���悤�Ɋ������B�����Ɋ��z��\���グ��A���㒆�w�V�ے��̐��k�����Z�����Ŏ����Ƃ��Ă��A�ނ炪�͂����č��Z���炵�������𑗂�邩�ǂ����Ƃ����s�����c��B�w�Z���Ƃ��ẮA����������قǂĂ��˂��ɕ�K��ʑΉ����s���Ă���킯�����A���̂ԂZ�����g�̐����͌��݈ȏ�Ɋw�K��ӓ|�ɂȂ�A���ʂƂ��Ċw�Z�����̃o�����X�͒����������̂ł͂Ȃ����낤���B�i�@�`�D�n���j
http://www.kaijo.ed.jp/
����a�w���@�m�Ώې�����i�O�Q�N�V���P�O���j
�r�f�I��f�i��P�T���j
�@����a�w���̊w�������𒆐S�ɍ쐬�����r�f�I����f�B�i���[�V����������Ȃ���w���̋��痝�O��w���s�����킩��₷����������Ă���B
����a�w���̖��́@���c���O�����搶
�@�J�u���ĂP�V�N�B�Ⴂ�w�Z�����[�������y�����w�Z�����𑗂��Ă���B���������ޗnj��ɐi�w�Z����낤�Ƃ��ĊJ�Z���A�ߋE�����S�ɐ��k���W�܂�A�i�w�Z�Ƃ��ĂȂ�ӂ�\�킸�撣���Ă����B���̌��ʂ��ꂾ���̎Ⴂ�w�Z�ł���Ȃ���A���N����Q�O���O��A����ɂ͂U�O�`�V�O���O��̍��i���o�����Ƃ��o���Ă���B���ł̓X�p���^�̊w�Z�ƌ����Ă��邪�ی�ҁA���k���������߂Ă���̂��H����ɍl���Ă���Ă����B
����a�̓��F�Ƃ��Č������i�̑����ł��B�T���f�[��������̎����Ƃ��āA����E����̑S���������i�������L���O�̏�ʂR�ʂɐ���a�w���������Ă���B
���ʁ@�J���@�@����P�O�W���@����@�Q���@���v�P�P�O��
���ʁ@��@�@�@����@�V�W���@����Q�R���@���v�P�O�P��
��O�ʁ@����a�@����@�P�X���@����T�Q���@���v�@�V�P��
���N�x���i�҂̓���Q�P�����P�X���i�X�O���j����U�X�����T�Q���i�V�T���j�ƍ����������i�����ւ�B�S�̂ł͍������Q�V�P���A����c�Q�W���A�c���R�T���A���u�ЂX�X���A�����قS�W���ƊJ�Z�P�V�N�̊w�Z�Ƃ͎v���Ȃ����ʂ������Ă���B
�@����a�w���ł͒��P���Q�̒�w�N����b�w�͂Ɛl�Ԍ`���̈ʒu�t���Ƃ��A���R���P�̒��w�N�̂��w�Ɍ�������{�̒蒅�A�A�����J�z�[���X�e�C�Ȃǂ����{�B���Q�Z�R�̍��w�N�ł́A�J���L�����������Q�ŏI�����邽�߁A���R�̂P�N�Ԃ͐i�H�ɍ��킹���w�����s���B����a�̓����Ƃ��Ă͂Q�O����ނ̑̌��w�K�i���D�ł̍q�C�̌��A�A�J�E�~�K���̎Y���A��̏W�A�K�[�l�b�g�T�t�@�C�A�̌��̏W�A�ߐύڏT�A�t�@�[�����_�̌��Ȃǁj��p�ӂ��A�g���ɂ�������Ă��肪������Ȃ��h�Ƃ������H��������{�B���̑̌����璆�w�̑��Ƙ_���Ɏ��g�݂܂��B���k�B�̐S�̒��ɐ��݂��鐺�Ȃ��������ݎ��܂��B�������y���݂Ȑ��k�B�����邱�Ƃ��o���܂��B��N�ɂ͂���ȃe�[�}������܂����B�i��`�q�ƃK�������̃��J�j�Y���A�����ɂȂ���Ƃ́H�A���S�������c���Ƃ��̐��ʁA�F���ƃu���b�N�z�[���ɂ��āA���^���̃o�C�I���J�j�N�X�A�N���[���Z�p�ɂ��āE�E�E���X�j
���̑����w�R�N�ł͌�w���C���s�����{�B��l�Ńz�[���X�e�C���S���ԍs���B���Z�P�N�ɂ͊C�O�T�����s�Ƃ��Ē����ɁB���O�Ɍ������̊w�Z�̐��k�ƕ��ʂ����Ă���A�w�Z�𗬂��s���B�܂��A���Ɛ��̂V�������Ȍn�ɐi�w���Ă��铯�Z�́A�����Ȋw�Ȃ̗����n�̉Ȗڂɏd�_��u���A���E�ɒʗp���錤���҂�Z�p�҂���Ă邽�߂̃J���L����������������u�X�[�p�[�E�T�C�G���X�E�n�C�X�N�[���v�ɓޗnj����B��w�肳��A����A����Ȃǂ̑����Ŋ��錤���҂̍u���E�����������{���A���E�I�����҂̈琬��ڎw���Ă���B
���łP�W�O�O�����̎u��҂��W�߂铯�Z�ł͂��邪�A��s�������ɎQ�����闝�R�́A���̏[�������������l�ł������̎q�ǂ������Ɏ��������Ɠ����ɁA����a��S���ɒm���Ă��炢�����Ƃ����肢����B�Ō�Ɂu�߂������A����a�w���͓�Ɍ�����ׂ܂��I�v�Ǝ��M�������Ă��b�����ꂽ�B�J�Z�P�V�N�̓����A��w�i�w���сA�̌��w�K�A������e�̏[���ȂǁA���i���Ă��鐼��a���S���ɔF�m�����̂����Ԃ̖��ł��낤�B
�_���ɂ��ā@�㑺���i�����搶
�@���Z�ɂ���_���ɂ��Ă̐����B
�P�w�N�ɂQ�O���A���v�P�Q�O������̃A�b�g�z�[���ȗ��B���݂͂V�O���قǂ��������Ă���B�K����������������������g�ɕt�������Ă��܂��B���É��n�悩��T�`�U�����邪���C����֓����ʂ̓����҂��Ȃ��B���̋@��Ɉ�l�ł��������Ă����q����]��ł���B���ɂ͐ꑮ�̃X�^�b�t�Ƃ����҂͂��炸�A�e�w�N�̒S�����@����Q���ÂA�X�ɒ��P�̋��@����̓����^���t�H���[�̂��߂Q�����Z�ݍ��݁A�ꑮ�ł͂Ȃ��Ă��P�S���̋��@�����k�̖ʓ|�����Ă���B���ɂ̓l�C�e�B�u�̊O���l���@���Z�ݍ��݂����āA�T�P��P���ԂR�O���̉p��b���Ƃ𗾓��ōs���B�i�����̂݁j
�������̂���w�Z�ł͂Ȃ��A�������������������K�v�������Ă���B�����ł͓��{��֎~�ʼnp�ꋳ��ɗ͂����A�P�N�Ԃ̗��w�V�X�e�����������Ȃǂ̗����Ǝ��̃V�X�e�����\�z�������ƍl���Ă���B
����p�^���P�O���~�@���Ɨ��Ȃǁ^�U�D�Q���~�ŁA�N�ԂQ�O�O���~�߂��K�v�����A����a�̑�w���i���т������悤�ɁA�\���Z�͑S���K�v�Ȃ����Ƃ��l�������قǍ����͂Ȃ��Ǝv����B
�����֘A�ɂ��ā@���������L��
�@�����܂ł��\�肾���Ƃ����O�u���ŁA
��W����@�@�@�j�q�Q�Q�O��
�o����ԁ@�@�@�����P�S�N�P�Q���P�U���i���j�`�����P�T�N�P���V���i�j
���@�@�@�@�P�W�D�O�O�O�~
�K�v���ށ@�@�@�菑�E�[�E�[�ԐM�p����
�Ȗځ@�@�@�@�@����E�Z���i�P�T�O�_���_�A�U�O���j�Љ�E���ȁi�P�O�O�_���_�A�S�O���j
�������@�@�@����c��w�@������c�L�����p�X�P�T����
�������@�@�@�@�����P�T�N�P���P�R���i�j�j
���i���\�@�@�@�����P�T�N�P���P�T���i���j���^�b�N�X�ɂĒʒm
���ی�ґΏۂ̐�����G�P�O���Q�V���i���j�P�O�F�O�O�`����c��w�P�S����
�i�@�`�D�r�j
http://www.nishiyamato.ed.jp/ny/
�����w���@�m�Ώې�������i�O�Q�N�U���Q�S���j
�u�����w���͗����~�܂�Ȃ��v
�@�ݍZ���̈ꕔ�Ɂu�^�C�^�j�b�N�̐�[�v�ƌĂ�Ă��鏬�u���ŁA���Z���Ɛ��̌��y�l�d�t�{�N�����l�b�g�̉��t�B�I����A������J�n�����B�i����ʖ؋��@���i�s���A�O�c���F�Z���A�g�c�p������L���̏��Ő������ꂽ�B�ȉ��A���̊T�v���L���B
�P �O�c�Z��
(1)�V�Z���Ƃ��āu���M�\���v�B
�@�O�C�N��Z�������ւ����S�`�T���ɂ́A�ی�҂���u�����w���͕ς��̂��v�Ƃ������₪������ꂽ�B����ɑ��铚���́u�����͎�Ԃ����v�Ƃ������̂ł���B�l�C�e�B�u�Q�l���ӂ��ތv�T����V�̗p�A�����̕��ϔN��͂S�O�D�W�B�ی�҂̔N��w�Ƃ���r���Ȃ���A�P�Q�`�P�W�܂ł̎v�t�����u�w�Z����̉Ƒ��Ƃ��āv�l����ƁA���n���Ƃ������闝�z�I�ȔN��\�����Ǝv���B
�@�����Ƃ���14�N�A��l�̍Z���̉��Ŋw�Z���v�Ɍg����Ă����B
�@��؍Z������('87�`'94)
�@�����̒Z�啍���E�N���u�������S�̊w�Z�̍\�����v�B�͍��m�T�e���C�g�Ȃǂ��o�āA�u�K�������h�Ɏ��g�ދ��t�������B�p�E���̃O���[�h����������A�p���𐄐i�A�����TOEFL�ւ̓]����}��B���ʁA�X�Q�N�̌c��Q�����i�́A�i�w�Z�ւ̓]���̐�ڂ������B
�A�N��Z������('95�`'01)
�@�Z���̋��͂ȃ��[�_�[�V�b�v�̉��A�i�w�Z�ւ̃��X�g���N�`�������O�Ɏ��g�ށB�N��Z���́u���܂�ς�邩�A���̂Ƃ���Ŋ��Ă����������v�Ƃ������ƂŁA�R�O���i�S�����̂T�O���j������ւ��B�V�����̗̍p�͔\�͗D��ŁA���E�������ǂ�ǂ�̗p�B����ɁA�i�w��O��Ƃ����V���o�X�����s���A���Ƃ̌��J���s���āA���t�̌��r�Ɛ��k�̐l�i�`���i�����邱�Ƃɂ���āA����������j��_�����B����Ȓ��A�X�W�N�A�R�w�@��ւQ�P���̍��i���ʂ����A�i�w�Z�Ƃ���簐i���邽�߂̃x�N�g���������A�ی�ҁA���k�Ƃ�����ɂȂ����B���̌��ʂɔ����A���\���q�S���l���㏸���A���k�́u���v�����サ���B���S������ё̐��Ɉڍs�B�i���Z��W�͋A���q���A����щ��y�Ȃ݂̂Ɂj
�@�܂��A�V�Z�ɂ��������A�V�V�X�e���i������A���ƂT�����A�V�O���܃R�}���j�͎O�N�ڂ��}����B���ƌܓ����́A���k�̉ƒ�ɃA���P�[�g���s���A���ʂ��̖�W�O�����T�x����̃T�����[�}���ƒ�ł��������߁A���{�ɓ��ݐ����B�����ƈˑ��̒��ԂɈʒu���鐢��̐��������āA�c���s�s�������Ƃ����n�搫�ɖ����������@���Ƃ����B�y�j���́A�s������сA���k�̎��R���ԂƂ��Ċw�Z���J���A���k������͐����̃����n�������Ƃ������ƂŊT�ˍD�]�B
(2)�w�Z���v�ɏI���Ȃ�
�@�ǂ̂悤�Ȑ��k����Ă邩
�@�����U�N�Ԃ͒m���A�i���A��������Ă�ł��d�v�ŖL���Ȏ����B�����ł́A�i�H���l���Ă�邱�Ƃ��ł��d�v�B��w�i�w�͈�̃n�[�h���ɂ������A�Љ�ɏo�邱�Ƃ�O��Ƃ����L�����A�v�����j���O�A�w�����K�v�ł���B
�@�L���X�g���ɗR������Z�������A�@���I�Ȋ����͂��Ȃ��B�N�Ɉ�x�q�t�̍u�b��������x�B��ɐ��k�ɘb�����Ƃ́A�u���[���v�u�}�i�[�v�u�v���C�h�v�Ƃ������Ƃł���B
�@�u���[���v�́A�i�i����Ă�Ӑ}�͂��邪�A���k�ɂ́u����̈��S������Ă���郏�N�ł���v�Ƌ����Ă���i�Z���j�B�u�}�i�[�v�͈��A����{�B����̑��݂�F�߂邱�Ƃ���B����͂܂��A���ꂩ��̉ۑ�ł�����B�u�v���C�h�v�́A�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�������Ƃ��Ă̌ւ肪���Ă�悤�ȍs�������Ȃ����Ƃ������ƁB�s�A�X�Ȃǂ͖��O�����A�����Ȃǂ͎���̗�����������鎋�_���K�v��������Ȃ��B�������A�����͓��X�i�����B�b���ė��������邱�Ƃ���ł���B
�A������т̗��_�E���Ƃ̏[��
�@���Ƃ́A�w�͌`���ƂƂ��ɐl�i�`���̌��_�B�����̐������܂�o�������̂܂ܐ��k�ɉe����^����B�V�w�K�w���v�̂Ɋւ��ẮA���݊w�Z�Ŏ��g��ł��邱�ƂĂ͂߂邾���ŁA���킹�ĉ��������Ȃ���s���Ȃ��Ƃ������̂ł͂Ȃ��B�����I�w�K�ɂ��Ă��A�p��̎��Ԃ̍��ۗ�����{�����e�B�A�����̃��|�[�g�i���Q�j�Ƃ����`�ŏ]��������g��ł��邵�A���͂ނ���h�s�̉A�̕�����������Ƌ����邱�ƂɈӖ�������Ǝv���Ă���B�w�K�ʂ́A���R�Ȃ��狌�ے��x�[�X�ŃV���o�X��g��ł���B�i�{�N�x�͋��ے����ȏ����g�p�j�����A������ɂȂ�̂́A���ȏ��E�����ނ͐V�ے��̂��̂ɂȂ�킯�ŁA����߂鎩�勳�ނ̍쐬���ۑ�ƂȂ�B�i�ȉ��A���Ȃ��Ƃ̎��g�݁j
����F�I���W�i�����ނ͂قڊ����B���Ǝ��Ƀf�B�x�[�g���s�����Ƃ�����B
�p��F�v���O���X�͂��łɌÂ��B�ȒP�ȗ���������multimedia�Ƃ����P�ꂷ������Ă��Ȃ��B����āA���������ƂŎg�p�A�c������勳�ނƂ��āANews Week�Ȃǂ̈��p�Ȃǂ��v�����g�����Ă���B
�Љ�F���P�͓��{�n������B���ȏ����A�Q�l���x�[�X�̎��ƁB
���ȁF�����𒆐S�Ƃ����Q��������ƁB
�̈�F�ߔN�̐��k�̗̑͂̂Ȃ����Ӗڂ��́B�l�H�ł̃O�����h�͉��䂱�����Ȃ����̂́A�ؓ���ɂ߂邱�Ƃ���ɂ���B�̗͂Â��肪��{�B
�|�p�F���_���������B���t���S�ɁA��͂�Q��������ƁB
�ƒ�F���Ă������Ȃ����k���������B�Ƃ̎�`�����ł���悤�Ȏ��w�I�Ȃ��̂��w�������B
�@�S�̂Ƃ��čēx���ȓ��e�̌������A�w�����@�̌��r���s���Ă���B���k�̎����������Ă������Ƃɂ��A�h����������������A����w�K�̒B���x�𑪂鏬�e�X�g�^�֏��X�ɐ肩������i�W�O�_������܂ł͍Ď�������������Ƃ̂��Ɓj�B�ڎw���̂́A�O���[�o���X�^���_�[�h�̊w�́A�u������v�Ȃ�ʁu��Ƃ苳��v�Ƃ����X���[�K���ɂ͒Ǐ]���Ȃ��B
�B�Љ�ɗL�ׂȏ�������Ă�
�i�����ł́A�{�N�x���Ɛ��ŁA���w�̎��ɐG������A���A�œ����Ƃ�����]�������āA������w���Ȉ�ނɐi�w�������k�̘b�ɐG���ꂽ�B�ޏ��̕]��͕��ϓI���������A����Z�����荞��ŁA�����������Ԃ�ɂ���ŕ����鍂�R���̃��[���c�Ԃ�����S���Ęb����Ă����B������������y����ړI�ӎ��������Ƃɂ��āA�����������k�������Ƃ̂��Ɓj
(3)�i�w��
�@��w�̃O���[�o�����ւ̑Ή�
�@�A�����J�̑�w�͂ǂ�Ȑ��k�����߂Ă��邩�B�i���w������ɂ́jTOEFL�U�O�O�ȏ�̃X�R�A�Ə��_���i�p���j�쐬����ʓI�ŁA�X�R�A�T�O�O��ł����Ă���̃e�[�}���瑍���I�Ɍ������鎑���Ɣ��W����\�������������k�͍��i����B
�@�{�N�x�́A�S���łQ�������i�B���s������l�͌c��A��q�ɐi�w�������A�Ē����_���Ă�Ƃ̂��ƁB
�A���������
�@�{�N�x�P�V�����i�B���݂̑̐��ł́A����ō��i���Ă������k���܂������B���ʂ͓y�j���̍�������u���őΉ����Ă��邪�A������͎��Ƃł̑Ή����������B��Ȏ��Ȍn�������Ă���B
�@�ʏm���͒��w�����Q����A���P�`�Q���Q�O���A���R���U�O�����x�B�S�̂Ƃ��ĉ������Ă���̂́A�w�Z������K��P�ȍu���Ŏ̑Ή����s���Ă��邩��B
�@�i�w���т̐L�т́A�����̎w���͋����A���Ƃ̃��x���A�b�v�����邪�A�n�f�̊撣������i�͂ɂȂ��āA�ӎ��̌���ɂȂ����Ă���B����ɁA�V�O�����Ƃ́A�ƒ�w�K�̎��ԑ������������B�܂��A���ȕ\����������g�q���ƂȂǂɂ��A�v�l�͂����サ�Ă���悤���B
�Q �g�c�p������L��
(1)�O�Q�N�x�̌��ʂƂ���
�@���q���E�s���ɂ�鉞��l���������X���ɂ���B�������A���͂P�O���㏸�A���u�]�Ƃ��Ă̈ʒu�Â��Ŏ��鐶�k���������B���ȕʂł͎l�Ȗڐ��̊������㏸�B
�@���i����@�́A�S���̓�Ȗڂł̐��я�ʎ҂Ŕ��\���̖�W�O��������A�c��̐l�����l�Ȗڐ��̒��ł̏�ʎҁi��Ȗڍ��i�҂��܂܂��j�Ō���B����āA�l�Ȗڎ��͓�x�`�����X������B���N�̓��ڂ��ɂƂ�ƁA�X�P�����i�̂����A��Ȗڔ���łV�R���i�����A�S�V�����l�Ȗڎ��j�A�l�Ȗڔ���P�W���B
�@����_�͂Ȃ��B�������������k�́A�����Ɋ���A�����b�N�X�������������A�O������ł̍��i�����������i�O��A�������o��҂R�V�O���B���ڂł̍��i�҂P�W�U���B�O�x�ڂ̐����A�O��ڂ̂ł̍��i�҂͂Q�P���j�B���ߐ�͂Q���V���A�J��グ�͂Q���P�P���B�葱�����ގ҂͋A�����ɑ����B
�@��ʎ��̍���ł̓_���̂�����Ȃ��Ԃ�A�Z���Ō��܂����P�[�X�������悤���B�A���������ɂ�A������B����������A�`�͏����ɃC���^�[�i�V���i���X�N�[���������B�p��̎����Ɩʐ�(ESL�����ɂ��)�ō\�������B�܂��A�a�͉p�ꂪA�����Ղ����A�Z���E�������ʎ��������Ղ����B�p��̕����������Ƃ̂�����{�l�w�Z�������B�܂��́A�����ł��p���������ƕ����Ă������k�͑Ή��ł���B�`�E�a�Ƃ��ɖ͋[�ʐڂ����{����B�a�̕��Ȃǂ͎����ň�ʐ����邱�Ƃ��B�Ȃ��A�A���ɏo�肵�Ă����ƂQ���Q���̎��i���擾�ł���B
(2)�O�R�N����
�@ �Q���Q���i��P��j�@�Q�Ȗځ@���@�Q�ȂS�ȑI�𐧂�
�A ��P��ځE��Q��ڂ̔��\�͓����Q�P�F�O�O�ɂe�`�w����уC���^�[�l�b�g�ɂ���Ĕ��\�B�����Ɍf���B�R��ڂ͓����B
�B �Ȗڂ̏o��X��
����F�����I���́{���w��i�̐ݖ�Q��͓����B�������A�u����펯�v�̒m�����̏o������炵�A�L�q���𑝂₷�B
�Z���F�R�E�S�E�T�_�̌X�Δz�_�B���ɂ���ēr�����ł̉��_���̗p�B����āA���萔�����炷�B
�Љ�A���ȁF�L�q���ݖ���o��B�o��͈͂͑S�͈́B
�C���̂ق�
�@�A�������͍�N���l�̂`�E�a�����i�O�q�j�B���Z�����́A�A�����Ɖ��y�Ȃ̂݁B
�i���z�j
�@���ƌ��w�̐܁A�҂ƈꏏ�ɎQ�������҂Ɗ猩�m��̐搶�������������āA�Z�Ɉē������Ă����������B���̍ہA������𗣂�Ă����v�Ȃ̂��Ƃ����₢�ɑ��āA�����������ʒu�ɂ͕ʂ̐E���i�搶�j�����f���ē����܂���A�Ƃ̂��ƁB���̏_��������w�Z���v�����̌��_�Ȃ̂��낤�B�N��Z������O�c�Z���ɑ����Ă̊w���̕ω��́A�g�b�v�_�E���̐F���Z�������O�̐��ɔ�ׁA�{�g���A�b�v���Ȃ����悤�ɂȂ����Ƃ̂��ƂŁA����̐������f���Ă��邻�����B
�@��؍Z������̋�N�O�ɏ��߂ĖK�₵���Ƃ��Ƃ́A�S���ʂ̊w�Z�̈�ۂ�^����B�w�O�̍ĊJ�����s��ꂽ�Ƃ��������ɉ����A�V�Z�ɂł��邱�Ƃ����̐S��ɂ͑傫�ȉe����^���Ă��邪�A�Ȃɂ�����������ł���B���k�̊w�K���e�͈�V����A�����������ɂ��������R�[�X����������܂Ƃ߂��āA���̖ړI�u���̐F�������Z���B�w�Z�S�̂ɃC���e���W�F���X���Y���܂łɂȂ��Ă���B���Ƃ��s���Ă���搶�����̔N��͎Ⴍ�A�G�l���M�b�V���Ȉ�ۂł���B���k�������A�̂Ȃ���̖��邭���C�Ȑ������̋C���͎c�����A���ɑł����ގp�́i�����Ȃ�Ƃ��A���w�����邱�Ƃł̊w�Z���̉��o�͂����Ă��j�A�D�܂������̂ɉf��B�������A�܂��܂��ۑ�Ƃ��Ďc�镔���͂���B���k�̗��q�ɑ��鈥�A��ޏ��������g�̊w�K�̍H�v�A���t���̎��Ɩ@�̍H�v��k�Ƃ̊w��I�ȕ����ł̋������ȂǁB�������Ȃ���A�҂́u���l�v���l����ƁA��w�̐i�w���т��܂߂ĐM�p�ɒl����킯�ŁA���t�T�C�h�̗͗ʂ��Z���̌��u���J���Ƃɂ�錤�r�v����������A���̌o������ނ��̂��o�Ă��邾�낤�B
�@����̐�����ň�ۂɎc�����̂́A�i�w��̐����̏������@��w�̃O���[�o�����A�������Ή��B��ȁE���Ȃւ̑Ή��Ƃ������ƂŁA�p���t���b�g�Ȃǂ��p��𒆐S�Ƃ������ۋ���̃y�[�W�ɐ�����������Ă���_�ł���B�P�Ȃ�C���[�W�헪�Ƃ�����킯�����A�e�W�҂͂ǂ̂悤�ɕ]���������낤���B
�@��삯�ɂȂ邱�ƂƂ́A�ْ[�ɂȂ邱�Ƃ��Ӗ�����킯�ŁA�V�������g�݂��s���ɂ͑����ȃG�l���M�[���K�v�Ȃ͂��ł���B���݂ł͂�����x���Ԃ̋��ʔF���ł���ɂ��Ă��A�u�p������TOFEL�v�Ƃ����X���[�K���́A���̔F�m�x��̐��]���̖ʓ|�����������ւ��āA���Z���������E�Ƃ��ĉ��v��i�߂Ă�����؍Z���ݔC�����Ƃ��ẮA�ȒP�Ɋw�Z�̊Ŕɂ͂ł��Ȃ������͂��ł���B�ɂ�������炸�A�i�w�Z�ւ̓]���Ǝ����ɂ��Ă���𐄐i�����̂�����A�����ɂ͑���ȘJ�͂Ɛl�I���a瀂��������ɈႢ�Ȃ��B�i�����Ƃ��ẮA�N��Z������̋����ɑ���u�ς�邩��߂邩�v�Ȃǁj�@�����A����́A���ʓI�Ɏ���̗���ɉ��������ʂ���邱�ƂɂȂ����B�A���N���X�����݂���Ƃ͂����ATOEFL����щp���̃X�R�A�͌����ł���B�����āA����́A�Ŕ��ނ���v���O���X���u��̂Ă�����v�i���Ȃ��Ƃ��Â������Ɣے�I�ɑ����Ă���j�ł���B�i�w�F���Z���Ȃ��Ă����Ƃ���Łu��w�̃O���[�o�����v�ł���B�����āA�����Łu�i���݂ɂ�����j�ێ�I�Ȃ킩��₷���v�̃V�[�N�G���X���O���킯�ł���B
�@�A�����J����щp�ꌗ�̍��̑�w�ւ̐i�w�Ɋւ��ẮA����j�q��i�w�Z�̋����́u���̂قƂ�ǂ������Ƃ��Ă̗��w���v�Ƃ������Ƃ��v���N�������B��w���ƌ��ESL�̂���B����w��R�~���j�e�B�[�J���b�W�ȂǂŒZ���i�P�����`���N���x�j�̌�w���w������̂́A���̃����g���A���Ƃ��Ă̕]��������Ɠ`�������B���ԓI�ɂ́i���Ȃ��Ƃ��A��ƃT�C�h����́j�t���̕]�������蓾��Ƃ������Ƃ��B�����A�����̉p�ꋳ��́A����ESL���w���ōs�����ƂŁA���n�̃��C���X�g���[���ɓ���܂ł̎��ԒZ�k���\�ɂ��邾�낤�B�������A����ł́A�u����l�C�e�B�u�p��ȃX�^�b�t�̑��݂́A���k�̉p��w�K�̃��`�x�[�V�����E�A�b�v�E�c�[���Ƃ��ē����Ă��銄�����傫���ƌ�����B�ł́A�uTOEFL��v�̎��ɁA�����͂ǂ�Ȏ��ł��낤�H
���{��ESL�̋��������āA�u�����Ƃ�Β����ԉp��ɐZ�������́A�A�����ɂ͂��肪�����BTOEFL��ESSAY WRITING���u���Ƃ��đI���ł��A������w�Ƃ����I�����Ȃ�A�u���{��v�̎�����͓��R�������肵�����̂�����A�A���g���x�[�X�Ƃ�����w�͂��Ȃ�L���ɂȂ�B�C�O���w�ł�AO�F�̋����w�Z�Ȃ�ATOEFL��GPA�Ŏ��\�Ȃ킯�ł���B�w�Z���̂��C�O�i�w�ɗ����������Ă���̂����A�X�^�b�t�����@�_��S���Ă���͂��ł���B���̂̒m��Ȃ��m�ɍs���Ȃ��Ă���������A�S��I�ɂ��y�ł���B�܂��A���̂悤�Ȋ����A�u���Ƃ����J���ꂽ�Ƃ���ɂ�����āA�Ȃ����������Ƃ��Ă��̓���ڎw�����̂�����Ƃ������́A��ʐ��k�ɂ����Ȃ��炸�e�����y�ڂ����낤�B�����œ�֍����̘b�������o���̂��������A�u���升�i���o���̂͑傫���v�Ƃ����O�c�Z���̂��Ƃɂ�����Ƃ���AOG�̐��ݏo�����i�͂Ɗw�Z���̓w�͂�������ʂނ��炾�BOG���J�������́A��l���p�ӂ������[���Ƃ͐�����S���قɂ���B�\�Ȃ�A�i�H�͍����O����Ȃ��͂����B
�@�����I�ȏ���(10�`15�N��E���ݓ�\�㔼�̐��オ��\��㔼�Ō����A�q����������Ɖ��肵��)�ɁA���̕ی�҂̒���TOEFL�o���҂⌻���̐l������鎞�A�u����w�Z�Ƃ��Ă̕����ɂǂ�ȏ��i���l���������邩�B���q����ɂ����Ă͂܂��܂��ێ�I�ȓ��{�Łi�o�ϓI���R�����߂āj�A���̎��_�ŗ��w����ʓI�ɂȂ�Ƃ͍l���ɂ������ASAT�U�܂Ŋw�Z���ʓ|��������悤�ɂȂ�A�b�͕ʂɂȂ邾�낤�B�i�j�q��֍Z�́A�����֎��_���߂Đl�ފm�ۂɓ����Ă���߂�����B�j�܂��́A���̉p������S�Ȏc�[���Ƃ��Ė𗧂ĂāA�{�i�I�Ȑi�w�Z�Ƃ��āu�i���v���邩�B
�@�]��������ɑۂ͐����Ȃ��B�����܂ł̊w�Z���v�͑听�������߂Ă���悤�Ɍ�����B����W���p���E�h���[���̑̌��w���͉ʂ������Ƃ��Ă���킯�ŁA����̓W�J����ڂ𗣂��Ȃ��B�i�@�`�D�n���jhttp://www.int-acc.or.jp/senzoku/
���l�p�a���w�@�@�m�Ώې�����O�Q�N�V���W��
�w�@�̋�����j�@�X�R�Z���搶
�@�P�W�W�O�N�鋳�t�g�E�f�E�u���e���ɂ��u���e�����w�Z�Ƃ��Đݗ����A���l�p�a���w�Z�ɁB�P�X�P�U�N�A�W��Z���̃I���[�u�E�A�C�E�n�W�X�i�R�S�N�Ԃ��̊ԁA���l�p�a�Ŏw���j�̎���Ɍ��ݒn�Ɉړ]�B���a�P�S�N�ɐ����w���ƍZ�����̂��邪�A�����W�N�ɐ�O�̖��̂ł��鉡�l�p�a���w�@�ɉ��̂����B�L���X�g����̊w�Z�Łu�S�𐴂߁@�l�Ɏd����v���Z�P�Ɍf���A�P���͂��F�肩��n�܂�B�n�������͍���Ɖƒ�ȈȊO�͑S�ĉp��Ŏ��Ƃ��s���Ă����B�A�����������ݐЂ��A���ې��̖L�����͓`���I�Ȃ��̂ł���B�ƁA�w�Z�̉��v�A���痝�O�A���l�p�a���ڎw���u�����őI������E�I���ł��鏗���v�̋��������B
�w�@�̃J���L�������@�ɓ������搶
�V�w�K�w���v�̂ɂȂ��Ă��w�K���e�̍팸�͂��Ă��炸�A�T�����������̒��ōH�v���Ȃ�������悭�w�����Ă���B�ǂ̕��ʂɐi��ł����v�Ȃ悤�Ɋ�b�Ȗڂɗ͂����Ă���B�p�ꋳ��ł͒��P�E���Q�ł͏��l�����ƁA���R�ȍ~�ł͑I�𐧃O���[�h�ʁE���l�����Ƃōs���Ă���B�v���O���X�����C���ŁA�u�b�N�P�`�R�܂ł̂R���𒆂P�`���P�܂ł̂S�N�ԂŏI����悤�ɐi��ł����B���Z����͑I���Ȗڂ�݂��A�e���̐i�H�Ɍ������w�K���\�ɂ��A���P�ł͂Q�P�ʁA���Q�łP�Q�P�ʁA���R�ł͂P�T�P�ʂ��I���ȖځB���R�̑I���Ȗڂł͇T�ށ`�X�ނɕ����ĂQ�T�`�R�O�̍u�����݂����Ă���B�̎Z�͓x�O���̐ݒ�̎d���ł���B�L�x�ȑI���Ȗڂ̒����玩���̐i�H�ɕK�v�Ȃ��̂����R�ɑI�ׂ�悤�ɍH�v����Ă���B
�i�H���с@�i�H�w�������{�搶
�Q�O�O�Q�N�x��w�������ʂ��A�i�H�w�����ɂ��W�v���͂���������z�t�������B�e��w�ւ̍��i�l���̉��אl�����A���E�E��ʁE�Q�l�Ƌ敪���A�i�w�l���܂Ŏ����Ă���A�킩��₷�������ł������B���k��l��l�������̐i�H��I�����A�Z�偨�l��ւƃV�t�g���Ă��Ă���̂��A�X�U�N�ɂR�P�D�T����߂Ă����Z��i�w���O�P�N�ɂ͂P�V�D�Q���ƂT�N�Ŕ������Ă��Ă��邱�Ƃ��炱�̊w�Z�ɐ������킩��B
���N�x���Ɛ��Q�R�X���̐i�H�́A��w�P�R�P���i�T�S�D�W���j�Z��i�P�V�D�Q���j���w�Z�i�P�O�D�X���j���̑��U�i�Q�D�T���j�Q�l�R�T�i�P�S�D�U���j�B���Ɛ��̐i�H���ڂł́A�P�X�X�X�N�ɑ�w�i�w���U�P�D�R�����s�[�N�ɂT�X�����T�S�D�W���Ɖ��~���Ă��邪�A�Q�l��I�Ԑ��k���������Ă���̂ŁA��T�ɉ��~�Ƃ͌����Ȃ��B�������A�l�N����w�̎u�]�҂Q�O�X���ƌ���i�H�̂P�R�P���A���̍��V�W���̂����R�T�����Q�l�̓���I�����A�c��̂S�R�����Z�����w�Z�ɐi�H��ύX���Ă���B���̂S�R���̐i�H�ύX�������Ɍ��炵�Ă������Ƃ��o���邩������Ɍ������ۑ�ł͂Ȃ����B
�������X���Ƒ�@�S���ȒS�����@
����E�E�E�]�_���A�����A�����A���B�`�A�a�A���ʓ����ǂ̉�ł��傫���o��X���͕ς��Ȃ��B���N�x�����ł��ŋߋC�ɂȂ�̂́A����l���n��Ȃǂ͊w�K���Ă��邱�Ƃ��悭�o���邪�A�u���Ƃv��m��Ȃ����ƁB�Ⴆ�u���߂����v�u�͂��炸���v�Ƃ��������Ƃ̈Ӗ������́A���������Ⴂ�B���ꂪ�lj�͕s���ɂȂ����Ă���Ǝv����B
�Q�O�O�R�N�����ł́A���ɌX���͕ς��܂��A�����E�����������lj����l���Ă���B�V������ǂޏK���������Ă��ė~�����B
�Z���E�E�E�l���v�Z�A��s��A�}�`�Ƃ�������b����O���ɁA�㔼�ɂ̓O���t�A�������̖���z�����B�k�P�l�k�Q�l��������Ɠ��_�ł���U���ȏ�̓��_�Ɍ��т��̂ŁA��b�����̖�����K���Ă����ė~�����B
�Љ�E�E�E���{�̒n���i�s���{�����A�ʒu�Ȃǁj�A���j�A�����ŏo��B�n���̌����ł����������A�����ŏ�����悤�ɁB���j�ł̓y���[���q�����ɂ��āA�]�ˁ`���q�A���q��`����̕����ōl���Ă���B�����ł͍����匠�A��{�I�l���A���a��`�̕����𒆐S�ɍl���Ă���B���ꂼ��P�U�`�P�V�_�̔z�_�ō\�����邪�A�Ƃɂ��������ŏ�����w�K���I
���ȁE�E�E���p���͂��������o�肵�Ă��Ȃ��B�������͂̊W�A�ˁ@�n�w���C�ہA�V���@���w���ߋ��̌X���ʂ�@�����������A�ώ@�Ƃ������Ƃ���ŏo����l���Ă���B
�Q�O�O�R�N�x�����ɂ��ā@�@�J��������
���N�x�ύX�_�E�E�E�@�Q�^�Q�̂a�������Q�^�R�ɁB�A�Q�^�T�Ɏ��{���Ă������ʑI�����b�����ƕ\���ύX����B�B�`�����T�O�����U�O���@�a�����T�O�����S�O���ɒ����
�Q�ȂS�Ȃ̑I������̔�����@�́A�`���܂��Q�ȁA�S�Ȏ������Z���v�łV�T���`�W�O���肵�A�c����S�Ȏ��Ŕ��肷��B�@�a���S�ȍ��v�ł܂����肵�A�Q�ȍ��v�Ŕ���B�X�Ɏ��̓���������������P�O�����i���Ђ܂��͎Z���j�@�b�����A�Z�̂ǂ��炩�悢��������B����A�Z���A���v�Ƃ��ꂼ����l���o���A�l�X�Ȋp�x���猩�Ĕ��肷��B
�O���[�v�ʐڂ͕ύX�Ȃ��A�A���������͂P�Q�^�P�Q�ƂP�^�P�O�̂Q���\��B
�Q�O�O�S�N�x�i���T�N���̓����j�ɂ́A�Q�^�P�����j���ɂ����邽�߁A�Q�^�Q�A�R�A�T�Ŏ��{���邱�Ƃ��l���Ă���B�i�@�`�D�r�j
http://www.yokohama-eiwa.ac.jp/
�X���w���@�O�R�N�����v��
�@�P��@�Q���Q���@�j���T�O���@�Q�ȂS��
�@�Q��@�Q���S���@�j���Q�O���@�Q�ȂS��
�@�R��@�Q���U���@�j���Q�O���@�Q�ȂS��
�@���w�葱�͊e��Ƃ��Q���P�V���P�T�F�O�O�܂ŁB
�O�Q�N��������
�@�P��@�@�@�j�q�@�@�@���q
�@��W�@�@�@�@�@�T�O��
�@����ҁ@�P�S�Q�@�@�@�P�V�X
�@�ҁ@�P�Q�P�@�@�@�P�S�X
�@���i�ҁ@�@�T�P�@�@�@�@�V�Q
�@�Q��@�@�@�j�q�@�@�@���q
�@��W�@�@�@�@�@�Q�O��
�@����ҁ@�P�W�V�@�@�@�P�X�W
�@�ҁ@�@�X�W�@�@�@�@�V�U
�@���i�ҁ@�@�Q�T�@�@�@�@�P�X
�@�R��@�@�@�j�q�@�@�@���q
�@��W�@�@�@�@�@�Q�O��
�@����ҁ@�P�U�T�@�@�@�P�W�O
�@�ҁ@�@�V�S�@�@�@�@�U�S
�@���i�ҁ@�@�P�W�@�@�@�@�P�Q
�X���w��������ƌ��߂����R�i��������E�E�E�V�����A���P�[�g���j
�@���k�A�ی�҂̂��������R�̏�ʂT���ڂ�������蔲���i�����j
�@���k
�@�P�@���R���@�P�W��
�@�Q�@�搶�̕��͋C�@�P�V��
�@�R�@�ݍZ���̕��͋C�@�P�T��
�@�R�@�w�Z�̕��͋C�@�P�T��
�@�R�@�ʊw�̕ց@�P�T��
�@�ی��
�@�P�@�搶�̔M�Ӂ@�R�S��
�@�P�@�ƒ�I�ȕ��͋C�@�R�S��
�@�R�@���@�Q�W��
�@�S�@�J���L�������E���Ƃ̎��@�P�V��
�@�T�@�ʊw�̕ց@�P�T��
�X���w���̖ڎw������i����������j
�X���w�����E�������@�Z���@�x���_�s
�@�u���������s������悤���炵�A���������݊Ԃ�e���ɂ��A���m�ɂ���Đ������s�^�ƁA�K�v�ɂ���Đ������s�^�Ƃ���ʂ��A�O�҂�����A��҂���s�����ڂ����ƂȂ��ς��E�Ԃ��Ƃ��������m�I���{�̓A�e�i�C����N�������v�i�C�\�N���e�X�j
�@���̈��p���̍Ō�̌��A�A�e�i�C��X���ɒu�������āA�������蓯�����𑲋Ɛ��Ɍ��킹�Ă݂����A���ꂪ�������X�t�w�����E���������E���̖��ł��B
�@���⍑����w���܂߂Ċw�Z�ԋ����̎���A���悢�������ׂ��e�w�Z�͑��݂ɐ؍��������Ă���܂��B�������Ȃ��Ƃ���ɐi���͂���܂���A����܂ŎЉ�̓����Ɩv���Ŗ����ɂ̂�т�\���Ă����w�Z���o���������Ƃ́A�Љ�S�̂ɂƂ��đ傫�ȃv���X�ł��B�w�Z�͐��k�̊w�K�ւ̓��@�t���������ƍH�v���A�����������n�������z�����ނ悤�ɒm���Ƌ��{�k�ɓ`�B���邽�߂ɂ����Ƃ����Ɠw�͂��ׂ��Ȃ̂ł��B�������ɐl���͒����A���̒��ł̊w�Z�݊w���Ԃ͌����Ă��܂�����A�l�ԂɂƂ��Ċw�Z�����ׂĂł͂���܂���B�����A�O�q�̍��S�܂łƂ�����悤�ɁA�l�ԂɂƂ��ėc�����͑�Ȏ����ŁA���l�Ȃ��Ƃ��w�Z�ɂ����Ă͂܂�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ǂ̂悤�ȋ�����ŒN�Ɖ߂������̂��͑�Ȃ菬�Ȃ肻�̐l�̐l���ɉe����^���܂��B
�@�{�Z���������N�A���������ߋ�����v�Ɏ��g��ł܂���܂����B�������A�����ɗ��ĒɊ�����̂́A�w�Z�͏��S��Y��Ă͂��߂��A���_�ɕԂ�Ȃ�����߂��Ƃ����P���Ȏ����ł����B���v���A�s�[�������Ȃo�q������̂��悢���A�X�̋��������Ȍ[�����A�\�͂��s�����Ă���҂͂��̂��Ƃ����o���Č��r��ς݁A�����̎��Ƃ̎������߂Ȃ���ΐ��x���v�͖{���]�|�ł��胔�B�W�����͕����ǂ���G�ɉ悢���݂ƂȂ��Ă��܂��܂��B�����Ɛ��k���ꎞ�Ԉꎞ�Ԃ̎��Ƃ��ɂ���w�Z�A������Q�P���I�̐X���̐V�����`���Ƃ��Č`�����Ă䂫�����̂ł��B�܂��A�w�Z�Ŋw�Ԃ��Ƃ͕��ʂ����ł͂���܂���B�l�X�Ȋw�Z�s����ʂ��Čo�����L���A�L���Ȋ�����n���������Ăق����Ɗ���Ă��܂��B��������k����������������A���k�B�̎��厩���̐��_����ĂĂ䂫�����Ǝv���Ă��܂��B
http://www.morimura.ac.jp/
����������
�����掄�����w�����w�Z�i�w�������@�i�V���P�S�����{�j
���\�����J�͎��A�l�J��ˌ��J�͎��Əd�Ȃ�Q���҂͍�N������⏭�ȖځB
�e�w�Z�̌ʑ��k�u�[�X�̑��ɁA�~�j������̉����p�ӂ����B
 �@�ʑ��k�̗l�q
�@�ʑ��k�̗l�q
���c�E�������w�t�F�A�@�i�V���Q�O�����{�j
�V�O�O�g�̕ی�ҁE���k���Q���B�I���ԍۂɂȂ��đ��k��]�҂��������Ă���w�Z���������B
 �@���k��̗l�q
�@���k��̗l�q
������
�Z���^�[�����@�O�U�N�x���烊�X�j���O����
�i�����V���@�V���P�Q���j
�����Ȋw�Ȃ́A�O�U�N�x�̑�w�����Z���^�[�����ɊO����̃��X�j���O�e�X�g��������j���ł߂��B���Z�̐V�w�K�w���v�̂����N�x���瓱������A�V�ے��Ŋw���k����w���}����O�U�N�x���œK�Ɣ��f�����B���Ȃ͍���A��w�⍂�Z�W�҂Ƃ���ɍו��ɂ��ċ��c���A�S�N��̎��{�ɔ�����B
�@���X�j���O�e�X�g�ɂ��ẮA�O�O�N�P�P���̑�w�R�c��i���E��������R�c���w���ȉ�j���\�ŁA�Z���^�[�������v��i�߂���j��ł��o�������ɐ��荞�܂ꂽ�B���\���A���ȏȂ͑�w�����Z���^�[�ȂǂƋ��c���d�ˁA�e�X�g�̎��{���@�⓱���N�x�A�����Ȃǂ̒�����}���Ă����B
�@���݂̃Z���^�[�����́A�P�����{�ɂQ���Ԃ̓����Ŏ��{����Ă���A���ȁE�Ȗڂ̎��Ԋ��ݒ�͂��肬��ɂȂ��Ă��邽�߁A�����������R���Ԃɂ��邱�Ƃ��܂߂Ă���Ɍ�����i�߂�B
�p��͐헪�\�z�@���ȏȂ��p��͂����߂�헪�\�z���\
�i�����V���@�V���P�Q���j
�@�����ʼnp��b�n�j�A�呲�Ȃ�p��Ŏd�����\�\�B�u�p�ꂪ���ȓ��{�l�v���������邽�߁A�����Ȋw�Ȃ͂P�Q���A���{�l�̉p��͂����߂�u�헪�\�z�v���܂Ƃ߁A���\�����B�����ɋ��߂���p��͂���̓I�Ɏ�������ŁA����������钆�w�E���Z�̉p�ꋳ���ɋ��߂���p��͂Ƃ��ĉp�ꌟ�菀�P���Ȃǂ̖ڕW���������B�܂��A�p�����Ƃ���O���l�𐳋K�����ɍ̗p������j�B���Ȃ́A���߂ɂł���{�痈�N�x�̊T�Z�v���ɐ��荞�ޕ��j���B
�@���{�l�̉p��͕͂č���w���w�̂��߂̉p��\�͎����i�s�n�d�e�k�j�̕��ϓ_�łP�T�U�J���E�n�撆�P�S�S�ʁA�A�W�A�Q�R�J���E�n��łQ�Q�ʂƋɂ߂ĒႢ�B
�@�\�z�ł́A���k�����̖ڕW�Ƃ��āu���Z���ƒi�K�ŁA�p��b���ł��邱�Ɓv�u��w���ƒi�K�ł͎d���E�����ʼnp�ꂪ�g����v�Ȃǂ�ݒ�B���̂��߂ɁA�p�ꋳ���ɑ��Ă��p�����P���̂ق��A�s�n�d�e�k�T�T�O�_�A���ۃR�~���j�P�[�V�����̂��߂̉p��\�͎����i�s�n�d�h�b�j�V�R�O�_�ȂǁA��r�I�������x�������߂Ă���B����ɁA�����̗p�̍ۂɂ������̓_����]��������A�����̕]���ɍl�����邱�Ƃ�����ψ���ɋ��߂�B
�@����ɗ��N�x����T�N�v��ŁA���E�̒����̑S�p�ꋳ���i�U���l�j�Ɍ��C�����{���A���݂ł̓A�V�X�^���g�Ƃ��Ď��Ƃɂ�������Ă���O���l���t���A����R�J�N�Œ��w�Z�łR�O�O�l�قǐ��K�����Ƃ��č̗p���A�����I�ɂ͒����łP�O�O�O�l���̗p���邱�Ƃ��v�悵�Ă���B�܂��A���Z���̊C�O���w�����i����B
�@���̂ق��A���N�x����n�܂����u�����I�Ȋw�K�̎��ԁv�̎��Ԃʼnp��b�����{���Ă��鏬�w�Z�ɂ��A�O���l���������Ǝ��Ԃ̂R���̂P���x���w���ł���悤�x������B���̊w�K�w���v�̉����ŏ��w�Z�ł̉p��b�����̈ʒu�t�����c�_���邽�߁A���Ԕc���⌤����i�߂�Ƃ��Ă���A�����I�ɉp�ꂪ���w�Z�Ő��K�̎��ƂƂ��Ĉʒu�t������\�����o�Ă����B
�ƒ�̋�����@�e�̂U�V�����u�ቺ�v�ƔF��
�i�����V���@�V���P�Q���j
�@�q�ǂ������l�̂V���߂����u�ƒ�̋���͂��ቺ�����v�Ɗ����Ă��邱�Ƃ��A�������琭�����̑S�������ł킩�����B���w�Z���w�O�A�����̎q�ǂ����u�͂����g�����v�u�ЂƂ�Ŏ��������ł����v�Ƃ����́A�Ⴂ�e�قǏ��Ȃ��B���������́u�������蔖�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����������v�Ƃ��Ă���B
�@�ƒ닳��Ƃ����ɂ��Ă̒����́A���������Ƃ��Ă͏��߂āB��N�P�O���A�q�ǂ������S���̂Q�T�`�T�S�̒j���P���Q��l�ɗX���ň˗����A�R�W�T�X�l������B�҂̒j����͂S�U�B�i�P�j�Q�T�`�R�S�i�Q�j�R�T�`�S�S�i�R�j�S�T�`�T�S�ɕ����ĕ��͂����B
�@�u�ƒ�̋���͂��ቺ�����Ǝv�����v�Ƃ̎���ɁA�u���̒ʂ�v�u������x�����v���v�Ɠ������̂͂U�V���B�S�T�Έȏ�ł͂V�Q���A�R�S�Έȉ��ł͂T�T���ƁA�N�オ�����قǑ����B�ቺ�̗��R�Ƃ��ẮA�u�ߕی�A�Â₩���߂���ߊ��Ȑe�̑����v�Ƃ̉����������B
�@�����̎q�ǂ��ɂ��āA���w�Z���w�܂łɁA�ǂ̂悤�Ȑ����K�����g�ɂ��Ă��������������B�u�͂����g���ĐH�����ł����v�́A�S�T�Έȏ�͂W�O�����������A�R�T�`�S�S�͂V�Q���A�R�S�Έȉ��ł͂T�Q���B�u���ӂЂƂ�Ŏ��������ł����v�́A�S�T�Έȏ�ł͂S�V�������A�R�S�Έȉ��͂Q�P���������B
�@���w�Z��w�N�܂łɎq�ǂ����ł������������������A������K�v������Ǝv������ʂ����I�����Ă��炤�ƁA�S�̂ł́u�������������v�i�T�U���j�A�u����e���ɂ������v�i�Q�V���j�A�u�ア�҂����߂��������v�i�Q�U���j�����������B
�@�����N��قǁu�e�̂����������Ȃ��������v�u�킪�܂܂����������v�������A�Ⴂ�w�́u�\�͂��ӂ�������v�������̂������I�������B
����ւ̊�����ЎQ���@����̗v���A�Ό��s�v�S����
�i�����V���@�V���P�S���j
�@�Ό��L�W�s�v�S�����͂P�R���A���s�s���ŊJ���ꂽ���{������w�A���w����c�ōu�����A�w�Z�o�c�ւ̊�����Ђ̎Q���ɂ��āu�_�ƁA����A��ÁA�����Ƃ����S����ւ̊�����ЎQ����}���˂̊J���͎���̗v���ł͂Ȃ����v�Əq�ׁA�K���ɘa��ϋɓI�ɐi�߂Ă����p�������������B
�@�Ό����͋��番��ւ̊�����ЎQ���ɂ��āu����̈ӌ��ň��Ղɋ�����e���Ό�����Ȃ����ȂǂƎw�E����Ă���v�ƔF�߂������ŁA�u�i�w�Z�o�c�́j�����̎s��K�͂�����A�o�ϊ������ɂ��v���X�ɂȂ�B�����i�K�ł͌����Z���S�ɂ����߂�w�����[���ɂȂ��Ă���B�Q�P���I�ɂӂ��킵���A�V�����w�Z�̂�������l���鎞���ɗ��Ă���v�Ǝ咣�����B
�@�Ό����͒����R�����\�����@�ȑ�w�@�̐ݒu��ɂ��Ắu�ߏ�Ǝv����ݒu�������ł���B�{���ɂ�낤�Ƃ��Ă���̂��M�ӂ��^�������Ȃ����v�Ɣᔻ�B�u��O�҂ɂ��]�����x��O��ɕK�v�ŏ����Ƃ��ė~�����v�ƒ����������B
�������ƌ�����Nj����銔����ЂƖ{���w�Z�ɋ��߂��鋳��Ƃ͗������Ȃ��̂ł͂Ȃ����B��
�֘A�L��
�w�Z�o�c�A������Ђ��@�K�����v��c�����Ԃ܂Ƃ߈�
�i�����V���@�V���R���j
�@���{�̑����K�����v��c�i�c���E�{���`�F�I���b�N�X��j�́A�������ɍ��肷�钆�ԂƂ�܂Ƃ߂ɁA��ÁA���番��ւ̊�����Ђ̎Q���≺�������Ƃ̖��ԊJ���A�n�����c��Ƃ̖��c�����i�Ȃǂ荞�ޕ��j���ł߂��B�P�Q���̍ŏI���o�Ċt�c���肳���ƁA�e�Ȓ��͒̎��s�⌟���𔗂���B����A�Ȓ���W�ƊE�̒�R���\�z�����B
�@�����K�����v��c�͍�N�x����R�J�N�ɂ킽���ċK���̌�������i�߂Ă���A���N�x�͌o�ϊ��������e�[�}�ɋK�����v����⊯���s��̌������ȂǂT������������Ă���B���̂��������s��̌������ł́A��ÁA�����A����A�_�ƂȂnj��I�֗^�������s��Q��������Ă��镪��̋K�����ɂ߁A���ԎQ���▯�Ԉϑ��A���c���Ȃǂ𑣂��A�s��̊�������_���B
�@���ԂƂ�܂Ƃߑf�Ăł́A����n�������c�́A�w�Z�@�l�Ɍ��肳��Ă���w�Z�o�c��������Ђɂ��F�߂�ׂ����Ɩ��L�B�������B�̑��l���⋳��T�[�r�X�̌���A�o�c�̌������Ȃǂ����҂ł���Ƃ��Ă���B
�@��N���̑�P���ŏI�ɐ��荞�݂Ȃ���A�^�}��W�c�̂̒�R�Ŋt�c����ł͍��ꂽ��Ë@�o�c�ւ̊�����ЎQ�����Ăѐ��荞�ޕ��j�B
�@��������ł́A�s�����ƎЉ���@�l�Ɍ��肵�Ă�����ʗ{��V�l�z�[���̌o�c�Ɋ�����Ђ̐V�K�Q����F�߂�ׂ����Ǝw�E�B�����t���ŎQ�����F�߂��Ă���_�Ɛ��Y�@�l�̎Q��������P�p���邱�Ƃ����߂Ă���B
�@�����疯�ւ̎��ƈڊǂ̐��i�ł́A���Ԉϑ����F�߂��Ă���㐅�����Ƃɉ����A�V���ɉ��������Ƃ̖��ԊJ�����f���A�������ݔ��̈ێ��E�X�V���܂߂���I�Ȗ��Ԉϑ���i�߂�ׂ����Ƃ��Ă���B���c�K�X����c�o�X���ƁA�����̕a�@�Ƃ������n�����c��Ƃɂ��Ă��A���̋Ɩ����e�ɉ����Ď��Ə��n�ɂ�閯�c���▯�Ԉϑ���i�߂邱�Ƃ荞�ޕ��j���B
�T�T�������@�ċx�݊��ԒZ�k�����Ƃ���K�ɁA���{�����U�Z
�i�����V���@�V���P�R���j
�@���{�����Z�̂U�Z���A���N�̉ċx�݂�Z�k���A���Ƃ���K���s�����Ƃ��P�R���A���������B�w�Z�T�T�����̊��S���{�ɔ������Ǝ��Ԃ̕s����₤���߂����A�ċx�݂��X�����Z���Ȃ�ȂǁA�N�Ԏ��Ɠ�������N��葝���Ă���w�Z������B�ߋE�ł͋��s�A�a�̎R�ł����l�̓���������A�u��Ƃ苳��v�ւ̓]�����K�����������ɐi��ł��Ȃ����Ƃ������Ă���B
�@���{���ς͂���܂ŁA�u�w�Z�^�c�Ǘ��K���v�ŁA�{�����Z�̒����x�Ɂi�ċx�݂͌����A�V���Q�P���`�W���R�P���j���ꗥ�ɒ�߂Ă����B�������A���N�S���̊w�Z�T���������Ŏ��Ɠ����͏]���̂P�X�O������P�V�T���ɍ팸�B�w�͒ቺ�����O���鐺���w�Z���ꂩ��オ��A���N�x���璷���x�ɂ��ő�Ŗ�P�O���ԁA���Z���Ǝ��ɒ����ł���悤�ɋK�������������B
�@��؍��i��؎s�j�͉ċx�݂�y�A���j���������W���ԒZ�k���A�W���Q�P������S�w�N�ŌߑO���Ɏ��Ƃ����{�B�Q�X�A�R�O�����͎��͎������s���B�����ɁA���N�x����Q�w���������Ċw�Z�s�������e�X�g�Ȃǂ����炵�A���Ǝ��Ԃ��P�T�������U�T���ɁB���̌��ʁA�N�Ԃ̎��Ɠ����͏]�����������������B
�@���̂ق��A���ʍ��i���ʎs�j�́A�R�N�����ċx�݂��X���ԒZ�k���ĂW���Q�O������A�P�E�Q�N�������Q�U��������Ƃ��n�߂�B���䍂�i��؎s�j�����ƊJ�n�͂R�N�������Q�P���A�P�E�Q�N���͓��Q�W���ɂȂ�B�܂��A���|���i�r�c�s�j�́A�P�w�����ɍs���Ă����_����K�i��P�T�ԁj���J�艺���A�ċx�ݒ��Ɏ��{����B
�@���l�̋K���������s�������s�{���ςł͕{���S�W���Z�̂�������썂�i���s�s�j�ȂǂR�Z���ő�R���A�a�̎R�����ςł͌����R�S���Z�̂������z���i�a�̎R�s�j�ȂǂT�Z���ő�T���A�u���Ǝ��Ԃ̊m�ۂ̂��߁v�i���{�����ρj�A���ꂼ��ċx�݂�Z�k����B���ɁA�ޗǁA����̊e�����ς͋K�������͂��Ă��Ȃ��B
�@�������������ɑ��{���ς́u�����x�ɂ̒e�͉��́A�w�͒ቺ�ւ̑��ł͂Ȃ��B���F����w�Z�Â���ɂ����p���Ăق����v�i�w���ہj�Ƙb���Ă���B
��Ε]���P�@���t�̍��Z�������\���A�V���̓s���{���Ő�Ε]���̗p
�i�����V���@�V���P�S���j
�@���t�̌������Z�����̒������i���\���j�̊w�͕]�����߂���A�����ȂǂQ�P�s���{�����u��Ε]���v�ŋL�����Ƃ����߂����A���A���m�ȂǂP�O�{���́u���Ε]���v�̈ێ���ł��o���ȂǑΉ�������Ă��邱�Ƃ������V���Ђ̒��ׂł킩�����B�����L���ēƎ��̑Ή������錧������B��Ε]��������̍��۔���Ɏg�����Ƃ̓�����������킹�Ă���B
�@�V�w�K�w���v�̂ɔ����A�����Ȋw�Ȃ̕��j�ŏ����w�Z�̒ʒm�\�Ȃǂ͍��N�x�A���Ε]�������Ε]���ɑS�ʈڍs�������A�������̕]���@�͊e���ςɔ��f���ς˂�ꂽ�B
�@�������͍��Z�����ŁA�w�̓e�X�g�ƕ��ԏd�v�ȍ��۔��莑���B�S���ɖ��_�����邱�Ƃ��\�Ȑ�Ε]���Łu�\���Ȕ��肪�ł��邩�v�Ƃ��������O������A�ǂ��Ή����邩�͏œ_�ɂȂ��Ă���B
�@�P�R���܂ł̏ł́A�R�S�s���{�������t�����̕����𐳎����肵���B���̂�����Ε]���ŋL���͓̂����{�𒆐S�ɂ����Q�P�s���{���B�ق��ɂW��������ɉ��������ŁA�ŏI�I�ɂ͑S���̂قڂV���̋��ς���Ε]�����̗p���錩���݂��B
�@��Ε]����I�ԗ��R�́A�u�������ɑ��Ε]�����c�����ꍇ�A�w���v�^�Ȃǂ̐�Ε]���Ɠ�d��ɂȂ�A�����������v�i��t���j���u��̕]���̕����͋���エ�������v�i�É����j���u�q�ǂ��̂����Ƃ����L����Ε]����蒅���������v�i��ʌ��j�\�\�ȂǁB
�@����A���Ε]����I�Ԃ̂͂P�O�{���B���C����k���A�ߋE�ɂ����Ă̒n��Ŗڗ��B���̂����V���A���A���m�A���挧�Ȃǂ͂Q�A�R�N��A��Ε]�����w�Z�ɂȂ��i�K�Œ���������ւ�����j�B�ޗnj��͂O�T�N�t�܂ő��Ε]���𑱂��A�O�U�N�ȍ~�͉��߂Č�������Ƃ����B
�@�u��Ε]���͎n�܂�������B�q�ϐ��A�������̊ϓ_����A���Ȃ��ƕ]�������ɂȂ��Ă��Ȃ��v�i���{�j�A�u�ی�҂�̗�����ɂ͑����̊��Ԃ��K�v�v�i�x�R�A���挧�j�ȂǂƐ������Ă���B
�@�������A�ʏ�̒ʒm�\�͐�Ε]���A�������͑��Ε]���ƂQ�ʂ�̍�Ƃ����Ȃ���Ȃ炸�A���t�̕��S��S�z���鐺���o�Ă���B
�@�Ǝ��̕������Ƃ�͕̂����A�F�{�A�L���̂R�����B�����́u���R�N���̒������͐�A���̗��]���L����v�ƌ��߂��B�F�{�͉p��A���w�A����Ȃǎ�v�T���Ȃ͒������̕]��������Ɏg��Ȃ��B�L���͐��E�����͐�A��ʓ����͑��Ǝg��������B
�@���̂ق��A��Ε]����I�ԎR�`�A�ȖA�������Ȃǂ́A���������w�̓e�X�g�̔�d�����߂�����ŁA���Z�̍ٗʂ̕����L����B�u��Ε]���͑I���Ɏg���ɂ����v�Ƃ������Z���̐��ɔz������˂炢������ƌ�����B
�@�y���Ε]���Ɛ�Ε]���z�@�w�N�A�w���łǂ̈ʒu�ɂ��邩�𑼂̐��k�Ƃ̔�r�Ŏ����̂����Ε]���B���Z�����̒������ł͂T�i�K�̏ꍇ�A�u�T�v�͉����A�u�S�v�͉����ȂǂƔz�������e�s���{�����ς����߂Ă����B��Ε]���́A���̐��k�ɊW�Ȃ��A���̐��k�l�̊w�͓��B�x�𑪂�B�ڕW�ɓ��B�������k�S���ɍō��_�́u�T�v�������Ƃ����肤��B��������P�O�i�K�œ_�����邱�Ƃ�����B
��Ε]���Q�@�u���Ε]���v����u��Ε]���v�ց@�搶�Y��
�i�����V���@�V���P�X���j
�@�V�w�K�w���v�́A���S�w�Z�T�����̓����ŋ��猻�ꂪ���ς����P�w�����I���A�S���̑唼�̏����w�Z�łP�X���A�P�w���̏I�Ǝ����s��ꂽ�B���̓��A���w�Z�ł́A�w�K�]���̕��@���W�c�̒��ł̈ʒu�������u���Ε]���v����w�K�̓��B�x�𑪂�u��Ε]���v�ɕς���čŏ��̒ʒm�\����n���ꂽ�B�T�i�K�́u�T�v��u�S�v�����l�ɂ��Ă��悢���߁A���т̗ǂ��q����������g���уC���t���h�̋�����w�E����Ă��邪�A�ǂ��Ȃ̂��B�搶�����ɐV�����]���̕]�������B
�@�u�ی�҂ɐ������邽�߂̎������������A�]�����₷���悤�Ƀe�X�g�����H�v���邽�߁A�y�j�A���j���o�����B�]���ɐU���āA���ƂɐS�̗]�T���Ȃ��Ȃ����v�����Q�R����̌������ɋΖ����鍑��̏������@�͂P�w����U��Ԃ����B
�@��Ε]���ł́A�w�K���e�̗���x�����łȂ��A���C��\���͂Ȃǂ𑽖ʓI�ɕ]������B���t�͊e�P������Ǝ��Ԃ��ƂɊϓ_���߁A����ɉ����ĕ]������悤���߂���B�e��k�ɂ��A����܂łƂǂ��Ⴄ���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@����A���Ε]���ł́A�T�i�K�́u�T�v�͂V���A�u�S�v�͂Q�S���Ȃǂƌ��܂��Ă������A��Ε]���ł͋K�����Ȃ��Ȃ�B�ɒ[�ȏꍇ�́A�u�P�v��u�Q�v�����Ȃ��Ă������B
�@�������@�́u���͊w�K���ł��Ă��Ȃ��q���ɂ́w�P�x�������B�ی�҂ɔ�������Ȃ����ȁv�Ƃ�����ƐS�z�������B
�@����A�����E�����n��̌������̒j���̗��ȋ��@�́u���܂łȂ���킸�w�P�x�����Ă����P�[�X�ł��A�ӗ~�E�S�����邱�Ƃɂ��āw�Q�x�������B��������J���Ă����v�Ɓg���уC���t���h�̎���𖾂�������A�u�P���Ԃ̎��Ƃ��ƂɎq���̈ӗ~��S��]������̂́A�w�������낻���ɂȂ�̂Ŗ������v�Ƙb�����B
�@����ɑ��A��t���̌������̒j�����@�́A���Ƃ̗l�q��L�^���āA���k�̈ӗ~��S�𒆐S�ɕ]�������B�u�P���Ԃ��Ƃ̎��Ƃ̌�̕]���ł��A�R�i�K�̍Œ�̂b�]��������������A�ނ���撣�点��悤�ɗU�������B�S�����ō��̂`�]���ł͌���S���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��v�ƁA�]�����Â��Ȃ肷���Ȃ��悤���ӂ������Ƃ����������B
�@���Ɍ��ł͗��t�̍��Z�����̒������i���\���j�ŁA�]���ʂ葊�Ε]�����g���B���̂��ߒ��w�R�N���ł́A��Ε]���ł����т̕��z�����Ε]���Ƃ��܂���Ȃ��悤�ɂ���w�Z�����������Ƃ����B
�@�j���̎Љ�ȋ��@�́u��Ε]���̒ʒm�\���w�T�x�ŁA���Ε]���̓��\�����P�O�i�K�]���́w�U�x�ł́A�ی�҂ɕ���������Ă������ł��Ȃ��B�������A���\���ƊW�Ȃ��P�A�Q�N���̒ʒm�\�ł́A�w�S�x��w�T�x�������Ȃ����v�Ƙb���B
���Z�ɗ\���Z�o���@�u�t�h���L����
�i���o�V���V���P�W���j
�@�w�K�m�A�\���Z���������Z�Ƒg�݁A��w��̐�p�u������ی��y�j���ɊJ�݂��铮�����L�����Ă���B�u�t���e�Z�ɔh���A���k�̊w�͂ɉ������u�����A���N��1�N�Ԃ̃J���L�������ʼn^�c����B���i�ʂł������̏m�A�\���Z�ɒʂ��̂ɔ�א��k�̕��S���y���B���q���Ő��k�����钆�A�g�w�Z���\���Z�h�͕ی�҂ɂ��A�s�[���ł���ƁA���Z�����A�g�����߂�B
�@�w�K�m���̉h���͗��t�܂łɎ�s������s�𒆐S�Ƃ��������̖�30�̎������Z�ɍu�����J�݂���B�T1�A2��̕��ی�u���̂ق��A�y�j���A�������O�̒Z���W����A�āE�~�x�݂ȂNJw�Z���̂�����v�]�ɉ�����悤�ɂ���B�O���ɏ��A�n���s�s�ɂ��g�傷����j�B
���w�Z���\���Z���Z�[���X�|�C���g�ł͎��w�Ƃ��Ă��܂�ɗ҂����̂ł͂Ȃ����B���������V�X�e���������ꂽ�w�Z�̐搶�B�̋C�����͂ǂ��Ȃ̂��낤���B�����ōu����S��������͐��k�̗͂����āA���������͊y���ł��邩���ΓƎv���Ă�����̂��낤���B��
�ċx�݂̕�K�@�����s�`�旧�̏����w�Z�S�R�O�Z�ŃX�^�[�g
�i�����V���@�V���Q�Q���j
�@�ċx�݂��n�܂�������̂Q�Q���A�����s�`��̏����w�Z�ł͉ċx�ݕ�K���n�܂����B�w�Z�T�����Ŋw�͒ቺ��S�z���鐺�����邽�߁A�u�ċx�ݒ��Ɋ�b����������g�ɒ�����v�i�拳�ώw�����j�̂��ړI�ŁA�旧�����w�Z�S�R�O�Z���S�w�N�̊�]�҂�ΏۂɂS�`�P�T���Ԏ��{����B
�����{�@�@�S�ʉ���������
�i�ǔ��V���@�V���P�U���j
�����R�@�u�@������v���炸
�@�����Ȋw���̎���@�ցA��������R�c��i�����וF��j�͂P�U���A�����{�@�̌������ɂ��āA�S�ʉ�����������A�����̎��������A����ʼnƒ�̉ʂ��������Ȃǂ�lj����镔�������ɂƂǂ߂���j���ł߂��B�Q�O�O�O�N�P�Q���ɕ������܂Ƃ߂��̎���@�ցA������v������c�̋c�_�ł́u�V���������{�@�������̗����ƍ��ӂɂ�萧�肷�ׂ����v�ȂǁA���{�I�ȉ��������߂鐺���o�Ă����B���s�@���f���镽�a��`��l�̑����Ȃǂ̊�{���O���c�����ƂɂȂ����B�����R�͍��H�ɒ��ԕ��܂Ƃ߁A������ΔN���ɂ����\�����R���ȑ��ɒ�o����B
�@�����R���܂Ƃ߂������{�@�������̊�{���j�́A�q�P�r�Љ��̕ω��ɍ��킹�ĕs������������₤�q�Q�r���@�̘g���Ō������q�R�r���݂̋����{�@�Ōf�����Ă��镁�ՓI�ȗ��O�͎c���q�S�r����U����{�v��̍����K��荞�ށ\�\�ȂǁB
�@�V���ɕ₤�����Ƃ��āA�����߂�w������Ȃǂ̖��ɑΉ����邽�߁A�����̎g������Ӗ�����薾�m�ɂ��A�����̌���⌤�C�̏d�v���荞�ޕ����Ō������Ă���B�ƒ닳��ɂ��ẮA�ƒ�̉ʂ����ׂ�������ӔC�m�ɂ������l�����B
�@������v������c�̕ł́A�u�@������v�ɂ��āA�u�@���I�ȏ���͂����ނƂ������_����c�_����K�v������v�ƌ���������Ă���Ă����B�����R�ł��A���������i�߂��ŏ@���I�ȏ����Ă邱�Ƃ��K�v�Ƃ̈ӌ����o�����A���@��Z���Œ�߂��u�M���̎��R�v�ɒ�G���鋰�ꂪ���邱�Ƃ���A�����{�@����́u�@������v�̏͑啝�ȉ����������\�������܂����B
�@�����R�ŋc�_����Ă����u�`������v�u����̋@��ϓ��v�Ȃǂ̏Ɋւ��Ă��A���@�Ɋ֘A���Ă���A�u���@�Ɋւ���c�_�͗��@�{�ɂ䂾�˂�ׂ����v�Ƃ̈ӌ��������A�u���@�̘g���Ō������v�Ƃ��ē��ݍ��c�_�͔����錩�ʂ��B
�@�܂��A�����{�@�̑O���ɂ������Ă���u���E�̕��a�ɍv���v�u�l�̑������d�v�Ȃǂ̗��O�ɂ��ẮA�u���ՓI�ȗ��O�͎c���Ȃ���A�V���������{�@�͂ǂ�����ׂ����Ƃ������_���猩�����v�Ƃ��A���@�ɂ��f�����Ă��邱�Ƃ���A�c�������ƂȂ����B������v������c�̋c�_�ł́A�u���R�ƕ����A�l�̌����ɌX���Ă���v�u�����ŗL�̓`�������ɑ��鑸�d�ƈ���ꌾ���Ȃ��v�ȂǁA�ᔻ�I�Ȉӌ����o����Ă����B
�@���݁A����Ɍ����ċc�_���Ă��鋳��U����{�v��͂P�O�N��̎Љ�����ʂ��A����T�N�Ԃ̏d�_�{�������d�v�Ȏw�j�ƈʒu�Â��A�����{�@�ɍ����K��荞�ނ��ƂƂ����B
�@�����{�@�������Ƌ���U����{�v��̍���́A������v������c���̒��Œ�Ă����B�����̒��������́u�����I�Ɏ���C������̂ł͂Ȃ��A�V�����������낷�S�\���ł�������������v�ƑS�ʓI�Ȍ������Ɉӗ~�������Ă����B
�֘A�L��
�@������@�����{�@�������ŁA�����R������������ցi�ǔ��V���@�V���P�V���j
�d�v���͔F���A���L���_�c���K�v
�@�����Ȋw���̎���@�ցA��������R�c��i�����R�j�͂P�U���A�����{�@�̌������ɔ����A�u�@������v�̐ϋɓI�ȓ����͔����錩�ʂ��ɂȂ����B
�@���@��Z���́u�M���̎��R�v�ɂȂ炢�A�����{�@���ł́u���y�ђn�������c�̂��ݒu����w�Z�́A����̏@���̂��߂̏@�����炻�̑��@���I���������Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƒ�߂��Ă���B����Ɋ�Â��A�������w�Z�ł͎�����A�@�����炪�s���Ă��Ȃ������B
�@�펞���A�_���ɓ��ʂ̒n�ʂ�^���Ċw�Z�ł��@�����炪�s��ꂽ�ق��A���Ɛ_���̎x�z���ɑ��̏@����u���A�M���̎��R�������������Ƃւ̔��Ȃ��炾�B
�@�@�����猩�����̋@�^�����܂����̂́A�̎���@�ցA������v������c���܂Ƃ߂��Q�O�O�O�N�P�Q���̕����������B���������鏭�N�ƍ߂₢���߂Ȃǂ̖���O���ɁA�́u�@���I�ȏ���͂����ށv���_�̏d�v�����w�E���A�����{�@�����������Ƃ�����B
�@�w�i�ɂ́A�J���g�i���M�I�@���W�c�j�ɖ����o�Ȃ܂ܑ���ȂǁA�@���ɑ����{�I�m���������Ȃ���҂������Ă��鎖���A���{�l�����E�ŕp������@���I�Η��������̒n�整���𗝉��ł��Ȃ��Ƃ̎w�E������B
�@�����A�u�@������v�̎~�ߕ��͗l�X���B�����̏@���Ɋւ���m���������ď@���I���{���A�l�i�琬��ڎw���Ƃ����L�`�̍l�������������A�����Ӗ��ł́A����@���̋��`��V���������邱�Ƃ��d�v�Ƃ���l�������Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B
�@�P�U���̒����R��{��蕔��ł��A���s�m�[�g���_�����q��w���̊��c�b��ψ����u�@���͐l�ނ̏d�v�ȕ�����Y���Ƃ������Ƃ�Y��Ă���v�Ə@���̒m���Ɋւ��鋳��ɑO�����Ȏp����������A�������g���L���̓n�v�R���P�ψ��́u�펞���̗��j�̒����狳���{�@����͏o�Ă����B�����ւ�d�����v�ƐT�d�Ȏp���������A���_���J��L����ꂽ�B�����וF��������R����ōēx�c�_���邱�Ƃ��Ă��A�ЂƂ܂����߂����A�@������ɂ��Ē��W�邱�Ƃ̓�����_�Ԍ������B
�@����ɁA�傫�ȏ�Q�͌��@�Ƃ̊W���B�@������ɂ��Ē�߂������{�@����Ɏ������A�u���y�т��̋@�ւ́A�@�����炻�̑������Ȃ�@���I���������Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��錛�@��Z���O���̏������ɋc�_���g�y�����˂Ȃ��B�����R���ł́u���@�Ɋւ���c�_�͗��@�{�ɂ䂾�˂�ׂ����v�Ƃ̐������܂��Ă���A�ψ��̂P�l���u�����Ȋw�Ȃ́A���@�Ɋւ��镔�����^�u�[�Ƃ��邱�ƂŁA�i�@�������j������艻����̂���������̂��낤�v�ƕ��͂���B
�@�����Ƃ������R�ŋc�_��ςݏd�˂Ă������ʁA�q�P�r�@���ɂ��Ă̒m���Ƃ��̕����A���l�̗����ɂ��Ă̋���q�Q�r�J���g��}�C���h�R���g���[���ɑ������ňӎv����ł���̊m���̂��߂̋���\�\�̂Q�_���d���A�@������͉��炩�̌`�ŕK�v�Ƃ̃R���Z���T�X�͏o������B
�@�����R�����N�Q���A�u�V��������ɂ����鋳�{����݂̍���ɂ��āv�Ƒ肷�铚�\���܂Ƃ߂��ۂ��u�������̕����A���҂�ٕ����₻�̔w�i�ɂ���@���𗝉����邱�Ƃ̏d�v������w���܂�v�Ǝw�E�����B
�@�������́A�@��������w�Z��ƒ�A�n��ȂǂŁA�ǂ������`�ōs�����A�ӌ����傫��������Ă��邱�Ƃ��B�K�v�Ȃ̂́A�����R�ɐ��}�Ȍ��_�����߂��A�@������ɂ��āA������܂߁A�����S�̂��^�u�[�̂Ȃ��c�_���L���Ă������Ƃ��낤�B
���J�͎����
��s���͎��V���@���ꍇ���i�V���V���j
�O�N��S�D�U���̑����B�j�q�̂R�D�S���̑����ɑ��āA���q�͂T�D�V���̑����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�Q�N�@�@�@�@�O�P�N�@�@�@�@�@�O�O�N
�j�q�@�S�ȁ@�@�@�S�Q�T�Q�@�@�@�@�S�O�R�O�@�@�@�@�R�U�X�P
�@�@�@�@�Q�ȁ@�@�@�@�V�V�S�@�@�@�@�@�W�R�Q�@�@�@�@�@�W�R�R
���q�@�S�ȁ@�@�@�R�T�T�Q�@�@�@�@�R�O�S�P�@�@�@�@�Q�U�W�V
�@�@�@�@�Q�ȁ@�@�@�P�X�W�W�@�@�@�@�Q�Q�O�O�@�@�@�@�Q�T�X�P
���v�@�@�@�@�@
�P�O�T�U�U�@�@�@�P�O�P�O�R�@�@�@�@�X�W�O�Q
���\���͎��V���@�u�]�Z�I��i�V���P�S���j
���N�͎l�J��˂Ǝ��{�����d�Ȃ����ɂ�������炸�A��N��R�D�R���̑����B
�j�q�͂S�D�O�����B���q�͂Q�D�V�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�Q�N�@�@�@�@�O�P�N�@�@�@�@�@�O�O�N
�j�q�@�S�ȁ@�@�@�V�P�Q�U�@�@�@�@�V�O�T�O�@�@�@�@�U�S�W�R
�@�@�@�@�Q�ȁ@�@�@�@�V�O�O�@�@�@�@�@�S�V�V�@�@�@�@�@�U�P�V
���q�@�S�ȁ@�@�@�T�S�X�Q�@�@�@�@�T�P�Q�O�@�@�@�@�S�V�X�P
�@�@�@�@�Q�ȁ@�@�@�P�V�U�T�@�@�@�@�P�X�S�W�@�@�@�@�Q�P�W�T
���v�@�@�@�@�@
�P�T�O�W�R�@�@�@�P�S�T�X�T�@�@�@�P�S�O�V�U
�l�J����͎��V���@���s���\���i�V���P�S���j
���N�͓��\���Ǝ��{�����d�Ȃ����ɂ�������炸�A��N��S�D�X���̑����B��s�������ł��S�D�O���̑����B�j�q�͂Q�D�U�����B���q�͂V�D�U�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�Q�N�@�@�@�@�O�P�N�@�@�@�@�@�O�O�N
�j�q�@�S�ȁ@�@�@�S�V�W�S�@�@�@�@�S�U�O�X�@�@�@�@�S�X�R�P
�@�@�@�@�Q�ȁ@�@�@�@�S�S�V�@�@�@�@�@�S�W�V�@�@�@�@�@�T�U�Q
���q�@�S�ȁ@�@�@�R�T�T�T�@�@�@�@�R�O�S�W�@�@�@�@�R�Q�R�V
�@�@�@�@�Q�ȁ@�@�@�@�X�X�Q�@�@�@�@�P�P�V�W�@�@�@�@�P�T�R�S
���v�@�@�@�@�@�@�@�X�V�V�W�@�@�@�@�X�R�Q�Q�@�@�@�P�O�Q�U�S
�V���O�͎����v�@
�O�͎����v�őO�N��S�D�P���̑����B��������N�͎O�͎��Ƃ����{��������Ă����̂ɁA���N�͎l�J��˂Ɠ��\���̎��{�����d�Ȃ��Ă��Ȃ���̑����B
�j�q�̂R�D�S�����ɑ��āA���q�͂S�D�X�����ƍ�N�̌������J�o�[���Ă���B
���t�̎�s�������͂T���ȏ������������\���������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�Q�N�@�@�@�@�O�P�N�@�@�@�@�O�O�N�@�@
�@�@�X�X�N
�j�q�@�S�ȁ@�@�P�U�P�U�Q�@�@�@�P�T�U�W�X�@�@�@�P�T�P�O�T�@�@�@�P�S�U�X�O�@
�@�@�@�@�Q�ȁ@�@�@�P�X�Q�P�@�@�@�@�P�V�X�U�@�@�@�@�Q�O�P�Q�@�@�@�@�Q�R�Q�W
���q�@�S�ȁ@�@�P�Q�T�X�X�@�@�@�P�P�Q�O�X�@�@�@�P�O�V�P�T�@�@�@�@�X�V�X�V�@�@�@
�@�@�@�@�Q�ȁ@�@�@�S�V�S�T�@�@�@�@�T�R�Q�U�@�@�@�@�U�R�P�O�@�@�@�@�U�V�U�O
���v�@�@ �@�@�@�R�T�S�Q�V�@�@�@�R�S�O�Q�O�@�@�@�R�S�P�S�Q�@�@�@�R�R�T�V�T
���̑�
�ċx�ݎ��R�����T�C�g
�@�j�t�e�B�͂P�X������A���W�T�C�g�u�ċx�݂̎��R�����Q�O�O�Q�v���J�݂����B�X���P���܂łɍ��v�R�O�e�[�}�̌�����ނ��Љ��B
�@����̓}�C�N���X�R�[�v�Ŕ`���u�g�債�����E�v�����グ���B����A�킪�Ƃ�ADSL�A�o�^�[���A�n�g�̖͗l�ׂ�ȂǁA��l�Ǝq�����ꏏ�Ɋy���߂������Ă����B
�@���̂ق��A�Ă��e�[�}�ɂ����u������₵����H�ׂ��l�v�Ȃǂ̃A���P�[�g���ʂ����A���^�C���œ��{�n�}��ɕ\��������A�S���̐��ӎʐ^�̓��e���W���Čf�ڂ���ȂǁA�ċx�݂i�ł��鉞���R���e���c��p�ӂ���B
�m�ċx�݂̎��R�����Q�O�O�Q�n
http://portal.nifty.com/summer/index.htm
�V���̃R�������
�X�e�b�v�A�b�v�̔Y�� �i�����V���@�T���U���j
�@��B�̂��錧�Ŏ������Z�̉ƒ�ȋ��@�����Ă���m�l�̏������A�u�����ȁv�̖Ƌ���������B���N�x���獂�Z�Ŏ��{�����V�w�K�w���v�̂Ő݂���ꂽ�V���ȂŁA�Ƌ��������Ă���l�͌����ɐ��l�������Ȃ��Ƃ����B
�@�����ς̉ے������Ă��鍂�Z����̉��t�́u�����̖Ƌ�������̂Ȃ�A�������Z�̗̍p��������B���Ȃ��ɍ̗p�����v�Ɗ��߂��Ƃ����B�������Z�ł͕������@���s�����Ă���B���q���ɔ����ċ������������Ă���A��l������\�ȕ������Ȃ̖Ƌ��������Ă��鋳���͏d���B
�@�������̋����͈ٓ����Ȃ����߁A�����Ɠ����w�Z�ɋΖ����邪�A�������̋����͂��낢��Ȋw�Z�ŋ�������B������苳�������������߁A�Y�x��玙�x�ɂ����₷���Ƃ����B
�@�������A�Ζ��Z����͍̗p���Ɂu�������Z�ɂ͍s���ȁv�ƔO��������Ă���B�u�����Ɉڂ�w����ҁx�Ɣ����ڂŌ�����v�ƔY�ށB
�@�Ζ������̂����E��Ɉڂ�̂́A���R�̌����ł���B�ҋ��̊i������u�����܂܁A�X�e�b�v�A�b�v���悤�Ƃ���l�Ԃ̑�����������悤�Ȋw�Z���A���k�̌���S����Ă���̂��낤���B
�g���h�������䂪�g��
�i�����V���@�V���W���j
�@����A�n���S�ŏ��w���炵���j�̎q�ɐȂ�����ꂽ�B���͂܂��R�W�B���d�ɒf�������A�u����ȂɘV���Č�����̂��v�Ƃ�����ƃV���b�N�������B�������A�Ί�ŐȂ𗧂����j�̎q�̗�V�������ɁA�ƒ�̍s���͂��������Ɖ��������������C�������B
�@�������琭���������\�����u�L����v�q���̐�����ŁA�q����ǂ����މƂ̎���������B���e������I�ɖ\�͂�U�邤�Ȃǂ̋ɒ[�ȗ�̂ق��ɁA���e�����ԑ̂��C�ɂ�������A�q���Ɋ�����������A�����Ȃ�ɂȂ�ȂǁA���ʂ̉ƒ�ɂ悭���������������B
�@�v���A��������������ɂ̓L���Ă������ނɓ���B�Ɏ��s����ȂǁA�v���悤�ɂ����ʃC���C�����Ƃ̒��Ŕ������������Ƃ�����B�e�̂ǂ�ȑԓx���q���̃J���ɏ�邩�g�ɐ��݂Ēm���Ă���̂ŁA�����������Ƃ͂��Ȃ��悤���ӂ��Ă�����肾�������A�����̎w�E�͉䂪�Ƃɂ��ꕔ���Ă͂܂�C�������B
�@�q�͐e�̋��Ƃ����B���ɔ������p���f���ɂ́A�e�������������Ȃ��B�������A�䂪�g��苾�����Ƃ�����C�ɂ��Ă���e�������̂ł͂Ȃ����B�����g���܂߂āB
��Ε]���ŋ��s�Ă�
�i�����V���@�U���R���j
�@�u����Ȃ��̂��������l�Ԃ̊炪�������v�Ǝv�����B�������琭�������쐬������Ε]���̂��߂̎Q�l�����̂��Ƃł���B
�@�S�����珬���w�Z�̐��т̕]�����@���A�ق��̎q���Ɣ�r���ĕ]�����鑊�Ε]������A�w�K�̓��B�x�����ĕ]�������Ε]���ɕς�����B�ʒm�\������\���܂őS���ς�邩��w�Z�̍����͕K���B�����Łu����������ǂ����v�Ƌ�̗���������̂����̎����������B
�@���w�Z�̂��鋳�Ȃł́A���Ƃ��ƂɈ�l��l�̎q�����u�S�E�ӗ~�E�ԓx�v�u�v�l�E���f�v�u�m���E�����v�̎O�̊ϓ_����]������B�e�ϓ_�͂���ɎO�ɍו�����Ă��邩��A���k�P�l������X���ځB���ꂼ��u�\�������v�u�����ނ˖����v�u�w�͂�v����v�̂R�i�K�̐��т�����B���ۂɂ͎��Ƃ̓��e�ɉ����ĂP�l�R�`�S���ڒ��x�ɍi��Ƃ������A����ł��S�O�l�̃N���X�Ȃ�P���Ԏ��Ƃ��邲�ƂɂP�Q�O�`�P�U�O���ڂ̕]�����K�v�ɂȂ�B
�@�u����Ȃ��Ƃł���킯�Ȃ�����A�����݂͂�ȓK���ɂ�邳�v�ƁA�m�l�̒��w���t�B
�@���������������鍑�B�]�����ӂ�����錻��B����E�Œ��N�����Ă������s���A�܂��J��Ԃ����B
�G���[�g�̋���_
�i�����V���@�Q���P�W���j
�@�u�{�l�������ł��Ȃ����̂������狳���Ă����߁B�l�̈�`���ɉ�������������Ė{�l�̓K����L���Ă����̂������v
�@������v������c�����߂��]��扗�ށE�ʼnY�H�Ƒ�w�����A�����L�҂Ɍ��������_�ł���B
�@���̎咣�̍��{�ɂ���̂́A�l�Ԃ̔\�͂���`�q�ɂ���Č��肳���Ƃ���u��`�q����_�v�ƁA���܂�Ȃ���ɗD�ꂽ�l�Ԃ������l�Ԃ���I�ʂ��ׂ����Ƃ���u�D����`�v�ł���B
�@�i�`�X�E�h�C�c�����_���l��ʋs�E�ɓ������v�z�Ƃ��āA�D����`�͐��A�^�u�[������Ă����B�]�莁�͂�������m�ŁA�����ĐM�O���I�����̂��낤�B�u���E�Ƌ����ł���l����Ă�ɂ́A������x�A��`�q���ʂ��N���Ă��d���Ȃ��v�Ɗ���������������Ă���B
�@�������A�l�Ԃ̒m���͊��v���ɍ��E����镔�����傫���B��`�q����m�I�\�͂𐄒肷�邱�Ƃ��\���ǂ��������A�͂����蕪�����Ă��Ȃ��B
�@�q���ɏ��ʂ����邱�Ƃ���؋��ۂ��镽����`�ɂ����肾���A�ꈬ��̃g�b�v�����i�[����Ă邱�Ƃ������ɂȂ��m�I�G���[�g�̋���_�͂����Ƌ��낵���B
�����u�v���o�v�H
�i�����V���@�Q���S���j
�@�u��Ԉ�ۂɎc���Ă���̂́A�ċx�݂̊w�K���h�ł��B�����o�������Ȃ�܂������A��萋�����Ď��M�����܂����v
�@���茧�̂��鍂�Z�̑��Ǝ��ŁA���Ɛ����オ������������o�����̂ɋ������o��������B���Z�����̈�Ԃ̎v���o�����H�@���ɂ͂ƂĂ��l�����Ȃ��B
�@���h�ȊO�ɂ���B�̌������Z�ł́u�[�������v�ƌĂ�钩�̉ۊO�w�K����ʓI���B��B�o�g�̓����ɕ����ƁA�Q�O�N�ȏ�O���炠�����Ƃ����B
�@������i�w�Z�Ɍ���Ȃ��B�P�N������قڑS������u���A�����������ނ����R�N���͕��ی�ɂ���K����ꍇ�������B���ݗF�B�̏m�u�t���u�������Z�������܂ł���Ă����ˁv�Ƃڂ₢�Ă����B
�@�w�Z�ɂ��������͂���B��w�ł͓s��̍��Z���Ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�����A���ƈ���āA�n���ɂ͗\���Z�Ȃǂ̎M���Ȃ��B���̂��߁u�w�Z�łȂ�Ƃ����Ăق����Ƃ����ی�҂������v�Ƃ����B
�@�S����������w�Z�͊��S�T�T�����ɂȂ�B�������A�����̐i�w�Z�ɒǐ����铮���͂Ȃ��B����ɑR���邽�߁A�y�j���ɂ���ɕ�K���������Ă��錧�����Z������B
�@�u��w�ɓ��邽�߂����̍��Z�v�ł͎₵���Ȃ����B
�@
����聄
���̐}�ŁA�����`�`�a�b�c�ƎO�p�`�d�a�b�̖ʐς́A�Ƃ��ɂU�S���������ŁA�O�p�`�b�c�f�̖ʐς͂R���������ł��B
�O�p�`�`�a�e�̖ʐς����߂Ȃ����B�i�O�Q�N����c���Ɓj
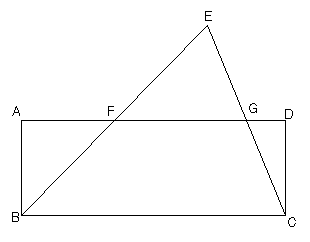
�������ɒ����S�W���
����聄
���̐}�͏����̋��\�������̂ł��B
����Ɠ������}�̂悤�ɏ��ɕ��ׂėւ�����܂��B
��͉��K�v�ł����B�������A�����̋�͍��E�Ώ̂ł��B�i�O�Q�N�a�J����a�J�j
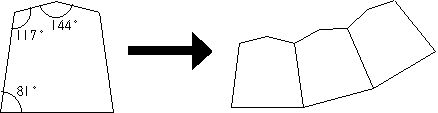
����
�ꌩ�A�ʓ|���������Ȗ��Ɍ����܂����A�����̋�ӎO�p�`�̈ꕔ�ł��邱�ƂɋC�Â��A�����ɓ������o���܂��B
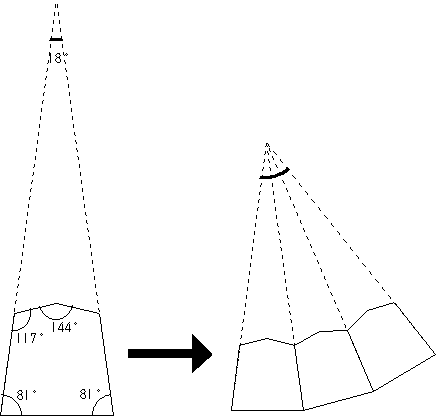
�}�̂悤�ɁA��̍��E�̕ӂ��������ēӎO�p�`������ƁA���̒��p��
�@�@�P�W�O�|�W�P�~�Q���P�W�i�x�j
�������ׂėւɂ���ɂ́A
�@�@�R�U�O���P�W���Q�O�i�j