
�m�n�D�U�T

�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�O�Q�N�@�U���@�P�T��
�ڎ�
|
�w�Z��� |
�w�Z��� | �w�Z��� | ������ | ���J�͎���� |
| ��쒆 | ��ȑ��� | �������w�@ | �w�͊i�� | �l�J��˂U��
�@ ���̑� |
�w�Z���
��쒆�@�O�Q�N��w��������
�@�@�@�@�@�@�@�@����@����@�ꋴ�@���H��
�O�Q�N�����@�@�P�R�@�@�@�Q�@�@�@�T�@�@�@�W
�O�P�N�����@�@�P�V�@�@�@�T�@�@�@�S�@�@�P�O
�@�@�@�@�@�@�@�@����@�c��@��q�@�����@�R�@�����@�����@�@���@���ȑ�
�O�Q�N�����@�@�U�U�@�@�U�X�@�@�P�W�@�@�P�U�@�@�Q�U�@�@�P�S�@�@�P�V�@�@�@�W�@�@�U�T
�O�P�N�����@�@�X�V�@�P�O�O�@�@�P�U�@�@�P�R�@�@�@�T�@�@�@�X�@�@�P�V�@�@�@�S�@�@�V�U
���Ɛ����i�Q�U�Q���j�ɑ��铌��A���c��̌������i�Ґ��̊����͂U�R�D�S���B��N�͂W�U�D�W���B
�J�����@�J�����̐��k�P�P�S�l�A�k���̓y�����@
�i�����V���@�U���S���j
����Ȃɋ߂��Ȃ�āc
�@�����̎����J�����̂Q�N���P�P�S�l���C�w���s�ō����s��K��S���A�[���z������k���̓y���g���@�h�����B�R���ɂ͌������̘b�����B�s���̓y���ɊS�������Ă��炨���ƂT������n�߂��[�����Ƃ̈�ŁA���̎���ƂȂ����B�W�҂́u���������`�̕��a���炪�L�܂��Ăق����v�Ɗ��҂��Ă���B
�@�������琰��オ�����S���A�[���z������͎����Q�����������茩�����B�L�k���܂Ŗ�R�E�V�L���B�R���D���i�䂤�ށj�N�i�P�U�j�́u����Ȃɋ߂��Ƃ͎v��Ȃ������B���V�A���k���̓y���O���J�[�h�ɂ���͎̂d���Ȃ����A���{�͂��������A�B�R�i������j�Ƃ����ԓx�ŗՂނׂ����v�Ƙb�����B
�@�R����ɂ́A�F�O���̌������A���c�E����i�V�R�j��������g���̋�J�b�����B���c����́u��ԍ����Ă���͕̂Ԋ҉^���̌�p�҂����Ȃ����ƁB�Ȃ��ŗL�̗̓y�Ȃ̂�������Ăق����v�Ƙb�����B���k����́u�Ԋ҂��ꂽ��A�Z��ł���l�͂ǂ��Ȃ�̂��v�Ȃǂ̎��₪�o���B
�@�J�����͐i�w�Z�Ƃ��Ēm����B�����苳�@�i�R�R�j�́u�����ɏZ��ł���l�̊S�̓[���ɋ߂��B���k�����ӎ����������@��ɂȂ�ł��傤�v�Ƙb���Ă����B
http://www4.justnet.ne.jp/~kaisei/
���M�@�w�Z������\�����ݕ��@
���M���w�Z�̓��w��]�҂���ѕی�҂�ΏۂƂ����w�Z������A�{���w������̂悤�Ɍv�悢�����܂����B�{�N�x���s�����͂����ɂ��\�����ݐ��t�Ƃ��ĊJ�Â������܂��B�J�Ó����͈ȉ��̒ʂ�ł��B
�P�D���{�����F�@�����P�S�N�P�O���P�X���i�y�j�A�Q�P���i���j�A�Q�Q���i�j
�P�X���i�y�j
�@�P��ځ@1�O�F�R�O�`�P�Q�F�O�O
�@�Q��ځ@1�R�F�O�O�`�P�S�F�R�O
�@�R��ځ@1�T�F�O�O�`�P�U�F�R�O
�Q�P���i���j
�@�S��ځ@�P�R�F�O�O�`�P�S�F�R�O
�@�T��ځ@�P�T�F�O�O�`�P�U�F�R�O
�Q�Q���i�j
�@�U��ځ@�P�O�F�R�O�`�P�Q�F�O�O
�@�V��ځ@�P�R�F�O�O�`�P�S�F�R�O
�@�W��ځ@�P�T�F�O�O�`�P�U�F�R�O�@
�v�W��A�e��̒���͂R�O�O���ł�
�Ȃ��A�{���w�͐�����I����ɂȂ�܂��B�ʂ̎������R�[�i�[������܂��B
�Q�D��@�@��F�@�{�Z�u��
�R�D�\�����@�F�@�����͂����ɁA�ȉ��̎������L���̂����A�X�����Ă��������B
�i�P�j�@���M���ʁF�@��]���Ɛ�����ԍ��i�P��ځ`�W��ڂ��R��]�܂Łj
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q���Ҏ����i�P�Ƒ��Q���܂Łj�A�Z���A�d�b�ԍ���K���L�����ĉ������B
�i�Q�j�@�ԐM�\�ʁF�@�Q���҂̈��Đ��K�����L�����������B
�i�R�j�@�ԐM���ʁF�@�L���s�v�i������������L�ڂ��ĕԑ����܂��B���̂͂����͓����̓��ꌔ�ɂȂ�܂��B�K���A�����Q���������B�j
�S�D�\�����ԁF�@�����P�S�N�W���Q�P���i���j�`�W���R�P���i�y�j
�@�@�i���肢�F�\�����Ԃ�����肭�������B�j
�@�@��������͗L���ł��B���̌�̂͂����ɂ��Ă͖����ƂȂ�܂��̂ł����ӂ��������B
�@�@�܂��A�d�b�ł̓������̕ύX�ɂ��Ă͈�������ł��܂���̂ł��������������B
�T�D�\����@�F�@���P�T�S-�O�O�O�P�@���c�J��r�K�@�S-�T-�P
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���M���w�Z�@�w�Z������W�@��
http://www.komabatoho-jh.ed.jp/
�ʼnY�H�咆�@���w�����{�b�g�Z�~�i�[�J��
�����@�V���Q�U���i���j�`�Q�W���i���j�@�P�O�F�O�O�`�P�U�F�O�O
�ꏊ�@�ʼnY�H�咆�w�Z
��p�@�W�C�O�O�O�~
����@�R�O��
�Ώہ@���w�Z�T�N���E�U�N���@�R���ԑ����ĎQ���ł���l
��Á@�ʼnY�H�吶�U�w�K�Z���^�[
�\�����݁@�\�����ɕK�v�������L�����Ăe�`�w�ő��t���邩�A�n�K�L�ɂĐ\�����݁B
�@�@�@�@�@�@����ґ����̏ꍇ�͒��I�B
���ߐ�@�V���P�Q���i���j�K��
http://www.shibaura-it.ac.jp/itabashi/
�����w�@�@�����w�@��m���i�O�Q�N�U���P���j
�ߑO�A�ߌ�̂Q��J�ÁB�\�����݂͌ߑO�P�R�O�O���A�ߌ�P�Q�O�O���B
���k�ɂ��i���
�P�@�o���Z�̐É������w�@�̏Љ�
�Q�@�T���Ȃ̋����ɂ��������쐬�̑_��
�R�@���P�A���R�̐��k�ɂ������̌��A�w�Z����
�̏��ɐi�s�B
�P�@�É������̏Љ��@�s�G�[���E���o�[�c�搶
�S�T�N�O�A�����w�@�̑n���ɗ�����P�O�N�ԋΖ��B���̌�A�É��ɁB
�É������͗��̂���w�Z�B�P�^�R�����ɁB
��������ʂ��Ĉ�܂�鎩���A�F��A���邳������B
�A�J�f�~�b�N�Ȋ��̊w�Z�B
���N�A�_�ސ쌧����Q�T�`�R�O�������w�B
�i�����͐����w�@�̈�p����āA�É������w�@�̑��k�R�[�i�[���݂����Ă����B�j
�Q�@�T���ȋ����ɂ��������쐬�̑_��
�i�����̔z�z�����Ɋe���Ȃ̏ڂ����_���ƁA���������g�������͂��ڂ��Ă���B�j
����
����̕��̎d�����킩��Ȃ��Ƃ��A����̐��т��グ��ɂ͂ǂ�����悢���Ƃ̎�����邱�Ƃ��悭����B
����̗͖͂����P���Ԋ��Ɍ��������Ƃ������̂ł͂Ȃ��B
�P�Q�N�Ԃ̌��ꐶ���̐ςݏd�˂Ō��t��g�ɂ��Ă��Ă���B
�N���Ă��鎞�ԑS�Ă̒��Ō��t�Ƃǂ��������Ă��邩����B
���t�͔������d�˂�悤�ɐg�ɂ��Ă������́B
�e���q���Ƃ킸���ȒP��ł������t�̂��������Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�q���ɂƂ��Č��t�̊����n�����Ȃ��Ă��Ȃ����낤���B
�U�N�����P�Q�N��ɂ͎Љ�ɏo�Ă���B�����v���Ɛe�Ɖ߂����鎞�Ԃ͒Z���B�����܂ł̂W�������̂��߂����ɉ߂����ė~�����Ȃ��B
�����w�@�ł̓v���[���e�[�V�����\�́i�l�O�ł������Ƙb����\�́j������悤�w�����Ă���B���P�ł͌Q�ǂ̎��Ԃ�݂��A�u���̕����ŁA�݂�Ȃ̑O�Ŏ��̘N�ǂ��s�����肷��B�K���݂��Ă������k�����X�ɓ��X�Ɠǂ߂�悤�ɂȂ�B���̂��߂ɐ��̔o�D����ʍu�t�Ƃ��ČĂ�ł���B
����ȂƂ��Ă͒�������Ŏq���̗͂�L�����Ƃ��l���Ă���B
�Z��
���N�x�����̓��e�͍��N�x�Ɠ����B���U��\���B�A���������܂߂R��Ƃ���Փx�͓����ɁB
�o�蕪��E�E�v�Z���A���̐����A�ꍇ�̐��E�m���A��A�����A���ʐ}�`�A���̐}�`���B
�����ł͕��i����������m���ɉ������Ƃ��厖�B
����ǂ݂Ƃ�A�������čl����B���̌�v�Z�ԈႢ�����Ȃ��悤�ɁB
�q���ɕ�����Ă��l�������������Ȃ��̂ł�������Ȃ������悢�B����������̂ł͂Ȃ��čl������������B
�ڐ�̂��Ɓi���������Ă��邩�A�����ɖ𗧂���j�̂��߂ɐ��w�������킯�ł͂Ȃ��B���w��ʂ��Ėڂɂ͌����Ȃ��厖�Ȃ��ƁA���̌����E�l�������Ă����B
�V���ɁA���w��������l�Ǝ��Ȃ��l�̔N���̍����ڂ��Ă������A�N�����ǂ��Ȃ邩�琔�w�����Ƃ������̂ł͂Ȃ��B
�������Ċۂ��R��ށi�I�����W���A�A�b�v�����A�O���[�v���j�̃K���̓����Ă��锠�ɁA�u�R�̃K���łV�̖��v�Ə����Ă������B���̌�A�u�R�̃K���łP�O��ނ̖��v�ɕς�鉽�̂V�̖���P�O��ނ̖��ɂȂ�̂������o���Ă݂邱�Ƃ���B
�ŋ߂̗�������̍ő�̌����͎q�����K�}���ł��Ȃ��Ƃ���ɂ���̂ł͂Ȃ����B
���Z�܂ł͐������A�w�ѕ��̌����������w�Ԏ����B
�����ł́A���̂ł���q�ł͂Ȃ��A�����ł���q����Ă悤�Ƃ��Ă���B
����
�o����e�͏]���ǂ���B
���W�������Ƃ��ɁA�����Ă킩�������Ƃɂ��Ȃ��Ŏ����ʼn����B
�킩�����A�킩��Ȃ��̋�ʂ�����B
�킩�����Ƃ������Ƃ͎����̌��t�Ől�ɐ����ł��邱�ƁB
�킩��Ȃ����Ƃ��͂����肳����E�E�ǂ��܂ł킩���Ăǂ�����킩��Ȃ��̂��B�킩��Ȃ��̋�ʂ��͂����肳����B
������čl����B
���Ԃ������Ė{���ɐG���@������B���̊ώ@���ʂ��c���B
�Љ�
���̂Ǝv����q���ɗ��ė~�����B
���͏���ӂ�Ă��邪�A��u���̂Ɨ����~�܂��C�����������ė~�����B
���̂Ǝv���邱�Ƃ���������͂��B���̍����͓V�C���ǂ��̂��A���̍ŋ߂�������͉Ƃɂ��邱�Ƃ������̂��A���̋~�����ЂƂ����łȂ���Ђ�����̂��B
�����ċ^���g�̉��̐l�ɕ������ƁB
�e���ꏏ�ɂȂ��čl���Ă�����B
�p��
���N����A�������������{�B
���N���ɂ��悤�ȃ��x���ŁA�z���͂�₤�����o�肵�����B
�A���������̂��߂̎������͓��ɕK�v�Ȃ��B
�p�ꌗ�łȂ��q�͉p������Ȃ��Ă悢�B�p�ꂪ�ł��Ȃ��Ă��s���ɂȂ�Ȃ��B
�p��͓ǂށA�����A�����A�b���̂S���o�����X�ǂ����K�v������B
�����ł͒��w�͉������d���B���Z�͓lj�́A�앶�͂��d���B
���{�l�͓ǂ݁A�����͂ł���悤�Ɏv���Ă��邪�ǂ݁A�������ł��Ă��Ȃ��B
���@���厖�ɂ��Ă���B
���n�͉p��Ř_����ǂ݁A�����ł���悤�ɁB
���n�͂d���[����v���[���e�[�V�������p��łł���悤�ɁB
���R�̊�]�ґΏۂɉp���A�J�i�_�ւ̃z�[���X�e�C�i�R�T�ԁj������B
�p������s�n�d�h�b�ɃV�t�g���Ă����B
�s�n�d�h�b�u���b�W�i�s�n�d�h�b�̂����Łj�𒆂Q�E���R�ŁB�s�n�d�h�b�����Z���ɁB
���̓��{�l�͓��{���b���Ȃ��B���ېl�ɂȂ�Ƃ������Ƃ̓A�����J�l�̂悤�ɂȂ邱�Ƃł͂Ȃ��B���{�l�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�e�B�[������Ȃ��悤�ɂ������B
�R�@���k���k��i���k����鐹���w�@�j
�i��̐搶�̎���ɂT�l�̐��k��������`�Ői�s�B
���P���Q�l�A���R���R�l�B�i�ߑO�̕��ƌߌ�̕��Ŕ������鐶�k�͕ʁj
�@ �����n�߂������B
���R�̂Q�����Q�l�B���S�t�A���T�t�A���U�t���e�P�l�B���U�t����n�߂����k�͋A�����B
�A �ǂ�ȕ������Ă������B
���U����n�߂����k�͍D���ȎZ���𒆐S�ɁB
�w�Z�̏h��͊w�Z�ōς܂��Ă����Ƃ������k��A�m�̎��Ƃ̂Ȃ������m�̎��K���ɍs���Ă������k�B���w�Z�ł݂�Ȃ̘b��ɂ��Ă�����悤�ɁA�e���r�����Ȃ�������Ă����Ƃ������k���B
�B ���A��������₨�ꂳ��ɂ��Ă�����Ă��ꂵ���������ƁB
�����̏�����Ă����Ă��ꂽ�B�����ٓ�������Ă��ꂽ�B���т������Ƃ���܂��Ă��ꂽ�B���ݕ�����������Ă��ꂽ�B���܂���҂���Ă��Ȃ������������A�ł�Ȃƌ���ꂽ�B
�C �����������ƁB
�e�X�g�̓_���𑼐l�Ɣ�r���ꂽ���ƁB
�D ���������̐S�\���B
�����𗎂Ƃ��悤�Ȋw�Z�ɂ͓��肽���Ȃ��B
�����l���Ȃ��悤�ɂ��Ă����B
����Ă������Ƃ������������Ď邩������Ȃ��Ǝv���Ď��B
�E �����ň�ۂɎc���Ă��邱�Ƃ́B
���O�͐Q���Ȃ������B
���т̂����l�͂�����������ƍl����̂�������Ȃ�����ǁA�����͂������������̂ł͂Ǝv���Ă����̂ŋC�y�������B
�F �N�ɂƂ��Ē��w�����Ƃ́B
���̂Ƃ��͐l���̑S�Ă̂悤�Ɏv���Ă�������ǁA�ʉߓ_�ɂ��������Ȃ��B
�����邱�Ǝ��̂���̓��e�ȊO�Ɋw�Ԃ��Ƃ��ł����B
�G �����̓��w�O�Ɠ��w��̈��
�i�w�Z�ŃK���ׂňÂ����k�������̂��Ǝv���Ă������A���邢�l�������B
�X�|�[�c�����l�������B
�j�q�Z�Œj�̐��k�������Ȃ��B
�H �����Ŋy���������s��
�ċx�݂̒��c��L�����v�ł̐�����e���g����A�e���g�ł̏h���B
�Ós���C���s�ł̔Ǎs���B
�J�i�_�ł̃z�[���X�e�C�B
�I �D���ȉȖځA�����ȉȖځB
�J ���w���ėǂ��������ƁB
���Z���Ȃ��A���w�R�N�ԍD���Ȃ��ƂɔM���ł����B
�F�l�W�Ɍb�܂ꂽ�B
���Ƃ��킩��₷���A������Ă����B
�K �u�]���R
�e�Ɋ��߂��āB���T�ňꎞ�A�������Ƃ������̐搶�Ƙb�����āB���S�̎������Ղɗ��āB�Z�������ɒʂ��Ă��āA�i�w�Z�ł��薾�邻������������B
�L ���Ғʂ肩�B
�����ɂ͍����Ă���Ǝv���B
�Z�����������Ȃ����R�B
���͂��Ȃ���B
�M �L���X�g���ɂ��āB
�P�T�ԂɂP�x�L���X�g���i�ϗ��j�̎��Ƃ����邪�A�s���͏��Ȃ��B
���{�l�͏@�����y���l���Ă���B
�ϗ��ρA���l�ς̈Ⴂ�Ő푈���N���Ă��邪�A���{�ɏ@��������Ǝv���B�@���̗������K�v�B
�L���X�g���̎��Ƃŕ����̍l�������w�ׂ�B
�N ���Ɉꌾ�B
�V�т������Ȃ�������������悢�B
�����̓��ӂȂ��̂�L���悤�ɂ��������悢�B
���Ԑ������̎��ɂ�������Ă��悤�ɁB
�����͒ʉߓ_�ɂ����Ȃ�����A�����Ă��C�ɂ��Ȃ��B
������C�ƃR���f�B�V��������B
����������Ă����傤���Ȃ��B�������Ƃ����C�����ŁB
�i�@�`�D�`�j
 �@�@���k�ɂ��w�Z�Љ�
�@�@���k�ɂ��w�Z�Љ�
 �@�@���勳�ނ̓W��
�@�@���勳�ނ̓W��
http://www.sphere.ad.jp/seiko-hs/index.htm
���喾���@���z�ړ]�͂Q�O�O�W�N
�@�X�ɏ[���������炪�������B�����ƂЂƂ�ЂƂ��厖�ɂ��鋳�炪�������B����Ȏv������Q�O�O�W�N�x���A�{�Z�͒��z�Ɉړ]���邱�ƂɂȂ�܂����B�Z�n�͌��݂̖�U�D�T�{�̍L���ɂȂ�A�ŐV�̎{�݂ƗΖL���Ȋ��ō��܂ňȏ�ɏ[������������s���܂��B
�Q�O�O�R�N�x���Z���ɂ͒��ڊW������܂��A�Q�O�O�R�N�x�̒��w���i���ݏ��w�U�N���j�̕��͍��Z�R�N�̂Ƃ��P�N�ԐV�Z�n�ɒʊw���邱�ƂɂȂ�܂��B
�Q�O�O�R�N�����v��
�P��@�Q���R���@�j�q�P�O�O���@�S��
�Q��@�Q���T���@�j�q�@�T�O���@�S��
�Q�O�O�Q�N�x���w��������
�@�@�@�@�@�@�@�@��P��@��Q��
�u��Ґ��@�@�@�V�U�X�@�@�U�P�R
�Ґ��@�@�@�U�R�O�@�@�R�X�Q
���i�Ґ��@�@�@�P�U�U�@�@�@�U�V
���i�Œ�_�@�@�Q�P�Q�@�@�Q�P�Q
(��P��)���ȁ@���_�@�ҕ��ρ@���i�ҕ��ρ@�ō��_�@�Œ�_�@����_
�@�@�@�@�@����@�P�O�O�@�@�@�V�P�D�T�@�@�@�@�W�P�D�O�@�@�@�@�X�V�@�@�@�P�R�@�@�@�R�U����
�@�@�@�@�@�Z���@�P�O�O�@�@�@�R�X�D�R�@�@�@�@�T�R�D�P�@�@�@�@�X�S�@�@�@�@�O�@�@�@�Q�O����
�@�@�@�@�@�Љ�@�@�V�T�@�@�@�R�V�D�U�@�@�@�@�S�U�D�U�@�@�@�@�U�T�@�@�@�@�S�@�@�@�P�X����
�@�@�@�@�@���ȁ@�@�V�T�@�@�@�S�O�D�W�@�@�@�@�S�W�D�U�@�@�@�@�U�U�@�@�@�P�R�@�@�@�Q�P����
�@�@�@�@�@���v�@�R�T�O�@�@�P�W�X�D�R�@�@�@�Q�Q�X�D�R�@�@�@�Q�W�Q�@�@�@�S�S
(��Q��)���ȁ@���_�@�ҕ��ρ@���i�ҕ��ρ@�ō��_�@�Œ�_�@����_
�@�@�@�@�@����@�P�O�O�@�@�@�U�O�D�V�@�@�@�@�U�W�D�S�@�@�@�@�W�W�@�@�@�P�W�@�@�@�R�P����
�@�@�@�@�@�Z���@�P�O�O�@�@�@�R�T�D�Q�@�@�@�@�T�R�D�R�@�@�@�@�W�S�@�@�@�@�O�@�@�@�P�W����
�@�@�@�@�@�Љ�@�@�V�T�@�@�@�S�S�D�W�@�@�@�@�T�P�D�X�@�@�@�@�U�S�@�@�@�@�W�@�@�@�Q�R����
�@�@�@�@�@���ȁ@�@�V�T�@�@�@�S�Q�D�Q�@�@�@�@�T�Q�D�O�@�@�@�@�V�O�@�@�@�@�V�@�@�@�Q�Q����
�@�@�@�@�@���v�@�R�T�O�@�@�P�W�Q�D�X�@�@�@�Q�Q�T�D�T�@�@�@�Q�U�O�@�@�@�R�R
http://www.meiji.ac.jp/ko_chu/index.html
���F�w���@�O�R�N�����v���i�\��j
�P���@�Q���P���@���q�@�W�O���@�S��
�Q���@�Q���Q���@���q�P�P�O���@�S��
�R���@�Q���S���@���q�@�R�O���@�S��
�e��Ƃ����w�葱�͂Q���P�S���܂ŁB
�R���R�P���܂łɓ��w���ނ�\���o���ꍇ�́A�[������S�z�ԋ��B
http://www.ohyu.ed.jp/
��ȑ����@�m�Ώې�����i�O�Q�N�T���Q�W���j
�@���́A���ʌ��ւ���K�i���オ��A��ȃR�^�J�̏ё������ڂɒ��w�P�N�̋����̑O��ʂ��Ẳ�c���B�Ő��̃O�����h�ɖʂ��Ă��āA�n���Ă��镗���S�n�悢�B�O�����h����́A�̈�Ղ̗��K�̎��Ƃ炵���A���C�Ȑ��������J�����������ɂ������Ă���B
�������͉��L�̒ʂ�B�ȉ��A�ʂ̎��⎖���Ȃǂ��D������āA���ɏڍׂ��L�q�B
�@�P �w�Z�����A�@�@�@�@�@�@�@�Z���@����l�q�搶
�@�Q �J���L�������ɂ��ā@ �����@��ؐ搶
�@�R �������o��X���@�@ ����@�t���M�͐搶
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z���@���V���搶
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Љ�@�쑺�^�l�搶
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ȁ@�ҖL�m�搶
�@�S �i�H�w���@�@ �i�H�w������C�A�����ψ��� �t���M�͐搶
�@�T ���ƌ��w
�P ����Z��
�i�P�j���O�͏����̎����A�ϋɓI�ɑ���w����
�@�u�F�l�A���@���悤�v�̈��A�������Z���̘b�͎n�܂����B���O�͂X�O�N�O����ς�炸�u�����̎����v�B���k�A�ی�҂̗l�X�ȃj�[�Y�f���āA���⏗�q��͋t���̎���B��ȑ����Z�́A��w�Ƌ��ɂ���B�������A���̗ǂ��͍m�肷�邪�A���k�̐i�H�͕ʂł���B�u��w�͑�ȑ������w�����w�Z�̕t���Z���v�ƌ����Z���̌��t�͈�ۓI�������B�{�N�x���Ɛ��P�R�Q�����A��ȏ��q��ւ̐i�w�͎w�萄�E�g���p�łP�O�l�A��ʎłW�l�̌v�P�W���B����w�ւ́u�i�w���т����A�w�Z�̐����v�ƁA�Z���͐i�w�Z�ł��邱�Ƃ���������B�܂��A����Ȓ��ł��u�^�v�Ɋւ��鐶���w���́A�[�����������ƌ��B�����b����ɂ���w�����s�������B��i�����A�M�ӂ̊�������b���Ԃ�ł������B
�i�Q�j�����ύX�_
�U���ɓs�\���A�V���P�P���̐R�c��Ō��肪�������u���e�v�̈ꕔ���Љ�B
��W�l�����P�Q�O���@���@��P�S�O���i�S�N���X�̐��j�@�\����
���̂��߁A���łɍZ�ɂ̑��z�v�悪�����Ă���A�V�K�������Q���̗p������B���l�����̗ǂ���ۂ��Ȃ���A����Ȃ�O���[�v�_�C�i�~�N�X�̑������˂炤�B
��P��@�Q���P���@���q�T�T���@�Q��
��Q��@�Q���Q���@���q�U�T���@�Q�ȂS��
��R��@�Q���S���@���q�Q�O���@�Q�ȂS��
�������ԁE�z�_�@�Z���i�U�O���P�O�O�_�j����i�U�O���P�O�O�_�j�Љ�E���ȁi���킹�ĂU�O���P�O�O�_�j
�i�R�j ���S�T�Z����
����ł́A�ϑ��T�ܓ���������Ă��邪�A��������S�T�Z�����ɕύX�B�E�B�[�N�f�C�̎��Ԃ�L���ɗ��p���邽�߁B
�i�S�j �J���L�����������i��q�j
�i�T�j �V���o�X�̍쐬
�O���팸�Ȃǂ͂������s��Ȃ��B�P�Ȃ����J���L�������ł͂Ȃ��A�蒅���˂�������̂ɂ���B
�i�U�j ���|�H��̑���
���|�H�ꂪ�߂��ɂ��邪�A�w�Z�̂���n��Ƃ������ƂŔr���V�X�e���͓s�����ʂɔz���������̂ɂȂ��Ă���B
�Q ��؋���
�i�P�j�J���L�������ɂ���
���w�@�P�`�R�N�Ƃ��@�T�R�T����
�p��U���ԁA���w�U���ԁi���P�͂T���ԁj�A����T����
���Z�P�N�R�V�P�ʁi�����Q�P�ʂ́u���v�B����͎��Ԋ����ɓ��ꂸ�A�����x�Ɏ��ȂǂɏW���u�`�^�ŒP�ʂ��o���Ƃ̂��ƁB�j�A�Q�N�R�T�P�ʁA�R�N�R�S�P��
�R �������X���i�e���ȐӔC�҂̐搶�����j
�i����j
��{�I�ɂ͍�N�܂łƓ����X���B�i�P�`�R��Ƃ��j
�E�����lj��Q��`��
�����Ȃǂ̕��w��i�P��A�������E�_�����␏�M�ȂǂP��
�E�����̏������i�P�O�O�_���Q�O�_�ȓ��j
�E���E�Z�́E�o��Ȃǂ�Ɨ��ݖ�ł͏o�肵�Ȃ��B
�i�҂��j����̕��ϓ_�́A�P�`�R��Ŏҕ��ςƍ��i�ҕ��ς̍��͖�U�`�X�_�i�ʕ\�Q�Ɓj�B�����̍̓_�́A�҂̔M�ӂ�]�����A�K�v�ȏ�Ɍ������͂��Ă��Ȃ��Ƃ̂��ƁB�܂��A�����o�����Ɋւ��Ă��A�r���_��݂���ȂǁA���ɕ��݊�����̓_���@�Ƃ�����B�u���Ƃ��e�X�g�v�ł͂Ȃ��A�u�����グ��e�X�g�v�Ƃ�����ہB
�i�Z���j
���N�A���������o�[�ō�₷��̂ŁA�ʁE���x���Ƃ��ɌX���͗�N�Ɠ����B�����݂̂������ŏ��̌v�Z���i�R�O�_���j�A�r�������������āA���̌o�߂��]�������₪�T�`�U��Ƃ����\���B���ׂĂ����܂鐶�k�͊�ŁA�U�O�`�U�S�_�̍��i�ҕ��σ��x���́A�ŏ��̌v�Z���͂��ߎ茘���Ƃ�����������ƂƂ�i�R�O�_�̂����A�������͂W�`�X���j�A�n���ɑ��ɑ�����̂��|�C���g�B���͓��Ƃ������A��������A����������Ȃǂ̒n���ȍ�Ƃ�v������́i�ꍇ�̐��A���ʐ}�`�A��Ԑ}�`�A�����Z�Ȃǁj�Ȃ̂ŁA��������ݖ�Ɏ��g��łق����A�Ƃ̂��ƁB���~���݂̉̂̍̓_�ł͎��͂𑪒�ł���Ƃ͎v��Ȃ��B�]���͓r�����ȊO�ɕM�Z�Ȃǂ������Ă����Ă����܂�Ȃ��B�����A�ǂ������o�H�œ����悤�Ƃ����̂��A���ꂪ�ǂ݂Ƃ��Ή��_����B�ŋ߂͓r���_�ł��Ȃ�̓��_���҂����k������Ƃ����B�Ȃ��A��̖��ɑ��A�ꑮ�̍̓_�������̂ŁA�����ɕ����_���^������B�ʏ�~�ɂȂ�w�x�~�X���A�u���_�ɂ���v�Ƃ����b�Ȃ̂ŁA���ꓯ�l�A�u�����グ��e�X�g�v�Ƃ����Ӗ��������Z���B
�i�Љ�j
�Q��E�R��ŏo��B�n���E���j�E�������삪���ꂼ��Q�F�Q�F�P�̊����ŏo�肳���B�H���u�W�����v�B�������A���j��̐l����p��Ȃǂ͊����ŏ�����悤�ɂ������B�܂��A�Z�������A�L�q�����o��B�������ɂ��S�������Ăق����B
�i���ȁj
��͂�A�W�����B�m���̗ʂ�����̂ł͂Ȃ��A�O���t�̐��ڂ�ώ@�͂Ȃǂ������ݖ₪���B��N�܂ł́A�v�Z���ʂȂǂ��I�����ʼn�������@���������A���N����͑I�����ȊO�̏o����l���Ă���B�v�Z�̌��ʂ͕����ł͕s�A�P�ʂ̕t���ԈႢ�́~�Ƃ���B
�Q�O�O�P�N�x�@�������ʁi�w�Z�������j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��P��@�@��Q��@�@��R��
��W�l���@�@�@�@�@�@ �T�O�@�@�@�@�T�O�@�@�@�@�Q�O
�o��Ґ��Q�ȁ@�@�@�P�Q�X�@�@�@�@�X�O�@�@�@�P�O�R
�@�@�@�@�@�@�S�ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�R�T�@�@�@�P�V�U
�@�@�@�@�@�@�v�@�@�@�@�P�Q�X�@�@�@�Q�Q�T�@�@�@�Q�V�X
�Ґ��Q�ȁ@�@�@�P�Q�U�@�@�@�@�T�X�@�@�@�@�T�W
�@�@�@�@�@�@�S�ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�O�U�@�@�@�@�V�X
�@�@�@�@�@�@�v�@�@�@�@�P�Q�U�@�@�@�P�U�T�@�@�@�P�Q�W
���i�Ґ��Q�ȁ@�@�@�@�U�R�@�@�@�@�P�Q�@�@�@�@�P�P
�@�@�@�@�@�@�S�ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�U�W�@�@�@�@�Q�X
�@�@�@�@�@�@�v�@�@�@�@�@�U�R�@�@�@�@�W�O�@�@�@�@�S�O
�葱�Ґ��@�@�@�@�@�@ �T�X�@�@�@�@�T�R�@�@�@�@�R�P
���w�Ґ��@�@�@�@�@�@ �S�X�@�@�@�@�S�X�@�@�@�@�R�P
���i�҃f�[�^
�z�_�i��P��`��R��Ƃ��j
����@�P�O�O�_�@�@�Z���@�P�O�O�_�@�@���ȁ@�T�O�_�@�@�Љ�@�T�O�_
���i�ғ��_�i�i�@�j���̐����͎ґS�́j
��P��@�@�@�@�ō��_�@�@�Œ�_�@�@�@���ϓ_
�@�@�@����@�@�@�W�O�@�@�@�@�S�X�i�R�O�j�@�@�U�R�D�W�i�T�V�D�P�j
�@�@�@�Z���@�@�@�X�R�@�@�@�@�S�O�i�@�T�j�@�@�U�R�D�R�i�T�P�D�W�j
�@�@�@�v�@�@�@�@�P�U�Q�@�@ �P�P�O�i�S�S�j�@�P�Q�V�D�Q�i�P�O�W�D�X�j
��Q��@�@�@�@�ō��_�@�@�Œ�_�@�@�@���ϓ_
�@�@�@����@�@�@�X�S�@�@�@�@�S�U�i�Q�R�j�@�@�U�V�D�S�i�T�W�D�S�j
�@�@�@�Z���@�@�@�X�S�@�@�@�@�R�Q�i�@�O�j�@�@�T�X�D�Q�i�S�W�D�V�j
�@�@�Q�Ȍv�@�@�P�U�V�@�@�@�@�X�V�i�R�T�j�@�P�Q�U�D�U�i�P�O�V�D�O�j
�@�@�@���ȁ@�@�@�T�O�@�@�@�@�P�W�i�P�T�j�@�@�S�O�D�W�i�R�V�D�S�j
�@�@�@�Љ�@�@�@�S�X�@�@�@�@�Q�P�i�@�X�j�@�@�R�U�D�W�i�R�R�D�W�j
�@�@�S�Ȍv�@�@�Q�U�Q�@�@�@�P�U�V�i�V�U�j�@�Q�O�R�D�S�i�P�W�Q�D�W�j
��R��@�@�@�ō��_�@�@�@�Œ�_�@�@�@���ϓ_
�@�@�@����@�@�@�W�S�@�@�@�@�S�Q�i�Q�U�j�@�@�T�W�D�W�i�T�Q�D�W�j
�@�@�@�Z���@�@�@�W�S�@�@�@�@�S�O�i�@�O�j�@�@�U�O�D�Q�i�S�Q�D�R�j
�@�@�Q�Ȍv�@�@�P�T�S�@�@�@�@�X�T�i�S�R�j�@�P�P�X�D�O�i�X�T�D�P�j
�@�@�@���ȁ@�@�@�S�S�@�@�@�@�Q�P�i�P�O�j�@�@�R�S�D�P�i�Q�X�D�O�j
�@�@�@�Љ�@�@�@�S�U�@�@�@�@�Q�T�i�@�W�j�@�@�R�W�D�Q�i�R�S�D�P�j
�@�@�S�Ȍv�@�@ �Q�Q�S�@�@�@�P�U�X�i�V�S�j�@�P�X�O�D�O�i�P�U�O�D�W�j
�S �i�H�w�������E�t���搶
�i�P�j ���w�������ʂɂ���
�Q�ȂS�ȑI�𐧎ł́A�ŏ��ɒ���̖�V�O���̐l�����A�Ȗڐ��ɂ�����炸�A�Q�ȖڂŔ��肵�A���̌�A�c��̐l�����S�Ȗڎ҂̐��я��Ō��肷��B���ʂƂ��āA�S�Ȑ��̕����L���Ȍ`�ɂȂ����B�i�O�o�u�������ʁv�Q�Ɓj
�e���Ȃ̎������Ԃ��T�O������U�O���ւɂȂ�B�Z���ȊO�̋��ȂɊւ��Ă͎��Ԃ̗]�������k�����������悤�Ɍ�����̂ŁA�Ώ����l���Ă���B
�i�Q�j �i�H�w���ɂ���
��w���O��ƂȂ�i�H�w�������A�P�ɑ�w���őI����̂ł͂Ȃ��A���ƌ�̐i�H���C���[�W������w�����s���B
�@���w�ł́A�u�E�ƒ��ׁv���s���A�ڕW�̎������̎w�j�Ƃ���B�Љ�Ȍ��w�Ƃ��Ă̐E��K���E�Ɛl�̕ی�҂̍u���Ȃǂ��s�����B
�@���Z�ł́A��w��O��Ƃ����w�������S�ɂȂ�B���ѕs�U�҂Ɋւ��ẮA���V���R�O������̑�������ی�Ɏ��o����K���s���B�܂��A���N�����ς��̓y�j�̌ߑO���i�O�q�̒ʂ�A���݂̃J���L�������͊u�T�T�x������j�ɂ͕�K���s���Ă���B
�@�����̖{�l��ی�҂̃j�[�Y�́A�u�����ʂ���v�Ƃ��������̑�w�ł��邱�Ƃ������B�����A��s���ł͍������A�������킸��֑�w�ł��邱�Ƃ������B�w�����w�̓�����悭�������āA�n���ɂ���悢��w�ɂ����ڂ���悤�Ȏw�����l���Ă���B
�@��w�S������̌��݁A���ђ���҂ł����Ă��i�w�͉\�ł���B�������A�������s���̒��A��́A�܂��͏��ł����w���o�����邱�Ƃ��\�z�����B�����ȉ��̑�w������ȂǂׂāA�u�����̔ޏ���̕�Z�v�����ł���悤�Ȏ��Ԃ���������Ă�肽���B
�i�R�j �s����
�U���P���i�y�j�@�@�̈�Ձ@�@�\��s�v
�U���Q�X���i�y�j�@�I�[�v���L�����p�X�@�i�g�o�^�e�����ɂč��m�j
�\��s�v�B�K��҂̊w�N�͖�킸�B�K��҂����l���̃O���[�v���A���R�`���P�̐��k���ē��B�Z�����w��̌����ƂȂǂ̍s����\��B�ی�҂ɂ͋������w�Z������B
�X���P�T�`�P�U���i���E�j�j�@������
�T ���ƌ��w����
�@���S�����̂́A���k�������A�m�̐搶�̖K��ɑ��ĕ�������������A��������A�C���U�����肵�Ȃ����Ƃł���B����Z���́A�����A���Ȃ��鎞�A�ׂ̃O�����h�ōs���Ă����̈�̎��Ƃ́u騂̐��v�ɑ��āA�u�^���Ȃ��Ă��Ȃ��Ă��p���������̂ł����c�c�v�Ƃ���������Ă������A���₢��A���k�����͂�����ƃ��[�����킫�܂��čs�����Ă��܂��B�ĉ���q�����́A�݂Ȋw�Z���y�����Ă��܂�Ȃ��Ƃ������z����ł����B
�@���w�́A���w�P�N���́u�������v�̎��Ƃ��Q�ς����B�������̃��[�������ؒ��J�Ɏw�����A�u�����̐��v�Ƃ̊֘A�A���ꂩ��w�K����u�������v�̓����Ƃ��āA���k���������₷���悤�ɘb��g�ݗ��āA���������q�ɑ���K�ʼn��a�Șb�����A�ƂĂ����H�v����Ă����B���w������A�s����Ȑ��k�����݂��Ă���ɂ�����炸�A�u���k�ɗD�������Ɓv�Ƃ������z���������B��������ɓ�����������̂łȂ��A�w���̎����ɂ��킹�����ƂŁA���W�ł͎��Ԃ̗]�鐶�k�ɑ��Ă͔��ő����̖����o���A���ԏ����̍ۂɖ��������̂��o���Ȃ�����͂̎q�ɑ��ď����Ȃ��悤�Ȕz�������Ȃ���K�Ȏw�������Ă��邠����ɁA��ȑ����̎w�����j���@���Ɍ���Ă���Ɗ�����ꂽ�B�u���@�ƕ����̊W�v�̎w���̎d���́A�䂪�A�N�Z�X�̎w�����j�ƃ}�b�`���Ă��āA�A�N�Z�X���Ɛ��Ƃ��Ă͗����̂��₷�����Ƃł���Ǝv���B�S�O�l�K�͂̎��Ƃł́A�S���������y�[�X�Ŏ��Ƃɂ��Ă����̂͂Ȃ��Ȃ���ςł��낤�Ǝv���邪�A������ی�̎��o����K���s���ĕ���Ă���Ƃ̂��ƂŁA���̋@��ɂ́A���̎��Ƃ�����Q�ς����Ă��������������̂��Ǝv���B�܂��A�ԋ߂̎��ɑ�����Ƃ��q�������Ē�������Ǝv���B
�p��́A���w�Q�N�̃��[�_�[�̎��ƁB���e�́u�؍���K�ꂽ�v�Ƃ������̂ŁA�����̕s�K���ω��Ȃǂ̕��@�����������Ȃ���̎��ƁB���t�̎萻�Ǝv����u�؍��N�C�Y�v�̃v�����g�Ő���グ�Ă���B�����Ԃ�Ƃɂ��₩�ȃN���X���������A���͒����̂���ɂ��₩���������B�u�m�̐搶�����Ă���v�Ƃ��������̊w�Z���̃v���b�V���[�͂������Ƃ��Ă��A�����̂��邱�Ƃɂ͐H�����A�����Ƃ���͕����Ƃ����̂́A���k�̎���������Ƃ���Ȃ���A���t�w�̏�����̎��Ƃ̂������낳�E�H�v�̂��܂��̂��낤�B�i�`�}�`���S���ƃI���h���̊W�ɂ��ċ��t���������n�߂��Ƃ��A�����Ƃ���߂����Â܂����̂ɂ͋������B�j���k���������[���h�J�b�v�Őg�߂Ȉ�ۂ������Ă���؍��ɑ��āA���������ɐ[�߂鋳�ތ����E�H�v���Ȃ���Ă���B�܂��A���̎Ⴂ�����̐搶�́A��������j���ւ̃v���[���g�̃G�s�\�[�h�ɂ����y���Ă������A���ꂪ�u�x���g�蕨�ɂ���Ƃ����̂́A�w���Ȃ�����߂ė����Ȃ��x�Ƃ����Ӗ��Ȃ́v�ƒ��w�����䂫����c�{�����������E���B���̌ł��x�e��������͖{�����e�ɂ͊W�Ȃ��Ƒ����̔��͖Ƃ�Ȃ����낤���A���k�ɋ߂������t�̐��ݏo���p���[�����k�����ɋy�ڂ����̂͌v��m��Ȃ����낤�B���t�̔��������ꂢ�ŁA���w�������ɕ������₷�������B�e�[�v���p�ӂ��Ă����悤�����A�҂��Q�ς��Ă���Ԃ͎g��Ȃ������B���k�����̐ēǂ��Ȃ��Ȃ������ł����B�D���x��B
�@������N���X�A���Z�Q�N�̎��ƁB������͎Ⴂ�j���̐搶�ŁA���Z�������ł�⑁�߂̌����Řb���Ă���B���Ɠ��e�́A�R�w�@��w�̉ߋ���炵���B���X�j���O���ނŁA���k�����̓w�b�h�t�H���𒅗p�B�����炭�A���X�j���O�̐����肾�낤�B��ʂ蕷���I�������A�{���̃|�C���g�ɒ��ӂ����N����悤�ȓ��e�����t������A���k�̎����B������ׂĉp��B���Z���Ȃ̂Ɂi����I�j�A���k�̏W���͂͂Ȃ��Ȃ��̂��́B
�@�S�c��Ƃ������A�҂̎藎���Ƃ������A�p����TOEFL�ATOEIC�Ȃǂɂ��Ăւ̉p��ȋ����Ƃ��čl���������������Ȃ������̂��c�O�B�i�p���̎擾�Ґ��͈ȉ��̕\���Q�Ɓj�@������̎������u�X�R�A�v��e�N�j�b�N���D�悳��āA���ۂ̉p��͂�����Ȃ����Ƃ������̂ŁA���ɂ͂����ے肳���搶��������������w�Z������B���̂�����̘b���܂߂Ă̐��k�̃L�����A�v�����j���O�ɂ��ẴC���^�r���[�͎���̖K��ŁB�i�V���o�X�ł́A�u���H�I�p��^�p�\�́v�𖾕����j�@����́A�p���ӓ|�ɂȂ邱�Ƃ��������q�Z�̒��ŁA��̂Ȃ��w�K�̂�����������Ă���Ƃ�����ۂ��������B
�Q�O�O�P�N�x�p�ꌟ�荇�i�Ґ��i�w�Z�z�z�������j
�@�@�@�@�@�@���w ���Z ���v
�S�� �@�@�@�X�R�@�@�@�@�@ �X�R
�R�� �@�@�@�W�X�@�@ �U�@�@�X�T
���Q���@ �S�X�@ �R�V�@ �W�U
�Q���@�@�@�@�Q�@�@�Q�S�@�@�Q�U
�Љ�Ɋւ��Ă͌��w�ƌ����قǒ������Ԃ͔q�����Ă��Ȃ��̂ŁA�ڍׂ͏q�ׂ��Ȃ����A���w�Q�N�̗��j�́A���ȏ��ɒ����ɁA�₳�������x���œW�J����Ă����B�Q�Ȗڐ��ւ̔z�����f���邪�A����A�S�Ȗڐ��̊�����������A���̃��x�����グ�邱�Ƃ��\���낤�B
�i���z�j
�@��C���͍����Ȃ�(��C�Q�W�i�j���P�U�����P�Q�j���A���u�t�Q�Q�i�j���V�����P�T�j���A�p��ȊO���l�u�t�R�i�j���Q���q�P�j���j���̂́A���Ɖ^�c��e���k�̌��C�Ŋw�K�Ɍ������l�́A�����̊w�Z������̉��o���������Ƃ��Ă��A���������͂̕\��ł���Ǝv���B�V���o�X��q������ƁA�����ށi��ɖ��W�j�Ƃ��Đ����A��L�ЁA����J���Ȃǂ̊w�Z�p���ނ��ڗ��B�I���W�i�����ފJ���ɂ͎��Ԃ��R�X�g���l����������킯�����A���̂ւ�͍��Z�R�N���d���ƌ����Ƃ��낾�낤���B���Ȃɂ���Ă͒��w���ł��g�p����Ă���B�������A�g���Ă���w�����ނ́A���Z���̂��̂Ȃ�p�ɒ�]�̂�����̂����A���w�����g�����̂͊�{�I�ȃ��[�N���獂�Z�p���ނ܂łƁA�u�킩���Ă���l�v���^�p����A���ӁA�s���ӂ���������t�H���[�ł�����̂ł���̂͊ԈႢ�Ȃ��B�N�����Ă��킩��₷�����������A�����ăX�^���_�[�h�ł����g�̂������肵���w�K�X�^�C����D�悵�����ƂƂ�����ہB���t�ƒ��ژb�����Ă��A�m�M�Ǝ��M�ɂ��ӂ�Ă���̂ɁA����ł͂Ȃ��̂��܂��悩�����B
�i�@�`�D�n�j
http://www.otsuma-tama.ed.jp/
���q�@�O�R�N�����v��
�P��`�@�Q���P���ߑO�@���q�Q�O���@���E�Z�܂��͍��E�p�@�ʐ�
�P��a�@�Q���P���ߌ�@���q�Q�O���@���E�Z�܂��͍��E�p�@�ʐ�
�Q��`�@�Q���Q���ߑO�@���q�Q�O���@���E�Z�܂��͍��E�p�@�ʐ�
�Q��a�@�Q���Q���ߌ�@���q�Q�O���@���E�Z�܂��͍��E�p�@�ʐ�
�R��@�@�Q���R���@�@�@�@���q�P�O���@���E�Z�܂��͍��E�p�@�ʐ�
�S��@�@�Q���T���@�@�@�@���q�P�O���@���E�Z�܂��͍��E�p�@�ʐ�
�R��A�S��͂Q�Ȗڂ̂��������_�̂P�ȖڂŔ���B
���w�葱�͊e��Ƃ��Q���U���P�U�F�O�O�܂ŁB
���w����������
��P��@�@�V���P�R���i�y�j�@�@�P�P�F�O�O�`
��Q��@�@�X���Q�P���i�y�j�@�@�P�P�F�O�O�`
��R��@�P�O���Q�O���i���j�@�@�P�O�F�O�O�`
��S��@�P�P���P�V���i���j�@�@�P�O�F�O�O�`
��T��@�P�Q���P�S���i�y�j�@�@�P�P�F�O�O�`
��U��@�@�P���P�P���i�y�j�@�@�P�P�F�O�O�`
���w���A��ʑΏۂ̉p��b�������J�݁E�E�E�ڍׂ̓z�[���y�[�W���������������B
<LET'S�@TALK!>�i�p��b�����̂��m�点�j
���ΏہF���w��
�ꏊ�F �w�����q���w�E�����w�Z�I���S�����[��
�u�t�F �l�C�e�B�u�X�s�J�[�̑I�C�u�t�w
�����{�l�̐搶���T�|�[�g���܂��B
��p�F ����
���ΏہF��ʁi���w���E��l�j
�ꏊ�F �w�����q���w�E�����w�Z�I���S�����[��
�u�t�F �l�C�e�B�u�X�s�J�[�̑I�C�u�t�w
�����{�l�̐搶���T�|�[�g���܂��B
��p�F ����
�\���ݕ��@�F
�{�Z�܂œd�b�i�O�R�|�R�R�O�O�|�Q�R�T�P�j�ł��A�����������B����]�̕��������ꍇ�͐撅���Ƃ����Ă��������܂��B
�����s���ȓ_���������܂�����A�S���̒���܂ł��A�����������B
http://www.kosei.ac.jp/kosei_joshi/
�������q�@�O�R�N��蒆�w��W���~
�i���A�����j
�q�[�@���Ă̌�@�M�Ђɂ͂܂��܂������h�̂��ƂƂ���ѐ\���グ�܂��B
�@���f�͒��w�Z�̕�W�����ɑ��Ă������Ƃ����͂�����A��������\���グ�܂��B
�@�{�w�����w�Z�ł͐��k�̖L���Ȑl�Ԑ�����ނ��Ƃ��d�����A������e�̏[���Ƃ��ߍׂ₩�Ȏw���ŁA���k��l�ЂƂ���Ɏw�����鋳�犈����W�J���Ă���܂����A�c�O�Ȃ��炱���ߔN�̐����e�ɍۂ��Ă͋ɂ߂ď��l���̓��w����]�V�Ȃ�����Ă���܂��B
�@���̂��Ƃ��畽���P�T�N�x�͒��w�Z�̐��k��W���s�킸�A���w�Z�̔��{�I�Ȍ������s�����Ƃƒv���܂����B�����̋���ƍ���̋���̕��������Ԃ��Ɍ������A���w���甭�W�̓���T�肽���Ƒ����܂��B
�h��
http://www.juntoku.ac.jp/
������ŗ��t���璆�w��W���~����w�Z�͓����łQ�Z�ƂȂ����B��
���w�@�@�O�R�N�����v��
�Q�������V�݁B
�P���@�Q���P���@���q�V�O���@�S�ȁ@�ʐ�
�Q���@�Q���S���@���q�Q�O���@�Q��
�Q�������͖ʐڂ����{�����B
http://izumi.seisen-h.ed.jp/
�������w���@�O�R�N�����v��
�Q������ɁB��W������P�X�O������P�V�O���ɁB
�P��@�@�@�Q���P���@���q�P�Q�O���@�Q�ȂS�ȁ@�ʐ�
�Q��@�@�@�Q���R���@���q�@�R�T���@�Q�ȂS�ȁ@�앶�@�ʐ�
�A�����@�P�����@�@���q�@�P�T���@�ڍׂ͌�����\
�P��̖ʐڂ͎��{�l�̂݁B�Q��̖ʐڂ͕ی�ғ����B
�Q��̍앶�i�R�O���j�́A�ʐڂ̂��߂̎����Ƃ��āA�u�]���R���ɂ��ď����Ă��炤�B
�s������
�I�[�v���X�N�[���E�E�E���O�\��E�㗚���͕K�v����܂���B
�@��P��@�@�U���Q�Q���i�y�j�P�O�F�O�O�`�P�R�F�O�O
�@��Q��@�P�O���Q�U���i�y�j�P�O�F�O�O�`�P�R�F�O�O�@
�w�Z������E�E�E���O�\��E�㗚���͕K�v����܂���B
�@��P��@�@�X���Q�P���i�y�j�P�O�F�O�O�`�P�Q�F�O�O
�@��Q��@�P�O���P�W���i���j�P�R�F�R�O�`�P�T�F�R�O
�n���P�P�S���N�L�O�ՁE�E�E���O�\��E�㗚���͕K�v����܂���B
�@�P�P���@�X���i�y�j�P�P�F�R�O�`�P�U�F�R�O
�@�P�P���P�O���i���j�@�X�F�O�O�`�P�U�F�R�O
�@��t�ɂĎ��e�q�ł��邱�Ƃ�����������Ă�������������ꂢ�������܂��B
�@�N���u�̓W���┭�\�A�����A���Q�̊e�N���X��L�u�ɂ�锭�\�A�w�Z�Љ��̈�Ղ̃r�f�I��f�A�����@���k�R�[�i�[�Ȃǐ��肾������̓��e�ł��B
�ʊw�Z���w��E�E�E�v���O�\��
�@�P�P���R�O���i�y�j�P�O�F�O�O�`�P�T�F�O�O
�@�P�Q���P�S���i�y�j�P�O�F�O�O�`�P�T�F�O�O
�@��L������ɂ��Q���ł��Ȃ����������ɂU�N���̕��̂��߂ɁA�{�Z���w�̋@���݂��܂����B
�@���O�ɂ��d�b�ɂĂ��\�����݂��������B���Ԃ��������Ă��������A�P���Ԓ��x�ōZ�������ē����A���@����E�����k������܂��B�e�q�ł����Z����������@��ł��B
�@�d�b�̂��\�����݂́A
�P�P���P�S���i�j���A�����i���j������j�j�̂W�F�R�O�`�P�U�F�R�O�ɒ����������@�@�i�O�R�|�R�S�O�O�|�O�W�U�P�j�ɂĂ��������܂��B
http://www.h.tjk.ac.jp/
�O�֓c�w���@�O�R�N�����v��
�O���i�m�n�D�U�S�j�ł��m�点���������v���ɒ���̒���������܂����B
�P��@�Q���P���@���q�P�O�O���@�Q�ȂS�ȁ@�ʐځ@
�Q��@�Q���R���@���q�@�T�O���@�Q�ȂS�ȁ@�ʐ�
�R��@�Q���T���@���q�@�Q�O���@�Q�ȂS�ȁ@�ʐ�
�A���@�P���P�O���@���q����@�Z���A�앶�A�ʐ�
http://www.miwada.ac.jp/
���_�w���@�O�R�N�����v��
�S������ɁB�ʐڂ�p�~�B
�P��@�Q���P���@���q�S�O���@�Q��
�Q��@�Q���Q���@���q�T�O���@�Q��
�R��@�Q���S���@���q�Q�O���@�Q��
�S��@�Q���U���@���q�P�O���@�Q��
���w�葱�͊e��Ƃ��Q���P�O���P�U�F�O�O�܂ŁB
�������w�@�@�O�R�N�����v��
��ʁ@�Q���P���@���q�X�O���@�S�ȁ@�ʐ�
�A���������͂P���V���ʐځi�ی�ғ����j�A�P���X���M�L�����B
�����m�p�a�A�������w�فA���{���q�啍���A�����Q������Ɉڍs���Ă������łP������ɂƂǂ܂�B�V�Z�ɂ��������A�S�T�����Ƃ���T�O�����Ƃւ̈ڍs�A�`�q�d�w�K�̒��w���獂�Z�ւ̔��W�A������w�ւ̐��E���@�̕ύX���A�������@�̕ύX�ɗ��炸�A���e�̏[���Ŏ��ɕ]�������w�Z�ł��낤�Ƃ���p���ɍD�������Ă�B��
�V�Z�Ɍ��݂ɍۂ���
�@�@������Ԃɂ�Ƃ����������B
�L����o���R�j�[���L���Ƃ�B�e�Z�ɂ̊ԂɃZ���g�����R�[�g�A�O���[���R�[�g�i����j�A���[�^���[���̗̋�Ԃ�����B
�A�@�K���X�ʂ�傫�����J�����ƃI�[�v���ȕ��͋C����������B
�B�@�����̍��Z�Z�Ɂi�P�X�R�O�N���݁j�Ɠ��ꐫ����������B
�������R�K���Ăɂ������A���������Ԋ��ɁB
�C�@�e�K�ɑ���������u���B
�D�@�w�K�X�y�[�X�Ɖ^���X�y�[�X�̗̈敪�����ł���B
�E�@�}���ق̏[����}��A�����������R���s���[�^�[�łł���B
�F�@�����̋��������ꏏ�ɁB
�S���Ƀm�[�g�^�p�\�R����z�z���A�A�������̓��[���ŁB
�G�@�Z���Ɍ��t�@�C�o�[���߂��炵�A�h�s�����ӎ����������ɂȂ��Ă���B
�H�@�g�C���̐����J�����p�ŁB
���J�s������
�I�[�v���X�N�[���i���ƌ��J�j
�@�V���P�R���i�y�j�@��P�����i�W�F�S�T�j�`���ی�i�P�U�F�R�O�j�܂�
�@�ʏ�̋��j���̎��Ԋ������̓��Ɏ��{���܂��B
�@�ʏ�̂P�Z���͂T�O���ł����C���̓��͂S�T���ōs���܂��B
�@�i���Ԋ��z�[���y�[�W���Q�Ɓj
�@�����̎��Ɠ��e�͂V���ɂ��m�点���܂��B
�@�����͕������̌��w�����Ă��������܂��B
�@���H�͐��k�H���������p���������܂��B�i�P�P�F�O�O�`�P�Q�F�O�O�j
�@�p�C�v�I���K���~�j�R���T�[�g���J�Â������܂��B�i�`���y���ɂā@�P�Q�F�R�O�`�P�R�F�O�O�j
�̌��͋[���ƁE�E�E�v���O�\��
�@�V���Q�Q���i���j�@�X�F�O�O�`�P�P�F�S�T
�@�v���O����
�@�@�W�F�T�O�@�@�@�@�@�@�@��t�i���w�Z���k���ցj
�@�@�X�F�O�O�`�@�X�F�P�O�@���̃V���[�g�z�[�����[���i�o���_�āj
�@�@�X�F�Q�O�`�@�X�F�R�T�@��q
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�R�[�X�@�a�R�[�X�@�b�R�[�X�@�c�R�[�X
�@�@�X�F�S�T�`�P�O�F�Q�T�@�p��@�@�@�@�p��@�@�@�p��@�@�@�p��
�@�P�O�F�S�O�`�P�P�F�Q�O�@���ȁ@�@�@�@�̈�@�@�@���y�@�@�@�ƒ��
�@�P�P�F�R�T�`�P�P�F�S�T�@�I��
�@�Ώہ@�@�@�@�{�Z��]�̏��w�Z�T�E�U�N��
�@�\�����@�@�����͂����Ɂu���������v�E�u�w�N�v�E�u�ی�Ҏ����v�E�u�Z���v�E�u�d�b�ԍ��v�E�u��]�R�[�X�i��Q�@�@�@�@�@�@�@�@��]�܂Łj�v�L���C���\�����݂��������B
�@�\�����@�U���Q�T���i�j����L��
�w�Z������
�@�P�O���@�T���i�y�j�@�P�R�F�O�O�`���J���Ɓ@�P�S�F�O�O�`�w�Z������
�@�P�P���R�O���i�y�j�@�P�S�F�O�O�`�A�����̂��߂̊w�Z������
�@�P�Q���@�V���i�y�j�@�P�R�F�O�O�`���J���Ɓ@�P�S�F�O�O�`�w�Z������
�}�[�K���b�g��
�@�P�P���R���i���j�@�P�Q�F�Q�O�`�P�U�F�O�O
�@�P�P���S���i���j�@�@�X�F�O�O�`�P�U�F�O�O
�@�������k�R�[�i�[����B
�`���y���R���T�[�g
�@�P�P���@�X���i�y�j�@�P�S�F�O�O�`
�N���X�}�X��q
�@�P�Q���P�S���i�y�j�@�P�T�F�O�O�`
�����J�s���Ɋւ���ē���������t�ɂ���܂���
 �@�}���ق̗l�q
�@�}���ق̗l�q
http://www.rikkyo.ne.jp/grp/jogakuin/
����@�O�R�N�����v��
�P��@�Q���P���@�j���U�O���@�Q�ȂR��
�Q��@�Q���Q���@�j���S�O���@�Q�ȂR��
�R��@�Q���S���@�j���Q�O���@�P��
�R�Ȃ͍���A�Z���ɎЉ�܂��͗��ȑI�������̂����̂悢�Q�ȖڂŔ���
�P�Ȃ͍���A�Z���̂ǂ��炩��I��
http://komagome.netty.ne.jp/
���C���@�O�R�N�����v��
�`�����P�@�Q���P���ߑO�@�j���Q�T���@�Q�ȂS��
�`�����Q�@�Q���P���ߌ�@�j���Q�O���@�Q��
�a�����@�@�Q���Q���@�@�@�@�j���R�O���@�Q�ȂS��
�b�����@�@�Q���S���@�@�@�@�j���P�T���@�Q�ȂS��
http://www.jishukan.ed.jp/
����������
�����掄�����w�����w�Z�i�w������
�����@�@�V���P�S���i���j�@�P�O�F�O�O�`�P�U�F�O�O
���@�@�����V�r�b�N�z�[���Q�e
�Q���Z�i���w�Z�̂݁j
�@�蕶�ف@���ؒ��@���k���@�Ջ����@����L�R
�@�Ռ��w���@�������@���؏��q�@�i���w���@��Êw���@�����w�@��w���q��
�@����@���M����t�����M��
���c�E�������w�t�F�A���������A�����k��
�����@�V���Q�O��(�y)�@�P�P�F�O�O�`�P�T�F�R�O
���@�A���J�f�B�A�s���J�i���w��فj�E�E�E�i�q�E�n���S�s���J�w�k���Q��
�Q���Z�i���w�Z�̂݁j
�@�����@������w�t������
�@��Ȓ��@�Éx���q�@�_�c���w���@�������q�@�����w���@���q�w�@�@���S���w���@���c���w��
�@�����Ɛ��w�@�@���{�����w�ف@�ԗt���@�O�֓c�w���@�a�m��i���q
�����������q���w�Z����������
�s���̏��q���w�Z�P�U�Z���Q�����āA�U���X���ɏa�J�ōs��ꂽ������̖͗l�ł��B
�����̎Q���҂͍�N��葝���R�T�O�g�ɁB
 �@�@�e�Z�̓W��������Q����
�@�@�e�Z�̓W��������Q����
 �@�@�ʑ��k�̗l�q
�@�@�ʑ��k�̗l�q
������
�w�͊i���@�u�����Ŋw�͊i���v�S�W���A�T�����Ŏ��Ǝ��Ԃɍ�
�i�ǔ��V���@�U���R���j
�@�ǔ��V���Ђ����N�x�A�p���I�Ȍ���Ȃǂ��˗����Ă���S���Q�W�Q�́u��_�ϑ��Z�v�ւ̃A���P�[�g�����i�Q�S�R�Z�j�ŁA�����Ǝ����w�Z�Ƃ̊ԂŊw�͊i���A������u�����i���v���N���邩�ǂ��������Ƃ���A�u���Ɋi���͋N���Ă���v�Ɠ������������Z���S�X�Z�i�Q�O���j�A�u���ꂪ����v�Ɠ������w�Z���U�W�Z�i�Q�W���j�ɏ�����B
�@���N�S������̊��S�w�Z�T�T�����ɂ��āA�����̏������Z�̂S�T�����������������Ă���B���̂��߁A�i�������O�����w�Z�̂قƂ�ǂ��u���Ǝ��Ԃɍ����t���v���Ƃ𗝗R�ɋ������B���Ɏ��w�̏W�������s�s���Ŋ�@���͋����A�u������w�͊i���͓��w���_���炠��Ǝv����v�i�����E�`�旧�Z�{�ؒ��j�ȂǂƁA�ӌ������������B
�@����A�u����͏��Ȃ��v���Q�W�Z�A�u���ꂪ�Ȃ��v�͂P�O�Z�����Ə��Ȃ߁B�u���̑��v�u�������Ȃ��v���V�T�Z�������B
�@�܂��A�A���P�[�g�ł́A�����Ȋw�Ȃ��ŋ߁A�u�w�K�w���v�͍̂Œ��v�u�L�т�q�ɂ͔��W�w�K���v�ƁA������̕��j�]����ł��o�������Ƃɂ��Ăǂ��~�߂邩�A�����ŕ������B�u���j�Ɂw���x�w�Ԃ�x��������v���P�R�T�Z�i�T�U���j�ƍł������A�u����̍������Ăт��˂Ȃ��v���V�W�Z�i�R�Q���j�A�u�w�͒ቺ�Ȃǂ̕s��������̂ł�ނȂ��v���U�W�Z�i�Q�W���j�Ƒ����A�u����܂Łw��Ƃ�x���������ꂷ���Ă����̂őÓ��ȕ��j�]���v���T�W�Z�i�Q�S���j�������B
�R�����@�����P�R���Z���y�j��K��
�i�ǔ��V���@�U���U���j
�@���S�w�Z�T�ܓ����̎��{�ɔ����A�y�j���ɕ�K�������������Z�͑S�O�\�l�Z�̂����\�O�Z�ɏ�邱�Ƃ��A�����Z���E���g���̂܂Ƃ߂ł킩�����B�T�Z�������ێ����Ă��鎄�����Z�ւ̑R�����łȂ��A�w�͒ቺ�_�c�̍��܂��w�i�ɁA�������Z�Ԃ̋������������Ă���悤���B
�@�������g�ɂ��ƁA�y�j��K�����{���Ă���͔̂B��A�b�{��A�b�{���A�b�{��A�b�{���A�����A�s��A�g���A�Θa�A����A���R�A��쌴�A�g�c�̏\�O�Z�B�܂��A�R���������̕����Ō������Ƃ����B
�@�\�O�Z�̂����b�{��Ɠ���������\��Z���ߑO���݂̂̎��{�B���e�ł́u����w�K�v���ł������Z�Z�B�u�t�͋��@�A�\���Z�u�t�A���Ɛ��̎O�ތ^�B
�@�\���Z�u�t�����p�����ۊO�u�����s���Ă���͍̂b�{��Ǝs��̓�Z�B�b�{��͉p��A���w�A����̎O���ȂŏK�n�x�ʍu�����J�u�B�s��͗\���Z�̉q�����Ƃ𗘗p���Ă���B
�@����A�n�a�̑�w���炪�w���ɂ������Ă���͔̂����A�s��A����̎O�Z�B���̂ق��̍��Z�ł͋��@�����[�e�[�V������g��ŒS������֔Ԑ����Ƃ��Ă���B�Q��������鍂�Z�͌܍Z�ŁA�ꋳ�ȓ�����l�S�\��~�������B
�@�����ς̂܂Ƃ߂ł́A�T�ܓ����ɂ����Ǝ����̌����ɑΉ����A�����̎����Z�������Ɏ��Z�������Ă���B�������g�ł́u�y�j��K�ɂ���ċ��t�����k���ܓ������{�O��蕉�S���傫���Ȃ��Ă���B�ܓ����̎�|���炢���āA�y�j���ɋ��t���Ζ�����͖̂��v�Ƃ��Ă���A�����ςɉ��炩�̑Ή������߂���j�B
�@����ɑ������ύ��Z����ۂ́u�ߓx�̕��S�ɂȂ�Ȃ����x�Ɏ��K�̏�����̂ł���\��Ȃ��v�Ƃ̗�����Ƃ��Ă���B
�����������@���E�p�~���A������Ǝ�����
�i�����V���j
�@�������Z�̓��w�ґI���ŁA���w�Z�ɂ�鐄�E���x��p�~���A����ɐ��k�����R�ɉ���ł���I�����x������Ƃ��낪�����Ă���B��ʓ����̑O�Ɏ��Ȑ��E����ʐځA���_���ȂǂőI�l������̂ŁA���Z�͈�ʑI���ł͕�����Ȃ��\�͂�Ǝ��ɔ��f�ł���B�s���i�ɂȂ��Ă��A������x�T���Ȃ̈�ʓ������ł��邽�߁A�������Z�̃`�����X���L����B�������w�Z�ɔ���ꂸ�Ɏł��邽�߁A���E���w�ɑ��������̓����Ƃ��č�����g�債�������B
�@���̓����́A��ʓ�����葁���Q�����߂���s���A���Z����ʓ����Ƃ͈قȂ�Ǝ��̊�ō��i�҂�I�l���邽�߁A�u���F���I���v��u�O���I���v�ȂǂƌĂ��B�ŏ��ɓ��������̂͌Q�n���ŁA�Q�O�O�O�N�t�ɐ��E���w��p�~���A���Ȑ��E�^�̑I�����B�������t���瓯�l�̓������n�߁A��t�A�É��������t������{����B�����A�_�ސ�A�����ȂNJe�����O�S�N�t�ȍ~�̓������������Ă���B
�@�������s�������w�Z�I�ׂ�
�@��t���ł͒莞�����܂ޑS���Z�E�w�Ȃ��A�w�Z�̔��f�Œ���̂P�O�`�T�O�����u���F���I���v�ɏ[�Ă�B���͒��w�Z���̐��E���̑���ɁA�u��̓��@�⎩�Ȃo�q�A��������{�����e�B�A�Ȃǂ̊������т��������u�u�藝�R���v�ƒ��������o����B���Z�͒������ƖʐځA�앶�Ȃǂ̂ق��A�Ǝ��Ɋ�{�≞�p�͂���������A���ȉ��f�I�ȑ������Ȃǂ��o�肷�邱�Ƃ��ł��A�����𑍍����č��i�҂�I�l����B
�@�]���̐��E���w�́u���w�Z�����ӔC�������Đ��E������v���k���������債�A�e���Z�͖ʐڂ�앶�A�������Ȃǂ����Ƃɍ��i�҂����߂Ă����B�������A���E���鐶�k�̐���x���Ȃǂ͒��w�Z���Ƃɂ�炾�����B�����̒��w�Z�̐i�H�w���S�����@��ł��錧���猤����i�H�w������̍�N�x�̒����ł́A��t�s���̂T�Q���w�Z�̒��Ɋw�Z���E�����R�N�����U�O������w�Z������A�P�O���ɖ����Ȃ��Ƃ�����������B
�@���E�҂��i���ē��藦�i���i���j���グ�邩�A���k�̊�]�d���đ����̎q���𐄑E���邩�A�w�Z�̍l�������قȂ邽�߂����A�u�w�Z��I�ׂȂ��������Ő��E�̎₷���Ɋi��������̂͂��������v�Ƃ����ᔻ���������B���E���鐶�k��I�Ԋ���s���m�Ȃ��߁A���k�̊Ԃɂ��u�Ȃ��A���������E���ꂽ�̂��v�Ȃǂ̕s�����o�Ă����B
�@�u�V���x�Ȃ�A���́w�s���������Z�x��I�ׂ邵�A���Z�����w�ق������k���x�������Ċw�Z���Ƃ̓��F���o����v�Ɛ�t�����ς̔����G�K�劲�͋�������B�������A���w�Z�̐��E�������Ȃ�����Z�ɓ���Ȃ��Ƃ����v���b�V���[���A���k�̕������Z�������Ȃǂ�}����������ʂ����Ă�����ʂ��ے�ł��Ȃ��B���̂��߁A���w�Z�ł́u�w�Z���E��p�~����ƁA���k�w����̎��~�߂��Ȃ��Ȃ�v�Ƃ����s����
�����B
�@��t�s���̒��w�Z���́u�V���x�ł͐��k��ی�҂���̓I�ɍ��Z��I�сA�ӔC�������̂ŁA�����x�͍��܂�B���E�̊���߂���s�������������v�Ɗ��}�������ŁA�u�w�u�藝�R���ɍZ��������d�g�݂����͎c���ׂ��ł͂Ȃ����x�Ƃ����Z��������v�Ƙb���B
�@����Ε]���ւ̕s�����瓱��
�@�É����ł͗��t�̓�������e�Z���ʐڂ�앶�A�������A���Z�����Ȃǂ�g�ݍ��킹�đI�l����u�O���I���v���w�Z�̔��f�Ŏ��{�ł���悤�ɂ���B�O���I���ł͊w��̘g����蕥���A�����S�悩��ǂ̍��Z�ɂ��u��ł���悤�ɂ����B�V���x��������̗��R�͐��ѕ]���̕��@�̕ω��������B���w�Z�ł͍��N�x���琶�k�̐��т����Ȃ��Ƃɐ�Ε]���ŕ\�����ƂɂȂ�A����������Ε]���ɕς��B
�@�]���̑��Ε]���ł͂T�i�K�̏ꍇ�A�w�N�̒��̏��ʂ����Ƃɐ��т��u�T�v�u�S�v�Ȃǂƕ\����邪�A��Ε]���͖ڕW��B���������ǂ����ŕ]�����邽�߁A�ɒ[�ȏꍇ�͑S�����u�T�v�Ƃ������Ƃ�����B
�@�É������ύ��Z����ۂ̊�閾�w���厖�́u����������Ε]���ɂȂ�ƁA�i�w�Z�̐��E���w�̎u��҂͂T���Ȃ��w�I�[���T�x����łقƂ�Ǎ����Ȃ��Ȃ鋰�ꂪ����B�w����ł͑̈��ƒ�ȂȂǂ̐��т̍����{�[�_�[���C���̍��ۂ����߂邱�ƂɂȂ�x�Ƃ����s�������Z���ɂ������v�Ɛ�������B
���Ɨ��[�t�@�������唭�\��ɁA���ȏȂ�������ɗv��
�����V��
�@������w�����w�����ނ������i�҂̔[�t�������Ɨ���{�ݔ��Ԋ҂��Ȃ����ŁA�����Ȋw�Ȃ͂R���J�������N�x�̑�w�����Ɋւ���W�҂̘A�����c��Ŏ�����ɑ��A���w���ȊO�̔[�t������������̍��i���\�O�ɔ[�t�����Ȃ��悤�v�������B�O�[�������ꍇ�͕Ԋ҂���悤���߂Ă���B
�@���c��ł͓��ȒS���҂��A�P�X�V�T�N�ɏo����Ă��铯�l�̒ʒm��ǂݏグ�A�u��w�̎��Ƃ��Ȃ��҂�����Ɨ����A�{�ݐݔ��𗘗p���Ȃ��҂���{�ݔ�����邱�Ƃ͍����̔[�����Ȃ��v�Ƌ����B�u��������w�̌�����������̍��i���\���ȍ~�ɔ[��������ԊҊ�����݂��邱�Ƃ��]�܂����v�Əq�ׂ��B��W�v���ł��A��������̍��i���\�O�Ɏ��Ɨ������A�u����̂�������킸�Ԋ҂��Ȃ��v�Ȃǂƕ\�����Ȃ��悤���߂��B
��Ε]���@���s�Ă�
�i�����V���@�U���R���j
�@�u����Ȃ��̂��������l�Ԃ̊炪�������v�Ǝv�����B�������琭�������쐬������Ε]���̂��߂̎Q�l�����̂��Ƃł���B
�@�S�����珬���w�Z�̐��т̕]�����@���A�ق��̎q���Ɣ�r���ĕ]�����鑊�Ε]������A�w�K�̓��B�x�����ĕ]�������Ε]���ɕς�����B�ʒm�\������\���܂őS���ς�邩��w�Z�̍����͕K���B�����Łu����������ǂ����v�Ƌ�̗���������̂����̎����������B
�@���w�Z�̂��鋳�Ȃł́A���Ƃ��ƂɈ�l��l�̎q�����u�S�E�ӗ~�E�ԓx�v�u�v�l�E���f�v�u�m���E�����v�̎O�̊ϓ_����]������B�e�ϓ_�͂���ɎO�ɍו�����Ă��邩��A���k�P�l������X���ځB���ꂼ��u�\�������v�u�����ނ˖����v�u�w�͂�v����v�̂R�i�K�̐��т�����B���ۂɂ͎��Ƃ̓��e�ɉ����ĂP�l�R�`�S���ڒ��x�ɍi��Ƃ������A����ł��S�O�l�̃N���X�Ȃ�P���Ԏ��Ƃ��邲�ƂɂP�Q�O�`�P�U�O���ڂ̕]�����K�v�ɂȂ�B
�@�u����Ȃ��Ƃł���킯�Ȃ�����A�����݂͂�ȓK���ɂ�邳�v�ƁA�m�l�̒��w���t�B�@
���������������鍑�B�]�����ӂ�����錻��B����E�Œ��N�����Ă������s���A�܂��J��Ԃ����B
�֘A�L��
�w�͐�Ε]���@��������`�̕ϊv���K�v��
�i�ǔ��V���@�U���P�P���j
�@�_���͂悭�Ă��A���z�ʂ�ɂ������ǂ����A�s�����������Ȃ��B
�@�S���̏����w�Z�ɁA���N�x�����Ε]�����������ꂽ�B���k�̊w�K���B�x�Ŋw�͂�]������V�X�e�����B���ȏȂ��w�K�w���v�^�L���ɍۂ��A�W�c�̒��̏��ʂɊ�Â����Ε]�������ւ���悤�ʒm�����B
�@���Ε]���ɂ́A�S�̂̃��x����������ΐ��k��w�͂��Ă����т͏オ��Ȃ��Ȃǂ̖�肪�w�E����Ă����B��Ε]�����ƏW�c���x���ɊW�Ȃ��A�e���k�̒B���x�����邱�Ƃ��ł���Ƃ����B
�@�������A���Z�����Œ��w���獂�Z�ɒ�o����钲����(���\��)�܂ŁA��Ε]���ŋL����邱�Ƃɂ́A���Z����ی�҂Ɍ��O�������B
�@��Ε]���͌X�̒��w���t�̔���ɂ��邽�߁A�q�ϓI�ȕ]�����Ȃ���Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ̕s�M�������邩�炾�B
�@���������傫�Ȕ�d���߂�������Z�����ł́A�����s��{�錧�����N�x�����Ő�Ε]�����������A���挧������ޗ��Ƃ��Ȃ����Ƃ����߂�ȂǁA�n�����ς̑Ή��͓���Ă���B
�@�����������w���Z����́A���E�����ł͒�����������ޗ��Ƃ͂����A�Ǝ��ɋ��ʎ������s�����Ƃ�ł��o�����B
�@���E�����̓y�[�p�[�e�X�g�ł͑���Ȃ��A���k�̑��l�Ȕ\�͂�������̂��B�����A������Ƃ����āA�w�͕]���������܂��ɂ͂ł��Ȃ��Ƃ��邱�Ƃ��낤�B
�@��Ε]��������ȏ�A���������s������|������g�݂��s�����B���w���t�Ԃ̕]���̂�����Ȃ����w�͂����߂���B��l�̋��t�ɔC������ɂ��Ȃ��`�F�b�N�̐����K�v���B
�@��̓I�Ȋw�͕]���̎d�g�݂Ƃ��ẮA�n�悲�Ƃ̊w�̓e�X�g�����{���邱�Ƃ��l���Ă��悢�̂ł͂Ȃ����B�C�M���X�ł́A���ׂĂ̐��k��ΏۂƂ���S����ăe�X�g���s���Ă�����B
�@��Q�ƂȂ�̂́A�K���Ȋw�͕]�����A�u���ʁE�I�ʂɂȂ���v�Ƃ��āA�������悤�Ƃ���X�����A���w���t�̈ꕔ�ɈˑR�Ƃ��Ă��邱�Ƃ��B
�@���Ƃ̐i�ߕ��ɂ́A���t�̓Ǝ������������҂����B�������A���̐��ʂ̔���ɂ͂�͂�A���ʐ��A���ꐫ�����߂���B��b�I�Ȋw�͂��ǂ��܂Ŕ�����Ă��邩�����邽�߂ɁA�q�ϓI�ȕ�������ݒ肷�邱�Ƃ́A����̍������B
�@�w�͕]���͓K�����s���A���k��l�ЂƂ�̓K������܂��������āA���۔��肷��B���ꂪ�����̌��_�ł���B
�@�����ɗ����߂�ɂ́A�w�͕]���������܂��ɂ��邱�Ƃ����k�̌����d�ɂȂ�Ƃ����A���t�́g��������`�h�̕ϊv���K�v�ƂȂ�B
���������E���ʎ����@�s���ς͔��̌���
�i�ǔ��V���@�U���P�R���j
�@�s���̑S�������Z���������铌���������w�����w�Z����A�������̐��E�����ɑ�������H���狤�ʎ����̓������������Ă�����ŁA�����s����ψ���͂P�R���A���̌������܂Ƃ߁A������ɓ`�����B
�@���w�̒������̊w�͕]�������Ε]�������Ε]���ɕύX�ƂȂ������Ƃɂ��āA�s���ς́u��Ε]���́A���k�̊w�K�ӗ~�����߁A�w���̉��P�A�[���ɂȂ���v�Ƌ����B���ʎ����́A�q�P�r��Ε]���̈Ӌ`��ے肵���˂Ȃ��q�Q�r�������������܂萶�k��ی�҂�����������q�R�r�s���╔�������܂ߒ��w�R�N�̊w�K�ɑ傫�ȉe����^����\�\�Ƃ��Ă���B
�@���ʎ����������ẮA�s���̌������w�̍Z����őg�D����s���w�Z������挎���A����\�������B
�֘A�L��
���ʃe�X�g�@�s����ψ�����Ε\��
�i�����V���@�U���P�S���j
�@�����������w�����w�Z������������E�����̎����ɂ��邽�ߎ��{�\��́u���ʃe�X�g�v�ɂ��āA�����s���ς��u���v��\�������̂ɑ��A������͂P�R���A�u��Ε]����ے肵����A���l�����߂���̂ł͂Ȃ��v�Ƃ̔��_�̃R�����g���o�����B
�@���w����́u��Ε]���ɂ�钲���������ł́A��������ɕK�v�Ȋw�͕]�����\���łȂ����߁A�⊮����f�[�^�Ƃ��ċ��ʃe�X�g���K�v���v�Ɛ����B�s���ς����Η��R�ɋ������u�������������܂�v�Ƃ̎w�E�ɂ��ẮA�u���ʃe�X�g�����Ȃ���A�Ǝ҃e�X�g�Ɉˑ�����ȂǁA�������đ��������N����v�Ƃ��Ă���B
����͒�x���@�đ傪�w���𗬂�ۗ�
�i�ǔ��V���@�U���P�P���j
�@���s�傪�A�T�N�O�Ɋw���𗬋�������ăJ���t�H���j�A�傩��u�������̃��x�����Ⴂ�v�ȂǂƁA����X�V��ۗ�����Ă��邱�Ƃ��P�O���A�킩�����B
�@������͗���w���疈�N�e�U�l�𑊌݂ɂP�N�ԗ��w��������́B�J�吶�́A���吶�ƈꏏ�Ɏ�u����w�����w���A�p��v���O������I���ł��邪�A���̂������{���w����j�Ȃǖ�Q�O�Ȗڂ��w�ԉp��v���O�����́A����A�������ς��Ȗڂ�����A�u���e�ɐ[�݂��Ȃ��v�u��ѐ����Ȃ��v�ȂǂƔᔻ�����o�B���N�ŋA������w��������A�J��͍ŏ��̍X�V�����������N�R����O�ɁA���呤�Ɂu�X�V���Ȃ��v�Ɠ`�����B���呤�́A�v���O�����̌������Ȃǂ̉��P��B�J�呤�́A���吶�����ꂽ���̂́A���呤�̉��P�����͂���܂ł͍X�V��ۗ����A���Z���̋���h�����T����[�u��������B
���J�͎����
�l�J����U���@���s������\���i�U���X���j
�O�N��P�Q�D�X���̑����B��s���̎Q���Ґ��͑O�N��P�S�D�O�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�Q�N�@�@�@�@�O�P�N�@�@�@�@�O�O�N
�j�q�@�S�ȁ@�@�S�R�W�V�@�@�@�@�R�W�V�U�@�@�@�@�S�O�V�T�@
�@�@�@�@�Q�ȁ@�@�@�R�X�P�@�@�@�@�@�R�W�R�@�@�@�@�@�S�S�V
���q�@�S�ȁ@�@�R�Q�R�W�@�@�@�@�Q�U�R�Q�@�@�@�@�Q�U�X�S
�@�@�@�@�Q�ȁ@�@�@�W�U�X�@�@�@�@�@�X�V�W�@�@�@�@�P�P�T�X
���v�@�@�@�@�@
�W�W�W�T�@�@�@�@�V�W�U�X�@�@�@�@�W�R�V�T
��s���͎��S���@���ꍇ���i�S���Q�P���j
�O�N��Q�U�D�P���̑����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�Q�N�@�@�@�@�O�P�N�@�@�@�@�O�O�N
�j�q�@�S�ȁ@�@�Q�U�T�W�@�@�@�@�Q�Q�O�U�@�@�@�@�P�W�S�S
�@�@�@�@�Q�ȁ@�@�@�S�R�Q�@�@�@�@�@�S�Q�Q�@�@�@�@�@�S�P�V
���q�@�S�ȁ@�@�Q�Q�Q�W�@�@�@�@�P�S�Q�O�@�@�@�@�P�R�S�U
�@�@�@�@�Q�ȁ@�@�P�P�X�T�@�@�@�@�P�P�P�T�@�@�@�@�P�Q�P�S
���v�@�@�@�@�@
�U�T�P�R�@�@�@�@�T�P�U�R�@�@�@�@�S�W�Q�P
����s���͎��A�l�J��˂Ƃ��ɑ�P��ڂ̌��J�͎��ŎQ���҂�啝�ɑ��₷�B�Q�O�O�Q�N���͍��t�̓����ł̎����ɂ͌��т��Ȃ��������A���ۂɊw�Z�T�T�����A�V�w�K�w���v�̂����{����A���̓��e�̔����ɕs���������A�m�ɒʂ킹��ی�҂������Ă���̂��Q���ґ��ɂȂ����Ă�����̂Ǝv����B�������A���̑��������w�����̑����ɒ��ڌ��т����́A��������܂߂����w�̍���̑Ή��ɂ������Ă���B��
���̑�
�o�����@�O�P�N�͉ߋ��Œ�P�D�R�R�@�������͑���
�i�����V���@�U���V���j
�@�P�l�̏��������U�ɏo�Y����q�ǂ��̐��̕��ς��������v����o�������A�O�P�N�͂P�D�R�R�Ɛ��Œ���L�^�������Ƃ��A�����J���Ȃ��V�����\�����l�����ԓ��v�̊T���ł킩�����B�V���I�ɂ��₩�����Ƃ݂��錋���̑����ŁA�������͑O�N��葝�������A���܂ꂽ�q�ǂ��̐��͓��v���c���Ă���P�W�X�X�N�ȗ��A�Œ�ɂȂ����B
�@��N�̏o�����́A�O�N���P���X�W�W�Q�l�����P�P�V���U�U�T�l�B��e�̔N��ʂł݂�ƁA�Q�O�Α�łQ���T�P�O�R�l�������Ă���A�Ƃ�킯�Q�O�Α�㔼�ł̌������ڗ������B�o�����ł݂�ƁA�ł����������̂͂R�O�Α�O���B�ŏ��̎q�ǂ����o�Y���镽�ϔN��͂Q�W�D�Q�ƑO�N���O�D�Q�Ώ㏸���A�o�Y�N��x���Ȃ�u�ӎY���v�̌X���������Ă���B
�@�o�����́A���N�P���Ɍ��\���ꂽ�������v�i���ʐ��v�j�̂P�D�R�S��������Ă���A�}���ȏ��q���𗠕t���錋�ʂƂȂ����B�Ƃ�킯��s���⋞��_�n��ŒႢ�X���������Ă���B�ł��Ⴉ�����͓̂����s�̂P�D�O�O�B�t�ɁA�o�������ł����������͉̂��ꌧ�i�P�D�W�R�j�A�����ō��ꌧ�i�P�D�U�Q�j�������B
��e�@�s���������Z�u���E�������ꎎ���v�̎�̖��@�i�f�r���j
�@�T���Q�P���̒����V���̈�ʂɁu���������E�ɓ��ꎎ���v�Ƃ����L�����f�ڂ��ꂽ�B�u�����P�V�O�Z�̑唼�ŁA���H������{�v�u���w���Ȑ�Ε]���E�������ɕs�M���v�Ƃ����T�u�^�C�g���⒆���o��������ꂽ��ʃg�b�v�̑傫�ȋL���������B�����͂��Ă������A�L����ǂ�Ŋ��������ƂƂ������̖����܂Ƃ߂Ă݂��B
�@ ���E�����̖ړI�́A ���u�]�œ��w����]������ɑ��A�e���Z���p�ӂ��Ă��鋳����e�⋳��ڕW�Ɍ��������鐶�k��I�����邱�Ƃɂ���B�I�����邩��ɂ́A�I���������ʓI�ɋ@�\�����邽�߂ɁA�q�ϐ��̂���u���̂����v�����߂���͓̂��R�ł��낤���A����̂悤�ȋ�̓I�ȕ������������̂��K�R�̐���s���Ƃ��l������B�����Ƃ���ɂ��A�����I����S�����ꂩ��̋����v�]�i�u���Z���������������ψ���v�̓��\�ɉ����Ă̎��{�Ƃ����j�ɂ���đł��o���ꂽ�Ƃ����B�������A���݂̓����S�̂������Ƃ��A�u���ꎎ���̎��{�v�ɂ́A������_������A���Ƃ̉^�т͂���ȂɒP���ł͂Ȃ��悤�Ɏv����B�ǂ��ɗ����������͕ʂɂ��āA���{�ɂ��Ă̊���̖��_�ɂӂ�Ă݂�B
�u���ꎎ���v�̎��{�́A�傫���͎��̓�_���ړI�ł��낤�B
��́A�P�T�N�x�������瓱�������u��Ε]���v�Ɋ�Â����\�_�ւ̑Ή��ł��낤�B�܂�A�u���Ε]���v����u��Ε]���v�Ɉڍs���钆�w�Z����̓��\�_���`�F�b�N����@�\���������邱�Ƃł���B�u��Ε]���v�ւ̈ڍs�̖�肪�A�u���E�����ł͊w�͎������s��Ȃ��v�Ƃ����\�����킹�����Ă��铌���̊e���w�ɂƂ��āA�u�w�͓͂��\�_�Ō���v�Ƃ����I���̊�{���h�炮���Ƃւ̕s�������܂�Ă����B���̕s���ɑ��A������������͑�𑣂���Ă����B
��ɂ́A�����u���̍��܂�̒��ŁA���w�������Ŏ��g�ރC���F���g��V���ɐ݂��邱�ƂŁA���w�ւ̊S�����߂邫�����������A���w�u�]�̐��k�𑝂₷���Ƃł���B���̂��߂ɓ����̎��w�͋ߔN�A�V�������g�݂������낢�낵�Ă��Ă���B�r�܃T���V���C���Ⓦ�����ۃt�H�[�����ł̋����Ấu���w�t�F�A�v�B���邢�͉����S�Z�̃z�[���y�[�W�̗����グ�B�����Ďx���ł�������C�ӂł������肷�邪�A���ꂼ��ɎQ���Z���W���u�����������k��v�̎��{�̑����A���X�B
��L�̓�̖ړI�ɒʒꂷ����̂́A��̌����Ȃ��o�ϕs���Ƌ}���ȏ��q���̒��ŁA�������Z�̕�W�������������ɒ��ʂ��Ă��邱�Ƃɂ���B�Ǝ��̋����W�J���邱�ƂŎ��т������A���ʂ��o�����Ƃ���̐��ʂ�搂��Ă�����i���w�̎��g�݂̑������A�ߔN�̓s�����Z�̍ĕ҂Ɖ��v�E���P�̃v���O�����̒��ɁA���ʂ�������荞�܂�Ă���B�����u���̍��܂�̌����́A���Ɨ��̊i������ł͂Ȃ��A������e�ɂ����Ă����l�ȃj�[�Y�i�i�w���т���s�o�Z�܂Łj�ɉ�����ƂƂ��ɁA���������ɑ��������F������e�Z�ɋ`���t���A���̓��F��ϋɓI�ɑł��o�����Ƃʼn��v�C���[�W���s�����Ă���Ƃ���ɂ�����B����Γs���Z���g�̐����c������������g�݂Ƃ��āA���܂łɂȂ��V�����ǖʂ��}���Ă���B�����������Ŋe�������Z�́A���w���k�̎����̈ێ��ɐ_�o���点����Ȃ��B�������A����͐��E�����̔�d�������A�P�R�N�x�����ł͍��Z����̕�W�͂Q�S�P�Z���A���E���������{���Ă���w�Z���P�V�Q�Z�B���w�҂͑S�̂̂قڔ����ɋ߂��S�V�E�W�����߂Ă���B�����āA��ʓ������܂߂Ă����q�Z�𒆐S�ɑ������̒������̏�����B
�ȏ�A�u���E���ꎎ���v��K�v�Ƃ��鎄�w���̏�w�i���q�ׂĂ����B�������{�������̏ɂ����Ă݂�ƁA�ʂ����Ď������\�ł��낤���Ƃ����^�����������Ȃ��B���{�̎����E���@�E�����E�^�p�Ƃ�������A�̗���̂̂Ȃ��ŁA���ꂼ��ɂ�����肠���Ȃ���̍���Ȗ�肪����l�����邩��ł���B
���w�u�]�̎�����荞�ރC�x���g�ɂ��邱�Ǝ��̂��A���z�͂����̂����A���E��u�]�Z�̌��莞���𑁂߂邱�Ƃ��l����ƁA���ꂾ���̋z���͂����܂��̂��Ƃ����뜜������B���̎��w�̂ǂ��ɂ���ȃG�l���M�[������̂��B�܂��A���{���邱�ƈȏ�ɖ��Ȃ̂́A���̃e�X�g�̉^�p�ł��낤�B��������W�ɂ��鎄�w���A�ȉ��ɂ�����悤�Ȗ��_���N�����[���Č������w�Z�̐i�H�w���Ɛ��������Ă����͂��{���ɂ��邩�Ƃ������Ƃł���B�[�I�Ɍ����A�u��Ε]���̓��\�v���������Z���ł́u�M�����͏\������v�Ǝ����\�����Ă���̂ɑ��A���w���́u����e�X�g�v�̎��{�E���p�́A�������w�Z�̍쐬����u��Ε]���v��F�߂Ȃ��Ɛ錾���邱�Ƃ��Ӗ�����B���k�m�ۂ̂��߂̍L���������ɂ��̂�����鎄�w���������A���̑����̎��w���A�l�̒B���x���݂�u��Ε]�v��F�߂邩�A�V�����n�[�h����݂���u����e�X�g�v���Ƃ邩�A���邢�͑�O�̓���T�邩�A�Ƃ������W�����}�ɗ�������邱�Ƃ͕K��ł��낤�B
�ȉ��Ɂu���E���ꎎ���̎��{�v�ɔ�����̓I�ȓW�J�ɑ����āA���ɂȂ肻���Ȃ��Ƃ��v�����܂܂ɕ��ׂĂ݂��B�i���͑��݂Ɋ֘A���Ă���A�J��Ԃ��������Ȃ邱�Ƃ����e�͊肢�����B�j
�P�D���{�̎���
�����̈Ăł͂P�P�����{�ł��������A�x�����Č����I�ł͂Ȃ��Ƃً̈c���o�ĂP�O�����{�ɂȂ����Ƃ����B�m���ɁA���������{���A�̓_�ƃf�[�^�������l����A�P�P�����{�ł͎g���������肳��Ă��܂��B�f�[�^�쐬�ɂ͍Œ�Q�O���ʂ͂�����ł��낤�B�e���w�̎��Ƃ́u�ʑ��k�v�̎����A�P�Q���P�T�����ւ́u�������k�v�Ȃǂɂǂ��Ή������邩�B
�Q�D�������E�e�Z�ł̎��{�Ƃ̂���
��L�P�̎��{�����Ƃ��֘A���邪�A�u�]�Z�ł̎Ƃ������ƂɂȂ�ƂP�O���A�P�P�����{�̂ǂ���ɂ��Ă�����܂łɎu�]�Z�����܂��Ă��Ȃ����k�ւ̑Ή����ǂ����ׂ����B�܂��A�u�]�Z�̌���𑁂߂�������A�\���I�Ȏ𑣂��悤�ȃP�[�X���o�邱�Ƃ��l������B���̍ۂɕK���o�Ă���g�c����h�Ƃ̔ᔻ�ɂǂ��Ώ�����̂��B
�܂��A�����i�K�ł̎u�]�Z�ł̎��{�������ւ̃��`�x�[�V���������߂�ꍇ�͗ǂ����A�Ґ��̑��ǂŋt���ʂ̋�͂Ȃ����B
�R�D���쐬�B
���ꎎ���̖��̓��e�����x�����ǂ��ɂ������B�e�Z�ōs�����ʓ����́A�e�w�Z�����ꂼ�ꋁ�߂鐶�k�̃��x���ɉ����Ė����쐬���邱�Ƃɂ�莎�������藧���Ă���B���ꎎ���̃��x���ݒ���ǂ�����̂��B�e�w�Z�̋��߂郌�x��������e�ɂǂ����f������̂��B���̓��e�������ł́A�Q�����Ȃ��w�Z���o�Ă���̂ł͂Ȃ����B�܂��A���u�]�D���Ő��k���W�߂Ă���w�Z����������ł́A�����̓��e����ł͊w�͒ቺ�������v���ɂȂ�\��������̂ł͂Ȃ����B
�S�D�����̍̓_�ƃf�[�^�쐬
�����̌��ʂ��҂ɕԋp����܂łɁA�̓_�����Z���S�����A���Z�œƎ��Ȕ���ޗ��ɂ��邱�Ƃ͉\�ł��邪�A���̌�̎u�]�Z�ύX�ւ̑Ή����K�v�ł��낤�B���̂��߂̑S�̂̒��ł̃��x���Ƃ������N�Ƃ��̃f�[�^�������ǂ�����̂��B�\�ł͂���Ǝ҂Ɋۓ����Ƃ����b������悤�����A���̕ӂ̌������Ɛv�������ǂ�����̂��B�@
�T�D�����̌��ʂ��ǂ����p����̂�
��Ԃɍl������̂͐��E�����{�Ԃł̓��\�_�Ƃ̔�r�����Ƃ��Ă̊��p�ł��낤�B�������A�����́A�P�Q���P�T���ȍ~�̒��w�Z�̐i�H�S�����t�Ɓu�������k�v�ł̎����Ƃ��Ă̊��p�̗L��������B���l�Ǖ��̘_�����猩��Ζ�莋�����ł��낤���A�֗��Ȏ����i����j������Ύg����\������ł���B�ŋ߁A��ʎ��w�̓����ɑR���Ď��{����w�Z�������Ă���u�ʑ��k�v�̎����Ƃ��Ă̊��p�i���ꂱ�����g�����Ƃ��Ă͖{���ł͂Ȃ����j���l������B
�U�D�@���w�Z�i�H�S�������Ƃ́u�������k�v�Ǝ��E�ی�҂Ƃ́u�ʑ��k�v
�O�q�����悤�Ɂu�ʑ��k�v���������w�Z�������Ȃ��Ă��Ă��钆�ŁA���w�Z�Ƃ́u�������k�v�Ƃ̌��ˍ������ǂ�����̂��B
�V�D�����{�Ԃł̈���
���\�_�ɕς����̂Ƃ��Ă̈ʒu�Â����ł���̂��B����ł��u���E�����v���{�Z�̂S������W����ɖ����Ȃ����ŁA�L���Ȋ��p���\�Ȃ̂��B�������Ď҂����炷���ʂ��������˂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
����ɁA���ꎎ�������ĂȂ����k�͐��E���i��r�����Ă��܂��̂��B�ƂȂ�Ǝu�]�Z����͒x�����A�m���ɓ��w�u�]�������k���݂��݂��������ƂɂȂ�Ȃ����B
���̑��D��������̎�]�҂̖����ǂ�����̂��B
�W�D���̑�
���́u���E�������ꎎ���v�����{���ꂽ�ꍇ�ɁA�w�Z�̃����N�t���ɐV���Ȏ����ɂȂ�̂ł͂Ȃ����B�e�Z�Ƃ����i�̖ڈ��ƂȂ�A���т̃����N���A���_�ɂ���A���l�ɂ���A���炩�̌`�Ō��\���Ȃ���Ύu�]�҂̖ڂ����Z�Ɍ��������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̏�A���N����͉��e�X�g�Ǝ҂̑��͎����s����悤�ɂȂ�B���ꂪ���w�̐��E�����̕��͋C��グ�邱�ƂɂȂ���ł��낤���B�ǂ������n�̌��łȂȂ����B����A���w���̂�������\���̕��������̂ł͂Ȃ����B����Ȋ낤����������͎̂������ł��낤���B
�����x�ꂽ���A���́u���E�������ꎎ���v���̂��̂ɑ��铌���s���w�Z����i�T���R�O���̓ǔ��V���ɂ��Ɣ���\���j�A�s�̊w�����A���邢�͋��璡�E����ψ���Ƃ�������������̒����┽���A�傫���e����^����ł��낤�B���₻��ȏ�ɑ傫�Ȃ��̂Ƃ��āA�Ό��s�m���̑����I�Ȕ����̕�������I�ȗv���ɂȂ邾�낤�B�i�O�Q�N�U���U���j
����聄
�@�Q�ȏ�̐����̒��ŁA�P�Ƃ��̐����g�ł��������Ȃ�����f���Ƃ����܂��B�Ⴆ�A�Q�A�R�A�T�͑f���ŁA�S�͑f���ł͂���܂���B
�@�f����������̂Ɏ��̂悤�ȕ��@������܂��B
�@�@�@�@�i�菇�P�j�@�Q����n�߂āA����ɑ������������Ԃɏ����B
�@�@�@�@�i�菇�Q�j�@�Q���c���A�c��̂Q�̔{���������Ă����B
�@�@�@�@�i�菇�R�j�@�R���c���A�c��̂R�̔{���������Ă����B
�@�@�@�@�i�菇�S�j�@�T���c���A�c��̂T�̔{���������Ă����B
�@�@�@�@�i�菇�T�j�@�V���c���A�c��̂V�̔{���������Ă����B
�@�@�@�@�i�菇�U�j�@�P�P���c���A�c��̂P�P�̔{���������Ă����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F
�@���̎菇���J��Ԃ��Ă����ƁA�f�������������ꂸ�Ɏc��܂��B
�@���́u�Q�`�X�T�v�̕\���g���Ȃ���A���́i�P�j�`�i�R�j�̖₢�ɓ����Ȃ����B
�i�P�j�@�Q�ȏ�Q�O�ȉ��̐����̒��ɂ���f���̘a�����߂Ȃ����B
�i�Q�j�@�Q�ȏ�X�T�ȉ��̐����̒��ɂ���f���͑S���ʼn�����܂����B
�i�R�j�@�����Q�ł���悤�ȂQ�̑f����o�q�f���Ƃ����܂��B�Ⴆ�A�R�ƂT�A�T�ƂV�Ȃǂ͑o�q�f���ł��B�Q�ȏ�X�T�ȉ��̐����̑g�̒��őo�q�f���͑S���ʼn��g����܂����B
| �Q | �R | �S | �T | �U | �V | �W | �X | �P�O | |
| �P�P | �P�Q | �P�R | �P�S | �P�T | �P�U | �P�V | �P�W | �P�X | �Q�O |
| �Q�P | �Q�Q | �Q�R | �Q�S | �Q�T | �Q�U | �Q�V | �Q�W | �Q�X | �R�O |
| �R�P | �R�Q | �R�R | �R�S | �R�T | �R�U | �R�V | �R�W | �R�X | �S�O |
| �S�P | �S�Q | �S�R | �S�S | �S�T | �S�U | �S�V | �S�W | �S�X | �T�O |
| �T�P | �T�Q | �T�R | �T�S | �T�T | �T�U | �T�V | �T�W | �T�X | �U�O |
| �U�P | �U�Q | �U�R | �U�S | �U�T | �U�U | �U�V | �U�W | �U�X | �V�O |
| �V�P | �V�Q | �V�R | �V�S | �V�T | �V�U | �V�V | �V�W | �V�X | �W�O |
| �W�P | �W�Q | �W�R | �W�S | �W�T | �W�U | �W�V | �W�W | �W�X | �X�O |
| �X�P | �X�Q | �X�R | �X�S | �X�T |
�i�O�Q�N���j
�������ɒ����S�S���
����聄
�@�}�̎l�p�`�`�a�b�c�̖ʐς͂�����ł����B�������A�_�`�͔��a�Qcm�̉~�̒��S�ŁA�a�C�b�C�c�͂��̉~�̎���ɂ���܂��B�i�O�Q�N���厛�w���j
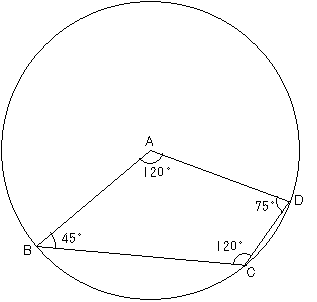
����
�@���̐}�̂悤�ɁA�l�p�`�`�a�b�c��Ίp���`�b�ŁA�O�p�`�`�a�b�ƎO�p�`�`�b�c�ɕ����܂��B
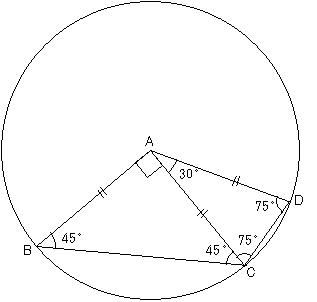
�O�p�`�`�a�b�͒��p�ӎO�p�`�Ȃ̂ŁA�ʐς́@�Q�~�Q���Q���Q�i㎠�j�ł��B
�܂��A�O�p�`�`�b�c�͒��p�R�O�x�̓ӎO�p�`�Ȃ̂ŁA�`�b���ӂƂ����Ƃ��̍����c�g�͂Pcm�ł��B
����́A�O�p�`�`�g�c�����O�p�`�̔����ł��邱�Ƃ���킩��܂��B
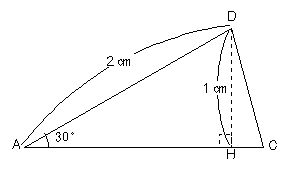
�O�p�`�`�b�c�̖ʐς́@�Q�~�P���Q���P�i㎠�j�ł��B
������A�l�p�`�`�a�b�c�̖ʐς́A�@�Q�{�P���R�i㎠�j�ƂȂ�܂��B