

�m�n�D�Q�X�S

�Q�O�O�W�N�P�Q���P�T���@
�A�N�Z�X������Z���^�[
�ڎ�
|
�w�Z��� |
���J�͎���� | ������ | ������ | ���̑� |
|
�˕����w�Z
�@ |
���\���͎�12�� | �������Z���� | ���ې��w�E���ȋ��瓮������ | �����E�����E���� |
�w�Z���
�˕����w�Z�@���w���R����
�D�G��i�ɃA�N�Z�X����̐i�w�҂S�l�̍�i���I���B
���܁@���Q�@�m�N�@���w�@�@�@�@�@�@�o�q�f���̌���
��܁@���R�@�n�N�@�|�p�E���y�@�@��ȁu�X�E�K�N�@�`�~�̊w�Z�ł̂P���`�v
�W���@���P�@�s �N�@�ƒ�@�@�@�@�@ �I�����c�̌���
�W���@���P�@�s
�N�@�|�p�E�Z�p�@�@�싅�̃s�b�`���O�}�V���ɂ���
���Q�ŋ��܂ɑI�ꂽ�m�N�͂Q�N�A���̋���܁B
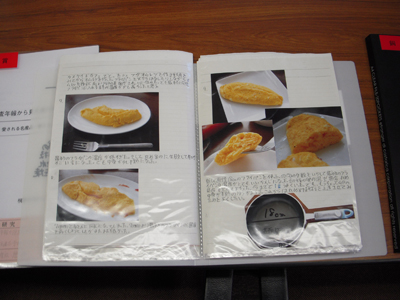 �@�I�����c�̌���
�@�I�����c�̌���
 �@�싅�̃s�b�`���O�}�V���@
�@�싅�̃s�b�`���O�}�V���@
��ȑ����@�w�Z�������i�O�W�N�P�P���Q�T���j
�@�P�P���Q�T���ɓ��Z�Ő�������{���ꂽ�B��ȑ������w�Z�͑����L�����p�X���o���Ă��獡�N�łQ�O�N�ɂȂ�B�P�X�X�S�N�ɒ��w�Z���J�Z���A���݂ł͍��Z��W�Ȃ��̊��S������эZ�A�܂������Z�ł͂Ȃ���w�ɒ����Ȏ��т��݂���i�w�Z�Ƃ��ĕ]���������B���K�͍Z�i��N�x���Ɛ����P�P�T���A���N�x�ȍ~�͖�P�U�O���j�Ȃ̂ō��i�Ґ��͖ڗ����Ȃ����A�������{���c��q�{GMARCH���i�w�҃x�[�X�Ŗ�W�O���ȂǁA�w�Z���悭�m��ی�҂قǐl�C�������w�Z�ł���B
�@��ȑ����͍��N�x��������������P���E�Q���E�S���̂R��ɕύX����B�i��N�͂P���E�Q���E�R���j���������͏��T�ΏۂƂ������ƂŁA����ɂ��Ă̌��y�͂Ȃ��������A���̕ύX�̓T���f�[�V���b�N����݂̂��̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�R���ԑ�������P���������ق������ׂĂ̓������������ɂƂ��Ď₷���i�R���ɉ������Z���₷���j�Ƃ������f�̂悤�ł���B�S���������n��̓������{�Z�����Ȃ��Ƃ����̂��ύX�̑_���ł��낤���A���ۂɎ����҂��ǂ̈ʏW�܂邩������S���̓����������蒅���邩�ǂ����̔��f�ɂȂ邾�낤�B
�P�j�@����Z��
�@��ȑ������w�͓������N���A���ĒB�����������ē��w���Ă��鐶�k�̑����u�悢�W�c�v�ł���B�����Ă��̂悢�W�c�ɍ��̎���ɂ����������^���Ă������Ƃ��d�v���ƍl���Ă���B���낢��s�������邪�A�w�Z�ł܂���ԑ厖�Ȃ͎̂��Ƃł���B
�@���ꂩ��Ɍ������Ă����ɂ������āA�e������点������S�Ńv���b�V���[��^�������邱�Ƃ͂�߂����������B�����d�������Ă���Ȃ瑱���Ăق����B�e��������ē����Ă���p���݂Ďq�ǂ��͈�B��Ȃɂ͊w�H������̂ŁA��ɂ��ٓ������Ȃ��Ă��ʂ킹����B��e�������̂����Ĉ�A����͑�Ȃ̐��_�ɂ���v����B
�@���q�Z�ł͏��q���ϋɓI�ɂȂ��B��w�i�w�ł���ȏ��q��Ƃ����ی����g�����k���قƂ�ǂ��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B�`�������W���_�����������k�������B
�Q�j�@��Ր搶�i���Q�w�N��C�j
�@��Ȃ̋���́A�u�������A�Љ�ɍv���ł���i�ʂ��鏗���v��ڎw���Ă���B���ׂ̈ɁA���P�ł͂܂������K���A�w�K�K���̊m����厖�ɂ��Ă���B�u�w�Z�����K�C�_���X�v�Ƃ������q��z��A���̒��Ƀ������Ƃ点�A���������K����g�ɕt��������B����͖Y�ꕨ�����炷���ʂ�����B�܂��A�E�Ƒ̌����s�Ȃ��A���w��ł��邱�Ƃ������Ɍ��т����Ƃ����������Ă���B
�R�j�@���Ȃɂ���
����@����搶
�@����͒��w�R�N�ԁA�T�T���Ԃ��B����T���R���ԁA����U���Q���ԂƂȂ��Ă���B����T�͓lj��ŁA�]�_���̓lj����d�����Ă���B�v�A��҂̌����������Ƃ��Ƃ炦����K���J��Ԃ��B�܂������͍���w�K�̊�ɂȂ���̂Ȃ̂ŁA�����w�K��O�ꂵ�Ă���B���w���Ŋ����Q�����Ƃ鐶�k�������B
����U�͌��t�╶�@�ŁA�܂����㕶�A�����Ē��Q�̌㔼����͌Õ��E�����̎��Ԃɏ[�ĂĂ���B���Z����̌ÓT�ɂ܂œ��ݍ��ށB
�@�Ǐ�������͂̌���ɂȂ���̂��H�Ƃ���������悭��B�m���ɏd�v�����A���R�Ɠǂ�ł��Ă��d�����Ȃ��B�����̓ǂ݂������̂����łȂ��A�搶��F�B�̐��E����{�Ȃǂ��ǂނ��Ƃ��d�v�ł���B
���w�@�|�c�搶
�@���w�Z�̊Ԃ͐��w�������ɂ����Ȃ��Ƃ������ƂɋC��z���Ă���B�Z�������ł����w�����ӂɂȂ鐶�k�͂�������B���̂��߂ɂ͊�{����������g�ɕt�������邱�Ƃ��d�v�ƍl���Ă���B
�@���Ԑ��͐��w�T���R���ԁA���w�U���Q���ԁB���w�T�ł͑㐔�A���w�U�ł͊������B���R�ł͏K�n�x�ʃN���X���T�P��ݒ肵�A�U�N���X�Ґ��Ŏ��Ƃ��s�Ȃ��B�K�n�x�ʃN���X�͊w�����Ƃɓ���ւ����s�Ȃ��B
�p��@�V�c�搶
�@�p��͊�b�w�͂̍\�z���d�v�ƍl���Ă���B���@�A�P��̓O����v�邽�߂ɕ⑫�v�����g�uSuper Input�v�����b�X���O�Ɏ��{����B�܂��A�e�w���V�E�W��{�L���u�����[�R���e�X�g���s�Ȃ��B���O�Ɋo����P������߁A�Q���ԂŃe�X�g����B���Ԃ��Z���̂ł�������o���Ȃ��ƍl���Ă��鎞�Ԃ͂Ȃ��B�����ėD�G�҂�\������B
�@���ȏ��́uNew�@Crown�v�͗ʂ����Ȃ��̂ʼnߋ��̃��b�X������lj���̃v�����g�E�����̐���Ȃǂ��s�Ȃ��Ă���B
�@��K�͒����x�ɂɉ��ʕ�K�𒆂P����s�Ȃ��ƂƂ��ɁA���R����͏�ʕ�K���s���A���x���ɍ��킹���w����S�|���Ă���B������ʕ�K�ɂȂ�Ȃ��悤�ɓ����납��m�[�g��o�⏬�e�X�g�A���ǃ`�F�b�N�Ȃǂ��s���Ă���B
�S�j�@�����������
������̂͂T�N���Ώۂ̂��ߓ����ׂ̍����b�͂Ȃ������̂Ŏ������⑫�B
�Q�O�O�X�N�x�����v��
�@�@�@�@�������@�@�@�@�@�@��W�l��
�P��@�Q���P���i�P���j�@�@�U�O���i�T�O���j
�Q��@�Q���Q���i�Q���j�@�@�T�O���i�T�O���j
�R��@�Q���S���i�R���j�@�@�R�O���i�S�O���j�@�@�@�@�@�@�i�@�j���͍�N����
��
��W�l�������͂P�S�O�������A��N�x�P�U�R���葱���B�������N�P�U�T���O��̓��w�Ґ��ł���A���N�x�����l�B�Q���P���͂P�O�O�����x�̍��i���\���ɂȂ�͗l�B
��N�x�������Z���E����̔z�_���P�O�O�_�A�������Ԃ��T�O���i���N�͂U�O���j�A���ȁE�Љ�̔z�_���U�O�_�i���T�O�_�j�A�������Ԃ��S�O���i���R�O���j�Ǝ���Ђ̔�d�����܂����B�������Ԃ̒Z�k�ƂƂ��ɎZ���͖�肪�Չ����A���i�ҕ��ς͊e��Ƃ��V�T�_�ȏ�ƍ����B�������Ȃ���ҕ��ς͂U�O�_���ƍ������Ă���A���N�������o����j�Ƃ̂��ƁB�܂��A����_�͐ݒ肵�Ȃ��B
�T�j�@���z
�@��ȑ������w�͏��c�}�������̏I�_���ؓc�ɂ���A���K�͂ȍ��Z��W�Ȃ��̊��S������эZ�Ƃ������ƂŁA�u�����������v���͋C�������Ă���w�Z�ł���B���j���w�Z�̂��߁A�ꎞ���w�Z������Ői�w�A�w�K�ʂ��苭���������߂Ɉꕔ�̕��Z���炪��w�Z�̃C���[�W��������Ă��܂��Ă���悤�����A���q�ɂ͂߂��炵���T�b�J�[��������ȂǁA�N���u����������ł���B�����n��⏬�c�}�����ɏZ�ޏ��q�i�w�Z��]�ҁA�܂������Љ�ɏo�Ċ��������q�ɂ͂����߂̊w�Z�ł���B
�@���N����̂S�������͍�N�܂ł̂R�������Ɣ�ׂē���Ȃ�̂��Ղ����Ȃ�̂��A�ǂ݂Â炢�B�P�����Ƃɂ����҂̐����ǂ��ω�����̂��A�܂���W����͌��������̂́A���i�Ґ�����N�̂R�������i�T�R���j�ɔ�ׂĂǂ̒��x�ω�����̂��A�ϓ��v�f�������B�S���͎Z�̋��Ȃ̂ŁA�����ڂ̔{���͍����Ȃ�Ǝv���邪�A�����܂�ɂ���Ă͈ӊO�Ɠ���₷���\��������̂ŁA������߂��Ɏ������B
�i�@�e�D�g���j�@
http://www.otsuma-tama.ed.jp/
���{��w�@�@�R�w�@��w�Ƃ̘A�g�ɂ���
�i�w�Z�z�z�������@�P�P���P�V���j
���{��w�@�́A�I�풼��̂P�X�T�O�N�ɁA�R�w�@���{�ꕪ�Z�i��啔�@�B�ȂƓy�،��z�ȁA������j���p�����Đݗ�����܂����B�܂��A�ݗ��������̈��䐳�j���i����������j�E���[�����h�n�[�J�[���i�R�w�@�鋳�t�j�A��Q��@���������鎁�i��P�O��R�w�@�@���j�A��S��@���֓��E���i�R�w�@�_�w�����Ɓj�ȂǑ吨�̐R�w�@�W�҂��A�n���ȗ��̉��{��w�@�̋����S���Ă��܂����B
���̊W����A�������v���i�O�R�w�@��w�w���j�̑�S��@�l�������A�C�ڂ̌_�@�Ƃ��āA�ߔN�A�R�w�@��w�ƘA�g���Ƃ��s���ȂNj�̓I�Ȍ𗬂�[�߂Ă܂���܂����B����ɂ��̊ԁA���w�Z�E���w�Z�Z���E�@���ƐR�w�@�����Ƃ̊ԂŁA�l�X�ȋ��c���d�˂��A���̂悤�Ȉ��̕�������o���Ŋm�F����Ɏ���܂����B���{��w�@�̋���Ɉ�w�̂������Ƃ��x�������肽���A�F�l���ցA���݂̌��̐i�������m�点�������܂��B
���A���̉��{��w�@�ƐR�w�@�Ƃ̘A�g�E��g�́A�I�A�݂��̊w�Z�@�l�Ƃ��Ă̓Ɨ�����ۂ��Ȃ���̎��Ƃł��邱�Ƃ�\���Y���܂��B
���āA���{��E�O�Y�����̒n�ɃL���X�g���Ɋ�Â�������s���w�����p���ŐV���ɃX�^�[�g�������{��w�@�́A�n���������A���w�Z���獂�Z�܂ōŒ��łP�Q�N�Ԃ̃L���X�g����������H����w�Z�Ƃ��āA���X��q������Ă��܂����B�R�w�@���܂��A�c���N�����獂������܂ŃL���X�g���Ɋ�Â�������s���w�Z�ł��B���̈Ӗ��ŁA���{��w�@�ƐR�w�@�́A���j�I�ɂ������č�����A���������ɋ��痝�O���f���Ă���w�Z�ƌ����܂��B
�������Ȃ���ߔN�A�R�w�@��w�ɂ����ẮA���w�Z�⒆�w�Z����L���X�g��������ē��w����w�����������Ă���A���w�̗��O�E�{���́u�w�炵���v�̊���J������Ă���Ƃ̂��Ƃł��B
�����ʼn��{��w�@�́A��������i���w�E���Z�j�ƍ�������i��w�j�ɂ�����L���X�g������̘A�������������邽�߂ɁA�R�w�@��w�Ƃ̒�g��ϋɓI�ɐ��i���邱�ƂƂ������܂����B����́A��ɏq�ׂ����{��w�@�ƐR�w�@�Ƃ̑n�݈ȗ��̋��͊W�ɂ����̂ł��B
��̓I�ɂ͎��̂悤�Ȓ�g���s�������Ǝv���܂��B
�P�D�Q�O�P�O�N�ɉ��{��w�@�𑲋Ƃ����уR�[�X���i�U�N�Ȃ����P�Q�N�Ԃ̃L���X�g����������ҁj�́A���Z�R�N�Ԃ̕]��l�����ȏ�ł���Ίw���w�Ȃ����炸�R�w�@��w�ɗD��I�ɐi�w���邱�Ƃ��ł���B
�Q�D�܂��A�݊w���ɃL���X�g���̊����𐽎��ɑ������ƔF�߂��鐶�k�ɂ��ẮA�D�����ꂽ�]��l��K�p����B
�R�D�A���A���w�Z�E���w�Z����̓��w���̏��Ȃ��ߓn���i���N�ԁj�ɂ����ẮA���Z����̓��w���ɑ��Ă������[�u��K�p����B
���݁A�R�w�@�ł́u�Q�P���I�̐R�w�@���ڎw�����́`�`���̒��ł̐V���A�R�w�@�̐V���ȏo���`�v�Ɍ����A�A�J�f�~�b�N�E�O�����h�f�U�C�������肵�āA���̋�̉��Ɍ����đS�w�I�Ɏ��g��ł��܂��B���{��w�@�Ƃ̘A�g�ɂ��ẮA�R�w�@�����̋��c���s���Ă���A���{��w�@�ɑ���i�w�g���m�ۂ�������Ō������i�߂��Ă��܂��B�܂�A�Q�O�P�P�N�ȍ~�ɂ����Ă��A�l���g�𑝂₵�Ă��������ŐR�w�@�Ƃ̌���i�߂Ă��܂��B
���N�x����n�܂�������A�g���Ƃɂ��ẮA���ݐi�w�g�̂���w���𒆐S�Ɏ��N�x�ȍ~���p�����čs���܂��B�����āA�ł��d�v�ȏ@�������L���X�g���s���ɂ����鑊�݂̌𗬁A���w�Z�E���w�Z�̋������C�Ȃǂ����s���ĒNjy�������Ǝv���܂��B
����̓I�ɂ�
�W�w���~�T�l�̂S�O���̘g��ݒ�B�]�蕽�ςłS�D�O�B
�݊w���ɐ��̑���{�����e�B�A�����Ȃǂ̃L���X�g�������𑱂������k�͕]�蕽�ςR�D�V�B
���Z����̓��w�҂͑I����炷�̐��k�ƈ�ʃN���X�̐��k�Ŋ�ƂȂ�]�蕽�ς��ς��B
�����Q�̑I���N���X�ݐЂS�W�����P�P�����]�蕽�ςS�ȏ�B�����S�l�͑��̓�֑�w�u�]�A�Q�`�R�l�͐R��w�ɂȂ��ʂ̊w���u�]�B�S�`�T�����ΏۂɂȂ�B
�Q�O�P�O�N�̒��w���w�҂���͂P�S�O���ɘg���L���������悤�B�@
http://www.yokosukagakuin.ac.jp/y-gakuin3C.html
���J�͎����
���\���͎��P�Q���@���i����e�X�g�i�P�P���R�O���j
�O�N��T�D�R���̌����B�j�q�͂U�D�W���̌����A���q�͂R�D�V���̌����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�S�N�@�@�@�@�O�T�N�@�@�@�@�@�O�U�N�@�@�@�@�O�V�N�@�@�@�O�W�N
�j�q�@�S�ȁ@�@�W�P�Q�U�@�@�@�@�V�X�Q�S�@�@�@�@�V�X�Q�T�@�@�@�V�T�S�V�@�@�@�V�O�R�W
�@�@�@�@�Q�ȁ@�@�@�V�S�R�@�@�@�@�@�W�T�U�@�@�@�@�@�X�R�U�@�@�@�@�W�U�Q�@�@�@�@�V�X�W
���q�@�S�ȁ@�@�U�V�T�V�@�@�@�@�U�X�V�V�@�@�@�@�V�S�W�V�@�@�@�V�P�U�R�@�@�@�U�W�U�U
�@�@�@�@�Q�ȁ@�@�P�R�V�R�@�@�@�@�P�O�T�P�@�@�@�@�@�V�X�U�@�@�@�@�T�W�S�@�@�@�@�T�X�S
���v
�@�@�@�@�P�U�X�X�X�@�@�@�P�U�W�P�P�@�@�@�P�V�P�S�S�@�@�P�U�P�T�U�@�@�P�T�Q�X�U
���P�P���̓��\���͎��͑O�N��Q�D�T�������������A�P�Q���͂T�D�R���̌����B��N�܂ł͂ƈႢ�A���N�͎�s���͎��Ɠ��������炵���ɂ�������炸�̌����B��
�P�P���O�͎��w�Z�ʎu�]�ґO�N��i�_�ސ�n��j
������
�������Z�����@�i�ދ���
�i�����V���@�P�P���P�O���j
�u�����v����u�����v��
������ł́c�Ǝ��̖��ō����w�͌��ɂ�
�@�u���ۂ̃J�M�͑I�������Ŏ�肱�ڂ����Ȃ����A�L�q�͂��A�b�v���邱�Ƃł��v�P���A�����s������̓s�������Z�B�����o�z�[���ɒ��R����ی�Җ�R�O�O�l���W�܂�A�����̘b�ɒ����������B�������N�A�ꕔ�̓s�����ŊJ�Â����悤�ɂȂ����u���Z�������v���B�������̓����Ƃ����A�ǂ�����ɂ��Ă��A�S�����ʂ̖��������Ƃ����̂����܂����X�^�C���������B�����s����ψ���������߂��̂͂O�P�N�����������B�e�Z�̓Ǝ��o���F�߁A�܂�����J��������A���w�A�p��̂R���Ȃœ����B�����A�ˎR�A�����q���ȂǂP�Q�̐i�w�Z�����ǂ����B
�@�u�w�����Z�������{�̒��w���͊w�Z�������y����ł���̂��x�Ƃ����č��̒��w���̖₢�����ɁA�����̍l�����R�O�`�S�O��̉p���ŏ����Ȃ����v�u�w�G�̌v�����J���p�x�̃J���p�������Łv�B�Ǝ������̏o��Ⴞ�B�s���ς��p�ӂ����ʖ��̒����p��̒P�ꐔ�͂P���O�ゾ���A�Ǝ������ł͂P�E�T�`�Q�{���x�ɑ�����B���w�̊w�K���e�ݏo���Ă͂��Ȃ����A���Ȃ�̗���́A���p�͂������B�u�Ǝ�������v���f����w�K�m�������Ă���B
�@�Ǝ������̍��Z�̖ړI�́u�����w�͂������k�̑I���v���B��ʂ̋��ʖ�肾�ƁA�����̎��������_�Ōł܂�B�P�A���X�~�X�����ۂ̕�����ڂɂȂ肪���ŁA�������x���̊w�͍����킩��ɂ����\�\�Ƃ����l��������B�Ǝ������̓s������ڎw������s�̒��R���q�́u�_���I�ɂ�����Ɨ������Ȃ��Ɖ����Ȃ���A�Əm�Ō���ꂽ�v�B��e�i�S�V�j�́u�s������ɉ����Ă���ƕ����B�͂����ɂ߂�ɂ͎d���Ȃ��̂ł��傤�v�Ƙb�����B�����͍L����B�_�ސ쌧�ł́u�w�͌���i�w�d�_�Z�v�Ɏw�肳��鉡�l�����A�Ó�ȂǂP�O�Z���Ǝ����������{�B�Q�n�A�L���A��������ʎ����ɓƎ����̒lj���F�߂��B����͓�Փx�̈قȂ�Q��ނ̋��ʖ���p�ӂ��A�e�Z�ɑI���Ă���B
���w�i�ɂ́c�u�U�蕪�����v���������o����
�@�s�����̐��x���ς̔w�i�ɂ́A�u�����v��������������ւ̌��������B�s���ς̓����ɂ́A���Ă̓������x�ɂ���Ď��w�ɐl�C��D��ꂽ�A�Ƃ����v���������B�s���̕��ʉȍ��Z�̓����ɂ́A�U�V�`�W�P�N�A�u�w�Z�Q�v�Ƃ������x���������B������w�Z�̒�������I��ŏo�肷��̂ł͂Ȃ��A�����w��̊w�Z���Q�`�S�Z�P�ʂ̃O���[�v�ɂ��āA�S�̂̍��i�g�ɓ��������k�̎����̐��тȂǂɉ����ċϓ��ɐU�蕪����������B
�@�u������ړI�Ƃ��鋳��͍s��Ȃ��v�B�s�̋��璷������ȒʒB���o���قǁA�i�w�w�����^�u�[�����ꂽ���ゾ�����B�u�P�T�̏t�͋������Ȃ��v�Ƃ������t�̂��ƁA���Z�ɍs���Ȃ����k���ł��邾�����܂Ȃ��悤�A�e�n�Ŏ��X�Ɗw�Z���V�݂��ꂽ�B�����āA�����̂悤�ɕ����̊w�Z���ꏏ�ɂ��ĕ�W����u�����I���v�ƌĂ�鐧�x���L����B�ꕔ�łł����x�������s�{���́A�W�O�N�O��ɂ͂P�S���x�ɏ�����Ƃ����B�e�Z�Ԃ́u���v�͑啝�ɔ��܂����B����������ŁA�����w�̓��x���̏W�c�����������A�w�͂�L�������@����������B�s�s���ł́A�o�ϓI�Ȃ�Ƃ肪����ƒ�̎����A�ǂ�ǂ��֗���Ă������B�������Ђ̑�w�ʐM�ɂ��ƁA�T�W�N���_�ł́A���升�i�Ґ��̏�ʂQ�O�ʂɌ��������P�T�Z�����Ă����B���̂����A�s���͂X�Z�B
���ꂪ�A���t�ɂ͉���i���m�j�A���Y�a�i��ʁj�A�F�s�{�i�Ȗj�̂R�Z�ɂ܂Ō����Ă���B�s���͈�������Ă��Ȃ��B
�����_�́c�w�Z�̏��������鋰��
�@�����o�Ă��܁A�����I�������c��͕̂��Ɍ��Ƌ��s�{�̈ꕔ�̊w�悾���ɂȂ����B���ɂł͗��t�̓���������ɑS�p����邱�Ƃ����܂��Ă���B
�@�X�X�N�ɑ����I������߂����R���ł́A�傫�ȕω����������B�������w���瑱���Ă��錧�����R�������i���R�s�j�͂X�V�N�ɓ���Ƌ���̍��i�Ґ������킹�ĂS�l�������̂��A�P�ƑI���ɂȂ��đ����A���N�͂R�U�l�ɂȂ����B�����I���ł�����Ă������w�Z�̐��я�ʑw���W�����Ă���Ƃ݂���B�����͌����ŗB��A�Ǝ��̓��������������Ă���B�n���̊w�K�m�́u�����̓lj���Ȃǂ̎���O��I�ɂ�����A���Ȃ�w�͂������q�ǂ������w���Ă���v�Ǝw�E����B
�@��r�I�����w��ō����i�w�����\�\�B����Ȍ������Z�́u�����v�́A���ƕی�҂ɑI�����𑝂₵�Ă���悤�Ɍ�����B�s������J�����U�O�N��ɂQ�O�O�l�߂��������升�i�҂����葱���A�X�R�N�ɂ͂P�l�ɂȂ������A���x���ς̌�ɍĂё����ɓ]���A�O�V�N�ɂ͂Q�W�l�ɂ܂ő������B
�@�������A�����Ɋ낤�����������������B�w�͂ɒ��������k������̍��Z�ɕ�A���̑��̊w�Z�̐i�w���т͐L�єY�ށB���q���ɂ���Ă��˂č��Z�̓��p���͐i��ł���A���Z�������x�̌����N�����Ă��鐹�w�@��w�̏���m�����i����w�j�́u�w�Z�Ԃ̏������ɂȂ�A�w���k���W�߂��Ȃ��w�Z�x�͂��������ꂵ���ɒǂ����܂ꂩ�˂Ȃ��v�Ɗ�ԂށB�u�i���v�̖���������������B�u����ꂽ�ꕔ�̊w�Z��ڎw���������������Ȃ�A�q�ǂ��̋���ɂǂꂾ���������������邩�A�ی�҂̎Љ�I�E�o�ϓI�Ȋi�����i�w��ɋ����Ă���v�u���������w���ҁx�����ɁA�b�܂ꂽ����^���Ă��܂����ƂɂȂ�v�@�u�����v�Ɓu�����v�̊Ԃ�h�ꓮ��������́A�܂��m���铚���������Ȃ��ł���B
���Ɨ��l�グ�@���̎��������̔������A�{�������팸��
�i�����V���@�P�P���Q�V���j
�@���{���̎������w�E���Z�P�T�S�Z�̂����A�������W�S�Z�����N�x�̐V�����̎��Ɨ���l�グ����B��㎄�����w�Z�����w�Z�A����Q�V�����\�����B�P�O�`�R�O�Z�̗�N�ɔ�ב啝�ɑ����B�唼���{�ɂ�鎄�w�������̍팸�𗝗R�ɋ����Ă���Ƃ����B
�@���Z�́A�X�S�Z���T�O�Z�����Ɨ��ςS���X�X�O�O�~�l�グ����B���w���Ǝ��Ɨ������킹���V�����[�t���̕��ϊz�͂V�V���W�O�O�~�i�ΑO�N�x��Q���U�T�O�O�~���j�ɂȂ�B���Ɨ��̒l�グ�����ł��傫���̂͗��t���瑁��c��̌n���Z�ƂȂ鑁��c�ۗˁi���E�ۗˁB���{��؎s�j�̂P�U���~�B���w�́A�U�O�Z���R�S�Z�����Ɨ��ςT���W�T�O�O�~�l�グ����B�V�����[�t���̕��ϊz�͂V�X���U�U�O�O�~�i�ΑO�N�x��Q���X�V�O�O�~���j�B���w�A���Z�Ƃ��ɒl�グ���͉ߋ��ő�ƂȂ�B
�@���{�̋����O�m���͍����Č���̈�Ƃ��āA�W���ȍ~�A�����w�Z�̉^�c��ւ̏����������w�Z�ƒ��w�Z�őO�N�x��Q�T���A���Z�œ��P�O���A�c�t���œ��Q�D�T���팸�B����ɂ��Ώo���Q�X���~�}�����B���N�x���ʔN�Ŗ�S�T���~�̍팸��\�肵�Ă���B���A����l�グ����w�Z�ɗ��R��q�˂��Ƃ���A���Z�łX���A���w�őS�Z���{�̏������팸���������Ƃ����B
�s�����{�����Z�@�����œ_��������
�i�����V���@�P�Q���P���j
�@�����s�����{�����Z�i������j�̂O�U�N�x�̓����ŁA��肪�N���������ƍl�����Q�l�̐��k�̓_�������������ĕs���i�ɂ���s�������o�����B��ɐ_�ސ�̌������Łu�����A������v�Ƃ������u����v�ŗ��Ƃ�����肪���炩�ɂȂ������肾���A���{�����ł́A�����̍Z���̎w���̂��ƁA���Z�����_���̉�����s�ׂɂ܂ŋy��ł����Ƃ����B�������������������̂��B����ȋ���ɁA�w�Z�͂ǂ��������������̂��B
�@�u�����̍����ɂ�����邱�ƂŁA�f���Ă����Ă͂Ȃ�Ȃ��v�u���ׂĂ̎ҁA�ی�ҁA�s���ɐS���炨��т��܂��v
�Q�W���ߑO�A�����s���ł������L�҉�B�匴���s�E�s���璷�́A�[�������������B�s���i�ɂ��ꂽ�Q�l�͒��w�����ŁA�O�T�N�Ɉ�x�A���{�����ɓ��w���Ă����B�����A�P�l�͍Z���Ŗ\�͂��͂��炫�A�����P�l�͍Z�O�Ŗ����N�����ĕ⓱���ꂽ���Ƃ��������Ƃ����B���N�P�Q���A�Q�l�Ƃ��u��g��̓s���v�Ŏ���ފw���A���߂ĂO�U�N�x�����ɏo�肵�Ă����B���Z�͑S�������ʉȂŁA���k���͖�S�Q�O�l�A���E���͖�T�O�l�Ƃ����K�͂��B����W�҂ɂ��ƁA���k�w����A��������ꕔ�ɂ������Ƃ����A�O�U�N�x�ɂ͂R�X�l�����ނ��Ă���B
�@�s���ςɂ��ƁA���Z�̂O�U�N�x�����́u�w�͌����U�O�O�_�A�������S�O�O�_�A���Ȃo�q�J�[�h�P�O�O�_�v�̌v�P�P�O�O�_���_�Ŕ��f����d�g�݂������B�j�q�͂U�Q�l�������B�Q�l�̓����̐��т́A�R�S�ʂƂT�X�ʁB�u�Q�l�����i�҂ƂȂ�Ȃ��悤�Ɂv�B���۔����c��O�ɁA�c���[�Z���́A���c�x�Y���Z���ɂ����w�������Ƃ����B
�@���Z�����s����������͂������B�Q�l�����Ȃo�q�J�[�h�œ����U�O�_���u�O�_�v�ɁB����ɁA���N�Ɏ������w�������W�l�̑S�����̒������̓_�����u�I�[���P�v�����ɁB���̏�ŁA���ۂ̋��ڂɂ����ʂ̎��̎��Ȃo�q�̓_�����Q�O�_���Z�\�\�B
�p�\�R���ł���ȑ�����J��Ԃ��A�Q�l�̐��т��u�U�P�ʁv�Ɓu�U�Q�ʁv�Ɉ����������Ƃ����B���Z�͒j�q�̕�W�l�����U�U�l�Ƃ��Ă������A���ǁA���i�҂͂U�O�l�ɍi��A�҂̒��ł͂Q�l������s���i�Ƃ����B�u���w������Ɛ����w����̉ۑ肪�Ĕ�����ƌ��O�����v�B�Z���́A�s���ς̎����ɂ����b�����Ƃ����B
�@�Q�l�͌��݁A�P�W�ƂQ�O�B�s���ς͂Q�V���ɂQ�l�̕ی�҂ɎӍ߂��Ă���A���ł����w�������C���������邩�ǂ������m�F������ŁA�ǂ�ȑΉ����ł��邩�����������Ƃ��Ă���B
�@���o�̔��[�́A�����V���A�s���ςɂ����������������B�Z���ƕ��Z���͕ʂ̍��Z�ł��ꂼ��Z���A���Z���Ƃ��ċΖ����Ă������A�s���ς͍X�R�B���N�x�����ς��̓Z���^�[�Ō��C��������ƂƂ��ɁA�����ȏ�������������B������̌Y���ӔC�ɂ��Ă��u���Ƃɑ��k���ċl�߂Ă���v�Ƃ����B�����̌��ʁA�s���ς́u�Q�l���ȊO�̕s���͌������炸�A���̋��E���̊֗^���Ȃ������v�Ɛ������Ă���B�Ό��T���Y�m���͂Q�W���̒��L�҉�Łu�t�F�A�łȂ��A����܂������Ɓv�u�����X�^�[�y�A�����g�Ȃǂ���绁i�����j���A�搶���q�ǂ���b���������Ƃ͔��ɓ���Ȃ����̂��낤���A���t��I�Ȃ炻�̎g���������͖Y��Ăق����Ȃ��v�Əq�ׂ��B
���{�����ɂ��ƁA���Z�̒��ގ҂͂O�U�N�x�ȍ~�����Ă���A�O�V�N�x�͂P�T�l�A���N�x�͂Q�W�����_�łU�l���Ƃ����B
�u�r�����肫�v�Ɍ��O
�@�u����Ȑ��k���܂������Ă������ς��A�Ƃ�������̋C�����͕�����B�������A�f�[�^�̉�����͍l�����Ȃ��v
�X�V�N����O�R�N�܂œs�����Z�̍Z���߂���؍��O����i���E��C��w�t�����Z���j�͂����b���B������C�����s�������A�����͐��k�̔����߂����ފw����u�w������Z�v�ŁA�����N�����Ă�������ފw�����̂ɂ܂����鐶�k�������Ƃ����B�K���X�������A���݂͎U���A�L���ɂ͎���Ƃ���ɓy���̐ՁB�o�Z���Ă����ڂ�����A�W�Q�����肷�鐶�k�������Ď��Ƃ��������Ȃ��B����ȏ���A�w�Z�Č��Ɏ��g�B�܂��͖����A����W���[�W�[�ɒ��ւ��A�ق�����K�����͂����ւ����ɂ��āA�Z����|�����ĉ�邱�Ƃ���n�߂��B�������͋C���Ȃ����Ƌ��ɁA���k�ƌ��t�����킷���������ɂ����B���Ƃ͂����ɑދ������A�������Ђ����ɒm�b���i�����B���k���w�Z���甲���o���Ȃ��悤�A�w�Ԋy�������������邱�Ƃ��ŗD��ɂ����B�߂��̃S���t�����āA�̈�ɃS���t���̂���ꂽ�B�R�N�ڂ���͐V�����J���L���������J�n�B���ʉȍ��Z�����A���ƌ�ɖ𗧂ł��낤��������ȂǃR�[�X�ʂɊw�ׂ�悤�ɂ����B������ꂪ������O�����������{���͂Q�{���A���ގ҂�����Ɍ����Ă������B�w�Z�����v���A���k�����������Ă����B�]�����ǂ��Ȃ�A�ӗ~���鐶�k������������Ă����B�u���{�����Z�ɂ����̒����͂������̂ł́v�Ɨ����݂͂�B�s���ɗ��Ƃ��ꂽ���k�͂�������j�q�����A��肪�������O�U�N�x�̓����ŁA���q�̔{���͂P�D�U�W�{�Ɣ�r�I���������B�u��������Ȃǂɗ͂���ꂽ�w�Z�̓��F�Â��肪�]�����ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���v
�@����ꓬ���錻�ꂪ�����邾���ɁA�����͍���̖����c�O����B�_�ސ쌧���_�c���Z�i���ˎs�j�ł��O���ɂ�鍇�۔��肪����݂ɏo�����A��肪���鐶�k�͐�̂Ă�Ƃ����u�r���̘_���v����s���Ă���̂��C�ɂ�����Ƃ����B�u���[���Ƃ��Ă̍��i������������A����ċ��炷�ׂ����B�����╞���͓��w��̐����w���̖�肾�낤�v
�u�P�l�����ގ҂��o���Ȃ��Ƃ������ӂƁA���̂��߂̖��͂���w�Z�Â���ւ̓w�́B�w�Z���{���̋��ꏊ�ƂȂ�A�R�N�ԂŐ��k�͑傫���ς��B���ꂪ����̎g���ł��傤�v
������͍Z���A���Z���̌l�I�ȐӔC�Ƃ���ςނ��ƂȂ̂��B�s�����Z�⌧�����Z�S�̂����̂��鐶�k�����������Ƃ��ɁA����ψ���⋳�璡���猵������������ꏸ�i�ɋ����悤�ȑΉ�������Ă���̂ł͂Ȃ����B�Ǘ��Ƌ������i�ތ����w�Z�̒��ŁA�\�ʏゾ���ł�����Ɋw�Z�^�c�����Ȃ���Ƃ����ӎ������������ʂł͂Ȃ��̂��낤���B��
��������@�A�g��T��
���P�M���b�v
����́\�����P�T�S�Q�Z�A�Ǝ��Ɏ��H
�@�d��ɁA�����ƃu���U�[�̐��������������B�����͂T�N����U�N���B�u���U�[�́u�V�N���v��u�W�N���v���B�݂�ȁA�������t�y�����B�A�j���\���O���I����ƁA����̑̈�ق�����ł킢���B���t�J�Z���������s�i��旧�̏��E���w�Z�A�����w���B�������߂̕����Ղ̕��i���B�`������̊��Ԃ���̂ƂƂ炦��u������эZ�v�B�i���ł͂O�U�N�x�ɃX�^�[�g���A���P�`���R�́u�V�`�X�N���v�ƌĂ��B�X�N�Ԃ��u�U�E�R�v�łȂ��u�S�E�R�E�Q�v�ɕ����A�w�ԓ��e�ɂ��Z�ʂ𗘂�����̂��������B���ȒS�C�������T����n�߂�B�u��B�������Đ�y�Ɍ���ꂽ��v�B����̎�w�i�S�U�j�͍ŋ߁A�^�����ɓ����Ă��鏬�U�̖����炱��Șb���悭�����B�u��y����{�ɖڕW�������Đ�������悤�ɂȂ����v�Ɗ�����Ƃ����B
�@�������������́u������ы���v�́A�O�O�N�̍L�������s���n�܂�Ƃ����B����ے��̓���Ŏ��{���Ă���w�Z�͏������킹�đS���łP�T�S�Q�Z�B�ߗׂ̊w�Z�őg�ރP�[�X���������A�w�Z�̌������̂���̉�������Ƃ�����o�n�߂Ă���B�w�N�̋������u�T�E�S�v�i���쌧�������Ȃǁj�A�u�R�E�S�E�Q�v�i�{�錧�o�Ďs�j�Ƃ��܂��܂��B�Ìy�C���ɖʂ����X�����ʁi�Ђ����E�ǂ���j���ł́A�R�N�O�ɂP�U�Z���������w�Z�𗈏t�ɂ͂P�Z�ɂ�����ŁA�ꑫ�����P�Z�ɂȂ������w�Ƃ̈�эZ�ɂ���B������эZ�́A�@�I�ɂ͂����܂ŕʂ̏��A���w�Z�ŁA���w���⑲�Ǝ��͒ʏ�́u�U�E�R�v�ɍ��킹�čs����B
�w�i�́\�����̋��ځA�u�U�E�R���v�Ƃ���
�@���w�ɐi�Ƃ���A���̓��e����̕ω��ɂȂ��߂��A�w�Z�ɓK���ł��Ȃ��Ȃ�u���P�M���b�v�v�B������ы���͂��̑Ή���Ƃ����Ӗ������������B�[�I�Ȃ͕̂s�o�Z�₢���߂��B�O�V�N�x�̍��̒����ł́A�s�o�Z�͏��U�Ŗ�W��l�����A���P�ł͂R�{���̖�Q���T��l�ɒ��ˏオ��B�����߂����U�̖�P�������璆�P�Ŗ�Q���P�猏�ɂȂ�B
�@���{���瑊�k���������̖؉��M������́A�����́u�i���v�̑傫�����w�E����B�܂��A���̃X�s�[�h�Ɨʂ��B���ȒS�C�����ꂼ��h����o���A����e�X�g�̑O�ɂ͒x������߂����Ǝ��Ƃ��}���B����ɁA��������ӂ���̊w�Z�����ł́A���w�Z�Ōo�����Ȃ�������y�A��y�̌������㉺�W������B
�@�q�ǂ��̑̂�S�̐��������܂��Ă���B�L�������s���̏�����эZ�E�������w�����S�����v�����Ƃɒ��ׂ��Ƃ���A�g�����ł��L�т�̂͂P�X�T�O�N�͒j�q�P�T�A���q�P�Q���������A�O�S�N�ɂ͒j�q�P�Q�`�P�R�A���q�P�O�`�P�P�Ƒ��܂��Ă����B�u���肩��F�߂��Ă���Ǝv���H�v�Ƃ����Z���̃A���P�[�g�ł��A�u�v���v�q�����S�܂łW���ȏア��̂����T�łU���قǂɌ���B�v�t�����L�̐S�̕ω�������������B���F���F�E���勳���i�J���L�������w�j�́u���B�̑傫�ȋ��ڂ����Ă��A���܂̊w�Z�ł͎v�t���Ƃ��Ĉ����Ă��Ȃ��v�Ǝw�E����B
�@�����́u�U�E�R���v�͐��A���t�ɐ݂���ꂽ������V�ψ�����A�S�V�N�Ɏn�܂����B�����̕č��̐��x�̉e�������Ƃ���邪�A���̕č��ł͂��܁A���Z�����킹�āu�T�E�R�E�S�v���嗬�ɂȂ��Ă���B�i���̎ጎ�G�v���璷�͌����B�u�U�E�R���Ƃ����C�͂����q�ǂ��̑��ɍ���Ȃ��Ȃ����v
�����A����ς��Ă��A�V���ȋ��ڂł܂��܂����\��������B������т͊w�Z���n�߂��͍��̑������B
�ۑ�́\�������m�A���O���L�ł��邩
�@�{�茧�����s�̎s���剤�J�i�����E�����E���Ɂj�����w�Z�B���t�̈�эZ����O�ɁA�s�������₷���悤�ׂ荇�킹�̏������P�T�O���[�g���̓n��L���łȂ����B���t���āu�w�т̂������v�B�����鎞�Ԃ͂T���قǂŁA�x�ݎ��Ԃ̈ړ����\�ɂȂ����B���́u�P�T�O���[�g���v����ы�����\�ɂ���ڈ��ƂƂ炦�A�������琭�����̐؉h�ꌤ���������ׂ��f�[�^������B���w�̐����U�Z�܂ł̏��K�͎����̂��璊�o����ƁA�ߗׂ̏������P�T�O���[�g���ȓ��Ɏ��܂����P�[�X�͖�P���ɂƂǂ܂����B���P�M���b�v�̏���ⳁi����j���A�ǂ��ł��ł���킯�ł͂Ȃ����Ƃ��킩��B
�@���ۂ̋��猻��ɂ��ۑ�͂���B���w�����̌o���������������w���̓�{�������@�͍ŏ��̂���A���T�̎��ƂŔ��������狳�������[�b�Ƃǂ�߂����B�u�搶�A�����v�B���w���ɂ͓��Ɏ菇��ǂ����������K�v�Ȃ̂ɁA���̊Ԃɂ������哱�ɂȂ��Ă����B�ӎ��̖����傫���B���߂͋����ԂŘA�g�̕K�v�����������ꂸ�A�����ŕǂ�����悤�Ȍ������������B���w�Z�̋����́u���w�͉�������v�ƕs�����Ԃ����B���w�͒��w�Łu�A�g�ɘJ�͂��Ƃ��ĕ����Ɋ������Ԃ�����v�Ƌ��͂�������Ȃ������������Ƃ����B�������A�o����ς�ʼn^�c�͒蒅���A�ڂɌ����鐬�ʂ��o�Ă����B�Ⴆ�A�����̐i����͂��錧�̊w�͒����ŁA���܂̒��R���́A���T�̎��ɍ���̐��������V�O�E�T���������̂����Q�ł͂W�O�E�V���ɃA�b�v�����B���Q�̐��w�ł͌����ς��V�|�C���g�������B���w�̕s�o�Z�͂O�Q�N�x�̂Q�O�l����O�V�N�x�͂T�l�ɁA�\�͍s�ׂȂǂ̖��s���͂V�S������P�U���Ɍ������Ƃ����B
�@������т̎��g�݂͏��ɂ�������ŁA�܂Ƃ܂����͂܂���������Ȃ��B���P�Ɠ����w�N�W�c�ɓ��������T�⏬�U���{�����q�ǂ����ۂ��Ȃ�Ƃ����w�E������A��{��������\�Ƃ͎v���Ă��Ȃ��B�u�q�ǂ��Ɠ��X�Θb���A�������w�э����Ă������Ƃ��������܂���v
��t��̓V�}�����i�w�Z�o�c�w�j�́u�n��ŃJ���L��������w�����@���������A�H�v���d�˂邱�Ƃ�����B�������߂�������̂ƈႤ�V����������v�̃X�^�C���ɂȂ肤��v�Ƙb���B
�@�ǂ�ȋ�����ǂ��܂Ői�߂邩�B�u�킪���v�̎����������B
���ې��w�E���ȋ��瓮�������@���{�A�����w�͉����~�܂�
�i�����V���@�P�Q���P�O���j
�@���ۋ��瓞�B�x�]���w��i�h�d�`�j�́A�O�V�N�Ɏ��{�������ې��w�E���ȋ��瓮�������i�s�h�l�r�r�j�̌��ʂ����\�����B���{�́A���Q���Ȃ̕��ϓ_���T�T�S�_�i�R�ʁj�őO��O�R�N�����̂T�T�Q�_�i�U�ʁj������ȂǁA���{�S�Ȗڂ̕��ϓ_�͂��ׂđO��ȏ�i���Q���w�͓��_�j�������B���S�ł́u�����y�����v�Ɠ����������̊����������A�w�K�ӗ~�����P�X�����������B�����Ȋw�Ȃ͏����w���̗����̊w�͒ቺ�Ɏ��~�߂����������Ƃ݂Ă���B
�@�����ɂ́A�R�V�J���E�n��̑�S�w�N�i���{�͏��S�j��P�U���l�ƁA�T�O�J���E�n��̑�W�w�N�i���Q�j��Q�Q���l���Q���B���{����͌v�W�V�X�X�l���Q�������B�_���͌o�N��r���\�ɂ��邽�߁A�S�Q���҂̕��ς��T�O�O�_�ɂȂ�悤�ɒ��������B���{�̏��S�̕��ϓ_�́A�Z�����O����R�_�����T�U�W�_�A���Ȃ��T�_�����T�S�W�_�B��������f�[�^��r�\�ȂR�U�J���E�n�撆�S�ʁi�O��͂Ƃ��ɂQ�T�J���E�n�撆�R�ʁj�������B���Q�̐��w�͑O��Ɠ����T�V�O�_�ŁA�S�W�J���E�n�撆�T�ʁi�O��͂S�U�J���E�n�撆�T�ʁj�������B
�@�u�����y�����v�Ɠ��������S�̊����́A���Ȃ��W�V���i�O���U�|�C���g���j�ō��ە��ς̂W�R�����������B�Z�������ە��ςɂ͂P�O�|�C���g�y�Ȃ����̂́A�V�O���őO����T�|�C���g�������B����A���Q�́A�u���w���y�����v���P�|�C���g���̂S�O���A�u���Ȃ��y�����v���O��Ɠ����T�X���ŁA���ە��ς����ꂼ��Q�V�A�P�X�|�C���g��������B
�֘A�L��
��Ƃ�]���œi�����V���@�P�Q���P�O���j
�@�O�V�N�Ɏ��{���ꂽ���ې��w�E���ȋ��瓮�������i�s�h�l�r�r�j�ŁA���{�̏����w���̕��ϓ_�͑O��ȏ�ƂȂ�A�ӗ~�����������Ƃ̌��ʂ��o���B�e�X�g�����̂́A�w�͒ቺ�̌����Ƃ��ꂽ�u��Ƃ苳��v�Ŋw�q�ǂ������B���Ǝ��Ԃ��w�K���e�����₷�V�w�K�w���v�̂ւ̈ڍs�����N�x����n�܂邪�A�u��Ƃ�ł��w�͒ቺ�Ɏ��~�߁v�Ƃ̌��ʂ��o���̂͂Ȃ��Ȃ̂��B
�@�������̗L�n�N�l�E���{�Ȋw�Z�p�U�����c��́u�w�E�l�ߍ��݁x�̂��ƁA�����Ɋw�͂��͂����܂�Ă��邱�Ƃ��킩�����v�Ƌ�������B�O��O�R�N�̌��ʂȂǂ���w�͒ቺ���w�E����A�u�E��Ƃ�v�̎w���v�̂ւ̉���ɂȂ��������A�L�n����́u���{�̊w�͂͂����ƃg�b�v���x���ŁA���������Ƃ̔F�����̂��ԈႢ���v�B����܂ł̏��ʒቺ�́A�Q�����̑����������ƌ���B�U�ʂ���R�ʂɏオ�������Q���Ȃɂ��Ắu�����w�K�����Ŏ��Ƃ����������A�����̒�͂�����B�����̓w�͂⍑�ɂ�闝�Ȏx�����̔h�����A���x���ɂȂ����v�ƕ]������B�����A���ւ̈ӗ~�͓��ɒ��w���ŒႢ�B�u�m��������������̂ŁA�ʔ�������ɂ���ɂ��̂�������Ȃ��B���я�ʂ̑�p��؍��ł������X��������v�ƕ��͂����B
�@����A�u�������ł��Ȃ���w���v�̋��������鐼���a�Y�E����o�ό����������́u�P�A�Q�ʃO���[�v�̓_���Ƃ͑傫�ȊJ��������A���E�g�b�v�N���X�Ƃ͂����Ȃ��B���ђቺ�͂R�O�N�߂���������Ƃ苳�炪�������v�ƌ���������������B���̈ӗ~�����܂�Ȃ��̂́A�w�͕]���ɂ�����y�[�p�[�e�X�g�̔�d���߂����Ƃ������Ƃ݂�B�u�W�X�N����̎w���v�̂́A�w�K�ւ̑ԓx��S��]���ɉ�����w�V�w�͊ρx���������A�������߂�ׂ����v�B���̂����Łu�g�b�v�ɕԂ�炭�ɂ́A�����w�K����߁A��w�����̉Ȗڂ��������đ����I�ȉ��v�����Ȃ��������B��������͎��Ǝ��Ԃ�������̂ŁA����ȏ㉺���邱�Ƃ͂Ȃ����낤�v�ƌ��_�Â����B
���ƂE�E�E���ې��w�E���ȋ��瓮�������i�s�h�l�r�r�j
�@��Ɏ��ƂŏK�������m���̒蒅�����钲���ŁA�X�T�N�ȍ~�͂S�N�ɂP����{�B���{�͂W�P�N�����Œ��Q���w���P�ʂɂȂ�Ȃǂ������O�R�N�����͂R�`�U�ʂŁA�w�͒ቺ������c�_���ĂB�o�ϋ��͊J���@�\�i�n�d�b�c�j�̊w�K���B�x�����i�o�h�r�`�j�́A�P�T��ΏۂɂR�N�ɂP����{�A�m���̊��p��lj�͂Ɏ���u�����Ƃ���o��X�����قȂ�B
�����ې��w�E���ȋ��瓮�������̏��ʂƕ��ϓ_
�@�@�@�����S�Z�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�����S���ȁ�
�@�P�@���`�@�@�@�@�@�@�U�O�V�i�@�Q�j�@�V���K�|�[���@�T�W�V�i�@�P�j
�@�Q�@�V���K�|�[���@�T�X�X�i�@�P�j�@��p�@�@�@�@�@�@�T�T�V�i�@�Q�j
�@�R�@��p�@�@�@�@�@�@�T�V�U�i�@�S�j�@���`�@�@�@�@�@�@�T�T�S�i�@�S�j
�@�S�@���{�@�@�@�@�@�@�T�U�W�i�@�R�j�@���{�@�@�@�@�@�@�T�S�W�i�@�R�j
�@�T�@�J�U�t�X�^���@�T�S�X�i�|�|�j�@���V�A�@�@�@�@�@�T�S�U�i�@�X�j
�@�U�@���V�A�@�@�@�@�@�T�S�S�i�@�X�j�@���g�r�A�@�@�@�@�T�S�Q�i�@�V�j
�@�V�@�C���O�����h�@�T�S�P�i�P�O�j�@�C���O�����h�@�@�T�S�Q�i�@�T�j
�@�W�@���g�r�A�@�@�@�@�T�R�V�i�@�V�j�@��@�@�@�@�@�@�T�R�X�i�@�U�j
�@�X�@�I�����_�@�@�@�T�R�T�i�@�U�j�@�n���K���[�@�@�@�T�R�U�i�@�W�j
�P�O�@���g�A�j�A�@�@�T�R�O�i�@�W�j�@�C�^���A�@�@�@�@�@�T�R�T�i�P�S�j
�@�@�@�����Q���w���@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Q���ȁ�
�@�P�@��p�@�@�@�@�@�@�T�X�W�i�@�S�j�@�V���K�|�[���@�T�U�V�i�@�P�j
�@�Q�@�؍��@�@�@�@�@�@�T�X�V�i�@�Q�j�@��p�@�@�@�@�@�@�T�U�P�i�@�Q�j
�@�R�@�V���K�|�[���@�T�X�R�i�@�P�j�@���{�@�@�@�@�@�@�T�T�S�i�@�U�j
�@�S�@���`�@�@�@�@�@�@�T�V�Q�i�@�R�j�@�؍��@�@�@�@�@�@�T�T�R�i�@�R�j
�@�T�@���{�@�@�@�@�@�@�T�V�O�i�@�T�j�@�C���O�����h�@�@�T�S�Q�i�|�|�j
�@�U�@�n���K���[�@�@�T�P�V�i�@�X�j�@�n���K���[�@�@�@�T�R�X�i�@�V�j
�@�V�@�C���O�����h�@�T�P�R�i�|�|�j�@�`�F�R�@�@�@�@�@�T�R�X�i�|�|�j
�@�W�@���V�A�@�@�@�@�@�T�P�Q�i�P�Q�j�@�X���x�j�A�@�@�T�R�W�i�P�Q�j
�@�X�@��@�@�@�@�@�@�T�O�W�i�P�T�j�@���`�@�@�@�@�@�@�T�R�O�i�@�S�j
�P�O�@���g�A�j�A�@�@�@�T�O�U�i�P�U�j�@���V�A�@�@�@�@�@�T�R�O�i�P�V�j
�@�i�J�b�R���͂O�R�N���ʁA�|�͕s�Q���܂��̓f�[�^�s���j
���y�������{�ʼn��ʁi�Y�o�V���@�P�Q���P�O���j
�@�����w���̗����n�̐��т͍��ے����łT�ʈȓ��ƗD�G�����A�u���͊y�����v�͍ʼn��ʃ��x���|�B�P�O���t�Ŕ��\���ꂽ�u���ې��w�E���ȋ��瓮�������v�i�s�h�l�r�r�Q�O�O�V�j�ŁA����ȃA���o�����X�Ȍ��ʂ��o���B�O�R�N�̑O������P�X���݂͂�ꂽ���A���ɒ��Q�ŃM���b�v�������B���҂�́u���ƕ��@�ɖ�肪����v�Ǝw�E���A�q���̑̌��┭�����d�������w�����K�v�Ƃ��Ă���B
�@�Z���E���w�Łu�����y�������v�Ƃ����₢�Ɂu���������v���v�Ɖ����̂͏��S�łR�S���ŁA�R�U�J���E�n�撆�R�Q�ʁB���Q�ł͂킸���X���ŁA�S�W�J���E�n�撆�S�U�ʂƒ�������B�u�����v���v�����킹���m��I�ȉ͏��S�łV���ɒB���邪�A���Q�ł͂S���ɂ܂ŗ������ށB�u���w�������Ɠ��퐶���ɖ𗧂v�Ɂu�����v���v�Ƃ������Q�͂V�P���i���ە��ςX�O���j�łS�V�ʁB����ł��O�R�N���͂W�|�C���g���サ�Ă����B�Z���E���w����ɏڂ����}�g��̒ؓc�k�O�����́A�D���тƂ̃M���b�v�ɂ��āA�u���{�̎q�������͌����̊ۈËL���w�Ȃ��x���ɂ����ʔ����������邱�ƂɋC�t���Ă���̂ɁA���Ƃ��Ή��ł��Ă��Ȃ����Ƃ��w�y�����Ȃ��x���R�ł́v�Ɛ����B�u����������邾���łȂ��A�q���Ƃ��Ƃ肵�A�����������Ƃ��K�v���v�Ƙb���B
�@���Ȃł́A�u�����y�������v�̖₢�ɏ��S�̂T�V�����u���������v���v�Ɠ����A���ە��ς̂T�X���Ɠ������B�Ƃ��낪�A���Q�ł͂P�W���ɗ������݁A���ە��ς̂S�U���Ƒ傫�ȍ����o���B�����w�K�Ńr�I�g�[�v���ȂǗ��ȋ���ɗ͂����铌���s�V�h�旧�˒ˑ�̐�z�H�L�Z���́u�y�����v�̒ቺ�ɂ��āu���R���ۂɐG���Ƃ������̌��s���������v�Ǝw�E�B�u���w�Z�ł́g�����ȁh�ɂȂ肪���ŁA�O�̐��E�Ƃ̂Ȃ��肪��Ă��܂��B�V�����w�K�w���v�̂œ��e��������̂͂������A�����A�g�ŗ��ȃC�x���g���s���ȂǁA�q�������ɗ��Ȃ̊y������`����H�v���K�v���v�Ƙb���Ă���B
�@�s�h�l�r�r�ł́A�w�Z�O�ł̎��Ԃ̉߂������������B���{�̒��Q�̓e���r�������Ԃ��P���Q�E�T���ԂŁA�Q�����E�n�撆�ōł������A���S���Q�E�O���ԂŁA�V���K�|�[���Ɏ����Q�ʂ������B�ΏƓI�Ɂu�Ƃ̎d��������v�͏��S���O�E�W���Ԃōł��Z���A���Q���O�E�U���ԂŃA���W�F���A�Ɏ����łQ�ԖڂɒZ�������B
����֎~�ʒm�@�s���ς͔��Љ�I�g�D
�i�����V���@�P�Q���P�O���j
�@�u�����s����ψ���͔��Љ�I�g�D����Ȃ����v�B����]�_�Ƃ̔��ؒ������X���A�s���ŊJ�����L�҉�ŁA�s���ς̎p�������]�����B�E����c�ł̋���E�̌����ւ����ʒm������A�s���ς��s���O�鍂�Z���̓y��M�Y����������炪�Ăт��������J���_�ɉ����Ȃ��܂܁u�ʒm�ɖ��Ȃ��v�ƌ��_�Â������Ƃ��������B�������͉��߂Č��J���_�����߂�v�������o�����B��Ŕ�����́A�s���ςɂ��āu��Ӊ��B�̃q�G�����L�[�i�x�z���x�j���m���������Љ�I�g�D�ɂȂ��Ă��܂��Ă���v�Ɣᔻ�B�s���ς��s���Z�̍Z���A���Z���̍l�����������Łu�ʒm�͌��_�̎��R��D���Ă��Ȃ��v�ƌ��_�t�������Ƃ��u���Ȗ����ɂ����Ȃ��v�Ɛ�̂Ă��B
���{���Z�����@�������w�䗦�V�F�R�u�ς������v
�i�����V���@�P�Q���P�O���j
�@���{�̋����O�m�����A�{���̌������Z�Ǝ������Z�Ƃ̊ԂłR�O�N�߂��u�V�R�v�̊����Ǝ�茈�߂��Ă������w��W�̒���g�ɂ��āA�����̒���𑝂₹�Ȃ����{���ςɌ��������߂����Ƃ��킩�����B����ɑ����w���́u�o�c�������Ȃ��v�Ƃ��č���c���ɂ���A������\�����݂��Ă���B�����m���͂X���A�����V���̎�ނɁu�i����g�́j�J���e���݂����Ȃ��́B����ł͉������v�ł��Ȃ��v�Əq�ׂ��B
�@�����Č��̂��ߕ{�͍��N�W������A���w�ւ̏��������J�b�g�A���Z�͈ꗥ�P�O�����Ƃ����B���̂��߁A�������Z�̉ߔ��������N�x�̐V�����̎��Ɨ��̒l�グ������B������A�m���͗��N�x�\�Z�Ă��߂���P�P�����̕{���ςƂ̋��c�ŁA�����ւ̎u�]�҂���葽���������Ԑ��Â���ɂ��āA�u���}�Ɍ������Ă������������v�Ɣ����B�����A����g�̌������Ă�����悤���߂��B
�@�{���̎��w�ł����㎄�����w�Z�����w�Z�A����i�����A�j�͂�������������m��A�������߁A�����ő��I�o�̍���c����Q�O�l�ɂV�R�̒���g���ێ�����悤��B�߂��c���������Ēm���Ƌ��c���������������l�����B�@���Z�ł̒���g�̐ݒ�͂V�T�N�A��Q���x�r�[�u�[���ɂ�鐶�k�}�������z���������̕����Ȃ��A�����Ǝ��������͂��Đ��k�������悤���҂̋��c��ݒu�����߂����Ƃ���n�܂����B���{�ł͂W�O�N��̓�������{���ςƒ����A�����c���A�����Ǝ����̓��w�Ҕ䗦���قڂV�R�̊����ƂȂ�悤��߂Ă����B�{���w�ۂɂ��ƁA��s�s���ł͓����s�T�X�D�U�S�O�D�S�A�_�ސ쌧�U�S�A���m���U�U�R�R�A�������U�S�i��������O�V�N�x�j�Ȃǂƒ���g���߂Ă���B�����A���w������ɂ͋��t�̑����⋳���̊m�ۂȂǁA�傪����Ȑ��x���v�Ƒ����̗\�Z���K�v�ŁA�{���ϊ����́u�����ȒP�ł͂Ȃ��v�Ƃ����B����A�����A�����́u�i����g��P�p����j�Ԃ�鎄�w�͏��Ȃ��Ȃ����낤�v�Ƙb���Ă���B
�������Ԃ̒���g�����c�������A���k���e��ψ���ƌĂԂ��������A�w�Z�͐��k�̎��e���Ȃ�ł��傤���B�����A���k�̋}�����Ɏ����ɐ��k�̎���������Ă��炢�Ȃ���A���k�����Ȃ��Ȃ��Č����ł��イ�Ԃ������邩�玄���͂���Ȃ��Ƃ��������́A�ŋ߂̑���Ƃ̏]�ƈ����قƓ������ӔC����������B�����̎���g��P�p����ƂƂ��ɁA�����������������y�U�̏�őI�ׂ�悤�Ɏ����ɐi�w���鐶�k�̊w��⏕���[������ׂ��B���̏�Ő��k�ƕی�҂��w�Z��I�ׂ悢�B��
�w�Z�I���@�Ȃ���p
�i�����V���@�P�Q���P�Q���j
�w�Z�I�𐧂���������āc����s�́\���k���̊i���[���Ɂc�p�~��
�@�V�P�U�V�B�O���s����w�Z�̏��q�o�X�P�b�g�{�[�����́A�H�̐V�l��ł���ȃX�R�A�ŕ����Ă��܂����B�����͂T�l�B�M���M���̐l���������Ȃ��B����ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��ƁA�V�l�������Ȃ��o���[�{�[�����ƍ������K���n�߂��B����̍�ŁA�o�X�P�b�g�A�o���[�̑o���̕�������̂ɂȂ�A�ǂ���̎����ɂ��o����悤�ɂ����B���������A�w�Z�̐��k���������Ă���B�����̍��N�̐V�����͂P�N���X���̂R�S�l�B�w����ɂ͂T�T�l�̎q�ǂ������āA�{���Ȃ�Q�N���X�ł���͂����������A�悻�̒��w�ɐi�ސ��k�������o���B
�@����Ȃ��ƂɂȂ������R�́u�w�Z�I�𐧁v�ɂ���B�����Z�ł��A�n���̍Z�悩�痣��A�s�������w�Z���u�]�ł��鐧�x���B�w�Z�ɂ���ẮA���ꂫ�ꂸ�ɒ��I�ɂȂ�Ƃ��������B�K���ɘa������s�M���L����Ȃ��A�q�ǂ���ی�҂Ɂu�I�Ԍ����v��^����B�u�I���v����ɂȂ����w�Z���́A���ǂ��^�c�ɓw�͂���悤�ɂȂ邾�낤�\�\�B����ȍl���̂��ƂōL�������B�O�U�N�̒����ł́A���w�Z�łP�S�E�Q���A���w�Z�łP�R�E�X���̎����̂��������Ă���B�������A�l�C�A�s�l�C���I���ɕ\���A�c���Ȑ��x�ł�����B
�@�O���s�ł͐��x��������T�N�������A�w�Z�Ԃ̊i�����傫���Ȃ����B���w�ł́A�w�Z�ɂ���Đ��k���ɂP�T�O�`�U�O�O�l���x�̊J�����o�Ă���B��̏ꍇ�A��r�I�߂��ꏊ�ɕʂ̑�K�͂Ȓ��w������B�������Ȃǂ������ŁA�w����̐��k������Ă���Ƃ����B�������j�Z���́u���K�͂������ǂ��͂��邪�A����ɂ����E������v�B��x���k������n�߂�ƁA�}�C�i�X�̖ڂł݂�ꂪ���ŁA�s�l�C�ɔ��Ԃ�������B�u�ǂ��C���[�W�ɕς���͓̂���v
�@����ȂȂ��A���s�͂X���A�I�𐧂��P�O�N�x�̐V��������Ŕp�~������j�����߂��B�u�����܂ō����J���Ƃ͎v��Ȃ������B�N���X�ւ����ł��邱�Ƃ��w�Z�̓K���K�͂̍Œ�������v�Ƃ����s���ς́A�w�Z�́u���p���v�����N�x����i�߂�B�������킹�ĂU�U�Z�̂����P�O�Z���Ȃ����v��ŁA������������������B�S�Z����C�ɂQ�Z�ɂ���n�������B�ی�҂ɂ́u�s���͑I�𐧂������̂悤�Ɏ������݁A���p���̍������Ɏg������Ȃ����v�Ƌ^�������o�Ă���B
�u�����́v�\�I�������炵�Ă����I�Z���o
�@�O�Q�N�ɑS�����w�Z�Ŋw�Z�I�𐧂����������s�]����������������߂��B����܂ł͋���S��A�ǂ��ł��s�������w�Z���u��ł���悤�ɂ��Ă������A�d�Ԃ�o�X�Œʊw���鏬�w�����o�Ă��āA�n��̂Ȃ��肪���ꂽ���Ƃ�S�z���鐺�������Ȃ��Ă����Ƃ����B���N�x����A���w�Z�ł́A�����Ēʊw�ł���͈͂̊w�Z�����u��ł��Ȃ��悤�ɂ����B�܂��A�l�C�Z�ł͂���܂ŁA�n���w����̎q�ǂ��̐��Ɉ�萔���v���X���������p�ӂ��Ă������A���w���܂߂Ă������߂邱�Ƃɂ����B���ꂾ�ƁA�w��O����u�肵�Ă��A���̊w����Ŏ����Z�Ȃǂɗ��ꂽ�u�l���v���x�̘g�����Ȃ��B�������\�\�B�ӂ����J����ƁA�u�w�Z��I�ԁv�����͎~�܂炸�A���N�x�̓��w�Ҏ���Œ��I�ɂȂ�\��̊w�Z���啝�ɑ������B���w�Z�͍�N�͂S�R�Z���X�Z�������̂����N�͂Q�O�Z�ɁB���w�Z�ł͍�N�͑S�Q�Q�Z���V�Z�������̂��Q�P�Z�ɁB���w�Z�Œ��I�ɂȂ�Ȃ��̂́A���N�V�l�����V���������Ȃ��w�Z�����������B
�@��x�u�I�ׂ�v�ƂȂ�ƁA�ی�҂̋C�����͎~�܂�Ȃ��B�i�w���e�A�{�݂̏[���x�A�Z��̍L���A�������̊������A�F�����Ƃ̊W�c�c�B�I�����������Ă��A���̒��Łu���ǂ��v�w�Z��I�т����ƐS�������B�Ⴆ�A����������ōZ�ɂ����z���ꂽ����̐[���O���B���N�x�̊w����̓��w�\��Ґ������łQ�Q�T�l���邪�A����ɁA���w�悩��R�Q�O�l�̊�]�\�����o���B���I�͂P�Q���P�P���ɂ���A�w����̎��ގ҂��o�����������ɌJ��オ��B�u�s���邩�s���Ȃ����v�́A�ŏI�I�ɂ́A������]�҂̍s���悪��܂�Q��������܂Ŋm�肵�Ȃ��Ƃ����B
�u��i�n�́v�\�ی�҂̂U���u�����Ăق����v
�@���w�œ������ĂS�N�����������s���n��́A���̈ψ����ݒu�����B�����ւ̑I�����̃A���P�[�g�ł́A��U�T�����u���킳�╗�]�Ŋw�Z���I���悤�ɂȂ����v�Ɠ������B�w�Z�I�𐧂̊̂Ƃ�������u�w�Z�̋��������ŋ���̎������サ���v�Ƃ������ڂ��m�肵�������́A�킸���P�E�T���������B
�@����A�O�O�N�ɓs�s���ŏ��߂đI�𐧂������i���́u�斯�Ɏx������Ă���v�Ƃ����B���N�Q���̃A���P�[�g�ł́A�ی�҂̂T�������x�ɖ������A�U�����p����]�B�u�I�𐧂ŁA�܂��Z���̈ӎ����ς�����v�u���ʂ�]�����ӎ����A�q�ǂ��������͂����Ă��邩����������m�F����悤�ɂȂ����v�B���ꂪ���拳�ς̕��͂��B�x�c�ˎq�w���ے��́u�ۑ�̂���w�Z������A�\�Z���l�����Ďx�����Ă���B�������R�Ɓw���x������Ί��������邾�낤�x�ƍl���ē��������̂ł́A���܂��͂����Ȃ����낤�v�Ƃ����B
�@����ɂ���āA�傫���قȂ�]���〈���B���x�̍s����͌��ʂ��Ȃ��B�S���̓���������Ă�����C��̗�䐳�狳���i���琭��w�j�́u�搶�̓w�͂Ƃ͊W�Ȃ��Ƃ���Ŋw�Z���I��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��v�Ǝw�E����B�{�݂��V�����A�����������A�w�ɋ߂��c�c�B�u�l�C�v�̂��Ƃ͗l�X���B��̏�ɂ���Ƃ��������Ŕ������Ă���w�Z������Ƃ����B�u�l�C�Ɋi�����o�邱�Ƃ͑I�𐧂��n�߂�Ƃ�����\�z���ꂽ���A�v�����ȏ�ɑ傫�������v�B�N��ǂ����Ƃɑ����Ă������x�����̓������u�����܂�̂ł͂Ȃ����v�Ƃ݂�B
���̑�
�����E�����E����
�i�X���́@�������ю�j
����ς�A�ق�܂���̗͂�����ɂ͗]���Ȃ��Ƃ���ƁB���m�����ɓ������炷�����o�����Ă��炦�邩�Ƃ����ƁA�����łȂ��B���͑|���A���ѐ����A�����Č�Еt���A����Ȃ̂����[���Ƃ���Ă��āA���O�A�����֍���A���ꂩ�炨�o�ł��B�q��₨�g��������Ȃ��B���ꂪ�v���X�ɂȂ��ł���B
���������̂͒N��
�i�ǔ��V���@�P�Q���V���j
�@�����͂U����A���茧�|���s�Ŏ����}���茧�A����Â����̉�����ʼn������A�lj��i�C��̒��ł����z���t���ɂ��āA�u�n�����l�ɂ͑S���тɓn�����A�w���͂���ȋ������炢�����Ȃ��x�Ƃ����l�͂����Ȃ��Ⴂ���B�i�N�����j�P���~�����Ă��A���������P���Q�O�O�O�~���~�����Ƃ����l�����邩������Ȃ��B����͓N�w�A����(���傤��)�̖��ŁA����ׂčׂ����i�����������j�������Ԃ���ς��v�ƌ�����B
�@���{�͏���������݂��邩�ǂ����ō����������A�u�N�ԏ����P�W�O�O���~�������v�Ƃ����ڈ������������A���ނ��Ăт����邩�ǂ����͎s�撬���̔��f�ɈςˁA�����I�ɐ������Ȃ���Ԃ������܂�Ă���B���ꂾ���ɁA����̎̔����͔g����L���������B
���P�Q�O�O�O�~�̋��t���Ől�C����낤�Ƃ��āA�������������������������Ƃ͒N�Ȃ�ł��傤�B��
���������i�@�H�i���[�J�[�A�茘���l�C�Ő푈�ߔM
�i�����V���@�P�Q���P�O���j
�@�V�[�Y����O�ɁA�H�i���[�J�[�������Ď��������i������B���̉Ԃ��f�U�C��������A�u��g�v�̂��݂�����������Ǝ���͂��܂��܂����A�������N�A���N���������ɍ������l�C�B�������̒��A�茘���҂��鏤�i�Ƃ��Ē蒅������B�������i�̂͂���́A�l�X���̃`���R���[�g�u�L�b�g�J�b�g�v�B��B�̕����u�����Ə��Ƃ��i�����Ə���j�v�ɋ��������Ă��邱�Ƃ���b��ɂȂ�A�l�X���͂O�R�N�̓~����}�t���[�Ƃ̃Z�b�g�Ȃǂ̉������i�N�̔��B�L�b�g�J�b�g�́u�S�l�ɂP�l����������Ɏ����Ă����قǂ̐l�C�v�i�L��S���ҁj�ƂȂ�A�O�V�N�̔��㍂�͂O�Q�N�̖�P�E�T�{�ɐL�т��Ƃ����B���̓~�͋��������ނƂ̎v�������߁A�T�c�}�C���̐l�C�i��u�Ȃ�Ƌ����v�̃N���[������荞�u��w�������v���i��]�������i�P�R�U�~�j���Q�X���ɔ�������B
�@�O�S�N����̉������i��̔�����i�J�����A�u�����Â��̑f�v�̑��ʃT�[�r�X�Ƃ��āA�p�b�P�[�W���ʂɁu��g�v�u���g�v�̂��݂����������u�J���[���Â��v�P�܂����������i�����Q�Q���ɔ�������i���Q�R�P�~�j�B�J���[�́u��[�v�̌�C���킹���������B�|�b�J�R�[�|���[�V�����͂P�T���A�g�����ɖ��J�̍����f�U�C�������X�[�v�Q��i���Q�S�P�~�j������B�i�J����|�b�J�͖�H���v��������ł���A�u���ɖ�H�ŐH�ׂĂ�����āA����グ�͌����v�i�i�J���L�j�ƍ��N�����҂��Ă���B
�E�T�M�����S�@���Ȃ��e��������
�i�ǔ��V���@�P�Q���P�P���j
�@�����S�̔���E�T�M�̎��Ɍ����ĂĂނ��u�E�T�M�����S�v�B���ٓ��̒�ԂƂ�������E�T�M�����S�̍�����m��Ȃ��e���オ�R�T��������Ƃ����������ʂ��܂Ƃ܂����B�����͐X���̐ʔ̔��Ǝ҂�ł���u�X����c��v���P�P���Ɏ��{���A�S���̂P�O�`�U�O�Α�̒j���S�O�O�l������B
�@���̂����A�Q�`�P�Q�̎q�����Q�O�`�S�O�Α�̒j���X�T�l�ɁA�E�T�M�����S�ɂ��Đq�˂��Ƃ���A�u�������킩��Ȃ��v�u���Ȃ��v�Ɠ������̂��Q�X�l�i�R�O�E�T���j�����B�u�m��Ȃ��v�i�S�l�j���܂߂�ƁA�q��Đ^���Œ��̐e����̂R�S�E�V�������Ȃ����ƂɂȂ�B�T�O�`�U�O�Α�ł́A���Ȃ��l�͂Q�O�E�U���B�T�O�`�U�O�Α㏗���Ɍ���A�u���Ȃ��v�͂S���̈���A�V�Q�����u���̂����Ӂv�Ƃ��Ă����B
�@�����Ȃ̉ƌv�����N��ɂ��ƁA�����S�̍����P�l������̔N�ԍw�����ʂ́A�P�X�W�U�N�̂S�E�W�L���E�O��������Q�O�O�T�N�ɂ͂S�E�O�L���E�O�����Ɍ����B�����c��̒����ł��A�u�W���[�X����H�i���܂߁A�����S���ǂ̂��炢�̊����ŐH�ׂ邩�v�Ƃ̖₢�ŁA�U�O�Α�͂Q�Q�����u�قږ����v�Ȃ̂ɑ��A����e����̂S�P���́u���P��ȉ��v�������B
�@�����c��́u��N�w�̃����S���ꂪ�w�E�T�M�����S�x��m��Ȃ��l�̑����ɂȂ����Ă���v�Ǝw�E����B
�������S�̔�ނ����������Ƃ̂Ȃ��q�ǂ��������Ă���̂��ނׂȂ邩�ȁB��