

NO.268

2008年 3月15日
アクセス教育情報センター
目次
|
学校情報 |
学校情報 | 入試情報 | 教育情報 | 教育情報 |
| 浅野中 | 玉川聖学院 | 入試結果5 | 経済力と学力 |
公立中高一貫
その他 |
学校情報
浅野中 春の学校説明会
1回 5月17日(土) 12:30~14:00
2回 5月17日(土) 14:30~16:00
3回 5月19日(月) 11:00~12:30
4回 5月20日(火) 11:00~12:30
5回 5月21日(水) 11:00~12:30
6回 5月22日(木) 11:00~12:30
説明会終了後、学校施設見学会あり。
定員 各回とも500名。5・6年生の保護者優先。
申込方法 往復はがきにて
申込期間 4月8日(火)~4月22日(火) 消印有効
詳細はホームページにて
http://www.asano.ed.jp/
安田学園 新校長インタビュー
(全私学新聞 1月13日号)
企業出身の鈴木行二・安田学園中学・高等学校長(東京都墨田区)は昨年一年間、顧問の立場で、学校運営の様子を見てきた。そこで、「学校現場の素晴らしいところをさらに生かしながら、民間の(考え方の)いいところも取り入れて、明確に改革を行っていきたい」と考えている。校長就任に当たって、教師として心得ておくべきこととして教職員に示したのは、(1)建学の精神・教育の理念を大切にする(2)学園の伝統を守る(3)学園はだれのために存在するのかを忘れない(4)教育の担い手としての自覚を持つ(5)情報は正しく速やかに収集し、各人の責任の所在を明確にする(6)コンプライアンスの考え方を導入する(7)学園の財政基盤の安定に努める(8)生徒及び保護者や同窓会、塾など外部との対話を重視する――だ。「学校運営の基本はクラス運営にある」と指摘し、現在取り掛かっているのが、クラス運営強化のためのマニュアル作りだ。
同校では、各種資格試験・検定試験合格のために力を入れている。最近、大学への進学率の向上に併せて、バリューフィールド構想に基づいた満足度の高い授業の実現に向けて、平成十七年より新中高一貫制度をスタートさせた。現在、普通科は特別進学、進学選抜、総合進学の三コース制を軸に進学体制を整えた。同校は基礎学力向上とともに、『人間力』(生きるための力)を養うために、冊子 安田学園流生きるための言葉『人間力をつける』(ホップ・ステップ・ジャンプ編の三冊)をこのほど作成し、在校生全員に配った。ホップ編では、生徒からの悩みに答えるという形で、生命、誠実、感謝、家族、友情などについて考え、ステップ編では、先生と二人の生徒が各テーマについて語り合う形式で進んでいく。ジャンプ編では、クイズ風の問いかけに自分なりに考え、親孝行、判断力、戦争、責任、人間関係について学ぶようになっている。来年から、中学一年から高校二年まで朝のホームルームで取り扱う方針だ。同校は「実業界にとって有用な人材の育成は社会発展の基礎である」という創立者、安田善次郎氏の信念の下に大正十二年に設立され、今年、創立八十五周年を迎える。鈴木校長は教職員に示した方針の実現のために自らも全力で取り組んでいる。
http://yasuda.netty.ne.jp/
大妻多摩 入試報告会(3月4日)
1.入試報告
① 2008年度入試総括・・・入試対策部 小澤剛先生
(ⅰ)出願者数増加 18年度1040名→19年度833名→20年度1047名と出願者は増加した。増加の原因としては、①2007年度の大学進学実績が良かったこと ②メディア・書籍での取り上げ ③10月にホームページのリニューアル(記事も随時更新) ③受験のしやすさ等があげられる。(筆者としては、在校生の様子や評判も増加の一因と思う。)
(ⅱ)入学手続き率については、第1回では昨年より減少(71%→61.4%、17年度は約80%)し、第3回は増加(56.1%→68.6%)した。全体としたは昨年より少し減少したが、一昨年並だった。今年度は第1回の受験生に第1志望者が多いとは限らなかった。合格最低点は60~65%で第1志望者には厳しかったか?
招集日前日の2月8日に6名の繰り上げ合格者を発表する(昨年12名)。
(ⅲ)昨年の大手模擬試験での志望者動向は、9・10月は一昨年と変わらず、11月から増加した。大学受験の実績だけでは判断しないのか?併願校は横浜富士見ヶ丘(午後入試等)が新たに加わったが、他は例年とあまり変わらなかった。
(ⅳ)算数の平均点が出題者の予想より良かった。
② 2009年度入試について
(ⅰ)試験日程の変更・・・第3回試験を3日から4日に変更し、2月1・2・4日になる。
(ⅱ)募集定員・・・140名で変更なし。
(ⅲ)オープンスクール・・・6/14(土)10:00~(要予約)
入試説明会・・・・・・10/15(水)10:30~12:30
11/8(土)9:30~11:30 (算数ワンポイント講座あり)
学校説明会・・・・・・10/26(日)10:30~12:30(はじめて日曜日に開催)
11/25(火)10:30~12:30
入試直前の1/7にも予定
サポートプログラム・・・算数の添削指導を秋以降に実施
③ 2008年度入試問題について
試験時間と配点の変更・・・国語・算数は各60分→各50分、理科・社会は各30分・50点→各40分・60点に。
国語科船橋先生、数学科松田先生、理科大塚先生、社会科海野先生から各科目の今年度の入試問題についての講評がありました。
国語・・・題材として取り上げる文章は小学生が読む本ではないが、作問で小学生が正解にできるように工夫した。記述問題で合否の差が出た。
過去に出題した文章・作家のものは出題しない。漢字は、今年度からは過去4年以内に出題したものは出題しない。
漢字は本文中で出題した(例年は最後にまとめて出題)。カタカナの書き方に注意。
算数・・・(ⅰ)動点の問題は必ず出題する (ⅱ)規則性、場合の数などの思考力を問う問題 (ⅲ)整理・作業を問う問題(細かい作業のできる努力家を)
50分になったので、大問を1問減らした。計算問題は項数を減らしたため正答率が80%→90%に。全体としても算数の出来は良かった。以前の難問といわれた問題等は出題しない。来年以降も難易度を変えず、60%を超える平均点にしたい。
面積や体積の問題で、合否の差がつく。
合格点をとるためは①計算ミスをしない。②図形問題の十分な練習。③規則性の見つけ方。④簡単(典型的)な問題を確実に正解する。また、秋から行われる算数サポートプログラムをぜひ受講してほしい。
社会・・・40分・60点になり、増えた10点分は小学校の教科書レベルの用語を問う基礎・基本問題を出題。30分位で解けるので、見直しを丁寧にしてください。記述・論述問題は3~4題で各3点。リード文を丁寧に読むこと。当事者意識で考える問題も出題。記述問題はよく書けていた。
時事問題は、予想されるような問題を出題する。
理科・・・40分・60点になる。実験・観察に関する問題は、小学校では扱わない題材だが、知っていることから考えさせる問題を出題した。理科の受験対策をあまりしていない生徒が多かったように思われる。標準レベル問題をくり返し解き(特に過去問)、基本をしっかり理解してほしい。なぜだろう?と追求し、今まで習ったことを使って、どう解決するかを考える姿勢をもってほしい。
理科が不得手な生徒も、入学後学んでいくうちに変わっていき、理科に興味を抱く生徒も増えている。
2.学校長挨拶・・・・・安川校長先生
今年は大妻多摩中高の開校20周年で、大妻学院100周年です。記念行事を行う予定。3/24新校舎完成。
今年度の高校卒業生は3クラスで、来年度以降は4クラスで大学実績も一層期待される。大妻大進学者は1名。お預かりした生徒を、大妻多摩で楽しい6年間を過ごし、希望する大学へ進学させ、ご両親にお返ししたい。
今年度は日曜日(10/26)や1月(1/7)にも学校説明会を設けました。
3.質疑応答・・・・繰り上げ合格者の入学後の成績は様々(上位の生徒もいる)。他の合格者も入試での成績と入学後の成績が必ずしも一致しない。入学後の「大妻多摩で一所懸命やろう」とい意欲が大切です。
(報告 A.Is)
08年入試結果
第1回 第2回 第3回
2月1日 2月2日 2月3日
募集人数 50 50 40
応募者数 234 457 356
受験者数 228 342 192
合格者数 88 129 51
合格基準点
4科320 192 202 207
http://www.otsuma-tama.ed.jp/
共立女子第二 ユニーク教育
(全私学新聞 1月23日号)
共立女子第二中学・高等学校(関和彦校長、東京都八王子市)は昨年十二月二十一日から二十三日まで、八王子市・八王子東急スクエアビルのギャラリーホールで「第一回共立女子中学高等学校芸術展」を催した。土曜、日曜日にわたって、親子連れや創作した生徒たちが連れ立って訪れ鑑賞に浸っていた。受け付けでは、高校生が一生懸命入場者の対応に当たっていた。この芸術展は、クラブ活動の成果ではなく、また「芸術展」を意識したものではなく、日ごろの授業の中から創作された作品が出展されている。それは、同校が「女性の自立」を建学の精神に掲げ、〝生きる力〟の育成に力を注ぎ、中学・高校を通して、バランスの取れた教育を行うことを教育方針としているからだ。進学のための教科はもちろんだが、芸術・技術家庭・保健体育といった教科もおろそかにせず、全人的教育を展開しているところに表れている。「芸術展」はこうした同校の教育方針の中から生まれた創作展となった。
当日出展された作品は、高校三年を中心に中学生の優秀作品も含み、美術関係が六十点、書道関係が九十点に及んだ。この中には、「百人一首」を英訳したものや、屏風(びょうぶ)に書いたもの、篆刻(てんこく)、張り絵、切り絵、絵本作り、ドレス創作など、生徒たちが考えたさまざまな作品があった。中学、高校生とは思えないような書道の作品、奇抜なアイデアによる美術作品など、生徒の個性が光る作品が目についた。馬場浅雄教諭書道担当は「生徒たち一人ひとりの思いが作品に表れています。一面では修練、鍛錬の部分、他方、楽しさや作品制作の達成感、満足感を味わえるという、その過程が好きなようです」と、この「芸術展」にかける期待を語った。「写経では何回も失敗して泣きながら仕上げた生徒もいた」という馬場教諭の言葉からも、生徒の作品に寄せる思いがうかがえるようだ。
同校は現在、中学一、二年で国語五単位の中の一単位を書写として、高校では芸術教科の中の書道の授業を一年で二単位、二年でそれぞれ一単位履修することになっている。例えば、中学の書写の授業では、毛筆、硬筆を半々とし、二年生で「漁父辞」二百十一字を半切に書写し、全員軸表装にするのが伝統となっている。また、高校では、一年生で中国史、漢字五書体の歴史を小論文を通して学ばせながら、楷(かい)書体、行書体、仮名、篆刻の四本の柱を実技として学習している。二年生なると、隷書体、写経を中心に細楷、古典仮名の発展として作品制作を、三年生では半紙作品、陶器作品、全紙、または料紙などを使った作品を制作している。一方、美術では、中学一、二年に各二単位、三年に一単位を、高校では芸術教科の選択で一年に二単位、二、三年に各一単位を履修することになっている。中学の授業では、絵画、デザイン、塑像、版画などを使っての課題をこなし、高校美術ではけん玉のデザイン、ペインティング、張り絵、切り絵、絵本制作などを行っている。
「芸術展」を通して、地域の人たちに同校の教育内容、そして生徒の生き生きとした様子をアピールする絶好の機会となった。
http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/
実践女子学園 08年入試結果
1回 グローバル 2回 帰国
2月1日 2月2日 2月4日 全回合わせて
募集人数 110 35 115 15
応募者数 355 52 775 213
受験者数 322 41 402 131
合格者数 173 39 155 100
入学者数 134 22 101 24
合格基準点
4科300 132 127 151
3科300 113
(3科は国、算、英)
http://www.jissen.ac.jp/chuko/
玉川聖学院 09年入試要項概要
08年入試では2月3日が日曜日だったため、3日の入試日を2回に分けて3回入試を実施。09年は2月1日が日曜日のため、1回を2日に移し、2日、3日の2回入試に。
1回 2月2日 女子100名 2科4科 面接
2回 2月3日 女子 60名 2科4科 面接
08年入試結果
第1回 第2回 第3回
2月1日 2月2日 2月4日
募集人数 100 30 30
応募者数 263 373 311
受験者数 247 218 146
合格者数 126 70 42
合格基準点
2科200 138 150 138
4科400 268 304 262
http://www.tamasei.ed.jp/
東京家政大学附属 新校長インタビュー
(全私学新聞 2月13日号)
東京家政大学附属女子中学・高等学校(湯山隼之助校長、東京都板橋区)は、理想の二十五歳の「私」になるために、総合学習「ヴァンサンカン(二十五歳)・プラン」を導入している。湯山校長はこう説明する。「この総合学習は、同校が創立以来掲げている建学の精神『女性の自主・自律』の下に、自己を確立し、社会の中で自らの力によりキャリアを築いていく『二十五歳』という年齢を見据えた教育プランです」総合学習をきっかけに、卒業後の自分について真剣に考えるようになった、ということが言われるようになった。高校一年を(1)「研究プラン」、二年を(2)「体験プラン」、三年を(3)「ステップアッププラン」と位置づけている。(1)では、「二十五歳の私」についての作文作成、職業研究、大学の学部・学科研究、OG講演会、ボランティア研究を行う。(2)では、体験学習としてボランティア体験、オープンキャンパスへの参加、小論文研究などが行われる。(3)では、「二十五歳の私」のまとめ、大学出張授業、面接研究などが行われる。ボランティア活動は、高校二年生全員で保育園、幼稚園、福祉関係の仕事場などを中心に行っている。
同校は、中学一・二年を基礎学力期とし、中三・高校一年では英語・数学で少人数習熟度別授業を実施する「スタンダードクラス」と授業内容を深め、問題演習を多く取り入れた授業を行う「アドヴァンストクラス」に分かれる。そして、高校二・三年になると、文系・理系・総合コースに分かれ、それぞれの希望する進路を目指すことになる。同校には「スクールカウンセラー」とともに、専任の「スクールソーシャルワーカー」を置き、保健室と連携して指導に当たっているのが特徴だ。生徒や保護者の悩みを教師が一緒になって考え、解決していく考えだ。この考えは、中学一年生と保護者全員に対し個人面談を行っていることにも表れている。
湯山校長は、生徒に対しては、「前向きに考え、たくましく生きてほしい」と期待をかけている。学校としても、「教師がお互いに信頼関係を築いて、生き生きとした学校にしていきたい」と希望を持っている。
http://www.tokyo-kasei.ed.jp/
慶應中等部 新校長インタビュー
(全私学新聞 3月3日号)
慶応義塾中等部は1947年に創立された比較的新しい中学校だが、慶応義塾の一貫教育校として、その伝統を受け継いでいる。「戦後民主主義の下でどのように自由を根づかせたらいいのか、いかに自由を身につけた生徒を育てるかという課題に取り組んできました。その基本は、各々
の状況に何がふさわしいかを生徒が自分で考え、行動し、それに対して責任を取るということです」と齊藤部長は基本的方針を語る。中等部は慶應義塾で男女共学をいち早く取り入れているが、同時に、生徒を独立した人格とみて、教員と生徒は対等な人間であるということを強く意識しており、創立当初より教壇がない。それは、教員が学業を一方的に生徒に授けるという意識を取り払い、授業を通して、生徒も教員もともに学んで成長していくということを意味する。生徒が教員を「さん」付けで呼ぶことや、「守るべきこと・知っておくべきこと」はあっても校則に当たるものはないことは、その精神の表れだ。齊藤部長は「自由とは、本当に自分のやりたいことを発見し、実行に移すことだと思います。学校はその能力を養う環境を与える場です」と持論を述べた。中等部の教育方針は多彩な教育プログラム、ユニークな活動など学校行事に支えられている。2、3年次には週2時間、普段授業では取り上げない内容などを選択授業で実施している。また、球技を中心とする学年ごとの校内大会、林間学校、英国への海外研修旅行(希望者のみ)、陸上・団体競技などをクラス対抗で行う運動会、英国ホカリル校生との研修受け入れ、各学芸部を中心とした展覧会、クラスごとの音楽会(3年生は創作曲)など、中等部を代表する行事が多い。生徒総会は、全生徒が一堂に会し、学校生活をよりよくするための意見を集約し、学校に呈示する。同窓会の活動も活発で、中等部ひまわり奨学金は、授業料など経済的に学業を続けていくことが困難な生徒のために、資金面での援助もしている。齊藤部長は慶應義塾大学文学部教授(哲学博士)を兼ねている。
合同説明会
ミッション女子8校 入試結果報告会
日時 2007年3月29日(土) 10:00~12:00
場所 カリタス女子短期大学 大教室
参加校 カリタス、函嶺白百合、湘南白百合、聖セシリア、聖ヨゼフ、聖園、横浜英和、横浜雙葉
内容 パネルディスカッション
第一部 入試を語る -2009年度に向けて-
第二部 入試問題を語る(国語と算数) -現場からの生の声-
個別相談会
申込 各校のホームページからインターネットまたはFAXで
春一番 合同相談会 25校が参加
日時 4月13日(日) 10:30~14:00
場所 立川パレスホテル4F
参加校 大妻多摩、桜美林、鴎友学園、共立第二、工学院大附、駒込中、駒沢学園、実践学園、実践女子、白梅学園清修、千代田女学園、帝京八王子、東海大菅生、東京純心、日本大学第三、富士見、藤村女子、文華女子、武蔵野女子学院、明治学院、明大中野八王子、明星中、明法中、目白研心、八雲学園
女子校アンサンブル 女子校9校が参加
日時 4月27日(日) 10:00~16:00
場所 学習院大学西5号館
参加校 跡見学園、学習院女子、恵泉女学園、香蘭女学校、実践女子学園、東京女学館、東洋英和女学院、三輪田学園、山脇学園
内容 基調講演、ミニ説明会、個別相談
http://www.gakushuin.ac.jp/girl/ensemble/
入試情報
入試結果5
これまでに判明した学校別の入試結果(抜粋)をアクセス教育情報センターの会員のページに掲載しております。
下記をクリックしてご覧ください。
教育情報
経済力と学力 学級担任の8割が影響を感じる
(朝日新聞 3月11日)
「家庭の経済力が、子どもの学力格差や進学に影響している」と感じる学級担任は8割――日本教職員組合(日教組)は10日、こんな調査結果を公表した。「影響がある」と答えた教員の比率が大きい都道府県ほど、昨年実施された全国学力調査の平均正答率が低い傾向にあったという。調査は昨年9~12月、35都道府県の小中高の学級担任3913人から回答を得た。結果によると、「家庭の経済力が学力に影響している」と感じる教員は、小学校81%、中学校84%、高校87%で、学校段階が上がるに連れて高くなった。都道府県によって回答数が異なるため単純比較はできないが、「経済力が影響している」と思う教員は、沖縄や大阪、北海道など、全国学力調査の平均正答率が低かった地域で多く、秋田や福井など平均正答率が高い地域では少なかった。
調査では、給食費や修学旅行費、副教材費などの未払い実態も聞いた。「未払いがある」46%、「ない」51%、「不明」3%。未払いへの対応を複数回答で聞いたところ、「そのままにしている」58%、「立て替える」30%、「その子は修学旅行や遠足に参加しない」11%だった。日教組は「所得格差があっても、公教育に影響が出ない条件整備が必要」と訴えている。
TOEIC 大学入試で3割が利用
(毎日新聞 3月12日)
大学や大学院など、全国の高等教育機関の約3割が、入学試験でTOEICの点数を利用していることが分かった。03年度から2倍以上増えた。TOEICテストを運営する国際ビジネスコミュニケーション協会(東京都千代田区)がまとめた。調査は07年9~10月、全国の大学、大学院、短期大学、高等専門学校に調査票を送付してTOEICテストの活用状況を聞き、計1769校が回答した。内訳は、大学721、大学院618、短大368、高専62校。
入学試験で優遇したり、出願資格の一つにしているのは計488校で、前年比45校増。同協会によると、AO入試で得点に加算したり、外国語試験の代替として認めているケースが多く、難関といわれる私大では600点から700点から加算対象にする大学もある。推薦入試などでは、高校卒業レベルの400点前後を出願資格にすることが一般的という。また、単位認定に使っている大学も前年より増えて435校になった。指定の点数を取らないと卒業できない大学もある。山口大学では、1年生は全員300~350点を取らなければならない。学部によってはさらに高得点が求められ、農学部の獣医学科などでは400点が2年生への進級条件になっている。
同協会は「90年代前半には、就職対策として、大学が希望する学生に受験を勧めるといった利用法が中心だったが、カリキュラムの一部として利用されるようになり、文系だけでなく、理工、農学部の利用も増えてきた」と話した。TOEICテストは1979年にスタート。06年度、受験者数は150万人を超えた。
全国学力テスト 私立参加率が大幅低下
(毎日新聞 3月13日)
来月22日に行われる全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)で私立学校の参加率が前年度比約8ポイント減の53.09%に低下することが、文部科学省の調査で分かった。私立小の参加率は前年度比約12ポイント減の50.0%、私立中が同7ポイント減の54.15%で、全児童・生徒対象とする全国学力テストの意義が問われそうだ。
今年2月末現在の調査で、参加は国立157校(参加率100%)、公立3万2060校(同99.96%)、私立472校(同53.09%)。国公立の参加率は前年度と同じで、公立では今年も愛知県犬山市(小学校10校、中学校4校)だけが参加しない。私立の参加が少ないことについて、東京私立中学高等学校協会の近藤彰郎会長は「昨年テスト結果の公表が当初予定よりも大幅にずれ込み、子どもたちに(結果の)フィードバックができないと考えた私立が多いのでは」と分析。また、関係者によると、比較的簡単な問題が多いため私立にとってはテストに参加するメリットが薄いことや、全国一斉で1日をかける方法が「時間のムダ」と考える学校が多いという。文科省は「私立は母数が少ないので、全員参加のテストの意義が損なわれることはないが、テストの趣旨を理解いただけるよう周知していきたい」と話している。
全国学力テストは昨年、全児童・生徒対象のテストとしては43年ぶりに復活。小6と中3の児童・生徒約233万人が参加した。
授業妨害 心労で校長は休職、教頭は休養
(毎日新聞 3月13日)
福岡県田川郡内の公立中学校で、一部生徒による“授業妨害”が続き、校長と教頭が心労で体調を崩し休職や自宅療養する事態となった。管理職不在を避けるため、校長は今月1日に後任が着任した。生徒たちは2月末まで約1年間、校内の一室に“隔離”されていたが、現在は指導が事実上及ばない状態にあり、教育委員会は「混乱のおそれがある」として卒業式の14日、県警に警備の要請を検討している。
教委によると、これらの生徒は2、3年生の計8人。廊下の窓や校長室のロッカーを壊すなどの器物損壊や教師への威嚇行為を繰り返した。また、校内を徘徊(はいかい)しては訪れた保護者につばを吐きかけたり、2階渡り廊下から放尿したこともあったという。学校側は生徒たちを美術準備室に個別断続的に“隔離”したが、生徒はテレビゲームや電熱器、ラジカセなどを自宅から持ち込み、喫煙や飲食するなど事実上のたまり場となったため、2月末に準備室は閉鎖された。現在も生徒たちは登校しているという。この間、教頭は昨年末に約1カ月間休養し、2月下旬から現在まで自宅療養中。校長も2月上旬から病欠し、今月1日から休職した。ともに心労で体調を崩したという。所管する自治体の教育長によると、学校側は生徒らの親に話し合いを求め、生徒が一度は学校や親の注意を聞いても、仲間で群れると再び荒れ出したりするといい、結果的には改善できなかったという。
校長の病欠を受けて、教委は事故防止のため職員6人を連日学校に派遣。一部保護者も週1回、校内のたばこの吸い殻などを拾う活動を始めた。実態に憤る保護者は少なくなく、2月末の緊急保護者会では「生徒らを出席停止にしてほしい」との要望も出た。また、4月に入学する新1年生数人は、親類宅などから通う形で隣接自治体の中学校への進学を決めているという。
関連記事
授業妨害中3と中2、2人を逮捕(毎日新聞 3月15日)
福岡県田川郡内の中学校で男子生徒8人が授業妨害を繰り返し、校長と教頭が休職・自宅療養となっている問題で、県警田川署は14日、グループの3年生(15)と2年生(14)を暴力行為等処罰法違反容疑で逮捕した。2年生は校長室の湯飲みを割り、3年生は校長用ロッカーをけって壊した疑い。2年生は容疑を認めているが、3年生は「ロッカーを足で閉めただけ」と否認しているという。
横浜市立小卒業生 19%が私立中へ
(毎日新聞 3月14日)
横浜市立小を卒業する6年生のうち、過去最高の19%が4月から私立中学校に進む予定であることが、市教育委員会が13日に発表した進路状況調査結果で分かった。市教委教育政策課は「私立大が付属校を増やし、選択の幅が増えているのでは」と上昇傾向の理由を推測している。3月卒業予定の3万671人を対象に、2月15日時点での予定を調査した。19・0%に当たる5819人が私立中に進学する。調査を始めた1960年度以降で、これまでの最高は03年度の18・8%だった。10年前の97年度は15・7%、20年前の87年度は9・1%だった。
区別で、最も私立中への進学率が高いのは青葉区の32%。2番目は都筑区(25・2%)、3番目は港北区(25・1%)で、私立中の多い東京都内に通いやすい市内北部の区が並んだ。
公立中高一貫 香川県、高瀬のぞみが丘中の募集停止
(四国新聞 2月10日)
信念なき苦渋の決断
2年連続の定員割れで、2009年度からの募集停止が決まった高瀬のぞみが丘中学(三豊市高瀬町)。県立では県内2例目の中高一貫教育校として産声を上げてわずか6年。この3月には、その1期生を大学や社会へと送り出す矢先のことだった。決定から2カ月半。定員割れによるケースとしては全国初という募集停止の周辺を探っていくと、県教委の「苦渋の決断」に疑問がわくばかりだ。
責任回避の県に募る不信
「学校としては、今の教育環境の質を落とさないよう全教員で取り組んでいくしかありません。県教委にはそのための教員配置や予算の配慮をお願いしていきたい」。休み時間の生徒の声が響く校舎の一室。のぞみが丘中の福本常雄教頭は、悔しさをにじませた。「ゆとりある環境」「豊かな人間性の育成」などをコンセプトに、高瀬高への併設型中学として2002年に新設された同校。初年度は競争率2・35倍の人気だったが、その後徐々に志願者は減少し、06、07年度と2年連続で定員の80人を下回った。「PR不足」「地元意識の強い地域性」「学力重視を求める保護者ニーズと学校の理念との開き」。国がゆとり教育の方針を転換した大きな流れも含め、人気が低迷した背景にはさまざまなことが言われている。
突然の通達
学校側はこうした分析を受けて、近隣市町の小学校にPRして回る一方、県教委と協議して英数の授業を増やしたり土曜課外を設けたり、高校生が中学生に学習のアドバイスを行うチューター制度を導入するなど、学力向上に向けた取り組みを強化してきた。その最中、突然の募集停止が県教委から伝えられた。昨年11月20日、午前中に開かれた教育委員会の定例会で、県教委は同校の募集停止について諮った。県教委のホームページに残る議事録を読むと、委員からはさしたる反対もなく、募集停止の方針が決定している。「委員とはこれ以前から勉強会を開き検討を重ねてきた。しかし、8月の体験入学に来た小学生の数を見ると、3年連続の定員割れは免れない状況だった」と県教委高校教育課。結局これが決定打となり、「このままでは在校生の教育環境や高瀬高にまで影響が及びかねない。将来の小中学校の統廃合を視野に入れれば、現在その基準を示す時期にきており、一クラス40人の定員を崩すわけにもいかなかった。充実した環境をキープできる体力があるうちにという苦渋の決断」に至ったという。
しかし、水面下で募集停止の話が進んでいることも知らず、必死の建て直しを模索する学校側にとっては、まさに寝耳に水の出来事。県教委は「ぎりぎりまで知らせなかったのは、現場を動揺させてはいけないという判断だった」と理解を求めるが、その日の午後、正門前を撮影するテレビ局のカメラを見て募集停止の事実を知ったという職員や保護者にしてみれば、県教委の“善意”は、不実としか映らない。同校の今後について、「在校生がいる限り、今まで通り中高一貫教育の特色を生かした充実した教育ができるよう支援する。教員の加配など人事面での配慮も検討したい」と、県教委は手厚いケアを約束している。
憤る保護者
「そもそも最初は地元は抵抗した。将来子供の数が減ることは明らかで、高瀬中と取り合いになる。それを県に押し切られた形なのに、卒業生の1人も出さないうちに…」。同校の設立の経緯を知る三豊市議は、当時の様子を振り返る。少子化承知で地元の抵抗を抑えて新設し、二回の定員割れにより、卒業生を待たず廃止。「これが企業なら社長が責任をとっている。県はだれが責任をとるのか」。保護者の1人は憤る。募集停止を受けた11月28日の保護者説明会では、会場から県教委の責任を問う声が上がった。これに対する県教委の回答は「現在、平成21年度からの募集停止について関係者に説明している。生徒が充実した6年間の学校生活を送り、個性を伸ばすことが最も重要である」と、まったくの的はずれ。高校教育課にさらにただすと、「さまざまな意見を聞き、議会の承認も経て開校したもの。特定のところに責任を押しつけられるものではない」と、言葉を濁す。保護者会では、募集停止の撤回を求める要望書を県教育長と県議会議長に対して提出しているが、「卒業生もいない状態では署名活動しようにも広がりが期待できず、力不足を悔いるばかり」と、十川圭次会長はうなだれる。
他県から拙速の声も
同様のケースを探ろうと、近隣の七県一市に取材を試みた。愛媛と徳島でも今年初めて定員割れとなった中学が出たという。高知でも定員ぎりぎりという中学がある。岡山では、既存の中学と高校を組み合わせた「連携型」と呼ばれる一貫教育を敷いているケースがあるが、高校の方は連携以前の12年前から定員割れが続いている。 「しかし、すっぱりあきらめたもの。驚いている。うちならもっと時間をかける」。取材した担当者の中には、今回の香川の決断をホームページで知っていて、経緯を逆取材してくる人も。 ほかにも、「高瀬高にまで影響が出ないうちにという理由が分からない。特色は薄まるかもしれないが、他の中学から進学する子で高校の定員はカバーできるのに」「12年定員割れでも、あくまで存続を前提に今後を検討中。香川の事例を参考にするつもりはない」「廃止の決定以降にあった最後の募集で50人の志願者があったのが驚き。ニーズがあることの証明。香川県は一貫教育の成果について検証を続けているのか」など、疑問、苦言が相次いだ。
欠いた展望
他県の担当者が指摘するように、廃止が決まったにもかかわらず、のぞみが丘中には今年度50人の志願者があった。「確かに入学した生徒や保護者からの満足度は高く、方針自体は間違っていなかった」と県教委も強調する。ならば設置責任者として、その教育方針や理念を伝える努力をもっとすべきではなかったのか。一連の取材から見えてくるのは、中高一貫教育、さらには公教育に対する県教委のビジョンのなさだ。学校側は、小学校へパンフレットを持って行っても「のぞみが丘中だけ宣伝するのは平等性を欠く」と門前払いをくらうなど、PRも困難な状況だった。建て直しは事実上学校任せ。その現場を無視して突然の募集停止。責任の所在も明らかにしないのでは、不信感はぬぐえない。
国公立大学への進学者が10人程度という高校に中学を新設して、4年前から一貫教育を始めた広島県福山市では、市を挙げてPRに取り組んだという。「この中学をリーディング校にして公立中学全体を引っ張っていく。市としての姿勢をしっかり示さなければ、市民の理解は得られない。ボランティアの回数や部活加入率など細かな数値目標を掲げ、“こんな6年間にしたい”という理想をとことん説いた」。競争率六倍という人気の背景には、設置者の断固とした信念が感じられる。
必要な検証
全国の中高一貫教育校は、昨年4月時点で257校。1999年度に中高一貫教育制度が導入されて以来、年々増え続けている。文科省では今回の募集停止を把握していたが、「存廃はあくまで設置者である都道府県の判断。あれこれ言う立場にない」(教育制度改革室)と、制度導入の当事者とは思えないつれない返事だ。
中高一貫教育の現状について、香川大学教育学部付属教育実践総合センターの山岸知幸准教授は、「制度開始から9年が経ち、成果や問題点を整理するべき時期」と指摘する。「地方の中には同じような定員割れに悩む学校があり、地域的な格差も出始めている。理念や学校の特色をいかに具体的レベルで伝えることができるか。そして、学校の存在に対して地域の共通理解を得られるかどうかが、今後の中高一貫教育を定着させる重要な鍵になる」。 苦渋の決断は、早すぎた決断ではなかったのか。「理念を持って設置したもの。どんな子供が育つかで判断すべき」。募集停止決定以来、動向を注目してきたという他県の担当者はそう言い切った。 高瀬のぞみが丘中から高瀬高へ―、6年間の薫陶を受けた一期生が学舎を巣立つのは3月7日。香川の中高一貫教育の成果が示されるのは、本当にこれからだったはずだ。
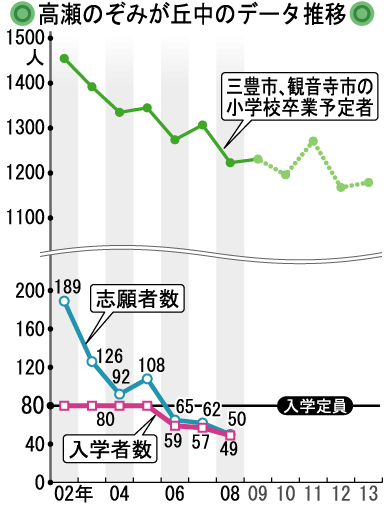
その他
名言・迷言・冥言
(東野圭吾 さまよう刃より)
警察は法律を犯した人間を捕まえているだけだ。警察は市民を守っているわけじゃない。警察が守ろうとするのは法律のほうだ。(中略)ではその法律は絶対に正しいものなのか。
総合学習も塾で 公教育のもたつき尻目に
(産経新聞 2月18日)
「さようなら、(上底+下底)×高さ÷2」現行の学習指導要領が告示された翌年の平成11年秋、大手学習塾の日能研(本部・横浜市)はこんな宣伝文句のポスターを作製した。上底…は台形の面積を求める公式で、イラストでは、指導要領が施行された「2002年」のバス停で降ろされた台形が、別れのハンカチを振っている。「円周率が3になる」も同社のコピー。子供の学力低下に対する親の不安をあおり、私立中受験へと駆り立てた。
「円周率が3・14ではなく3になるなんて、ばかな話が出回って…。実際は『目的に応じて3を用いてもいい』としただけだ」。告示当時の文部大臣、有馬朗人氏(77)は、今でも苦い顔をする。「塾からの批判は、少子化の時代にいかに子供たちを集め、自分たちや私学を守るかという発想だ。この時期に、『公教育はゆとり』だと解釈がねじ曲がった」
◇
その日能研が、ゆとり教育の目玉だった「総合的学習の時間」(総合学習)をカリキュラムに取り入れている。「この問題どうやって解こうか」「僕はこうする」「私は違う。ここに線を引いた方がいいよ」-。先生の力を借りずに、5、6人の児童が1つのチームを組んで図形問題の解法に知恵を出し合い、「一番いい解き方」を探している。見つかったら、他のチームと互いに発表して比べ合う。先生は最後まで、解き方を教えてくれない。これは日能研が4年前から首都圏の一部教室で開設する「Rコース」(小4~6年対象)の光景だ。あらかじめ用意した答えに児童を導かないことが特徴で、高木幹夫代表(53)は「自ら学び考える力を育てる授業。『総合学習』そのものだ」と話す。
こうした要素を一部取り入れる傾向は他の塾でもみられる。その理由は、「私立中や公立中高一貫校の入試が、単純な知識より応用、活用力を試すPISA(生徒の国際学習到達度調査)型になっている」(栄光ゼミナール)という状況があるからだ。その活用力こそ、現行の指導要領が「生きる力」などの呼び方で育成を目指したはずのものだった。公教育のもたつきを尻目に、民間が公教育を利用し、先を行く現実が垣間見える。
◇
昨年4月に文部科学省が行った全国学力調査では、公立と私立の格差が改めて浮き彫りになった。平均正答率(小学6年)を比べると、基礎力を試す算数Aは公立82・1%に対し、私立は10ポイント高い92・1%。応用力を試す算数Bは公立63・6%、私立77・1%で、差は13・5ポイントと大きく開いた。国語も同じ傾向。私立は上位校の多くが参加していない。
田村哲夫・渋谷教育学園理事長(71)は、私学の立場から、「高いお金を払う私立と、タダの公立とで『同じ結果を出せ』と押し付けることは間違いだ」と、単純な公私格差批判をいましめる。だが、「公立の代わりに私立」という選択肢があるのは、首都圏など都市部にほぼ限られるのも事実で、公教育の再生が急務であることに変わりはない。
渡海紀三朗文科相は、新指導要領案を公表した際の会見で「公教育への不安があるとすれば、学力低下と、学校現場の荒れだと思う」との認識を示し、「今回の改定で道徳教育は充実し、学力も向上するような方策を打った」と述べた。ただ文科相からのメッセージでも「今は『とにかく期待してください』としか言いようがない」というにとどまっている。