

NO.128

2004年 3月15日
アクセス教育情報センター
目次
|
学校情報 |
教育情報 | その他 | |
| 大妻多摩 | 公立中高一貫校 | 中教審委員を辞職 | 寄稿 無知な父母へのメッセージ |
学校情報
大妻多摩 大学入試結果速報(3月12日現在)
前期で国公立現役合格10名。
04年大学入試結果(抜粋)
東大 一橋大 東工大 東外大 大阪 都立大 国公立計
総数 1 1 1 1 1 2 10
現役 1 1 1 1 1 2 10
早大 慶大 上智 明治 青山 立教 中央 法政 理科大
総数 23 22 12 13 15 20 15 10 10
現役 21 22 12 11 14 20 14 10 9
卒業生122名に対する東大、早慶上への現役合格者数の割合(A率)は45.9%。
03年のA率は27.5%。
http://www.otsuma-tama.ed.jp/
品川女子学院 大学入試結果速報(3月8日現在)
MARACHへの現役合格者数が3倍増に。この学年は英語の先生の指導がよかったらしい。
04年 03年 02年 01年
早慶上 37名 21名 13名 6名
MARCH 94名 33名 29名 22名
早慶上への現役合格者の卒業生(214名)に対する割合(A率)は17.3%。03年のA率は9.3%。
MARACHへの現役合格者の割合は43.9%に。
http://www.shinagawajoshigakuin.jp/index.html
洗足学園 大学入試結果速報(3月9日現在)
早慶上の現役合格者数が昨年の22名から53名に。
04年大学入試結果(抜粋)
東外大 東医歯 筑波 千葉 都立 奈良教 国公立計
総数 1 2 1 1 2 1 11
現役 1 1 1 1 2 1 9
早大 慶大 上智 明治 青山 立教 中央 法政
総数 24 21 8 14 27 15 9 14
現役 22 20 8 14 27 15 9 14
卒業生225名に対する東大、早慶上への現役合格者数の割合(A率)は22.2%。
MARCHへの現役合格者の割合は35.1%。
03年のA率は9.5%。
http://www.int-acc.or.jp/senzoku/
穎明館 大学入試結果速報(3月10日現在)
東大前期で現役合格6名。
04年大学入試結果(抜粋)
東大 京大 一橋大 東工大 東外大 東北 千葉大 国公立計
総数 6 2 1 8 1 2 2 36
現役 6 0 1 5 1 1 1 25
早大 慶大 上智 明治 青山 立教 中央 法政 理科大
総数 45 29 18 38 15 7 35 11 25
現役 36 20 12 23 9 4 22 7 16
卒業生189名に対する東大、早慶上への現役合格者数の割合(A率)は39.2%。
03年のA率は38.9%。
http://www.emk.ac.jp/
教育情報
公立中高一貫校 京都の2校10倍超の「狭き門」
(京都新聞 1月31日)
公立の中高一貫校として4月に開校する京都府立洛北高(京都市左京区)と京都市立西京高(中京区)の各付属中で31日、入学試験があった。ともに倍率が10倍を超える「狭き門」で、児童が作文・製作の問題や面接に挑んだ。
西京高付属中には午前9時25分の試験開始を前に、1375人が各教室にそろった。担当者から試験に関する注意点を聞いたあと、真剣な表情で問題を解いていた。洛北高付属中でも820人が問題に取り組んだ。午後からは両付属中ともグループ面接があった。
洛北高付属中では、生ごみと環境のかかわりをテーマにした文章を読み、みずからの体験を交えて設問に答える問題などが出た。西京高付属中でも、ごみ問題が取り上げられた。
受検倍率は洛北高付属中が10・25倍、西京高付属中は11・46倍だった。合格発表はともに2月4日。抽選で決定する。府内の私立中学校13校でも同日、入学試験があった。
公立中高一貫校の波紋(1月21日)
今回の特集は、受験戦線の大きな異変です。
この春、京都で、中高一貫教育をめざす公立の学校が開校しますが、いずれも競争率は10倍を超える超難関となりました。中学から高校までの6年間を同じ学校で学ぶ中高一貫校は、受験対策に有利とされ、これまで私学の独壇場でしたが、ついに公立の巻き返しが始まるのでしょうか。
京都市南区に住む小学6年生の田中悠樹君(12)。
「医者になるのが夢」と言う田中君は、中学受験を目前に控えています。猛勉強の真っ最中ですが、机の上に算数や国語といった問題集はありません。田中悠樹君「自信はあるけど、どんな作文出してくるか分らんし。自分の思いを相手に伝えることができたらと思う」
田中君が目指しているのは私学の有名校ではなく、公立の中高一貫校です。京都では4月から、府立洛北高校と市立西京高校が付属中学を新設します。中学から高校までの6年を通じて同じ学校で学ぶ中高一貫教育なんですが、受験競争の低年齢化を避けるため学力検査は行わず、「作文・製作」と「面接」で適正検査を行います。田中君の両親も中高一貫校に期待を寄せています。
母・田中祥子さん「作文でとってくれるということで、勉強だけの子どもの集まりじゃない環境で、もまれてほしい」
実績のない公立の中高一貫校ですが、フタをあけてみればその人気は驚異的でした。先週、洛北高校付属中学では募集定員80人に対し874人が志願。競争率は10.9倍、西京高校付属中学は11.8倍となりました。
京都の私学の難関校として知られる洛星中学でさえ、3.4倍にとどまっています。
受験生の親「今までは私学しかなかったので限られた人しかいけない。高校受験もないし、ゆとりを持って勉強できるのでは」「うちの子は塾に行ってないので、いちがばちかの大勝負」
洛北高校付属中学校・勝間喜一郎校長「高校受験ないので6年間を通した教育できる。教育的にも様々なメリットがある」
洛北附属中学では、数学と理科を融合した独自の科目を取り入れたり、高校の教師に兼務発令を出して、科目によっては高校の授業内容も教えます。また、西京附属中学は教師を市内から公募し、校長自らが面接して選抜しました。
私学型の中高一貫教育に公立校が踏み切ったのは、年々高まる一方の私学人気を食い止め、公立校の存在感を打ち出したいという思惑がみてとれます。
府立洛北高校は 前身の府立第一中学時代に、湯川秀樹や朝永振一郎といったノーベル賞受賞者を輩出した伝統校です。当時、生徒の多くが京都大学に進学しました。ところが、蜷川府政時代、「15の春は泣かせない」と、公立高校のレベルの均一化を図ったために、大学受験を意識した生徒たちが私学に向かいました。
以来、私学優位の流れは強まる一方でした。
こうした中、初めて入試を行う洛北高校附属中学は、あえて試験日を主な関西の私学と同じ日にぶつけ、真正面から勝負を挑みました。
洛北高校付属中学校長「将来どう生きたいかが問題。京大に行きたいなら入れる義務はあるが、それだけを目標にしていない。大学はあくまでも途中過程」
公立の中高一貫の動きを歓迎する塾もあります。この学習塾では、去年10月から公立の一貫校を意識して作文対策を始めました。
洛南学舎・井尻良英塾長「今すぐ勉強できる子どもと、しっかりしたものの考え方ができる子を、複線で育てていけるので、大きな可能性の進歩」
大学受験で高い実績をあげている私学の中高一貫校の受け留め方は…。
洛星中学高等学校・村上哲哉教務部長「我々がやってきた中高一貫が評価されたのでは。公立中高一貫校の卒業生が社会に出て高い評価を受けると脅威。10年先が勝負」
公立であれ私学であれ、初めての受験は子どもにとってプレッシャーに変わりありません。
田中悠樹君「すごいプレッシャー。お母さんはよく全部あんたにかけていると口にするんです」
父・敏弘さん「結果出なくてもいい。自分を全て出してきなさい」
田中悠樹君「めちゃくちゃプレッシャーやけど頑張ります」
そして最後はやっぱり神頼み。試験日までは、あと10日です…。
洛北は思考力・知識幅広く 、付属中入試 西京は学習の力見る
(京都新聞 1月31日)
京都市内で4月に開校する公立高付属中の入学試験で31日、府立洛北高付属中は、児童に多数の立体図形や解説文、地図などを読み込ませたうえで、幅広い分野から思考力や知識などを見る問題を出題した。設問も計13題と多く、同日実施の市立西京高付属中の計4題を大きく上回った。
洛北高付属中では、試験を「作文・製作I」「同II」「同III」として各50分間で実施した。情報化社会をテーマにした内閣府の調査結果の特徴と原因について記述する問題や、12の図を示したうえで、立体作品の高さを求めて理由を文章や図、式で表す問題などがあった。
学校教育法規則は、受験競争の低年齢化を招かないため、中高一貫の公立中入試で学力テストを原則として禁じている。同中は「物事を整理、分析し、自分の考えを的確に表現する力を見た。小学校の6年間で学んだことや日常生活で身についたことで、十分に解けると考えている」としている。
西京高付属中は「作文・製作I」「同II」として各45分で実施。将来どの分野で活躍したいかをテーマに自分をアピールする作文や、指定された面積と体積にあう直方体容器の図面を方眼紙に書く問題などだった。同中は「学力検査のイメージを排除し、小学校の日ごろの学習の力を見る設題にした」という。
=来年スタートする都立中高一貫校も開校説明会や模擬問題の説明会への参加者数からして相当な倍率になるものと予想される。ただ見かけ上は私学が行っている中高一貫と同じように見えても、中高一貫の内容の深さが全く違うことを予期しておいたほうがよいと思う。=
小中一貫教育 全校で4・3・2制へ、東京・品川区
(毎日新聞2月15日)
東京都品川区は06年度から、区立の小中学校全校で、9年間一貫教育のカリキュラムを実施することを決めた。大崎地区で準備中の小中一貫校の開設に合わせて導入する。来年度予算案にカリキュラム開発費など1347万2000円を計上した。
区は、06年度に大崎地区の第二日野小と日野中を再編し、小中一貫校を新設。07年度には大井地区の原小と伊藤中でも開設する予定。
同区の小中一貫教育は、9年間を従来の「6・3」制ではなく、「4・3・2」で区分する。1〜4年生は学級担任制で基礎・基本の徹底に重点を置き、5〜7年生は教科担任制で個性や能力に合わせた学習を実施。8〜9年生は自ら学ぶ主体性を重視し、道徳と特別活動を合わせた「市民科」も設け、進路選択に役立てる。
区教委は「一貫校以外の学校でも一貫教育をしてほしい」という保護者の要望があったとして、一貫教育の拡大を決定。学校側の準備態勢も必要なため、06年度に全教科での実施は難しいが、1教科ずつなど学校の実態に合わせて導入を進めていく方針。
◇杉並も一貫校開設に着手
また、杉並区も小中一貫校の開設に向け、来年度からカリキュラム開発に着手する。読み書き、計算を含む基礎・基本の確実な定着を目指す教材を開発したり、小学校段階での英語教育導入を検討する。
=中学入試に携わっている者の目からすると、中学校1年での子供の成長を見ると小学校6年と中学校1年で分ける方が自然に思うのだが。初等教育と前期中等教育とは区別されてしかるべき。もっとも品川区を始め東京の各区の小中一貫構想は中学受験をするのを阻止するところにあるのだから、子供の発達段階に考慮するより行政の都合が優先するということであろう。=
海陽中等教育学校 トヨタなど計画の中高一貫校
の校名
(毎日新聞 2月21日)
トヨタ自動車、JR東海、中部電力の3社が愛知県蒲郡市に設立を計画している全寮制中高一貫校(06年4月開校予定)について、3社関係者などで作る設立準備委員会は20日、学校名を「海陽中等教育学校」に決めた。今後、県への申請を経て正式決定する。
学校は同市海陽町の複合レジャー施設「ラグーナ蒲郡」内に設置する予定。男子の中高一貫校で1学年120人。地名や海を連想させる明るいイメージがあるとして、校名を「海陽」とした。運営する学校法人も「海陽学園」とする。同校は「将来の日本をけん引する、明るく希望に満ちた人材の育成」を建学精神とし、国際社会で活躍する人材育成を目指す。
同委員会は7月に県に設置計画書を提出し、来年秋ごろ学校法人の許可を得たいという。
公立中の絶対評価 5は最大7倍差 自治体間で格差
(毎日新聞 3月6日)
自治体間で大きい格差−−公立中の絶対評価調査
02年度から導入された中学校の「絶対評価」について、県教育委員会が、県内公立中学3年生の5段階評価の分布状況を調査し、市町村別に集計結果をまとめた。「5」の評価がついた生徒の割合は、教科によっては自治体間で最大7倍の格差があった。絶対評価は、県内公立高校の入試の合否判定資料にもなるが、自治体間で大きな差が生じている実態が浮き彫りになった。
結果は、県教委が昨年8月、県内の公立中3年の今年度1学期の学習評価について、1〜5の評価を受けた生徒の割合をまとめた。
絶対評価は、02年4月から導入された。生徒が学習目標をどこまで達成できたかで評価する。全員が達成できたと判断すれば、理論上は全員に「5」をつけることも可能だ。
自治体間で評価の格差が生じた原因として、県教委は、評価の細かな判断基準を各市町村教委が指導していることなどを挙げる。「5と4の境目は微妙で各校の判断によるところもある」と話す。
入試で合否判定の資料となる調査書は、04年度から県内すべての公立高で、絶対評価を使うことになった。学力検査をせずに面接、作文などで選考する前期選抜では、調査書の点数が重視される。後期選抜でも調査書と学力検査の割合は、6対4と比重は大きい。
県教委は「絶対評価の意義は認めており、選抜資料に使うことに問題はないと考える。公平性に不信感があるなら、評価の付け方を改善するように検討する」と話している。
県内公立中3年生の今年度1学期の「5」の割合(抜粋 数字は%)
国語 社会 数学 理科 英語
横浜市 15.5 14.3 17.2 14.4 19.7
川崎市 11.5 12.8 12.8 11.8 15.4
横須賀市 9.6 12.1 12.9 8.7 11.3
相模原市 10.0 11.5 11.3 12.4 13.2
鎌倉市 9.6 10.8 13.0 9.9 12.6
藤沢市 16.0 24.0 24.5 18.6 21.9
茅ケ崎市 10.8 15.0 19.5 14.7 14.6
逗子市 10.4 13.1 9.0 10.1 9.3
二宮町 26.7 13.6 18.8 19.6 19.5
大井町 7.3 7.9 8.6 7.3 6.6
真鶴町 25.0 10.0 11.3 6.3 26.3
清川村 27.3 31.8 25.0 29.5 31.8
*調査は昨年8月。2学期制などの31校 は除く
塾教材で著作権侵害 作家ら33人が仮処分申請
(読売新聞 3月11日)
ねじめ正一さんや灰谷(はいたに)健次郎さんら計33人の作家や詩人が、大手の中学進学塾やインターネット配信会社計5社を相手に、「市販もされている塾教材やインターネット上の問題集で作品を無断使用され、著作権を侵害された」として、塾教材などの出版、販売、送信の停止を求める仮処分を11日、東京地裁に申し立てた。
塾教材の著作権侵害が問われるのは初めて。学習教材会社による著作権侵害が訴訟に発展して5年になるが、作家側は進学塾やネット上では依然として著作権侵害が続いている、として裁判所に判断を求めた。
塾教材の出版、販売、譲渡の停止を求められたのは▽首都圏を中心に中学進学教室を経営している「株式会社日能研」(横浜市)と、その教材を制作、販売する「みくに出版」(東京都渋谷区)▽関東一円に中学進学塾を運営する「株式会社四谷大塚」(同中野区)と系列の「四谷大塚出版」(同杉並区)の2グループ。
送信停止を求められたのは、「みくに出版」と受験教育情報の配信事業を手がける「インターエデュ・ドットコム」(同新宿区)。
申立書などによると、2つの進学塾グループは独自に教材を作成し、一部は市販もしているが、計40の塾教材の中で、ねじめさんの「鳩を飛ばす日」、灰谷さんの「兎の目」など70作品を92か所にわたって無断使用しているという。
また、ネット配信会社2社は、作家の作品が引用された中・高校の入試問題や解答、解説をホームページに掲載したり、作品を引用した模擬試験問題を作成したりしていた。無断使用は25作品、32か所に及ぶという。インターエデュ社は閲覧無料だが、みくに出版は登録者から1校あたり50円から80円の閲覧料金を取っている。
作品の無断掲載が訴訟に発展した例としては学校用教材があるが、学習教材会社が作家への損害賠償や副教材の出版差し止めを命じられるケースが相次いでいる。
関連記事
日能研・四谷大塚に出版禁止の仮処分申請 作家ら19人
(朝日新聞 3月11日)
谷川俊太郎さんや三木卓さんら19人の作家や詩人が、大手の中学進学塾「日能研」(横浜市)、「四谷大塚」(東京都中野区)を相手に、「塾教材で作品を無断利用され、著作権を侵害された」として、教材の出版、販売差し止めを求める仮処分を11日、東京地裁に申し立てた。
これまでも、作家らが小学校の副教材などについて仮処分申請したり訴訟を起こしたりした例はあるが、塾教材の著作権が争われるのは初めて。
また、同時に大岡信さんら14人の作家や詩人が、インターネット上に問題集を掲載する「みくに出版」(渋谷区)、「インターエデュ・ドットコム」(新宿区)に、送信差し止めを求める仮処分を申請した。インターエデュ社はネット上での閲覧を無料にしているが、みくに出版は閲覧料金を取っている。
〈日能研の話〉 争うつもりはなく、著作権料についても、支払う意思はある。
〈四谷大塚の出版部門を担当する四谷大塚出版の話〉 申し立ての書面が届いたら検討する。
中教審委員を辞職 早大前総長が高額寄付要求で引責
(朝日新聞 3月12日)
学校法人早稲田実業学校(早実、白井克彦理事長、東京都国分寺市)初等部が、入試で募集要項に記載した額の7倍の寄付金350万円以上を要求するなどしていた問題で、02年春の開校当時に理事長を務めていた奥島孝康・前早稲田大総長が、政府の中央教育審議会委員の辞職を申し出ていたことが12日、明らかになった。前総長は自ら高額寄付の要求を主導していたことを認めており、責任をとった形だ。
河村文科相が同日午前の記者会見で、5日付で辞職を申し出る文書が届いたことを説明した。前総長は中教審でスポーツ・青少年分科会長や大学分科会の副分科会長を務めていた。文科相は12日中にも辞職を認める手続きを取る。
奥島前総長は、面接試験で保護者に寄付を働きかけたことについて「(入学前に募集してはいけないとする文科省の)通知に違反したことは間違いないので、責任を取らないといけない」と述べた。辞職の理由を「早実の理事など早大関連の役職も辞任した。早実の信頼を低下させ、早大に影響を及ぼしてしまった。関係各位にご迷惑がかからないようにしたかった」と話した。
早実初等部は昨年11月の04年度入試の面接で保護者に対して1口10万円で35口以上を要求。02、03年度にも、合格発表後に保護者あてに出した「趣意書」で30口を依頼していた。法人を監督する東京都は1月、04年度入試について「適正を欠く行為」として私学補助約1億円の返還を求め、早実側が応じている。
教員採用の新制度 応募少なく、埼玉
(毎日新聞 3月9日)
退学・長期欠席者が多い「問題校」を活性化させるため、埼玉県教委が県立高校の校長に教員の採用権を与えた新制度「教員人事応募制度」で、25校38人の募集枠に7校14人の応募しかなかったことが8日、県議会予算特別委員会で問題になった。意欲ある教員を集める制度だったが、県教委高校教育課は「『問題校』に限定したために、集まりが悪かった可能性がある」と説明している。今後、募集校の拡大や人事異動を活性化させる補完的な新制度を検討するという。
応募状況は、同委員会で稲葉喜徳県教育長が明らかにした。同制度では、校長が学校の課題や求める教員像を明らかにして現役教員に募集を呼び掛け、校長が書類選考と面接を行う。「問題の多い学校だがやってやろうというやる気のある先生を見つける」(稲葉教育長)のが狙いだった。
初回となる4月人事に向けて、昨年8月、募集校25校を決め、募集を開始。だが、最終的にはわずか6校に7人程度が配属される見通しという。
同課は「初めての制度なので周知不足が原因」としながらも、「問題校にチャンスを与えるための制度だが応募者が少なく、このままでは先細りになる。人気校に応募が集中する恐れもあるが、学校の選択肢を広げれば、より多くの教員が制度に参加する可能性がある」と募集校拡大を示唆した。
新たな制度として、県教委が各学校長に個別の教員の異動希望を伝える方法も検討しているという。高校教育課は「自分から『問題校に行きます』と手をあげる勇気のない教員でも、多くの教員が異動希望を出して人事異動が活性化すれば、手をあげやすくなる可能性がある」と説明している。
児童生徒が授業評価 東京・墨田区
(毎日新聞 3月9日)
東京都墨田区教委は8日、新年度から区立の全小中学校40校で、児童・生徒と教員による授業評価を導入することを決めた。教える側と教えられる側が対応する「授業評価カード」を作り、評価を照らし合わせて授業改善につなげるのが目的という。
同区では、小中学校の教師で研究協議会を作り、授業評価を1年かけて検討し、小中8校で評価を試行してきた。
評価カードの試案は、児童・生徒用と教員用それぞれ12の質問項目につき、「全く思わない」から「とても思う」まで5段階に○をつける方式。質問項目は「先生の説明がわかりやすかった」(児童・生徒用)、「わかりやすく説明することができた」(教員用)など、双方が対応した内容になっている。
試行で教師から「あまり話さない児童・生徒が自由意見欄に書いていることが参考になった」「自分では気付いていない点を指摘されたのはよかった」などの感想があったため、導入に踏み切った。
評価項目や評価回数などは各学校ごと決める。区教委は「趣旨は授業の改善。先生のランク付けに結びつくものでは困る」といい、結果の公表は今後検討する。
児童・生徒による授業評価は、足立区で02年度から全区立小中学校で実施。都立高校でも新年度から全校で導入される。
=児童による授業評価には無理があるのではないか。単純な先生の人気投票になってしまう可能性の方が高い。=
私大志願者が減少 強気出願で、旺文社調査
(毎日新聞 3月8日)
私立大学の今年の一般入試で、志願者数は昨年より5%少ない199万人で、4年ぶりに減少したことが、旺文社の調査で分かった(2月20日現在)。3月入試や新設大学・学部の志願者数を加えても、最終的には260万人台の前半で、3年連続の増加から減少に転じるのは確実という。
今年の入試から国立大の9割近く、公立大の3割近くが大学入試センター試験で5教科7科目以上を課すようになった。このため負担を嫌う受験生の多くが国公立をあきらめたり、私大の併願を増やすとみられていた。
予想と違ったことについて同社は、(1)今年のセンター試験の平均点が多くの教科で上がったため、理系を中心に自分の持ち点を過信する強気出願で私大の併願校を減らした(2)昨年の受験生は、浪人すれば5教科7科目に負担が増えるため、浪人を避けて入れる大学に入った結果、今年の浪人生が減った(3)必要以上の受験料や入学金を払えないという家計の事情で、厳選出願に走った――ことが要因とみている。
主な大学では、法政や早稲田、関西学院などが志願者を減らしたのに対し、慶応や中央、立命館などが志願者を増やした。女子大の人気復活も特徴として挙げられるという。
女子大だけをみると、志願者は昨年より5%増えた。浪人を避けたい女子受験生が、ブランドイメージの高さの割に共学校より入りやすい女子大上位校を狙った結果ではないかと分析。センター試験を利用する私大の志願者も50万人で志願者全体の4分の1を占め、センター人気も続いているという。
その他
寄稿 無知な父母へのメッセージ
良い私学と悪い私学の見極め方 21世紀教育開発研究所 内田正信
第5回 プロ教師がどれだけいるか
プロ教師の条件
私立中等教育への父母からの期待は、六年間でどのような教育をしてくれるかの教育内容であり、教育実践です。どんな教育をしてくれるかの教育内容は「学園案内」やカリキュラム・シラバスなどをみればわかります。問題なのは、そこに書かれている内容が、その学校の教師によってどのように実践されているかが大切な問題になります。学校説明会での立派な教育内容に惹かれて入学したが、教師の教え方が悪く失望することもあります。「進学校にシフトを変えた」と言われて入学してみたが、教育内容のレベルが低く、「総合学習」や「体験学習」的なものが多く、不安を感じることもあります。これらは、すべてその学校の教師の問題であり、教育実践の問題です。
教え方が良いか悪いかは、生徒の教科学習に強い影響を与えます。同一学年の同一教科を違う教師が教えて、クラス平均点に大きな差が現れることがあります。中学時代に教科指導が悪い教師に出会うと、その教科が出来なくなったり、苦手科目になって、将来の大学受験に影響してくることもあります。これがいわゆる「あたり、はずれ」といわれる問題です。このような学校は悪い学校であり、プロ教師の少ない学校でおこる現象です。教師になるには、資格(教員免許)が必要であり、公立・私立を問わず試験によって教師として採用されます。にもかかわらず、教師として不適格であったり、生徒のレベルに対応した授業ができない教師がいます。良い私学か悪い私学かの問題は、優れた教育実践をするプロ教師がどれだけいるかの問題になります。プロ教師とは、どのような教師でしょうか。プロ教師が、どれほどいれば良い私学と言えるのでしょうか。
教育現場に必要なのは実践家のみ
教育現場では、より良い教師の育成とより良い教育実践を目指して、教育研究会(教研)が実施されます。教研活動は教科教研やテーマ別の教研を分散会(同一テーマで、グループごとの教研)か、または、分科会(グループごとにテーマを分ける教研)の形式で行われるのが一般的です。労働組合のある職場では、組合教研が実施されている学校もあります。さらに、学校の枠を超えての私学教研や日教組教研などもあります。日本の教育危機をもたらす「第三の教育改革」が進行する中で、全体的に教研活動が退潮傾向にあるのは残念なことです。
教研活動には、二つの悪いパターンがあります。一つは、「教育とはなにか」「学力とはなにか」「民主主義とはなにか」などの教育の本質にかかわるテーマで「〜であるべきである」というような議論が展開される教研です(私は、このような教研を「とは」・「べき」教研と名付けています)。もう一つのパターンは、「生徒は勉強しない」「遅刻者が多くて困る」「生徒指導が不統一である」などと教育現場の諸問題を話し合う教研です(私は、このような教研を「愚痴こぼし」教研と名付けています)。どちらも、「言いっぱなし」・「聞きっぱなし」教研です。このような教研ぐらい空虚さとむなしさを感じるものはありません。こうような教研を繰り返している私学には進歩も発展もありません。このような教研活動では、何ら新しいものを創造しないからです。
教育の本質について語るなら、それをどのように具体化し、どのように実践したかが大切になります。「生徒が勉強しない」のならどのようにして勉強させるのかの実践が重要になります。教育現場には評論家も理論家も必要としません。必要なのは実践家だけです。プロ教師としての前提条件は、実践家であることであり、職場にどれだけの実践家がいるかが良い私学と悪い私学を見極める大切な視点になります。
プロ教師は授業で勝負する
中等教育における教師の教育活動は大きく二つになります。一つは知育を中心とする教科指導であり、もう一つは徳育を中心とする生徒指導です。前者は各教科の授業であり、後者は学級経営を中心とする生徒指導になります。教師としてどちらの教育活動も大切ですが、どちらかと言えば教科指導になります。それには、次のような理由があげられます。
第一は、学校教育で一番大切なものは知育であるからです。教師は一時間一時間の授業が勝負です。すべての生徒にいかに分かる授業、興味を持たせる授業を展開するかが大切です。分からない授業ぐらい生徒にとって苦痛なものはありません。第二は、教科指導がしっかりできる教師は生徒から信頼され、生徒指導もうまくいきますが、教科指導がしっかりできない教師は生徒指導もうまくいかない場合が多いからです。
授業には、教科・科目・内容によって覚えること、理解すること、考えることなどといろいろな側面があります。これらをいかに組み合わせて展開するかが、授業の大切なポイントになります。また、私立中等教育においては、中学一年から高校三年までの六年間には大きな発達段階の違いがあります。在職期間中に入学者のレベルが大きく変化することもあります。このような発達段階やレベルの変化にも対応できるしっかりした教科指導を身につけることが、プロ教師としての基本条件です。
さらに、プロ教師として大切なことは、正しい教科指導法を通して、生徒に正しい学習法を身に付けさせることです(私は、これを教科教育学習法と名付けています)。今の生徒は、すぐ答えを求めようとします。わからなくなると、すぐに教師や塾に頼ろうとします。学習における過保護・過干渉が進行しています。現在の子どもたちの「学力低下」や「学習ばなれ」の原因は、生徒が正しい学習法を知らないところにあります。教師の正しい教育法と生徒の正しい学習法が一体となったとき、学習効果は飛躍的に向上します。中等教育の根幹は生徒が「自学・自習」の道を確立するところにあります。
教師は「聖職者」(か)
30年程前の組合教研では、教師は「教育労働者」か「聖職者」かというテーマでしばしば議論した記憶があります。このような教研テーマの背景には、国際社会では東西対立、国内政治では、「55年体制」がありました。教師は当然、労働者であり「聖職者」であると思います。「聖職者」という言葉に違和感があるなら、「尊敬される人」であることがプロ教師としては大切なことだと思います。それは、次の二点において必要な条件と言えます。
第一は、教科指導と生徒指導のところでもふれたように、教科指導がしっかりできない教師は生徒から信頼されず、生徒指導もうまくいきません。また、生徒指導は徳目をならべて説教することでなく、教師の態度や生き方を生徒に示すことです。それには、生徒一人ひとりを個人として尊重する(日本国憲法13条)民主主義の精神が大切になります。第二は、教師には教育目標なり教育理念があることが大切です。子どもたちに「より良く生きる力」「人間として生きる力」を与えてやるのが教師の使命であり、学校に責任です。しっかりした教育理念をもった教師は、教育実践にもそれが現れます。それが、生徒から尊敬される教師であり、父母から信頼される教師であり、プロ教師として大切な条件です。
戦後、日本の教育危機は、たびかさなる素人集団による教育行政の改悪と教育現場におけるプロ教師の不足にあります。現在進行している教育危機への対応は、教育現場における日々の教育実践であり、実践交流です。一人ひとりの教師が教師としてのプロを目指して、より大きなプロ集団を形成していくことが、日本の教育改革の早道であり正道です。
学校全体がプロ教師の集団であることが望ましいことですが、それは理想であって現実にはあり得ないことです。3分の1以上のプロ教師がいる学校は良い学校です。3分の1のプロ教師がいれば、学校全体の教育を良い方向に進めることが可能だからです。それ以下になると現状維持、5分の1以下になると「あたり、はずれ」のある悪い学校になります。最近、伸びている学校はプロ教師を育てる努力をしています。プロ教師がどれくらいいるかは、学校説明会だけではわかりませんので、在校生かその父母に聞くことが適当かと思います。
テレビ長時間見る子 言葉の遅れが2倍 日本小児科学会
(毎日新聞 3月10日)
日本小児科学会(衛藤義勝会長、約1万8000人)が1歳半の子供の親を対象にした調査で、テレビやビデオを長時間見ている子供は、そうでない子供に比べ、言葉の発達が遅れる割合が2倍になることが分かった。同学会は2歳以下の子供にテレビを長時間見せないよう呼びかける提言をまとめ、4月に公表する。
小児科学会の「こどもの生活環境改善委員会」が昨年、東京都や岡山県など3地域で、1歳半の健康診断の対象児(保育園児を除く)の親計1900人にアンケートした。子供が1日にテレビを見る時間を4時間より多いか少ないか、さらに子供が直接見ていなくても家族がテレビをつけている時間が8時間より多いか少ないかで四つのグループに分けた。通常、1歳から1歳半の子供は「主語」「述語」の2語文で話すことから、2語文が話せない子供の割合を四つのグループで比べた。
この結果、「子供が4時間未満で、家族が8時間未満」という最もテレビを見る時間が短いグループでは、子供に言葉の発達の遅れがあったのは約15%だった。これに対し、「子供が4時間以上で、家族が8時間未満」では約18%、「子供が4時間未満で、家族が8時間以上」が約23%、「子供が4時間以上で、家族が8時間以
上」が約30%。最も視聴時間が長いグループは、最も短いグループに比べると言葉の遅れが2倍になった。
このため、提言は「乳幼児にテレビ・ビデオを長時間見せるのは危険です」とした上で▽2歳以下の子供には、長時間見せない▽授乳や食事の間はテレビを消す▽子供の部屋にはテレビ・ビデオを置かない――などを盛り込む。
既に小児科の開業医ら約6500人でつくる日本小児科医会(師研也会長)が今年2月に、2歳までのテレビ・ビデオ視聴を控える提言をしており、小児医療の現場からの相次ぐ警告となる。
親の読書量 月1冊も読まない保護者が7割超、秋田県教委調査
(毎日新聞 3月4日)
親の8割が我が子に読書を勧めるが、自身の読書量は月1冊以下が7割超――。秋田県教委が昨年9月、小中生の保護者を対象に実施した初の読書実態調査で、「大人の活字離れ」を示す結果が明らかになった。
児童、生徒に実施した県の02年読書調査では、全国平均を上回っただけに、県教委は「子どもに読書習慣を身に着けさせるためにも、自らの行動で示してほしい」としている。
回答したのは、小学4年生と中学1年生の保護者計793人。うち女性が687人で86・6%、年代別では30、40代が96・9%を占めた。
調査結果によると、99・4%が「読書は大切」と回答。子どもへの読書推奨については、「よく勧める」が29・5%、「ときどき勧める」が57・9%。また82・1%が就学前の「読み聞かせ」を行っていた。
しかし自身の読書生活に関しては、月平均の読書量「0冊」が41・1%、「1冊」が33・3%。3冊以上は12・4%だった。一方児童、生徒計1103人を対象にしたアンケート(02年)では、小5平均が8・5冊(全国平均6・2冊)、中2が3・2冊(同2・1冊)だった。
「読書離れ」の背景には、公立図書館の未整備や書店の減少などがある。県教委生涯学習課によると、県内69市町村中、公立図書館があるのは32自治体のみ。書店があるのは全体の3分の1程度という。
同課は「読書は生涯学習の基本。今後は高齢者の現状把握にも努めつつ、県民全体の読書活動を推進したい」としている。
就職内定率 大学生は82.1% 99年以来2番目の低率
(毎日新聞 3月12日)
今春卒業予定の大学生の就職内定率は、82.1%(2月1日現在)で、前年同期を1.4ポイント下回り、この時期に統計を取り始めた99年以来2番目に低い数字となったことが12日、厚生労働、文部科学両省の共同調査で分かった。一方、厚労省が独自で行っている今春卒業予定の高校生の就職内定率は76.7%(1月31日現在)で、過去最低だった前年同期を2.3ポイント上回った。高校生は昨年11月末の調査では02年同期の内定率を下回っていたが、今回の調査では同年を1ポイント上回るなど、内定率の回復の兆しが顕著になった。
大卒予定者は、全国の大学、短大、専門学校107校の5840人を対象に調査した。男子学生は82.8%(前年同期比2.6ポイント減)、女子学生は81.2%(同0.3ポイント増)となった。男子学生の落ち込みに対して、女子学生は前年を上回り、99年以降では最高の数字となった。厚労省は「企業は優秀な学生についての採用意欲は強くなっており、一般的に女子学生は成績優秀と言われていることから、女子の内定率上昇につながっているのではないか。ただ、厳しい状況には変わりはない」と分析する。
一方、高校生は、学校、ハローワークを通じて調査。男子生徒が81.2%(前年同期比2.8ポイント増)、女子生徒は71.6%(同1.5ポイント増)となった。女子生徒は、前回の調査では前年同期比でマイナスだったのがプラスになるなど、回復の兆しを見せている。埼玉県内の普通高の進路指導担当の教諭は「内定が出る時期が遅くなっている。生徒たちもギリギリまで仕事を探し、あきらめる生徒もいる。この結果、就職希望者が減り、内定率が上がったのではないか」と話している。
<問題>
図のように直角三角形と半円があります。![]() 部分と
部分と![]() 部分の面積の合計は、136.97(平方cm)
部分の面積の合計は、136.97(平方cm)
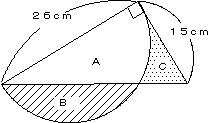
(04年フェリス)
入試問題に挑戦第107回解答編
<問題>
【二】次の文の(ア)〜(ソ)に入る語を後から選び、11〜30の番号で答なさい。同じ番号を二度使ってはいけない。
「雪月花」という言葉がある。いずれも日本の風流を代表する景物である。雪害に悩まされた雪の深い地方では、雪が風流などとんでもないことだろうが、「雪月花」という言葉自体、(ア)を中心とした文化圏の風流の代表ということであるから問題はなかろう。日本は(イ)の変化のきわだった国であり、俳句という世界に比類のない文芸が生まれ育った。
俳句(ウ)という書物には、春、夏、秋、冬と新年の(エ)と、その解説、それぞれの(エ)を用いた俳句がのせられている。ちなみに俳句でただ花と言えば(オ)の花をさし、月と言えば(カ)の月をいう。
日本人は完全な美しさを賞する心と同時に、不完全なもの、すでに盛りを過ぎたものを重んじる心があるようだ。
古人も書いているが、例えば(オ)の花もその盛りだけを楽しむというのだけがいいというのではない。ほろほろと散る時もよし、ほとんど散ってしまって、わずかに梢に残っている花もなお俳句の材料になっている。
仲秋の(キ)は、旧暦八月(ク)日の月で、古来、月見る月の月と鑑賞されている。その(キ)が、空模様が悪くて見えないことを(ケ)月といい、特に(コ)が降ってまったく顔を出さないことを(コ)月という。このように(キ)が実際に見られなくてもそれなりの雰囲気を楽しんで、句の材料にするのが俳句というものである。
(サ)の花を買うとき、日本人はどちらかというと(シ)分咲きぐらいの花を選ぶが、西洋人は完全に開ききったものを好むという。
旧暦九月(ス)日の月を(ス)夜の月といい、仲秋の(キ)と同様、だんごや(セ)を供えて祭る。まだいびつな月で、これも、これから育とうとするものに期待しようという気持ちだろう。
月をたんなる(ソ)としか意識しないという欧米人とはずいぶん異なった考えということができよう。
11 七 12
十三 13 十五 14 季語
15 京都 16 東北 17
さくら 18 すみれ
19 ばら 20 すすき 21
無 22 雨
23 文学 24 歳時記 25
天体 26 宗教
27 秋 28 名月 29
冬 30 四季
【六】 次のア〜オに示したいくつかのことばから連想される動物は何か。それぞれ一つずつ、ひらがなで答えなさい。
ア、嫁入り ごん うどん 火
イ、皮算用 はやし おやじ
ウ、尾を踏む 下手な頭の刈り方 安直な学習書
エ、舌 小判 背 ひたい
オ、まね 知恵 芝居 すべり まわし
(04年慶應義塾中等部)
<解説>
前回の慶應義塾普通部の入試問題では、「基礎学力=必要条件」という観点で展開しましたが、今回はそこに付加される「教養」という観点でのお話を展開します。
入試に必要な国語力をどう培ったらいいのでしょう 塾での学習説明会だけではなく、当然ながら学校での説明会でも質問としてよく聞かれる内容です。それに対する学校側の回答として、これまたよく聞かれるのは、「たくさんの本を読むことだ」というものです。しかしながら、どのような種類の本をどう読むべきなのかは明らかにされず、保護者は途方に暮れてしまう というのもよくある図式です。
私たちアクセスは、「読書は活字に慣れ、興味や世界観をひろげるためのもので、解法のテクニックには直接結びつくものではない」と考えています。興味や世界観 これを広い意味での「教養」とここでは呼ぶことにしましょう。
ところで、「教養」を成立させるものに「語彙」があるという考えがあります。
では、日本語の「語彙」というのは、いったいどのくらいの大きさなのでしょうか。もっとも普及している新明解国語辞典では75,000語(三省堂国語辞典が約76,000語、岩波国語辞典が約63,000語、旺文社国語辞典が81,500語)が収録されています。これが広辞苑になると約23万語収録されており、図書室や図書館に収録されている何巻ものの大辞典の類になれば、30万語を越す収録数になります。ただし、私たちがこれらの辞書をめくったときに感じるように、人生の中で眼にふれたり、使ったりするものは当然その一部になります。逆に言えば、その語彙が豊かであればあるほど(言葉をつかって思考するという観点に立てば)、その思考範囲が広がり、発想の可変性に富むわけで、この点で「語彙」=「教養の一部」という等式が成り立ちます。
早稲田大学教授・中村明氏は、その著書『センスのある日本語表現のために』(中公新書)のなかでこう述べられています。
「日本語がいくらあっても、実際に目にし耳にふれるのは、そのうちのある部分である。五万ある漢字でも、現実にお目にかかるのは普通の日本人で三千字以下という。それと同じように、たいていの日本人は小型辞典の言葉さえみな知っているわけではない。各種の調査によると、小学校に上がったばかりのときで三千語だったのが、中学校に入るころには二万語ちょっとになり、順調に伸びれば高等学校の入学時には四万語ほどに増えて、日本語の話者としての基礎作りが一応できあがるらしい。そして、その後も少しずつ蓄積され、成人では五万語前後に達するという。」
ちなみに、この続きの文には、これらの語彙数は、「聞けばわかる理解語彙」のことであって、自分が話したり書いたりするときに使う「表現語彙」になるともっと少なくなるとされています。
引用文中に「小学校に上がったばかりのときで三千語だったのが、中学校に入るころには二万語ちょっとになり」とありますが、小学生から中学生までの時期の語彙習得は教科書によるもののみではないでしょう。その要素として前述した「興味や世界観」をひろげる読書が当然入ってくるでしょう。しかし、それ以上に大人との会話の占める割合が大きいのではないでしょうか。大人とのやりとりとは、家庭、学校、そして塾での大人との関わりです。
では、ここで、今回の慶應義塾中等部の問題を材料に、塾での大人との関わり、授業のシミュレーションを行ってみましょう。
「【六】は簡単だから、【二】を考えよう。知識を問う問題なんだけど、きちんと本文を読もうね。まず、(ア)。すぐ前に「文化圏」という言葉があるね。携帯電話を持っている人? 画面を見てごらん。「圏外」って表示になってるよね。そうそう、これは、教室では通話できる「範囲・場所」ではないっていう意味なんだよね。つまり、「圏」は、「範囲・場所」って意味がある。だから、「雪」が「風流」として問題にならない場所といえばどこになるかな。」
「(イ)は、次の段落に俳句と春夏秋冬の関わりがあることからも判断できるね。なに、楽勝だって。じゃあ、(ウ)は知ってるかな? 新六年生のオープンテストで出題したら、正解者が少なすぎて、先生泣いちゃいました。(エ)はこれにのっている季節をあらわすことばだよ。俳句を作るときのルールというか、「お約束」だね。テキストにもあったように、江戸時代にだれかが「有季定型」として確立したものだね。さて、だれが確立したかな? そう、そのとおり、松尾芭蕉だね。この(エ)は、俳句の描く「場面(情景)」の「いつ・どこで・だれが」のうち、「いつ」をイメージさせるものになるんだね。単なる知識だけじゃなくて、イメージするためには大切なものになる。」
「ところで、(オ)や(カ)も「お約束」のうちの一つなんだが、これは俳句だけじゃなくて、もっと歴史の古い文芸からの影響が大きい。別名「みそひともじ」というんだけど、わかるかい? みそは味噌じゃなくて三十って意味だぞ。そう、五・七・五・七・七で、短歌だね。鎌倉時代に編纂された「小倉百人一首」にこんなのがあるよ。「ひさかたの光のどけき春の日にしずごころなく花の散るらむ」 ここに登場する花も(オ)と同じ花なんだけど、四段落を見ると「わずか梢に残っている」とあるから、木に咲く花だと判断できる。理科の問題でもあるね。」
「理科の問題といえば、湿度が下がって空気が澄んでいるから月や星が美しい。日本で、もっとも空気が澄んでいる、つまり、乾燥している季節はいつだろう? そうだね、真冬だね。しかし、防寒着や暖房のしっかりしている現代とちがって、俳句が俳諧と呼ばれていた江戸時代に、寒さにふるえながら真冬に空を見上げるのは、風流とはいえなかったろうね。現実的には、気温がもう少し高いころで、しかも空気が乾いているころと言えば? そうだね。秋になる。だから、秋の(エ)には、天体を題材にしたものがとても多いね。旧暦と新暦の期間のズレも関係あるけど。」
「旧暦は、別名太陰暦というのは、歴史で学んだから六年生は知っているね。現在使われている太陽暦と比較すると、場合によっては一ヶ月〜一ヶ月半ほど太陰暦が進んでいるんだ。だから、「五月雨」って言っても、実際は六月半ばの雨なわけで、ようするに「梅雨」ということになる。「仲秋」は「ちゅうしゅう」って読んで、現在は九月になるよね。
童謡で「うさぎ、うさぎ、何見てはねる(ク)夜お月さま見てはねる」というのを聞いたことあるかな。九月に、この(ク)夜の(キ)というのはニュースにもなるから、五年生でも聞いたことがある人はいるんじゃないかな。「常識」がうまくつながったかな。」
「さて、むずかしいのが次の(ケ)と(コ)。ただし、文中に「(コ)が降ってしまった」とあるから、ここにはいるのはしぼりこめるね。そして、もどって「空模様が悪くて見えない」わけだから、(ケ)に入るものも決定できる。ここの解答の「無月」は「むげつ」、「雨月」は「うげつ」って読みます。」
「では、次は花の問題。ここまで秋の話なのに、(サ)にはいるべき花の名前は「バラ」か「スミレ」になるわけだから、季ちがいになってるね。まあ、それはさておき、バラもスミレもお花屋さんで買うことができるけど、スミレのほうは春の野原に自生するイメージが強いし、なにより「花を買う」というより「鉢植えを買う」というほうがふつうかな。それと、(シ)のあとの「分」は、「ぶ」と読みます。お母さんのブラウスなんかで「(シ)分そで」といってそでの短いデザインのものがあるけど、聞いたことあるかい?」
「いよいよ選択肢も残り少なくなってきました。よーく、確認してみましょう。(ス)には、あとに「日」がつながるから数字が入るね。残っているのは「十三」で、答えは「十三夜」になる。現在の「十三夜」は十月で、「十五夜」は九月になるわけで、むかしの人は、この時期の食べものに結びつけて「十五夜」を「いも名月」「十三夜」を「くり名月」と名づけました。形を想像するとなんだかおかしいけど、親しみのわく表現だね。おそなえする(セ)はわかったかな?」
「そしてラストは(ソ)。日本と欧米の対立構造が最後に出てくるね。前の段落にあるように、日本人は月をなかば「擬人化している」、と考えられれば、欧米人は「モノ」としてとらえているという考え方ができる。まあ、残った選択肢を当てはめる問題ともいえるけど、ふだんの読解意識があれば、選択肢がなくとも内容が予想できるんじゃないかな。」
以上が、授業シミュレーションでした。俳句と旧暦に関する問題でしたが、子供たちの生活意識や大人とのコミュニケーションの土台の上に立っている問題であることがおわかりいただけたでしょうか。昨今でも時折見かけられる、中学生レベルの漢字を問うてみたり、センター試験を思わせる必要以上に曖昧な選択肢を選ばせたりという「悪問」とは一線を画した良問と言えます。まさに子供を大切にした大人の態度の設問ですが、試験開始前に答案上部に数字の書きとり練習をさせられた受験生はその子供扱いに少々辟易としていたようです。
さて、子供たちはこれからさまざまな知識を習得していくのですが、「(子供なんだから)知らなくていいんだ」というのは、成立しないのではないでしょうか。(もちろん、暴力的・性的なものを意図した不穏当なものは、いずれ判断がつく年齢に与えるのは当然です。)中学入試に「知っていなくてはならない基礎知識」に加え、「知りたい」という気持ちを大切にし、「知るおもしろさ」をかき立てる。そんな知的環境を通して「世界観としての教養」を身につける態度をもてることこそが、志望中学の中学生となる上での十分条件になるのではないかと思います。
〈解答〉
【二】 ア
15 イ30 ウ24 エ14 オ17 カ27 キ28 ク13 ケ21 コ22 サ19 シ11 ス12 セ20 ソ25【六】 ア きつね イ たぬき ウ とら エ ねこ オ さる