

�m�n�D�P�P�O

�Q�O�O�R�N�@�X���P�T���@
�A�N�Z�X������Z���^�[
�ڎ�
|
�w�Z��� |
���J�͎���� | ������ | ������ | ���̑� |
| �T���W�I�w�@ | ���\���͎��X�� | ��Ɛݗ��̑S������эZ | ���w���̊w�͒ቺ | ����G���̓������� |
�w�Z���
�T���W�I�w�@�@���獧�k��i�O�R�N�X���W���j
�����搶
 �@���k��̗l�q
�@���k��̗l�q
�P�j �͂��߂�
���͉ċx�݂��߂���Əł�͂��߂邪�A�ł�͎̂q�ǂ����ی�ҁB���ꂪ�q�ǂ����ł点�Ă��܂��B�Ɍ����Ďq�ǂ��𒆐S�ɍl���Ă����āA�e�͉�������`���悢�̂ł͂Ȃ����B�w�Z�������ŁA�ꌩ�A���������k�������Ĉ��������Ă����悤�Ɏv���邪�A�����̂͐��k�ł���A�����͐��k���������邾���B
������Řb������x�ɁA�T���W�I�w�@���u�]�����w����l�����łȂ��A�T���W�I�w�@�ɊS�������ꂽ�l�ɑ��Ă��w�Z�Ƃ��Ă������肵�Ȃ���ƐӔC��������B
�Q�j �Q�T�̒j���
�T���W�I�w�@�͐��N�̋�����s���j�q�Z�B
���Ƃ��Ƃ͐푈�ǎ����W�߂ċ���̏����邱�Ƃ���X�^�[�g�B�G���[�g����ł͂Ȃ������B
�T���W�I�w�@�̑傫�ȓ��F�͋��ɂ���i�A�V�c�e���c�@�j����B
�T���W�I�w�@���l���Ă��鋳��͂U�N�ԗa����Ȃ��Ƃł��Ȃ����A���̋���̌��ʂ͂U�N�Ԃł͏o�Ȃ��B�ǂ��̑�w�ɓ������������ʂł͂Ȃ��B�Љ�l�ɂȂ����Ƃ��ɂǂ������j�ɂȂ��Ă��邩�œ����o��Ǝv���Ă���B���̈Ӗ��łQ�T�̒j���ƌ����Ă���B
�j�̎q�͍��������Ă�����L�т�B�w�Z������Ŋw�Z�ɗ���ꂽ�ی�҂̕��̃A���P�[�g�Ɂu�T���W�I�͐��k�����A�����Ă����̂ŋC�����������v�Ə������B���������͂��ꂪ������O�̂��ƂƎv���Ă��邪�A���̈��A���ł���Ƃ����͉̂ƒ�ō��ꂽ�������邩��B���A���ł��邩�A�Ԃ����Ă��ꂢ���Ɗ������邩�Ƃ������Ƃ͗��e�̋���ɂ��Ƃ��낪�傫���B
���w�������邲�ƒ�Ƃ����͎̂q�ǂ��ւ̊S�∤�����Ƃ������ƁB�����ň�����q�ǂ��͍��������Ă���B�T���W�I�w�@�ł͂����������������Ă���q��a�����Ă���B
�܂��A�㋉�������A�����Ă���̂�����A���P�ɓ����Ă������k�ɂƂ��Ă��ꂪ������܂��Ǝv���B������������w�Z�̍Z���A�`���̒��Ŏq�ǂ��̎����Ă��鍪������Ă����B
�R�j�@���w�����ɗՂ��
���w�����͐e�q�ł悢�������I�����Ē���ł���B
�����A���������Ă������Ɣ��f���邩�͓���B��w�������т���l�̐����Ŕ��f����l������A�����Ō���Ȃ��Ƃ���Ŕ��f����l������B
�w�Z�I���͕��l�̐����ɂ������K�v�͂Ȃ��B�q�ǂ��̊w�Z�ɑ��ĉ��ƂȂ������ȁA���ƂȂ����₾�ȂƂ������o���厖�B�e�������Ɍ��߂č��i���Ă��A���w���̗�������x�ސ��k������B�ȑO�A�w�Z��ς�肽���ƌ������k�ɁA�e���P�w�������͒ʂ��Ȃ����ƌ������Ƃ���P�w���̏I���ɁA�P�w���ʂ����̂�����ς���Ă����ł��傤�ƌ���ꂽ���Ƃ��B�q�ǂ��Ƃ����Ă��ӎu�͂������肵�Ă���B
�T���W�I�w�@�̓I�[���}�C�e�B�[�ł͂Ȃ��B
�T���W�I�w�@�̓��e�Ƃ��ƒ�A�q�ǂ������߂���̂Ƃ������Ă��邩���d�v�B
�v���싅��ڎw�����߂ɃT���W�I�ɓ����̂͊Ԉ���Ă���B�T���W�I�̍d���싅���͑n���P�O�N�ڂʼnĂ̑������B����܂ł́A���N�͂悭�R�[���h���������Ȃ������Ƃ������x�B���ɏ��̂ɂ܂��P�O�N������B
�T���W�I�����āA�����̖�����������ɂ̓T���W�I�������Ǝv���đI��ł��炦��̂ł���ΊԈႢ�Ȃ��B
���w�Z�U�N���ɂȂ�ƖړI���͂����肵�Ă���B�����Ȃ����ƌ����Ȃ��Ƃ��Ȃ��q�͂܂��ړI���͂����肵�Ă��Ȃ��q�B�S�E�T�N���͂܂����Ԃ�����̂�����A�ł��邾���Ƒ��ʼn߂����@��������ė~�����B�_���ɕ\�����������Ȃ��q�͕Њ���������ɂȂ��Ă��܂��B�������K�v���Ǝv���B
�����ł̍��i�E�s���i���S�Ăł͂Ȃ��B�����͏��������ł͂Ȃ��B�����Ɍ����e�q�łǂꂾ���̓w�͂������ɉ��l������B��w�����ł��A��֍Z�ɒ��킷�邽�߂ɂ͂��ꂾ���̓w�͂��K�v�B�w�͂������Ƃ͐l�Ԑ��Ƃ��ĕ\���B
���i���Ċ�т�����Γ����w�Z��I�ׂ悢�B
�e�͎q�ǂ����]�ނ̂ł���Ή������Ă�����B�w�͂������Ƃ�]�����Ă����邱�Ƃ���B
�q�ǂ������s�����Ƃ������e�̖�ڂ�����B
�S�j�@�w�Z�����ɂ����鋏�ꏊ
�T���W�I�w�@���U�����𑱂��Ă���͎̂��Ǝ��Ԃ̊m�ۂ����łȂ��A�w�Z�s����N���u��������肽���Ȃ����߁B���k�����͍s����N���u�������瓾����̂���������B�s����N���u�����Ŏ����̋��ꏊ�������鐶�k������B�w�Z�ł̋��ꏊ�i�������]���������́j�͐��т����ł͂Ȃ��B
�������ł���ꏊ�Ƃ����F�߂Ă����ڂ����邱�Ƃ��厖�B
���ѓI�ɂ͖��N���i�����������A�Љ�ɏo�Ă���l�ԓI�ɐ����������k������B
���P�̉ċx�݂ɗъԊw�Z������N���X���ɏo������B���R�̒��łȂ���ł��Ȃ����Ɓi�l�Ԃ������̂̑��݂�m��j��A�F�B�Ƃ̊ւ������@��Ƃ��ďo�����邪�A�����ł͊���̕��ł͌���Ȃ��ʂ��o�Ă���B
�T���W�I�w�@�ɓ��w���Ă��鐶�k�͏��w�Z�ł͂�����x�ł��鐶�k�B���P�̒��Ԏ���������ƂP�W�O�l���P�T�O�Ԃ̐��k���o�Ă���B���̎��A�{�l�ɂ́u�P�T�O�Ԃł悩�����ˁB���ɂP�O�O�ԂɂȂ�Ί撣�����˂ƌ����邪�A�P�O�Ԃ̐l�͂Q�O�ԂɂȂ��Ă����ʂ����������Ǝv��Ȃ��Ă͂����Ȃ��B�v�ƌ����Ă�����B����ŋC�y�ɂȂ鐶�k��e�����邪�A���M���Ȃ����Ă��܂����k������B
���ԃe�X�g�̌��ʂŎ��M���Ȃ����Ėڂ�����ł������k���A�ъԊw�Z�Ńo�[�x�L���[�����ۂɁA�̂���������m���Ă������߂ɂ݂�Ȃ��瑶�݂�F�߂��A�����Ɏ��M�������Q�w���ɂ͖ڂ������������Ă����Ƃ����������B
���������Ӗ��ł��A���w���̎��ɂ��낢��Ȍo�������Ă������Ƃ��K�v�B���ɒɂ݂̂���o�������Ă������Ƃ��K�v�B���ۏ�Ԃň�����q�͌オ��ρB
�R�~���j�P�[�V�������[���ݒu���A���ی�A���ꏊ�̂Ȃ��q�����ƂȂ�����ꏊ�Ƃ��Ă���B�ی������������������������Ă���B
�T�j�@�q�ǂ��̐���
��������͑����Ȏ����B���낢��Ȗ�肪�N����B�����A��̂��������q�͂��̕���������B���܂Ŏ�̂����������Ƃ̂Ȃ��q�Ȃ�ł��ƌ�����ƁA��������Ȃ�ł��Ǝv���Ă��܂��B�ǂ����Ŏ肪������Ȃ�������Ȃ��B
���鎞�A�w�Z�ɂ��ꂳ��u�����̂��ٓ��ɋ��J�c����ꂽ�̂ł��������Ȃ������̂Ŏq�ǂ��ɒ��ӂ��Ă��������v�Ƃ����d�b���������Ă������Ƃ��������B
�e�͎����̎q�ǂ��̂��Ƃ͋߂ɂ��Ă悭������B���ꂾ���ɋߎ���I�ɂȂ��Ă��܂��B����Č���l�̃A�h�o�C�X���K�v�B
�T���W�I�w�@�ł͒ʊw��斈�ɒn��ʍ��k������{���Ă���B�����ł͒��P���獂�R�̕ی�҂��ꏏ�ɍ��k����@�����B
���P�̕ی�҂���u�ʊw���̃o�b�N���d�������Ƃ��Ȃ�Ȃ����v�Ƃ������₪�悭�o��̂����A���w�N�̕ی�҂��u����������������������A�����Ɋ���邩����v�ł���v�Ƃ��������������Ă����B��y�̕ی�҂̘b���Ĉ��S����B
�q�ǂ��͒��R�E���P������ł͐e�ɑ��āu���邳���ȁv�Ƃ��u�ق��Ă��Ă�v�Ƃ��������Ă݂��邪�A���R�ɂȂ�Ɛe�̌������Ƃ������悤�ɂȂ�B��͂荧�k��ŁA���R�̕ی�҂��u���R�ɂȂ��Ă���ƒj�̎q�̈�ĕ����킩��܂����B����͗]�v�Ȃ��Ƃ����Ȃ����Ƃł��v�Ƙb���ꂽ���Ƃ��������B
�w�Z�ē��̎ʐ^�ɂ���悤�ɒ����U�N�Ԃł̐����͊O�������łȂ����g���ʐl�̂悤�ɐ�������B���N����ɂ����Ȃ�Ƃ����C���[�W�������Ĉ�Ă��邩�B�������悯��Ƃ�����������Ă�����q�ǂ��͈炽�Ȃ��B
�e���C�����ɗ]�T������A�q�ǂ����C�����ɗ]�T���ł���B
�e������������Đڂ���ΐl�̋C�������@���邱�Ƃ̂ł���q�Ɉ�B
�T���W�I�ł͏㋉���ɂȂ�ƒ��Ԃɑ���C�����̗D�������k�������B
�e�͎q�ǂ��̂ł��Ȃ����Ƃ�����Ă����悤�Ƃ��邪�A�q�ǂ����ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ��āA�ł��邱�Ƃ�����ĂȂ��ꍇ������B���t�������ŁA�S�ċ����Ă��܂��Ă͂��߁B
��Ă��悤�Ɏq�͈�ƌ�����B���t���u�Ȃ����̎q�͂킩��Ȃ��̂��낤�v�ƌ������Ƃ����邪�A�킩��悤�ɂ��Ă��Ȃ��ꍇ�������B
�q�ǂ��͒Z���Ԃł͕ς��Ȃ����A�����͕ς��邱�Ƃ��ł���B�q�ǂ���ς���O�Ɏ����̌�����ς��Ă݂�B�q�ǂ��ɘb��������ꍇ�ł��A�u�����Ƃ���Ă���̂��v�Ƃ����ꍇ�Ɓu�ǂ������q�́v�Ƃ����̂ł͎������S�R�Ⴄ�B
�h���E�{�X�R�̌��t�Ɂu����������邾���ł͑���Ȃ��B���肪������Ă���Ɗ����Ȃ�������Ȃ��B�v�Ƃ������t������B�搶��e�����̎q�̂��߂Ǝv���ĂP���Ԑ������Ă��A���肪�����v��Ȃ���Ή��ɂ��Ȃ�Ȃ��B
�U�j�@�T���W�I�̋���
�J�g���b�N�̃~�b�V�����X�N�[���Ƃ��ď@�����炪��ɂȂ��Ă���B���P�ł͏T�Q���ԏ@���̎��Ԃ�����i�Z�����S���j�B�����A�@����������̂ł͂Ȃ��A�@���ŋ�����B�@����ʂ��Đ������A�l������������B�ƒ�̏@�h�͖��Ȃ��B
���N�͂P�W�W�������w�B�P�N���X�̐l�����S�V���ɁB
�T���W�I�w�@�͍��Z��W���Ȃ��A�r���A�]�Γ��Ŕ����鐶�k������B
�P�N���X�̐l�������Ȃ���悢�Ƃ������̂ł��Ȃ��B�N���X�̃G�l���M�[���Ȃ��Ȃ�B
���P�ł͊w�K�̏K���Â�����B�h�肪��������o��̂����̂��߁B
�h�肪���Ȃ��Ȃ����k�́A���Ԃ̎g�����⎩���̃R���g���[���Ɋւ��čH�v���K�v�Ȑ��k�B
���P�A���Q�Ŋw�K�̏K���Â����ł��Ă���U�N��̑�w�����͊y�B
���P���獂�P�͊e�w�N�S�N���X�Ґ��B���Q�E���R�͂U�N���X�Ґ��B
���P���獂�P�܂ŏK�n�x�ʃN���X�͂Ȃ��B�ꕔ�ɕ������Ƃ����邪������P���ɕ����B
���Q�ŕ��n�R�N���X�A���n�R�N���X�ɕ������B�{�l�̊�]�ɂ��B
���n�A���n�ɂP�N���X����֍Z�N���X��ݒu�B���C�̉Ȗڐ��������B���тƊ�]�̗����B
�p��͍��P�܂Ńv���O���X���g�p�B�a�n�n�j�S�܂ŁB
�S�C�����ƂU�N�Ԏ����オ�肪�����B
�����͑S���J�E���Z���[�̂���Ő��k�Ɛڂ��Ă���B
�T���W�I�̋���͗\�h����B�Ȃɂ������Ă���ł͂Ȃ��A���̑O�ɃP�A���l����B
���̓o�Z�̎��Ԃ����k�̗l�q�������ő厖�B�����ԓx�ɉ�������ƌ����B
�ʒk���ł��炽�܂��č\���Ă���Ƃ��ł͂Ȃ��A���R�̂ł���Ƃ��̗l�q���厖�B�x�ݎ��ԂɊO�ŗV��ł��鐶�k�̑��ɍs���Ċւ������B�T���W�I�ł͒��P�łP�Q�`�P�R���̐搶�Ƃ������B���ꂼ�ꂪ�ʂ̊p�x����q�ǂ�������B
�ی�҂Ƃ̖ʒk������I�ɗ\�肳��Ă��邪�A���ł��o�����Ă��Ă��������Ƙb���Ă���B�ی�҂ɂ͐��k�ƈꏏ�ɐe�����w���Ă��炤����ł���B�s�����ɂ������̐l���Q������Ă���B�w�Z�ɗ���̂ɒ���������l������B
�e���w�Z�ɗ��Ă���Ǝ��R�Ɗw�Z�̗l�q���킩��ԐړI�Ɏq�ǂ��̂��߂ɂȂ��Ă���B
���e�̐������������A�ŏ��͖�������������Ă����������X�Ɏ����̂��߂ɎQ�������悤�ɂȂ�B�������̂Ȃ����������ł���̂��悢�炵���B�T���W�I�Ղł͐e���̏Ē����o�X���Ă���B�q�ǂ��ɂ������̂͒S�C�����ł͂Ȃ��B
�����̂����T�������Ɛ��B�����������₵�����B
�u��@����_���ɂȂ��ăT���W�I�ɖ߂��Ă���l���R���B
�����̐�C�����͂P���i�p��b�j�B
���ϔN��͂R�X�B
�Z���A���Z���͐_�����A���B�T���W�I��̐l���Ō��܂邪�A��ɋ���W�ɏڂ����l���A���B�͍��Z���͐��k��l��l�������̎q�ǂ��̂悤�Ɏv���Ă��āA���k�Ƃ̊ւ�荇�������[���B
�V�j�@�N���u�����Ɋւ���
�T���W�I�̐��k�͂��ƂȂ����ƌ����邪����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�����B
�N���u���������Ƃ̗����̂��ߊ������̓����̐��������邪�A������������Ă���B
�T���W�I�̃N���u�����́A�e�j�X�����S�����ɏo�ꂵ���肵�Ă��邪�A�I��{���̂��߂̃N���u�ł͂Ȃ��B
�N���u�������w�Z�����̗��ւ̂P�B�N���u������ʂ��ėF�l�W���͂��߂��낢��Ȃ��Ƃ��w�ԁB���M�����[�ɂȂ邽�߂̓w�͂�M�����[�ɂȂ�Ȃ��l�̑��݂̑����m�����肷��B
�N���u�̊������͉E�E�y�B�N���u�̉����͊�]�������A���w���͂X�W�����Q���B
���E���E���̕��ی�͕�K�ɁB
�N���u�����ʼn^�����͌����Ƃ��Ē����ʂɊ����B���R�̉ċx�݈ȍ~���Z���ƈꏏ�ɁB
�������͒����ꏏ�Ɋ������Ă���B
�W�j�@��w�������ʂɊւ���
�O�R�N��w��������
�@�@�@�@�@����@���s�@�ꋴ�@���H��@���k�@�}�g�@�k��@�������v
�����@�@�@�U�@�@�@�P�@�@�@�Q�@�@�@�V�@�@�@�@�Q�@�@�@�P�@�@�@�S�@�@�@�T�W
�����@�@�@�T�@�@�@�O�@�@�@�Q�@�@�@�T�@�@�@�@�P�@�@�@�P�@�@�@�P�@�@�@�R�V
�@�@�@�@�@����@�@�c��@�@��q�@�@�����@�@�R�@�@�����@�@�����@�@�@���@�@���ȑ�
�����@�@�@�S�P�@�@�@�R�U�@�@�@�Q�Q�@�@�P�P�@�@�@�P�V�@�@�@�P�R�@�@�@�P�X�@�@�@�T�@�@�@�@�S�Q
�����@�@�@�Q�W�@�@�@�Q�Q�@�@�@�P�P�@�@�@�T�@�@�@�@�W�@�@�@�@�V�@�@�@�P�P�@�@�@�R�@�@�@�@�R�O
�����Ɛ��P�V�Q���ɑ��铌��A���c��ւ̌������i�Ґ��̊����i�`���j�͂R�W�D�S���B�l�`�q�b�g�ւ̊����i�a���j�͂P�X�D�W���B��N�̂`���͂X�Q�D�W���A�a���͂R�W�D�P���B��
���������Ō���A��w���i���т͍�N�̕����悩�������A���N�����N�̐��k�����Ă̌��ʂœ��e�I�ɂ͖������Ă���B����܂ł��A�ǂ��ɉ��l�����������������Ă������Ƃ͂Ȃ��B���k�ɑ��u�]�̊w�Z�Ɍ����ō��i���Ă��炦��悢�B
�����̖����������邽�߂ɑ�w�ɐi�w����B���̂��߂ɁA�܂������������������̂��A�����ōl���邱�Ƃ��d�v�B���̏�ŁA�w�Z�͂��̑�w�ɓ����悤�ɐi�H�w���A�i�w�w���ŋ��͂�����B�����A���k�ɑË��͂���Ȃƌ����Ă���B
���Q�ŕ��n�A���n�̃R�[�X���������邪�A�{�l�̊�]�ɂ��B
���n�A���n�̑I���ɍۂ��āA���P�̂Ƃ��ɂQ���R���̐i�H�K�C�_���X���s���B�T�O���߂����Ɛ����͂�ŃO���[�v�ɂȂ��Ęb���B�������������w�̎��ɍ��Z�ɂ�����y�̘b��������̂ŁA�b�����g�߂Ɋ�������̂��U�N��эZ�̂悳�ł���B
�w���̒��ŁA�w�Z���i�ǂ��̊w�Z���ł����j�͖��ɗ����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B���ꂩ��͊w�K���i�����w�̂��A�ǂ������w�K�������̂��j�������B
�X�j�@�O�R�N�������ʂɊւ���
�`�������ʁi�Q���P�����{�j
��W�l���@�j�q�P�O�O��
�@�@�@�@�@�@�@�@�O�R�N�@ �@�O�Q�N
����Ґ��@�@�@�T�V�P�@�@�T�P�S
�Ґ��@�@�@�T�Q�O�@�@�S�V�O
���i�Ґ��@�@�@�P�S�U�@�@�P�S�P
�����ρ@�@����@�@�@�Z���@�@�@�Љ�@�@�@���ȁ@�@�@���v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�U�P�@�@�@�@�U�P�@�@�@�@�S�S�@�@�@�@�T�Q�@�@�@�Q�P�W
�@�@�@�@�@�@�@�@�i�P�O�O�j�@�@�i�P�O�O�j�@�@�i�V�T�j�@�@�i�V�T�j�@�@�i�R�T�O�j
���i��_�@�S�ȂQ�S�Q�_�i�R�T�O�_���_�j
�a�������ʁi�Q���S�����{�j
��W�l���@�j�q�U�O��
�@�@�@�@�@�@�@�@�O�R�N�@ �@�O�Q�N
����Ґ��@�@�P�O�P�X�@�@�W�X�W
�Ґ��@�@�@�V�P�W�@�@�T�X�V
���i�Ґ��@�@�@�P�S�P�@�@�P�Q�O
���i�ҕ��ρ@�@����@�@�@�Z���@�@�@�Љ�@�@�@���ȁ@�@�@���v
�@�@�@�@�@�@�@�@�T�Q�D�T�@�@�V�T�D�X�@�@�T�S�D�P�@�@�T�S�D�S�@�@�Q�R�V�D�O�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�i�P�O�O�j�@�@�i�P�O�O�j�@�@�i�V�T�j�@�@�i�V�T�j�@�@�i�R�T�O�j
���i��_�@�S�ȂQ�P�V�_�i�R�T�O�_���_�j
�`�E�a�̂Q����������{�B
�T���W�I�u�]�̐l�ɂQ��`�����X��^���邽�߂ɁB�P��Ŏ��͂��ł��Ȃ��q������B
�O�R�N�����ł͂a�����̍��i�҂P�S�P�����R�T���͂`�����Ŏ��s�������B
�`�E�a�d�������Ă������b�g�͂Ȃ��B�Q��̃`�����X������Ƃ��������B
�������J��グ���o���ꍇ�͗��������l����B�O�R�N�ł͂S�U���J��グ�B
�N�ɂ���Ă͂Q���Ƃ�����������B
�������͂��̊w�Z�̊�Ƃ��A�������ɂǂ��������k���~�������������ƌ����邪���ۂ͓���B
���w�����Ńe�X�g��̕��l�͏オ���Ă��邪�A���w�҂̑w�͎����Ƃ��Ă͂��܂�ς���Ă��Ȃ��B
�O�R�N�����̃G�s�\�[�h�Ƃ��āA�����̌�A������u�����Ŏ��s�������A�ǂ����Ă��T���W�I�ɍs�������B���Z�������Ȃ��̂ŁA��w���o�Ă��狳���Ƃ��ăT���W�I�ɍs���܂��B�v�Ƃ����莆����������B
���F�w���@�O�S�N�����v��
�������\�̕�W�l���̔z����ύX
�P���@���q�P�P�O���@���@�P�Q�O��
�Q���@���q�@�X�O���@���@�@�V�O��
�R���@���q�@�Q�O���@���@�@�R�O��
�_�ސ�w���@�O�S�N�����o����j
�u����v�̏o����j
�y�P�z�����ɑ��鍑��Ȃ̍l�����E�E�E
�i�P�j���w�������݂Ȃ���́A����܂ł����Ȓn��ł����������ȍ���̎��Ƃ��Ă���̂��Ǝv���܂��B�ł�������w��A���ۂɎ��Ƃ��n�߂�O�ɁA����Ƃ͂ǂ�ȗ͂���Ă�ȖڂȂ̂��E���Ƃɂ͂ǂ̂悤�Ȏp���ŗՂނ̂��E�ƒ�w�K�͂ǂ̂悤�ɍs���̂��A�ȂǂƂ������Ƃ���������ɍl���Ă����܂��B
�i�Q�j�����́A�����ɂ��čl���邽�߂̓y��ƂȂ邽�����ȗ͂��͂�����̂��ƍl���Ă��������B
�i�R�j����܂ł̖{�Z�̓����ł́A�Q��̕��͑�̑��ɁA��{�I�Ȋ����⌾�t�A���p��₱�Ƃ킴�Ȃǂ��o�肵�ė��܂����B����́A���w�Z�܂ł̊�b�I�ȓ��e�𐽎��ɐg�ɂ���w�͂Ǝp�����������l�����ɁA���w���Ă������������ƍl���Ă��邩��ł��B�����Ȏp��������A����{�Z�ʼn߂����U�N�Ԃł�������Ƃ�������̊w�͂����Ǝv���܂��B
�y�Q�z�Q�O�O�S�N�x�����̏o����j�E�E�E
�i�P�j���w�Z�U�N���܂łɂ������Ă����Ăق����ƍl����A�u���Ƃv�ɂ��Ă̗�
�@�����ɂ��ẮA�V�w�K�w���v�̂̂U�N���܂łɊw�K����͈͂̒��ŏo�肵�܂��B�P�ɂ��̊������ǂ߂邩�E�����邩�Ƃ����͂��݂邾���łȂ��A�P�P�̊����������Ă���Ӗ���������Ɨ������Ă��邩�Ƃ������Ƃ����킹�Ă݂Ă����܂��B
�A���p��₱�Ƃ킴���ӂ��ށu���Ƃv�̓����Ɋւ�����́A�P�P�̌��t��\�����A���������̂Ƃ��Ďg���邩�E�����ł��邩�Ƃ����͂��݂Ă����܂��B���������ē���I�ɂ����Ύg���錾�t��\���𒆐S�ɏo�肵�܂��B
�B�ȏ�@�A�́A�o��̖��ꂩ����O�i�N�x�ɂ���Ă͖��̔ԍ��ɂ��ꂪ���邩���m��܂��j�ɂ�����܂��B���ꂩ����O�܂ł̍��v�_�́A��N�Q�T�_�O��ł��B
�i�Q�j���̒��������������͂ɑ��A������Ƃ����ǂ݂��Ȃ����
�@��N�Ɠ������A���͑�́A�o��l���̐S�̓��������ނ��Ƃ𒆐S�Ƃ��đI�����ƁA�������i�]�_���j�̂Q����o�肵�܂��B
�A���͂̕��ʂł����A���ɖ{�Ŗ�R�`�S�y�[�W���x���l���Ă��܂��B
�B�܂����͂̓�Փx�ł����A���w�Z���w�N���璆�w�O���̎�����k��ΏۂƂ����}������o�肷��\��ł��܂��B
�C�����͂Ƃ��ẮA�������甲���o������E�����̕\����p���Ď����ł܂Ƃ߂��肷��悤�Ȗ������肩�o�肵�܂��B
�D���͑�Q��ŁA���v��V�T�_�O��ł��B
�y�R�z�������̓_�̃|�C���g�Ɗ�E�E�E
�i�P�j�����̏���������L�q���̖��Œ��ŁA�뎚�E���╶�����Ă��˂��ɏ�����Ă��炸�ǂ݂Â炢���̂ɂ��Ă͂P�_���_���܂��B�����͈ꕶ���ꕶ���Ă��˂��ɏ����悤�ɂ��Ă��������B
�i�Q�j��������K���ȉӏ��╶���o���A���邢�͎����𐔂���ݖ�ɂ��ẮA�ݖ�ɂ����Ǔ_�̎w���ɏ]���Ă��������B������A�w�����������Ă��܂������Ăł����Ă��A����ɂ���Ď��ɕs�����Ȃ��悤�ɍ̓_���������܂��B
�i�R�j�L�q���̖��ł͍̓_�ɂ������ĕ����_��݂��Ă���܂��B�͔͉Ƃ��ƂȂ��Ă��Ă��A�|�C���g�������Ă������ɉ����������_���^�����܂��B
�u�Z���v�̏o����j
�y�P�z�{�Z�ɂ����鐔�w����̂˂炢
�@�{�Z�ł́A�ȉ��̂悤�ȖړI�Ő��w�����i�߂Ă��܂��B
�P�D����I�ɗl�X�ȏ�ʂɓo�ꂵ�Ă���l�X�Ȑ��l���邢�͗ʂ�������Ƃ����T�O�ł��ݎ��J���琬���Ă����܂��B
�Q�D����I�Ȏ����ɂ��āA���̌��ʂ��������Ȃ���A���𗧂ĂȂ���l���Ă����͂��琬���Ă����܂��B
�R�D������_���I�A���ۓI�ɍl���A���ʓI�ɂ��������Ȃ���A�������̕��@�Ƃ��Ċ��p���Ă����͂����Ă����܂��B
�S�D�������̓��͗l�X���邱�Ƃ��w�сA�L������ŕ��������Ȃ���������ɂȂ��Ă������z�̗͂���ĂĂ��܂��B
�T�D���m�̖��ɓ��킵�A������������邱�Ƃɂ���āA�V���������̊�҂̊����ƐV���ȉۑ�ɒ��킵�Ă������Ƃ����ӗ~�̈琬�����Ă����܂��B
�y�Q�z�������̕�����
�Q�O�O�Q�N�ȑO�̓��������������Ȃ���A�Q�O�O�R�N�����ł͕��j�����߂ďo�肵�Ă��܂����B
�Q�O�O�S�N�����ł��A��N�̓����̕��j�������p���ŏo�肵�Ă����܂��̂ŁA�������̕������͂Q�O�O�R�˂�ƕς�肪����܂���B�ȉ��ɂ܂Ƃ߂Ă����܂�����Q�l�ɂ��Ă��������B
�i�P�j��{�I�ȑg�ݗ��ĂƂ��ẮA��萔��z�_�Ȃǂ͗�N�Ƃقړ��������ō쐬���Ă����܂��B
�i�Q�j���P�Ōv�Z�͂��m�F���܂��B�����̎l���v�Z�E���������̎l���v�Z�E�t�Z�ȂǁB
�V����ے��ł͕����Ə����̍����v�Z�͈���Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂����A�����ƕ����̊W�͑�Ȃ��ƂȂ̂ŁA���G�ɂȂ�Ȃ��z�������Ȃ���A�����ƕ��������������v�Z�ɂ��Ă͏o��͈͂ƍl���Ă��܂��B�܂��A�����̉����揜�̌v�Z�����܂蕡�G�ɂȂ�Ȃ��悤�ɔz�����Ȃ���A�ѕ������܂߂čl���Ă��������Ǝv���Ă���܂��B
�i�R�j���Q�`�S�ɓƗ�����݂��A�F�X�ȕ���̖��ɂ��Đݖ₵�܂��B
�P�ɋZ�p�I�ɓ��Ă͂߂Ă����悢�Ƃ������͔����A���̍\����ǂݎ��A���̏�Œm�����g���Ȃ�������Ă����ԑ���ӎ����Ă���܂��B
�܂��A���̔z��́A���Q�ł͕��ՂȔ��z�ʼn������肩��o�����A���R�A���S�Ɛi�ނɂ��������ē�Փx�͍����Ȃ�悤�H�v���Ă����܂��B���̒��ɂ́A�̓r����]����������܂߂ďo�肵�܂��B�Ⴆ�A���ځA��`�̖ʐς�₤�悤�Ȑݖ�͔����܂����A�}�`�I�ɉ�ǂ��āA�O�p�`�Ⓑ���`�Ȃǂ̂悤�Ȏl�p�`�ɕ�������Ȃǂ̍H�v�����āA���ʂƂ��đ�`�̖ʐς��o���Ƃ����悤�Ȗ��͂��肤��ƍl���ĉ������B��������ɓ�Փx�̍������͔����܂��B��r�I���Ղɔ��z���Ȃ���ɂ��ǂ蒅����悤�A�S�̓I�ɋɓx�ȓ�₪�łȂ��悤�H�v���Ȃ����₵�Ă����܂��B
�i�S�j���ł́A�������̐ݖ��݂��A�ǂݎ��ƑO��Ƃ̊֘A�ʼn�i�߂Ă����͂������Ă����܂��B
���̕��͂��炻�̓��e��������Ɠǂݎ��͂��K�v�ł��B����ɃO���t��ǂݎ������A���������Ă������肵�Ȃ���̎��������ޗ́A�}�`�̗l�q��ǂݎ���āA�Ɍ��т��Ă����Ȃǂ̓������ɂ߂�͂����������ƍl���Ă��܂��B
�S�̓I�ɕ��G�Ȗ�������A���ł��Ō�܂Œi�K�����ǂ��Ė���i�߂Ă����H�v�����܂��B���ɁA�e���̑��A����ڂ�����ł́A��b�I�Ȓm���ʼn��Ă�����悤�Ȗ����o�肵�܂��B�܂����̓�Փx�ɂ��ẮA�قۍ�N���݂ɂ��Ă������ƍl���Ă��܂��B
�T�j���̑萔�́A�Q�O�����{�ɂ��āA�u���X�}�C�i�X�P�`�Q�͈̔͂ŏo�肵�Ă����܂��B�܂��A�z�_�͌v�Z��肩����܂ŁA�������Ȃ��悤�ɂقٓ����悤�ɔz�_���Ă����܂��B
�U�j�`�����A�a�����A�b�����̂��ꂼ��̖��ɂ��ẮA���ɓ�Փx�ɍ������Ȃ��悤�ɍ�₵�Ă����܂��B�z��Ȃǂ͂قۓ����悤�Ȃ��̂ɂȂ�Ǝv���܂�����A���d�˂邲�ƂɊ���Ă���Ǝv���܂��B
�u�Љ�v�̏o����j
�y�P�z�{�Z�ɂ�����Љ�ȋ���̂˂炢
�@�������_�ސ�w���̎Љ�Ȃł͂U�N�Ԃ̋����ʂ��A�l��l�̐��k���A�l�Ƃ��Ă̖L�Ȑ��E�ςƎ����S�����Ă�������`�����������Ǝv���Ă��܂��B���̂��߂ɁA
�i�P�j�u���P�v�ł͂܂��A���E�̐l�X���ǂ�ȎЉ������Ă����̂��A����`���Ă����̂��Ƃ����w���E�̗��j�x�����Ă����܂��B�����āu���Q�v�ɂȂ�Ƃ��̖ڂ���{�ƃA�W�A�Ɍ����āA����܂Ŏ����ǂ��Ȃ���l����[�߂�
�����܂��B���̗��j�̎������w�Ԃɓ������Ă͏�Ɂw�Ȃ��H�x�ƌ����^��������Â��ė~�����Ǝv���Ă��܂��B����͐_�ސ�w���̎Љ�Ȃ��ł���ɂ��Ă��鎖�̈�ł��B
�i�Q�j�u���R�v�ł́w���B�̎���Ɛ��E�x�Ƃ����e�[�}�̉��ɁA�u�n���v�Ɓu�����v�̕��삩�猻��Љ�𑍍��I�Ɍ��Ă����܂��B�u���j�v�̊w�K�Ŕ|�����v�l�͂���ӎ����X�ɍL���[�߂Ă����܂��B�u�I�[�X�g�����A���C�v������ɓ���Ȃ��琭������E�����̖�蓙�������������g�̖��Ƃ��Ĉꏏ�ɍl���Ă��������Ǝv���Ă��܂��B
�i�R�j���Z���ɂȂ�Ƃ��悢���含��[�߂��w�K���n�܂�܂��B�����́u�i�H�v��T��Ȃ���A�Ɍ������͂�t���Ă����܂��B�I���ŎȖڂ�O�ꂵ�Ċw��ł����܂����A���Ƃ��T�����u���R�v�ł́A�S���̕K�C�Ƃ��āA�U�N�Ԃ̎Љ�Ȋw�K�̏W�听�Ƃ��āw�Љ���x��u���Ă��܂��B�����ł͂��ꂩ��Љ�ɏo���l�̐l�ԂƂ��āA�܂������̗���Ȃǂ���A���݂̎Љ�������߂Ă����܂��B���������̎Љ�łǂ������Ă��������l����Ȗڂł��B���̒�����i�H�ւ̈ӎ���[�߂Ă������k���吨���܂��B
���̂悤�Ɂu���j�v�u�n���v�u�����v�Ƃ����e�X�̕���Ɓu�����v�̊w�K��ʂ��āA�L�����E�F����s�����ӎ��Ŗ������ւ��͂���Ă����Ǝv���Ă��܂��B
�y�Q�z�������̕�����
�i�P�j��N�x����̕ύX�_�ɂ���
�@��{�I�ɂ́A�P�ŏq�ׂ��y�˂炢�z�ɏ]���āA�u�n���v�u���j�v�u�����v���삩��o�肵�Ă����܂����A��N�x����̕ύX�_������܂��B
�@�n������E�E�E��N�܂ł́A�����ɂ���ďo��͈͂�ς��Ă����܂������A���N�x�͊e�����Ƃ������͈͂ŏo�肵�܂��B
�A�����E��������E�E�E��N�܂ł́A�u�����v����E�u�����v������e�X�P�肸�o�肵�Ă��܂������A���N�x�͌����Ƒ��������ɁA�P��ɂ��ďo�肵�����Ǝv�����܂��B
�i�Q�j�e���삩��
�n������
���e�����Ƃ��w���{�̔_�q�ƂƐH�Ɩ��x�ƌ����ϓ_����̏o��Ƃ��܂��B
�@�E�e�n�̓��F����_�q�Ƃɂ���
�@�E���ƕ�
�@�E���{�̔_�q�Ƃ̓����Ƃ��̕ω�
����������n�}��O���t�����čl��������o�肵�����Ǝv���܂��B
���j����
���e�����Ƃ��ߑ�ȑO�Ƌߌ�����P�肸�o�肵�܂��B
���ߌ���͖���������̐�̎���܂ł͈̔͂Ƃ��܂��B
�����ȏ��ɂ���j����}�ł���l�����������o�肵�܂��̂ŁA���J�Ɍ��Ă����ĉ������B
���P�ɔN���⎖���E�l���Ȃǂ̒��ړI�Ȓm�������łȂ��A�����̌�����w�i�E�e�����֘A�t�����o������Ă��������Ǝv���܂��̂ŁA���i���玖���̔w�i�Ȃǂ��l���ĕ����Ă����܂��悤�B
�����E��������
�����N�x���e�����Ƃ��A�u�����v�u�����v�Ɩ����Ȃ��ŁA�u�����E�����v����łP��ɂ��ďo�肵�܂��B
���e�����Ƃ����������ނɂ��Č����̊�b�I���e�����₵�܂��B
���������́u�Q�O�O�R�N�����O�̏d��[�X�v��u�����v����ɒ��ӂ��ĕ����ĉ������B
�������̊�b�I���e�Ƃ͍�N�Ɠ��l�A�u���{�̐����̎d�g�݁v�u���@�̎O�����v�u�������v�Ɋւ�镔�������S�ƂȂ�܂��B
���o�ςɊւ�镔���͏o�肵�܂���B
�u���ȁv�̏o����j
�y�P�z�{�Z�̗��ȋ���̂˂炢
�@���ȂƂ����Ȗڂ́A���R�ɑ��鋻���E�S�A�^����o���_�Ƃ��A�����E�ώ@��ʂ��āA���̂����݂��w�ҁA�w�Ղ��̎��g�̐S�Ɛ��������L���ɂ��Ă����w��ł���Ƃ����܂��B
�@�_�ސ�w���ł́A���̗���ŁA������ώ@���d�����A����𒆐S�Ɏ��Ƃ�W�J���Ă��܂��B���ɒ��w�ł͐��k�����̋@��𑽂��݂��A���k��l��l������̎�Ɠ������A���R�ɑ�����[��������������悤�ɂ��Ă��܂��B�܂��A���w�Q�N�ł̓t�B�[���h���[�N�u���ԑ�̐X�v�Ɏ��g�݂܂��B���O�w�K��X������̃|�����e�B�A�̕��X�Ƃ̌𗬂�ʂ��Ċ��w�K���s���܂��B���Z�����Ȃ�ƕK�C�́u�����v���͂��߁A�����́u�i�H�v��T��Ȃ���A�Ɍ������͂₳��ɐ��ɐi�ނ��߂̊w�K�ɓ���܂��B�I�𐧂ŎȖڂɑ����̎��Ԃ������w�҂܂��B�P�Ɏ��łȂ��A��]���Ċ��W�������u���Ȃǂ��g�ݍ��ނȂǁA����̕������ɂȂ�Ȃ��H�v�����Ă��܂��B
�y�Q�z�������̕�����
�@��L�u�˂炢�v�ɂ���悤�ɁA���R���ώ@�E�����������Ƃ𒆐S�ɏo�肷����j�ł��B�o��ɂ������ẮA���̓_��厖�ɂ��܂��B
�@���w�Z�Ŋw�����ŁA���w�ł����������w�K�����ɂ����ĕK�v�ƂȂ��b�I�Ȋw�͂�����B
�A���R���ۂ̂��ꂱ���m���Ƃ��ċL������ɏI��炸�A�@���I�ɂƂ炦�邱�Ƃ��ł��Ă��邩�B
�B���R���ۂ𗝉������ŁA�o���Ă��Ȃ���ςȂ�Ȃ������̖��́A����̎g�����Ȃǂ��g�ɂ��Ă��邩������B
�C�����E�ώ@�̕��@�A���̐�������舵�������ł��邩�A�܂��������ʂ����ƂɎ����ōl���āA���������_�����Ƃ��ł��邩�B
�D�ŋ߂̘b��i�Ⴆ�A�ΐ��Ƃ��̑�ڋ߂Ȃǁj���ꕔ�o�肵�܂��B
�Q�O�O�S�N�x�@���ȓ������o��͈́i���悭�����Ă����Ăق�������j�E�i���o�肵�Ȃ�����j
�u�����Ɗ��v
�P�D�A���̈炿��
���ԂƎ�
�������ƐA���̈炿��
���A���̕���
���G�߂ƐA���̂��炵
�Q�D�����̈炿��
�����̑̂ƈ炿��
�������̐����̈炿��
���G�߂Ɠ����̂��炵
�������̕��ށ@
�R�D�l�̑�
���H���̏����Ƌz��
�����t�̏z�Ƃ͂��炫
�u�����ƃG�l���M�[�v
�P�D�͂Ƃ͂��炫
���͂Ƃ�
�Q�D�d�C
���d����
�R�D�����̕ω�
�����̂Ƃ����Ɛ��悤�t�̂���
�����n�t�̐���
�����̔R����
���C�̂̐���
�S�D�M�E���E��
�������̏�ԕω�
�����x�ƕ��̑̐�
�����̐����Ɠ`����
�����̐i�ݕ�
�u�n���ƉF���v
�P�D�V�̂̓���
�����̓����Ɩ�������
�����̓���
���f��
�Q�D�n�\�̕ω�
���C���Ƃ��x�̕ω�
���V�C�̕ω�
����̐��̂͂��炫
���n�w�Ɗ��
�����j��
�����w���@�I�[�v���L�����p�X
�����@�P�O���Q�T���i�y�j
���ԁ@�P���Ԗځ@�@�X�F�R�O�`�P�O�F�R�O�@�Q���҂́@�X�F�Q�O�W��
�@�@�@�@�Q���Ԗځ@�P�P�F�O�O�`�P�Q�F�O�O�@�Q���҂͂P�O�F�T�O�W��
���e�i�����j
�@�@�@�@�P���Ԗځ@�@�@�@����@�@�@�@�@�Q���Ԗځ@�@�@�@���
�@�@�P�@�p��ŗV�ڂ��@�P�O�O�@�@�Q�P�@�p��ŗV�ڂ��@�P�O�O
�@�@�Q�@�����i�P�j�@�@�@�@�@�S�O�@�@�Q�Q�@�����i�P�j�@�@�@�@�@�S�O
�@�@�R�@�����i�Q�j�@�@�@�@�@�S�O�@�@�Q�R�@�����i�Q�j�@�@�@�@�@�S�O
�@�@�U�@�p�\�R�����D��@�S�O�@�@�Q�U�@�p�\�R�����D��@�S�O
�@�@�V�@���y���t���@�@�@�R�O�@�@�Q�V�@���y���t���@�@�@�R�O
�@�P�O�@�N�b�L���O���@�@�@�T�S�@�@�R�O�@�N�b�L���O���@�@�T�S
�@�P�P�@���p���@�@�@�@�@�@�R�O�@�@�R�P�@���p���@�@�@�@�@�@�R�O
�@�P�Q�@�������@�@�@�@�@�@�Q�O�@�@�R�Q�@�������@�@�@�@�@�@�Q�O
�@�P�T�@�d���e�j�X���@�@�U�O�@�@�R�T�@�d���e�j�X���@�@�U�O
�@�P�W�@�������@�@�@�@�@�@�S�O�@�@�R�W�@�싅���@�@�@�@�@�@�R�O
��]�҂�����ɒB�����ꍇ�A����]�ɓY���Ȃ��ꍇ���������܂��B
���l
�Q���ԗ����̎Q�����A�P���Ԃ����̎Q�����\�ł��B
�ی�҂̕��̌��w�͉\�ł��B
���������̎Q���E���w����t���܂��B
�㗚�͕K�v����܂��A�^���̂��߂̃V���[�Y�Ȃǂ͂��p�ӂ��������B
�����A�������k�R�[�i�[��ݒu���Ă��܂��̂ŁA�����Ȃ������k���������B
���ԏ�͂���܂���B���Ԃł̂����Z�͂��������������B
�\�����@
�Q������]�������́A�\�����ݗp���ɕK�v�������L���̏�A�X���AFAX�܂���E���[���ł����t���������B�i�K������]�����O��]�܂ł��L���������B�j
�Ջ�����@�O�S�N�����v��
�P��@�P���P�Q���@�j�q�T�O���@���q�T�O���@�Q�ȂS��
�Q��@�P���Q�S���@�j�q�Q�O���@���q�Q�O���@�Q�ȂS��
�R��@�Q���@�S���@�j�q�P�O���@���q�P�O���@�Q�ȂS��
�P��A�Q��͉��[���T�O�O�O�O�~��[�����āA���w�葱���Q���X���P�U���܂ʼn����ł���B
���J�͎����
���\���͎��X���@���i����i�X���V���j
��N��S�D�X���̑����B
�j�q�͂V�D�P�����B���q�͂Q�D�T�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�R�N�@�@�@�@�O�Q�N�@�@�@�@�O�P�N�@�@�@�@�@�O�O�N
�j�q�@�S�ȁ@�@�@�V�W�X�W�@�@�@�@�V�R�T�S�@�@�@�@�U�W�W�P�@�@�@�@�U�V�U�W
�@�@�@�@�Q�ȁ@�@�@�@�V�T�S�@�@�@�@�@�V�Q�S�@�@�@�@�@�V�V�Q�@�@�@�@�@�V�W�T
���q�@�S�ȁ@�@�@�U�P�Q�Q�@�@�@�@�T�T�X�W�@�@�@�@�T�O�P�V�@�@�@�@�S�X�X�S
�@�@�@�@�Q�ȁ@�@�@�P�S�Q�Q�@�@�@�@�P�V�U�R�@�@�@�@�Q�P�W�U�@�@�@�@�Q�R�R�V
���v�@�@�@�@�@
�P�U�P�U�X�@�@�@�P�T�S�R�X�@�@�@�P�S�W�T�U�@�@�@�P�S�W�W�S
������
��Ɛݗ��̑S������эZ�@���w����ٌ�m��\������
�i�����V���@�X���T���j
�@�g���^�����ԁA�����d�́A�i�q���C���Q�O�O�U�N�S���Ɉ��m�����S�s�ɊJ�Z��\�肵�Ă��钆����т̑S�����j�q�Z�ɂ��āA���É��ٌ�m��ٌ̕�m�L�u�P�R�P�l�i�j���X�P�l�A�����S�O�l�j���S���A���w�Z��j�����w�ɂ���悤�ɋ��߂�\�����ꏑ���R�ЂƓ��Z�ݗ�������ĂɗX�������B
�@���̖��ł͖��É��s�̏����c�́u���[�L���O�E�E�[�}���v�ȂǂP�T�c�̂��u������r�����邱�Ƃ͍��ʁv�ȂǂƂ��čR�c���Ă���B�ٌ�m�L�u�ɂ��ƁA�\������O�̂��Ƃ�ŏ�����́u�\������̎�|�͏������v�Ɖ����ɂƂǂ܂����B
�@�\�����ꏑ�ł́u�R�Ђ͒j�������Q��Љ�̌`���ɎЉ�I�ӔC������v�u���q�����₷��j�q�Z�̐ݗ��͎���ɋt�s���Ă���v�Ɣᔻ�����B
�@�������A�L�u�̂P�l�ł����{���q�ٌ�m�ɂ��ƁA�ٌ�m������ł��u����Ƃ̍s�����ƂȂ̂Ŏ��R�ł͂Ȃ����v�u�����̒j�q�A���q�Z�ɍR�c���Ȃ��̂ɍ����\�����ꂷ��̂͂��������v�Ɣ����鐺���������Ƃ����B�@��{�ٌ�m�́u�����Z�ɂ͓`��������A����܂œ��ݍ���ňًc�����������͂Ȃ��B����������̒j�q�Z�ݒu�͊�Ƃ��j�q�Ј������Ɋ��҂�������Ƃ������Ƃ̗��Ԃ��ł�����A�F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƙb���Ă���B���Z�̐ݒu�Ă͍��N�P���ɂR�Ђ��\�z�\�����B
�Q�w���������P�@��t�s���S�P�V�X�Z�œ���
�i�����V���@�X���T���j
�@��t�s����ψ���́A���N�x����s���̑S���E���E���Z�Ɨ{��w�Z�̌v�P�V�X�Z�ŁA�w�Z�Q�w����������B��N�S������w�Z�T�T��������������w�͒ቺ���w�E����钆�A�I�Ǝ��A�n�Ǝ��A����e�X�g�Ȃǂ̍s�������炵�A�N�R�O���Ԓ��x�̊w�K���Ԃ��m�ۂ��邱�ƂŁA�ɉ�������Ƃ肠��w�K�w�����s���_��������B�Q�w�����͑S���I�ɍL�����Ă���A�����ł��ꕔ�Ŏ��{����Ă��邪�A�s���S�Z�ł̎��{�͏��߂ĂƂȂ�B
�@�Q�w�����ł́A�O���͂S������P�O�����{�i�̈�̓��O��j�܂łŁA�����Ԃ̏H�x�݂��͂��݁A����͂P�O�����{���痂�N�̂R���܂łƂȂ�B�O���A������ꂼ��̊��Ԓ��ɉċx�݁A�~�x�݂̒����x�Ƃ����邪�A���Ԃ͂قڂ���܂Œʂ�Ƃ����B
�@�Q�w�����̃����b�g�Ƃ��Ă͉ċx�ݑO�A�~�x�ݑO�Ɋ����e�X�g���Ȃ����߁A�e�X�g�����Ȃǂɏ[�Ă鎞�Ԃ��y������A�I�Ǝ��Ȃǂ̍s���ɖW����ꂸ�A��b�E��{�̓O���K�n�x�ɉ������w�K���\�ɂȂ�B
�@����A�x�ݑO�ɒʒm�\���o�Ȃ����Ƃւ̕���̕s������A�P��̃e�X�g�͈͂��L���邱�ƁA�����x�Ƃ́u�J���x������v���ƂȂljۑ肪���邪�A�s���ς́u�i�āj�x�ݑO��x�ݒ��ɂR�Җʒk���s���ڕW���������邱�ƂȂǂőΉ��������v�Ƙb���A�����x�Ƃ̗L�����p��ڎw�����j���B���Z�����ւ̑Ή��ɂ��Ắu�s���v�������Ȃ��悤�z������v�i�s���ρj�Ƃ��Ă���B
�@�Q�w�����͊��ɐ��s�ō�N�x�����ĂɎ��{���Ă���ق��A���l�A���s�s�Ȃǂňꕔ���{�B�����ł͑D���s�A����s�A���P�Y�s�A�O�F���̈ꕔ�����w�Z�̂ق��A�Q�O�̌������Z�œ������Ă���B
�Q�w���������Q�@�e�Z���f�ցA�����拳��
�i�����V���@�X���P�Q���j
�@��������̋旧�����w�Z�A�{��w�Z�v�U�W�Z�ŁA���N�x����Q�w�������e�Z�̔��f�œƎ��ɓ����ł��邱�ƂɂȂ����B���F����w�Z�Â���𑣂��B
�@�拳�ς��u�旧�w�Z�̊Ǘ��^�c�Ɋւ���K���v�������B�w���̋��A�ċx�݂Ȃǂ̋x�Ɠ��̐ݒ�A���������̎����Ȃǂ��w�Z���ƂɌ��߂���B�Q�w�����̑S�w�Z�ł̓����͖ڎw�����A�e�͓I�^�p�����{����̂��������B
�@�Q�w���������ɂ��āA�拳�ς͂R���Ɂu�w���������ψ���v��ݒu���A������i�߂Ă����B���̓��\�ł́A�Q�w�����̗��_�Ƃ��āu���Ǝ��Ԑ�����������v�u�ʒm�\�̉����邱�Ƃŋ����ɂ�Ƃ肪�ł��A�ʎw���Ȃǂɂ��Ă���v�Ȃǂ�������ꂽ�B����ŁA�]���̂R�w�����ł��u���{�̕��y��G�߂ɍ����Ă��āA�C�����̋�肪�ł���v�u���ꂼ��̊w�����Ƃɂ��ߍׂ����w�����ł���v�Ȃǂ̌��ʂ��w�E����Ă����B
�@����ł͂O�Q�N�P���ɍ��肵���u�拳����v�A�N�V�����v�����v�̂��ƁA�w�Z�]�����x�A�w�Z��]���x�i�אڍZ�����j�Ȃǂ����A�w�Z�̋�����v��i�߂Ă������A��������̈�B�拳�ςɂ��ƁA�Q�w���������ɂ��āA���łɏ��w�Z�P�Z�A���w�Z�R�Z���O�������Ƃ����B
�@�s���ςɂ��ƂV�����݁A�s���łQ�w���������Ă���̂͏��w�Z�P�V�Z�A���w�Z�Q�V�Z����Ƃ����B�S���I�ɂ́A���s���O�Q�N�x����s���S�����w�Z�œ��������ق��A���l�s�Ȃǂł����N�x����̓��������肵�Ă���B
������т�S�s�œ����@�L�����{���s
�i�����V���@�X���U���j
�@�L�����{���s�͂T���A������ы�����s���̌����Z�ŗ��N�x���珇������������j�𖾂炩�ɂ����B�ɓ��g�a�s�����s�c��Łu�S�s�I�ɓ������邱�Ƃ������������v�Əq�ׂ��B�s���ςɂ��ƁA�����́g���ݏ�����h���s���A�����߂�s�o�Z���Ȃǂ̎q�ǂ��̐����w���������I�ɐi�߂邱�ƂȂǂ��ړI�B�����Ȋw�Ȃ́u�����Ȃǂŗאڂ��������w�Z�����ȘA�g�����P�[�X�͂邪�A�s�S��œ�������͕̂��������Ƃ��Ȃ��v�Ƙb���Ă���B�Ώۂ͗��N�S���ɍ�������㉺���̊w�Z���܂ߏ��w�Z�P�S�Z�A���w�Z�T�Z�B
�s���ς́u���ȕʂ̒S���������w�Z�������A���w�Z�Ő�含�̍���������s�����Ƃ��l���Ă���v�Ƃ��Ă���B�����w�Z�̑g�ݍ��킹�ȂǁA��ы���̋�̓I�ȕ��@�͍��㌟������Ƃ����B�{���s�͓��������s�̖k��Q�O�ۂɂ���l����S���P�O�O�O�l�B
����]�_�ƁE���ؒ�������̘b
�����������Ă��邪�A���Ɋ���������H��͂܂��Ȃ��B�����߂�����A�w�͂̒Ⴂ�q�ǂ��ɂƂ��Ắi���w���w�Łj��ւ��邫��������������B�܂����Ƃ������Ē��J�ȃV�~�����[�V���������ׂ����B
�����w���̊w�͒ቺ�@�ی�҂̂V�����s��
�i�����V���@�X���X���j
�@���t������{����Ă���V�w�K�w���v�̂ɂ��e���ɂ��āA���{�o�s�`�S�����c��͂X���A���������w���̕ی�҂̂V�����w�͒ቺ��S�z���Ă���Ƃ̒������ʂ\�����B�P�N���o���i�K�ł��A�����̕ی�҂��s�����������Ă��錻��������ɂȂ����B
�@�u�w�Z������v�v���e�[�}�ɂT�`�V���A�S���̕ی�҂U�O�O�O�l��ΏۂɃA���P�[�g�����{�B�S�S�Q�X�l�̉͂����B�w�͒ቺ�́u���Ȃ�S�z���Ă���v�i�Q�Q�D�U���j�A�u�����S�z���Ă���v�i�S�V�D�P���j�����킹��ƂU�X�D�V���ɂ̂ڂ����B�����A�O�N�x�̓��l�̒������͂S�D�X�|�C���g�Ⴉ�����B
�w�Z�I�𐧓������@�@��t���Y���s
�i�����V�� �X���P�O���j
�@��t���Y���s���ς͗��N�x���w�̏����w������A���w����w�Z��I�ׂ�u�w�Z�I�𐧁v������B�K���ɘa�Ŋw�Z���m�����������A�e�Z�ɓ��F����w�Z�o�c�𑣂��_�������A�����̔w�i�ɂ́A�����E���k���̋}���ŋ����s�����[���Ȓn�悪�o�Ă��邱�Ƃ�����B
�@�Y���s�͒n���S�������t�߂̋��s�X�n�u�����v�A��ɂV�O�N��ɖ��ߗ��Ă�ꂽ�i�q���t�������́u�����v�A�W�O�N��ɖ��ߗ��Ă�ꂽ�C�����́u�V���v�Ō`������Ă���B
�@�u�V���v�̓}���V�������݃��b�V���Ŏ��������}�����ċ����s�����[�����A�v���n�u�Z�ɂŋ}������̂���Ԃ��B�������A�u�����v�ł͏Z���̍�����i��ŋ������ڗ��ȂǁA�w�Z�ԂŐ��k���̕s�ύt����艻���Ă���B�I�𐧓����Łu�ߖ��Z�v������A�]�T�̂���w�Z�ɓ���I�������܂��B
�@����̐��x�Ŏ���ΏۂƂȂ�̂́A�����ɗ]�T������u�����v�̊w�Z�𒆐S�ɏ��w�Z�U�Z�ƒ��w�Z�S�Z�̌v�P�O�Z�B�P�O���P���ɗ��N�x���w�\��̎q��������ƒ�Ɋe�Z�̎�����z�z���A�U�`�Q�S�����u�w�Z���J���v�Ƃ��Č��w���Ԃ�݂���B�Q�W���܂Ŋ�]���t���A�\�����݂������ꍇ�͒��I���s���\��B
�w���͕s���������@���k�S�������������o���Ă����Ƒ��s�A�w���͕s���̎���
�i�����V���@�X���P�Q���j
�@�����Ȋw�Ȃ͎w���͕s�������̔F���Ƃ��Ĉȉ��̂悤�Ȃ��̂��������B
�y���w�Z���@�z
�E��b�I�Ȓm����Z�p���s���B�v�Z���⊿���ȂNJԈႢ�������邱�Ƃ�����
�E�����̗v�������ꂷ���ĐU���Ă���B�ƒ�K�₪�K�v�ȂƂ��ł��ی�҂ɂ͓d�b�������Ȃ�
�E���l�̈ӌ����������̔��F�߂Ȃ��B�w�E�����Ƌt�ɍU���I�ɂȂ�
�y���w�Z���@�z
�E���k�̖ڂ����Ęb�����Ƃ��ł��Ȃ�
�E���k���S�z����قǎw�����e�Ɍ�肪�����B���я����ɊԈႢ���J��Ԃ�����
�E���ƒ��A���k�̕��������A���̕��������Ĉ���I�Ɏ��Ƃ�����
�y���Z���@�z
�E���ƒ��A���k����������Ă����ӂ��Ȃ��B�S�����������甲���o�������A�C�ɂƂ߂����Ɍ������Ď��Ƃ𑱂���
�E���Ƃ����Ă����k�ɐ���������ꂸ�������ʂ����Ȃ��B�����Ƃ���b�������������肪���ɂȂ�
���̑�
����G���̓�������
�u�m���̂ǂ������炵���́H�v�@���q�s�g�D�x����
�i���T��@�X���P�T�����j
�@�������ǂ����Ă��������Ă���܂��B
�@���������ł����A���t������������̎������ɓ��w�������F�l����̏��ł��B
�o�s�`��Â̍��e��ŁA���ꂳ�m�u�m�͂ǂ��������H�v�Ƃ����b��Ő���オ��A�Ȃ�Ɓu�Q�l�ڂ͂m���ɂ͍s���Ȃ����ˁ`�v�Ƃ������_�ňꓯ�ӌ�����v�����̂������ł��B���R�́u�m���ɂ�������ƁA�ƂŐe���[�����狳�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ�����v�i�܂�A�m���ł͉��ɂ��o���Ă��Ȃ��B�e�͂P�l�ڂŒ���āA�Q�l�ڂ̎q����͑��̏m�ɂ�����Ă��Ƃł��B���킩��ł��傤���j�B
���Ȃ݂ɁA���̗F�l�̖�������m���ɍݐЂ��Ă͂������̂́A���U����͂قƂ�ǒʂ킸�A�ƒ닳�t�Ɍ��Ă�����Ă����Ƃ̂��ƁB�m�����̂����A�S���m���P�ƂŎu�]�Z�ɍ��i�����q�̕��������Ȃ̂ł͂Ȃ����H�Ǝv����悤�Ȏ��Ԃ��A���ꂳ���̉�b�Ŗ��炩�ɂȂ��������ł��B�u�ʓ|���������v�Ƃ����b�͂悭�����m���ł����A�����܂łƂ́E�E�E�Ƌ����܂����B���̂悤�ȁi�傫�ȁj�������邱�Ƃ��A����M���Ɏ��グ�Ă������������Ǝv���܂��B�m���ɂ���݂͂���܂��A����܂�Ȏ��Ԃł����́B�t�Ɂu�m�������ő��v�A�X�p���V�C�I�v�Ƃ�����������ϐ������������ł��B
���Z���^�[�ʐM�Ђ̐��T��Ɉȏ�̂悤�ȓ������ڂ��Ă��܂����B�ҏW���̋������炢�]�ڂ��܂����B�A�N�Z�X�Ƃ��Ă��̂ɖ����Ȃ���Ǝv���܂��B��
����聄
�@���̐}�ŁC�`�a�̒����͂Scm�ŁC�b�c�̒����͂Wcm�ł��B���̂Ƃ��C�p�i�A�j�̑傫���Ƃ`�d�̒��������߂Ȃ����B
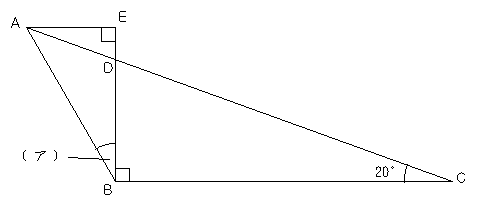
�i�O�R�N�W�j
�@
�������ɒ����W�X���
����聄
�@�P�� �C�R�� �C�T�� �C�V��
�̂S�̂����肪����܂��B�����̂�������g���āC�d�����͂���Ƃ��C���̖₢�ɓ����Ȃ����B
�i�P�j�@�ゴ��Ă�т�̍����̂���̏ゾ���ɂ�������̂��Ă͂��邱�Ƃ��ł���d���͉��ʂ肠��܂����B
�i�Q�j�@�E���̂���̏�ɂ�������̂��Ă��悢���Ƃɂ���Ƃ��C�i�P�j�̏d���̂ق��ɉ����̏d�����͂��邱�Ƃ��ł��܂����B���ׂē����Ȃ����B
�i�O�R�N�T���W�I�w�@�j
����
�i�P�j�@�����̂���ɂ�����������̂����Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�S�̂������g�ݍ��킹�č�邱�Ƃ��ł���d�������ׂ�悢�̂ŁA
�@�@�@�@�P���@���@�P��
�@�@�@�@�R���@���@�R��
�@�@�@�@�S���@���@�P���{�R��
�@�@�@�@�T���@���@�T��
�@�@�@�@�U���@���@�P���{�T��
�@�@�@�@�V���@���@�V��
�@�@�@�@�W���@���@�P���{�V���@�܂��́@�R���{�T��
�@�@�@�@�X���@���@�P���{�R���{�T��
�@�@�@�P�O���@���@�R���{�V��
�@�@�@�P�P���@���@�P���{�R���{�V��
�@�@�@�P�Q���@���@�T���{�V��
�@�@�@�P�R���@���@�P���{�T���{�V��
�@�@�@�P�T���@���@�R���{�T���{�V��
�@�@�@�P�U���@���@�P���{�R���{�T���{�V��
�@�@�ȏ�B�Q���ƂP�S���ȊO�͂��ׂĉ\�Ȃ̂ŁA�P�S�ʂ��B
�i�Q�j�@�E���ɂ���������悹����Ƃ������Ƃ́A���y�T���{�V���z���E�y�R���{���z�Ƃ����悤�Ȃ͂���������邱�ƂŁA�T�{�V�|�R���X�����͂��邱�Ƃ��ł���B
�@�@�����Łi�P�j�ȊO�̏d�����l����Ƃ��A�S�����g���P�U�����d�����̂͂͂��邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA�P�U���ȉ��ōl����ƁA�Q���ƂP�S�������Y�����Ȃ��B
�@�@�����Ŋm�F���Ă݂�ƁA
�@�@�@�@�Q���@���@�R���|�P���@�܂��́@�T���|�R���@�܂��́@�V���|�T��
�@�@�@�P�S���@���@�R���{�T���{�V���|�P��
�@�@����āA�����́A�Q���ƂP�S���B